今回は、民法でいきましょう。
択一でもいいし、記述式でもいいですね。両方、当てちゃいましょう。
まず民法145の当事者を書きなさい、という問題が出てもいいように、しておきましょうか。
当事者とは、「時効により直接に利益を受ける者であって、間接的に利益を受ける者は当事者ではない」(丁度40字か)「取得時効により権利を取得し、消滅時効により権利の制限又は義務を免れる者」(35字)てな具合です。
択一なら、判例ですね。ここは、援用できる場合とできない場合を確認しておきましょう。
保証人、連帯保証人、物上保証人、いいとしてさらに、抵当不動産の第三取得者も、当該抵当権の被担保債権について、その消滅時効を援用することができますね(最判昭48・12 ・ 14)
売買予約の仮登記がある不動産を取得し登記を経由した第三取得者も、その後抵当権を設定を受け登記を経由した者も、予約完結権の消滅時効を援用することができます。
また、被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、その共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ、取得時効を援用することができます(最判平13・ 7 ・10)。なぜなら、時効の完成により利益を受ける者は自己が直接に受けるべき利益の存する限度で時効を援用することができるものと解すべきからだ。
さらに、金銭債権の債権者は、債務者が無資力のときは、他の債権者が当該債務者に対して有する債権について、その消滅時効を、債権者代位権に基づいて援用することができます(最判昭43・9 ・ 26)。
詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権について、その消滅時効を援用することができる(最判平10・ 6 ・22)。時効の利益を直接に受ける者に当たるからだね。
では、できない者は、
後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権について、その消滅時効を援用することができない(最判平11・10・21)。
なぜなら、順位が上昇し、これによって被担保債権に対する配当額が増加することがあり得るが、この配当額の増加に対する期待は、抵当権の順位の上昇によってもたらされる反射的な利益にすぎないから、後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当するものではなからである。
さらに、取得時効が問題となる土地のその上の建物の賃借人は、間接的でダメだね(最判44・7・15)。
なーんか、全部チェックしました。
予想でなく、勉強か。
では、また。
※行政書士の予想問題は上記の本「らくがく(楽学)行政書士 直前模試」で解いてみよう。
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
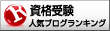
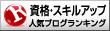
択一でもいいし、記述式でもいいですね。両方、当てちゃいましょう。
まず民法145の当事者を書きなさい、という問題が出てもいいように、しておきましょうか。
当事者とは、「時効により直接に利益を受ける者であって、間接的に利益を受ける者は当事者ではない」(丁度40字か)「取得時効により権利を取得し、消滅時効により権利の制限又は義務を免れる者」(35字)てな具合です。
択一なら、判例ですね。ここは、援用できる場合とできない場合を確認しておきましょう。
保証人、連帯保証人、物上保証人、いいとしてさらに、抵当不動産の第三取得者も、当該抵当権の被担保債権について、その消滅時効を援用することができますね(最判昭48・12 ・ 14)
売買予約の仮登記がある不動産を取得し登記を経由した第三取得者も、その後抵当権を設定を受け登記を経由した者も、予約完結権の消滅時効を援用することができます。
また、被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、その共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ、取得時効を援用することができます(最判平13・ 7 ・10)。なぜなら、時効の完成により利益を受ける者は自己が直接に受けるべき利益の存する限度で時効を援用することができるものと解すべきからだ。
さらに、金銭債権の債権者は、債務者が無資力のときは、他の債権者が当該債務者に対して有する債権について、その消滅時効を、債権者代位権に基づいて援用することができます(最判昭43・9 ・ 26)。
詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権について、その消滅時効を援用することができる(最判平10・ 6 ・22)。時効の利益を直接に受ける者に当たるからだね。
では、できない者は、
後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権について、その消滅時効を援用することができない(最判平11・10・21)。
なぜなら、順位が上昇し、これによって被担保債権に対する配当額が増加することがあり得るが、この配当額の増加に対する期待は、抵当権の順位の上昇によってもたらされる反射的な利益にすぎないから、後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当するものではなからである。
さらに、取得時効が問題となる土地のその上の建物の賃借人は、間接的でダメだね(最判44・7・15)。
なーんか、全部チェックしました。
予想でなく、勉強か。
では、また。
※行政書士の予想問題は上記の本「らくがく(楽学)行政書士 直前模試」で解いてみよう。






















