あれもこれも、予想したいのですが、残すところ4,5回ですから、やはり足りない点は上記の「予想問題」でカバーしてくださいね。今年も当たりますから。
最後まで諦めず、不得意だと思っているところの解説を読むだけでも、思い出せるからいいですよ。
あと、コンパクト解説、要はポイント、ツボもありますから、そこからその当たりの知識がフラッシュバックできればいいのです。
さて、今日は、最高裁の判例をひとつ指摘しておきましょう。
この判例、結構慌てていると間違えやすいので、まだ慌てていない時期にじっくり理由を押さえておけば、本試験では慌てません。
それは、抵当権設定登記後に賃借権の時効取得に必要な期間不動産を用益した者が賃借権の時効取得を当該不動産の競売又は公売による買受人に対抗することの可否、という判例です。
建物収去土地明渡等請求事件(平成23年01月21日判決)ですね。
裁判要旨は・・・・
不動産につき賃借権を有する者がその対抗要件を具備しない間に,当該不動産に抵当権が設定されてその旨の登記がされた場合,上記の者は,上記登記後,賃借権の時効取得に必要とされる期間,当該不動産を継続的に用益したとしても,競売又は公売により当該不動産を買い受けた者に対し,賃借権を時効により取得したと主張して,これを対抗することはできない。
というものですが、
では、少し理由もつけて・・・
抵当権の目的不動産につき賃借権を有する者は,当該抵当権の設定登記に先立って対抗要件を具備しなければ,当該抵当権を消滅させる競売や公売により目的不動産を買い受けた者に対し,賃借権を対抗することができないのが原則である。
このことは,抵当権の設定登記後にその目的不動産について賃借権を時効により取得した者があったとしても,異なるところはないというべきである。したがって,不動産につき賃借権を有する者がその対抗要件を具備しない間に,当該不動産に抵当権が設定されてその旨の登記がされた場合,上記の者は,上記登記後,賃借権の時効取得に必要とされる期間,当該不動産を継続的に用益したとしても,競売又は公売により当該不動産を買い受けた者に対し,賃借権を時効により取得したと主張して,これを対抗することはできないことは明らかである。
実は、時効取得者が対抗要件がなくても優先するという昭和36年判例があって、これとは異なる状況だとわかればOKです。
それは、不動産の取得の登記をした者と登記後に当該不動産を時効取得に要する期間占有を継続した者との間における相容れない権利の得喪にかかわるものであり,そのような関係にない今回の判例では、抵当権者と賃借権者との間の関係に係る本件とは事案を異にする、ともいっていますね。
先の昭和36年07月20日判決は、「時効による不動産の所有権取得とその対抗要件」についてなんです。
その裁判要旨は・・・
不動産の取得時効が完成しても、その登記がなければ、その後に所有権取得登記を経由した第三者に対しては時効による権利の取得を対抗しえないが、第三者の右登記後に占有者がなお引続き時効取得に要する期間占有を継続した場合には、その第三者に対し、登記を経由しなくとも時効取得をもつて対抗しうるものと解すべきである。
というぐあいです。
理解できましたか。2つの判例の違いが出るかもしれないし、ストレートに各内容が出るかもしれないし、まあ絶対に出る(そう信じて)、というものです。
では、また。
※行政書士の予想問題は上記の本「らくがく(楽学)行政書士 直前模試」で解いてみよう。
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
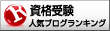
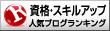
最後まで諦めず、不得意だと思っているところの解説を読むだけでも、思い出せるからいいですよ。
あと、コンパクト解説、要はポイント、ツボもありますから、そこからその当たりの知識がフラッシュバックできればいいのです。
さて、今日は、最高裁の判例をひとつ指摘しておきましょう。
この判例、結構慌てていると間違えやすいので、まだ慌てていない時期にじっくり理由を押さえておけば、本試験では慌てません。
それは、抵当権設定登記後に賃借権の時効取得に必要な期間不動産を用益した者が賃借権の時効取得を当該不動産の競売又は公売による買受人に対抗することの可否、という判例です。
建物収去土地明渡等請求事件(平成23年01月21日判決)ですね。
裁判要旨は・・・・
不動産につき賃借権を有する者がその対抗要件を具備しない間に,当該不動産に抵当権が設定されてその旨の登記がされた場合,上記の者は,上記登記後,賃借権の時効取得に必要とされる期間,当該不動産を継続的に用益したとしても,競売又は公売により当該不動産を買い受けた者に対し,賃借権を時効により取得したと主張して,これを対抗することはできない。
というものですが、
では、少し理由もつけて・・・
抵当権の目的不動産につき賃借権を有する者は,当該抵当権の設定登記に先立って対抗要件を具備しなければ,当該抵当権を消滅させる競売や公売により目的不動産を買い受けた者に対し,賃借権を対抗することができないのが原則である。
このことは,抵当権の設定登記後にその目的不動産について賃借権を時効により取得した者があったとしても,異なるところはないというべきである。したがって,不動産につき賃借権を有する者がその対抗要件を具備しない間に,当該不動産に抵当権が設定されてその旨の登記がされた場合,上記の者は,上記登記後,賃借権の時効取得に必要とされる期間,当該不動産を継続的に用益したとしても,競売又は公売により当該不動産を買い受けた者に対し,賃借権を時効により取得したと主張して,これを対抗することはできないことは明らかである。
実は、時効取得者が対抗要件がなくても優先するという昭和36年判例があって、これとは異なる状況だとわかればOKです。
それは、不動産の取得の登記をした者と登記後に当該不動産を時効取得に要する期間占有を継続した者との間における相容れない権利の得喪にかかわるものであり,そのような関係にない今回の判例では、抵当権者と賃借権者との間の関係に係る本件とは事案を異にする、ともいっていますね。
先の昭和36年07月20日判決は、「時効による不動産の所有権取得とその対抗要件」についてなんです。
その裁判要旨は・・・
不動産の取得時効が完成しても、その登記がなければ、その後に所有権取得登記を経由した第三者に対しては時効による権利の取得を対抗しえないが、第三者の右登記後に占有者がなお引続き時効取得に要する期間占有を継続した場合には、その第三者に対し、登記を経由しなくとも時効取得をもつて対抗しうるものと解すべきである。
というぐあいです。
理解できましたか。2つの判例の違いが出るかもしれないし、ストレートに各内容が出るかもしれないし、まあ絶対に出る(そう信じて)、というものです。
では、また。
※行政書士の予想問題は上記の本「らくがく(楽学)行政書士 直前模試」で解いてみよう。





















