これまで、宅建の出版を数多く出してきましたが、普通“資格本”には、テキスト+過去問+ドリル(1問1答など)+まとめ本(テクニック本など)+予想問題、などがありますね。
実は、単発では、ドリル分野は書いてませんが、いずれもこれまで書いているんです。
そうなんです。
そうみるとすごいのですが、実は読者の皆さんが力をつけて頂くには、テキストがあって、それをさらに過去問集で実践できるようになっていて、さらにそれを予想問題でしっかり確かめられ、そして自信をつけてもらい、受験して、合格へ、という流れだと思いますよね。
平成23年は、その中で“過去問”と“予想問題”は出したことは皆さんご存じでしょうが、肝心なテキストは出していません。
これ結構、マズイですよね。中途半端で効果半減です。
もちろん、シリーズ本でしたので、他の人が書いたテキストはありました。でも、それを読んでも私の過去問とはうまくつながっていませんでした。
ですから、今回は他の出版社の力を借りて、3点セットを出すことになりました。
3点セットとは、テキスト+過去問+ドリルです。出しますよ。
予想問題は、他の社(これまで通り「週刊住宅新聞社」)ですでに出ることが決まっていますから、それを入れれば4点セットとなります。
すでに、入門書(これも週刊住宅新聞社)は出版していますので、宅建における“高橋克典ワールド”をお届けできるようになりました。
安心して、テキストから勉強して頂けるんです。すごくうれしいです。
そのため、責任も重大です。身が引き締まる思いです。
でも、良い本ができたと自負しています。
これらの本を出すためには、生の声をいろいろ取り入れました。特に、協力してもらった生徒には感謝しています。
今回は、テキストの紹介ですが、そのテキストのタイトルは「宅建110 番 スイスイLIVE 講義」という名前に決まりました。
左側には、板書を、右側には、私の講義を書いて、なるべく私の講義がお届けできるように工夫しました。
また、これを読んで、宅建の受験生のみなさんに元気(?)が出るような内容になっていると思っています。
本当は、生講義を受けて頂けるのが一番なんでしょうが、全国の皆さんへ講義は物理的にできません。ですから、この本で。
このテキストですが、遅くても1月中旬には全国の各書店に並ぶと思います。ぜひ、楽しみにしていてください。
これから勉強される人へ、また合格された方も身近で勉強する人に紹介して頂ければうれしいですね。
また、詳細が決まりましたら、お知らせします。
では、また。
※上記宅建入門書は、「不動産取引の法律入門―図表・イラスト・写真で分かる(週刊住宅新聞社 (著)」です。ちなみに、私の名前で出版していませんので、注意してください。
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
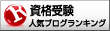
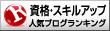
実は、単発では、ドリル分野は書いてませんが、いずれもこれまで書いているんです。
そうなんです。
そうみるとすごいのですが、実は読者の皆さんが力をつけて頂くには、テキストがあって、それをさらに過去問集で実践できるようになっていて、さらにそれを予想問題でしっかり確かめられ、そして自信をつけてもらい、受験して、合格へ、という流れだと思いますよね。
平成23年は、その中で“過去問”と“予想問題”は出したことは皆さんご存じでしょうが、肝心なテキストは出していません。
これ結構、マズイですよね。中途半端で効果半減です。
もちろん、シリーズ本でしたので、他の人が書いたテキストはありました。でも、それを読んでも私の過去問とはうまくつながっていませんでした。
ですから、今回は他の出版社の力を借りて、3点セットを出すことになりました。
3点セットとは、テキスト+過去問+ドリルです。出しますよ。
予想問題は、他の社(これまで通り「週刊住宅新聞社」)ですでに出ることが決まっていますから、それを入れれば4点セットとなります。
すでに、入門書(これも週刊住宅新聞社)は出版していますので、宅建における“高橋克典ワールド”をお届けできるようになりました。
安心して、テキストから勉強して頂けるんです。すごくうれしいです。
そのため、責任も重大です。身が引き締まる思いです。
でも、良い本ができたと自負しています。
これらの本を出すためには、生の声をいろいろ取り入れました。特に、協力してもらった生徒には感謝しています。
今回は、テキストの紹介ですが、そのテキストのタイトルは「宅建110 番 スイスイLIVE 講義」という名前に決まりました。
左側には、板書を、右側には、私の講義を書いて、なるべく私の講義がお届けできるように工夫しました。
また、これを読んで、宅建の受験生のみなさんに元気(?)が出るような内容になっていると思っています。
本当は、生講義を受けて頂けるのが一番なんでしょうが、全国の皆さんへ講義は物理的にできません。ですから、この本で。
このテキストですが、遅くても1月中旬には全国の各書店に並ぶと思います。ぜひ、楽しみにしていてください。
これから勉強される人へ、また合格された方も身近で勉強する人に紹介して頂ければうれしいですね。
また、詳細が決まりましたら、お知らせします。
では、また。
※上記宅建入門書は、「不動産取引の法律入門―図表・イラスト・写真で分かる(週刊住宅新聞社 (著)」です。ちなみに、私の名前で出版していませんので、注意してください。






















