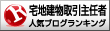では、今回は「借家」で一番難しい所を学習します。
難しいといっても、終了するのか更新するのかですので、実はたいしたことありません。ここが最も難しいなら、他もたいしたことないのです。
借家は、借地と異なって、期間を定めたバージョンと定めないバージョンがありました。
まずは、定めた場合を見てみましょう。
期間を定めたのですから、期間が満了がいつかは来ます。
まず民法なら、当事者が期間を定めたのだから、その意思を尊重するため、一度終了するというのが原則です。
しかし、それでは借主がまだ利用している場合には、不都合でしょう。この法律は、借主保護ですからね。
そうすると、どうなっているか条文を見てみましょう。
・・・・・・・・・
(建物賃貸借契約の更新等)
第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。
3 建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。
・・・・・・・・・・
さらに、借主が借りたいのに、終わるためには、正当事由が賃貸人に必要です。それが・・・。
・・・・・・・・・・
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
・・・・・・・・・・
読んで、理解できれば問題ないでしょう。
では、26条から分析しましょう。1項と2項があります。3項は適法な転借ですから、当面無視していいでしょう。
1項ですが、まず当事者とありますから、互いにアクションを起こさずに期間が満了がくれば当然に更新にしています。ふむふむ。納得。
これは合意ではないのですから、期間を除いて、従前の契約と同じでいくわけです。期間は違いますが、それは期間を定めてない状態としていくわけですね。ふむふむ。
では、終了したいときには、お互い6か月前にアクションをおこさないといけないとしています。そして、賃貸人においては、28条でその通知は終了するだけの正当理由がないと終了できないとしています。厳しいです。これも当然ですね。
これらが、第一関門です。
これは、終了の6か月前のことですから。その後、満了日がくるのですが、もう一つ関門がまっています。それが、2項ですね。
ついつい、そのまま使わせてしまったら、やっぱり強制的に更新されてしまいます。もし、ストップしたかったら、せっかく、事前に通知もし正当事由も認められたのですから、賃貸人が遅滞なく異議を述べればいいわけです。
これが、期間を定めた場合のストップの仕方でした。
ちなみに、更新される場合の民法の場合と比較しておきましょう。
・・・・・
(賃貸借の更新の推定等)
第六百十九条 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
2 従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、敷金については、この限りでない。
・・・・・
民法は、期間を定めたら、原則終了で、合意で更新するなら別ですが、それ以外なら、上記の黙示の更新(遅滞なく述べなくてもとにかく異議をすればいい、そしてみなすではなくて“推定”となっています)となります。もちろん、この場合には、期間の定めのないものとなります。
期間の定めのない場合は、次回にしましょう。
では、また。
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
 資格(行政書士) ブログランキングへ
資格(行政書士) ブログランキングへ
 資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ
資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

難しいといっても、終了するのか更新するのかですので、実はたいしたことありません。ここが最も難しいなら、他もたいしたことないのです。
借家は、借地と異なって、期間を定めたバージョンと定めないバージョンがありました。
まずは、定めた場合を見てみましょう。
期間を定めたのですから、期間が満了がいつかは来ます。
まず民法なら、当事者が期間を定めたのだから、その意思を尊重するため、一度終了するというのが原則です。
しかし、それでは借主がまだ利用している場合には、不都合でしょう。この法律は、借主保護ですからね。
そうすると、どうなっているか条文を見てみましょう。
・・・・・・・・・
(建物賃貸借契約の更新等)
第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。
3 建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。
・・・・・・・・・・
さらに、借主が借りたいのに、終わるためには、正当事由が賃貸人に必要です。それが・・・。
・・・・・・・・・・
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
・・・・・・・・・・
読んで、理解できれば問題ないでしょう。
では、26条から分析しましょう。1項と2項があります。3項は適法な転借ですから、当面無視していいでしょう。
1項ですが、まず当事者とありますから、互いにアクションを起こさずに期間が満了がくれば当然に更新にしています。ふむふむ。納得。
これは合意ではないのですから、期間を除いて、従前の契約と同じでいくわけです。期間は違いますが、それは期間を定めてない状態としていくわけですね。ふむふむ。
では、終了したいときには、お互い6か月前にアクションをおこさないといけないとしています。そして、賃貸人においては、28条でその通知は終了するだけの正当理由がないと終了できないとしています。厳しいです。これも当然ですね。
これらが、第一関門です。
これは、終了の6か月前のことですから。その後、満了日がくるのですが、もう一つ関門がまっています。それが、2項ですね。
ついつい、そのまま使わせてしまったら、やっぱり強制的に更新されてしまいます。もし、ストップしたかったら、せっかく、事前に通知もし正当事由も認められたのですから、賃貸人が遅滞なく異議を述べればいいわけです。
これが、期間を定めた場合のストップの仕方でした。
ちなみに、更新される場合の民法の場合と比較しておきましょう。
・・・・・
(賃貸借の更新の推定等)
第六百十九条 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
2 従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、敷金については、この限りでない。
・・・・・
民法は、期間を定めたら、原則終了で、合意で更新するなら別ですが、それ以外なら、上記の黙示の更新(遅滞なく述べなくてもとにかく異議をすればいい、そしてみなすではなくて“推定”となっています)となります。もちろん、この場合には、期間の定めのないものとなります。
期間の定めのない場合は、次回にしましょう。
では、また。
 | うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ) |
| 高橋克典 | |
| 週刊住宅新聞社 |
 | 2016年版うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分) (うかるぞ宅建士シリーズ) |
| 高橋克典 | |
| 週刊住宅新聞社 |
 | 試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 |
| 高橋 克典 | |
| 住宅新報社 |