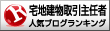では、前回の続きです。
債権者A、主たる債務者B、保証人Cが登場しました。
AB間で金銭消費貸借をします。
保証契約は、AC間で合意し書面を交わします。
そして、ここから重要ですが、Aは未成年者でその親がCだとしましょう。そうすれば、Cは事情をよく知っていることになります。
そして、Cはこのブロクをよく読んでいるので、実に法律をよく知っています。Aはこのブロクを読んでいませんので、いかんせんCに丸め込まれてしまっています。
では、どういう状況かというと、Cの本心は、Aから遊興費にあてるため、たくさんのお金を踏んだくろうとしています。
さて、そこでCは、Aに近づき息子にお金を貸してあげてほしい、あっ俺が保証人になるから心配しなくてもいい、と。Aは、お人好しで法律の勉強をしていませんので、あいいよお前が保証人になるっというなら貸してあげよう、と。
もちろん、BにはCは同意も与えていません、だってあとで取り消そうと思っているからです。
契約が成立し、Aからのお金でCはギャンブルにすべて使い、とうとうなくなってしまいました。そして、その弁済期日がやってきました。
AはCに返してくれといいましたが、Cは態度を急に変えて、ふざけんな、返す必要はない。
実はな、Bには同意を与えてないから、契約を俺は取消できるんだ。
・・・・・・・
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
・・・・・・・
できるけど、渡したものは、返すべきではとAは思ったとしても、実は・・・。
・・・・・・・
(取消しの効果)
第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
・・・・・・・
息子は全部ギャンブルに使って、現存してないから、返さなくてもいいんだよー。
Aは、すこし食い下がります。でも、Cは保証人として、かえすべきだろ、といったとします。
もしこの条文がなかったら、どうなるか。実は、附従性で保証もなくなる可能性があるわけですね。
でも、これはあまりにも結論がまずいでしょう。
だから、449条を置いた意味があるのです。もう一度、味わってみてください。
今度は、いろいろな情報をえましたので、条文の文言がスイスイ頭に入ってくるはずです。
入ってこない人は、そうですね。
「試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 」をぜひ読んでください。そのために書きましたから。
・・・・・・
(取り消すことができる債務の保証)
第四百四十九条 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。
・・・・・・
以上、どうですか。これで、よく理解できましたか。そうですか。ほっとしました。
行政書士なら、記述式にはうってつけですね。条文は、よくみるとおもしろい。
また、おなじトーンで書いた、「うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ 」もよろしくお願いします。
宅建合格のためにです。
では、また。
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
 資格(行政書士) ブログランキングへ
資格(行政書士) ブログランキングへ
 資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ
資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

dokusya
債権者A、主たる債務者B、保証人Cが登場しました。
AB間で金銭消費貸借をします。
保証契約は、AC間で合意し書面を交わします。
そして、ここから重要ですが、Aは未成年者でその親がCだとしましょう。そうすれば、Cは事情をよく知っていることになります。
そして、Cはこのブロクをよく読んでいるので、実に法律をよく知っています。Aはこのブロクを読んでいませんので、いかんせんCに丸め込まれてしまっています。
では、どういう状況かというと、Cの本心は、Aから遊興費にあてるため、たくさんのお金を踏んだくろうとしています。
さて、そこでCは、Aに近づき息子にお金を貸してあげてほしい、あっ俺が保証人になるから心配しなくてもいい、と。Aは、お人好しで法律の勉強をしていませんので、あいいよお前が保証人になるっというなら貸してあげよう、と。
もちろん、BにはCは同意も与えていません、だってあとで取り消そうと思っているからです。
契約が成立し、Aからのお金でCはギャンブルにすべて使い、とうとうなくなってしまいました。そして、その弁済期日がやってきました。
AはCに返してくれといいましたが、Cは態度を急に変えて、ふざけんな、返す必要はない。
実はな、Bには同意を与えてないから、契約を俺は取消できるんだ。
・・・・・・・
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
・・・・・・・
できるけど、渡したものは、返すべきではとAは思ったとしても、実は・・・。
・・・・・・・
(取消しの効果)
第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
・・・・・・・
息子は全部ギャンブルに使って、現存してないから、返さなくてもいいんだよー。
Aは、すこし食い下がります。でも、Cは保証人として、かえすべきだろ、といったとします。
もしこの条文がなかったら、どうなるか。実は、附従性で保証もなくなる可能性があるわけですね。
でも、これはあまりにも結論がまずいでしょう。
だから、449条を置いた意味があるのです。もう一度、味わってみてください。
今度は、いろいろな情報をえましたので、条文の文言がスイスイ頭に入ってくるはずです。
入ってこない人は、そうですね。
「試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 」をぜひ読んでください。そのために書きましたから。
・・・・・・
(取り消すことができる債務の保証)
第四百四十九条 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。
・・・・・・
以上、どうですか。これで、よく理解できましたか。そうですか。ほっとしました。
行政書士なら、記述式にはうってつけですね。条文は、よくみるとおもしろい。
また、おなじトーンで書いた、「うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ 」もよろしくお願いします。
宅建合格のためにです。
では、また。
 | うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ) |
| 高橋克典 | |
| 週刊住宅新聞社 |
 | 2016年版うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分) (うかるぞ宅建士シリーズ) |
| 高橋克典 | |
| 週刊住宅新聞社 |
 | 試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 |
| 高橋 克典 | |
| 住宅新報社 |

dokusya