おはようございます!
今日は、何の日??
- 二十四節気・雑節等
- 鮭魚群がる
- 七十二候の一つ(63候)。
- 飛行機の日
- 1903(明治36)年、アメリカ・ノースカロライナ州のキティホークで、ウィルバーとオーヴィルのライト兄弟が動力飛行機の初飛行に成功した。この日には4回飛行し、1回目の飛行時間は12秒、4回目は59秒で飛行距離は256m。
- マージャンの日
- (毎月第3木曜)
- いなりの日
- 日本の食文化の中で多くの人に親しまれているいなり寿司を食べる機会を増やすきっかけを作ろうと、いなり寿司の材料を製造販売している株式会社みすずコーポレーションが制定。日付はいなりのい~なで毎月17日に。
- 国産なす消費拡大の日
- 4月17日の「なすび記念日」の17日を、毎月なすの消費を増やす日にしようと、冬春なす主産県協議会が2004年2月9日に制定した。
鮭が群がりますか?
さけ・・・と言うと、酒を思い浮かべますね。
やっぱし、”シャケ”と発音してもらわんと、ピンときませんわ^^
さて、石仏はんの続き・・・

寒そう~~

なんか唇に・・・・






週の半ば・・・・
今週は、長いね
では、
本日も、笑顔と気合で乗り切りまっしょい!
去年の同日の日記
http://blog.goo.ne.jp/takomusume97/d/20081217
おはようございます!
今日は、何の日??
- 二十四節気・雑節等
- 新月
- 朔。月と太陽の黄経差が0°となる日。旧暦ではこの日が暦月の朔日となる。
- 念仏の口止め
- 正月の神様(年神様)は念仏が嫌いであるとして、この日の翌日から1月16日の「念仏の口明け」までは念仏を唱えないというしきたりがある。この日はこの年最後の念仏を行う日となる。
- 紙の記念日
- 1875年(明治8年)のこの日、元幕臣の渋沢栄一が設立した東京の抄紙会社が営業運転を開始したことによる。こちらは王子製紙の前身。
- 電話の日
- 1890年(明治23年)のこの日、日本で初めて電話が開通したことに由来する。
そういえば、なんとか流星群・・・
見ました??
夜中は、寝てるし、明け方はあせってるし・・・・
で見てませんけどね
さて、紅葉の写真もなくなってきましたので・・・・
石仏さんをば

場所は・・・・
忘れた^^




怒ってはります???

間違った・・・・
石仏ちゃいます、カメラマンはんどす


石垣と一体化してます・・・・
では、
本日も、笑顔と気合で乗り切りまっしょい!
去年の同日の日記
http://blog.goo.ne.jp/takomusume97/d/20081216
おはようございます!
今日は、何の日??
さて、紅葉めぐりシリーズ~~

先週の土曜日、高鴨神社の後・・・・・九品寺へ
ここも、何回か訪れたますが・・・・
お寺さんの紹介から


九品寺(くほんじ)
奈良県御所市にある『九品寺』(山号:戒那山(かいなさん))は、聖武天皇の詔により、奈良時代の僧「行基」が開基したお寺とされていますが、創建年などははっきりとしていません。1558年には、浄土宗に改宗しています。


本堂です。
御本尊は平安時代作の木造仏「阿弥陀如来坐像(重文)」です。

地蔵堂です。

本堂の裏山には、千体以上のお地蔵さんがいてはります。


このあたりは、本堂の屋根が同じ目線で見れて・・・・
いい感じ^^
登りたくなんねんな~~

イチョウの後ろ・・・・
奈良市内が一望です。
この日は、曇っててあきまへんでしたが

紅葉もね・・・・
あの日は、4箇所目でしたが、やっと紅葉にめぐり合えた感じでした

ありました・・・
地蔵さんのオーケストラ~~って感じでしょ

他にも、寺中お地蔵さんだらけ・・・




いいですね~~

続く・・・・
では、
本日も、笑顔と気合で乗り切りまっしょい!
去年の同日の日記
http://blog.goo.ne.jp/takomusume97/d/20081128
おはようございます!
今日は、何の日??
- 祝日・休日
- 勤労感謝の日
- 勤労をたっとび、生産を祝い、国民がたがいに感謝しあう
- 勤労感謝の日
- 「勤労を尊び、生産を祝い、国民が互いに感謝し合う日」として1948年(昭和23年)に制定された国民の祝日。戦前はこの日を新嘗祭と呼び、宮中では天皇が新しい米などを神殿に供えた。
- 新嘗祭
- 1873(明治6)年から1947(昭和22)年までの祭日。天皇が新穀を天神地祇に勧め、また、親しくこれを食する祭儀。明治5年までは旧暦11月の2回目の卯の日に行われていた。明治6年から太陽暦が導入されたが、そのままでは新嘗祭が翌年1月になることもあって都合が悪いので、新暦11月の2回目の卯の日に行うこととし、明治6年ではそれが11月23日だった。翌明治7年には前年と同じ11月23日に行われ、以降11月23日に固定して行われるようになった。戦後は皇室典範からこの儀式は除外されたが、各地の神社での新穀感謝の祭事は続いている。
- Jリーグの日
- 1992年(平成4年)のこの日、Jリーグ初の公式戦の決勝戦が行われたことを記念して1993年(平成5年)に制定。
- いいふみの日
- 郵政省が制定。「いい(11)ふみ(23)」の語呂合わせ。
- 外食の日
- 1984年(昭和59年)に日本フードサービス協会が協会創立10周年を記念して設けた日。家族で外食することの楽しさを知ってもらおうと、祝日の勤労感謝の日としたという。
- 手袋の日
- 1981年(昭和56年)に日本手袋工業組合が設けた日。冬に向かい手袋の需要が増すことから、手袋PRを目的に勤労感謝の日を選んだ。
- いい兄さんの日
- 「いい(11)にい(2)さん(3)」の語呂合せ。
- ゲームの日
- 全日本アミューズメント施設営業者協会連合会・日本アミューズメントマシン工業協会・日本SC遊園協会が制定。 仕事や勉強の尊さをはっきり自覚しながら、ゆとりある遊びとしてのゲームを楽しみ、ゲームと生活との調和が感じられる日であるとして、勤労感謝の日を記念日とした。
- いい家族の日
- 全国家族新聞交流会が制定。 「いい(11)ファ(2)ミ(3)リー」の語呂合せ。
祭日でございます。
昨日は、夫婦で今日は家族の日ですね^^
今日も、宴会しますか~
さて、紅葉めぐりシリーズ~~第??弾
今回は、いっぱい行ってきました。
まずは、観心寺
何回も、行ってますが、この季節、やっぱし行っておかないと^^
お寺さんの紹介から・・・・


朝早く、だれもいてないので、拝観料300円也をば・・・・
あそこへ入れて
ワンちゃん可愛いね
観心寺
伝承では、大宝元年(701)、役小角(えんのおづぬ、役行者)が開創し、当初、雲心寺と称したとされる。その後、大同3年(808)、空海がこの地を訪れ、北斗七星を勧請(かんじょう)したという。これにちなむ7つの「星塚」が現在も境内に残る(なお、北斗七星を祭る寺は日本では観心寺が唯一である)。
弘仁6年(815)、空海は再度この地を訪れ、自ら如意輪観音像を刻んで安置し、「観心寺」の寺号を与えたという。「空海が自ら刻んで」云々の話は伝承の域を出ないが、現在金堂本尊として安置される如意輪観音像は、様式的に9世紀の作品とされている。また、観心寺には奈良時代にさかのぼる金銅仏4体が伝来することから、奈良時代草創説もあながち否定はできない。
観心寺の実質的な開基とみられるのは、空海の一番弟子にあたる実恵(じちえ)である。『観心寺縁起資材帳』(国宝)などによると天長4年(827年)(または天長2年とも)、実恵の意を受け、弟子の真紹(しんじょう)が造営を始めている。 観心寺は楠木氏の菩提寺であり、楠木正成および南朝ゆかりの寺としても知られている。正平14年(1359)には当寺が後村上天皇の行在所となった。また、境内には後村上天皇桧尾陵がある。
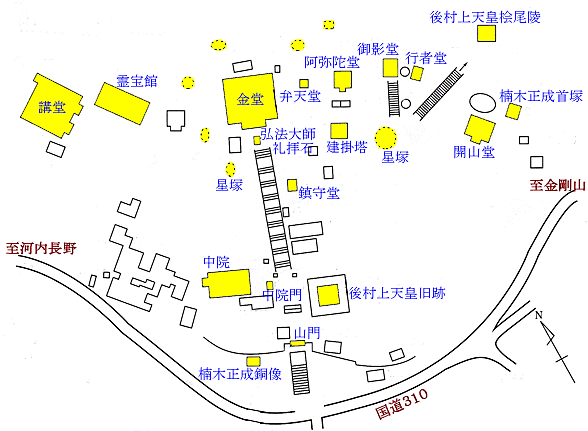
結構、広いです。
星塚っちゅうのんが、ほんとに7つあるんですね。
今、知りました・・・・
次回、訪れたおりには、ちゃんと見ようっと^^

まずは、手洗いから・・・


国宝の金堂です。

弘法大子、礼拝石・・・・





線香が太いねん^^
もちろん、交通安全・・・・


なんか、わからんけど・・・・水が貯めてあります。

鐘堂です。

建掛塔
なんかね、本当は3重の塔にするつもりやったんですが・・・
楠正成はんが、湊川で討ち死にしはったさかいに、ここでストップしたそうな


開山堂です。


紹介は、このへんにて・・・・
さっ、3連休も最終日です。
雨も上がりましたし、お出掛け日和となりました~~
どこ行くかな
では、
本日も、笑顔と気合で乗り切りまっしょい!
去年の同日の日記
http://blog.goo.ne.jp/takomusume97/d/20081123
おはようございます!
今日は、何の日??
さて、紅葉の名所シリーズ~~
今日は、円成寺
奈良~柳生へ行く途中にあります。

奈良市忍辱山町(にんにくせんちょう)にある真言宗御室派の寺院。山号は忍辱山、本尊は阿弥陀如来。
奈良市街東方の柳生街道沿いに位置する古寺で、運慶の作品としてはもっとも初期に属する大日如来像を所蔵することで名高い。
寺に伝わる「和州忍辱山円成寺縁起」によれば、天平勝宝8歳(756年)、聖武・孝謙両天皇の勅願により、唐からの渡来僧で鑑真の弟子にあたる虚瀧(ころう)により開創され、万寿3年(1026年)に命禅が再興して十一面観音を祀ったという。しかし、鑑真とともに来日した僧の中に虚瀧なる人物は実在せず、奈良時代にさかのぼる遺品、出土品等も見当たらない。以上のことから、この草創縁起は後世の仮託と思われ、「中興の祖」とされている命禅が円成寺の実質的な開基であると推定されている。
平安時代末期の保元元年(1156年)、京都仁和寺の寛遍が東密忍辱山流を開いて寺運は興隆した。この頃に本尊が当初の十一面観音から阿弥陀如来に代わったと思われる。
応仁の乱(1466年-1476年)の兵火により堂塔伽藍の大半が焼失したが、栄弘が入り再興された。江戸時代は寺中に子院23か寺を有するほどであったが、明治維新の際の混乱により現在の姿となった。
駐車場は、そんなにたくさん停めれませんが、無料だす

境内に入ると、いきなり名勝「浄土式庭園」が広がります。

池越しに見える「楼門(重文)」がとても美しく素晴らしいですよ^^


忍辱山(にんにくせん)。
読めませんよね・・・・^¥^
・・・忍辱は、食料のにんにくのことではなく、仏教の菩薩行六波羅蜜(布施・持戒・忍辱・精進・禅定・般若)の一つで、いかなる身心の苦悩をも堪え忍ぶという仏道修行の上の大切な徳目のことだそうです。
なるほど。。。。。


さっきの楼門からは、出入りできないのが残念ですが・・・・

こちらの山門を入って、参拝両400円なり

境内は、広くなくて全てを見渡せます。

本堂!
室町時代の建築だが、全体の意匠は寝殿造風である。入母屋造で妻入(屋根の形が三角形に見える方向を正面とする)とするのは仏堂建築には珍しい。寺の説明には文正元年(1466年)建立とあるが、文化庁の資料では棟木銘から文明4年(1472年)建立としている。内部には本尊阿弥陀如来坐像と四天王立像を安置する。内陣の柱には阿弥陀如来に随って来迎する二十五菩薩の像が描かれている

本尊阿弥陀如来坐像


楼門と多宝塔

多宝塔のなかには、国宝が・・・・

木造大日如来坐像
台座内部の銘により、安元2年(1176年)、仏師運慶の作であることがわかる。運慶は東大寺・興福寺などの復興造仏に尽力し、鎌倉時代を代表する仏師として知られるが、この作品は作者の20歳台後半頃の、現存するもっとも初期のもので、時代的には平安時代末期に入る。像高約99cmの寄木造、漆箔仕上げの像で、光背、台座も大部分当初のものが残る。作風は平安時代風を残しつつ、均整が取れ、引き締まった体躯表現、張りのある表情などに運慶の特色が現われている。もと本堂内に安置されていたが、多宝塔に移されている。
ガラス張りにしてあって、影が映って見にくいけど、素晴らしかった~~



鐘楼・・・

春日堂(左)・白山堂(右)(国宝)
安貞2年(1228年)-本堂の脇に建つ2棟の社殿で、2棟とも同規模・同形式である。春日造社殿の現存最古の例として国宝に指定されている。明治初期の神仏分離令による破壊をまぬがれるため、仏堂風に「堂」と称した。
見た感じは、しょぼいんですが・・・
国宝なんですね、びっくり


続く・・・・
では、
本日も、笑顔と気合で乗り切りまっしょい!
去年の同日の日記
http://blog.goo.ne.jp/takomusume97/d/20081120
おはようございます!
今日は、何の日??
さて、紅葉シリーズです^^
まずは、当麻寺!
ここは、牡丹の名所で去年も訪れましたが・・・・
紅葉の名所でもあります^^
行ってきました~~
まずは、お寺さんの紹介をば・・・・

迫力満点の仁王門
当麻寺
當麻寺(当麻寺、たいまでら)は、奈良県葛城市にある飛鳥時代創建の寺院。法号は「禅林寺」。山号は「二上山」[1]。創建時の本尊は弥勒仏(金堂)であるが、現在信仰の中心となっているのは当麻曼荼羅(本堂)である。宗派は高野山真言宗と浄土宗の並立となっている。開基(創立者)は聖徳太子の異母弟・麻呂古王とされるが、草創については不明な点が多い。
西方極楽浄土の様子を表わした「当麻曼荼羅」の信仰と、曼荼羅にまつわる中将姫伝説で知られる古寺である。毎年5月14日に行われる練供養会式(ねりくようえしき)には多くの見物人が集まるが、この行事も当麻曼荼羅と中将姫にかかわるものである。奈良時代 - 平安時代初期建立の2基の三重塔(東塔・西塔)があり、近世以前建立の東西両塔が残る日本唯一の寺としても知られる。


阿吽の仁王はん

後ろに聳える二上山が美しい~~^^

国宝の梵鐘
無銘ながら、作風等から日本最古級と推定される梵鐘で、當麻寺創建当時の遺物と推定される。2か所にある撞座の蓮弁の枚数が一致しない等、作風には梵鐘が形式化する以前の初期的要素がみられる。鐘楼の上層に懸けられており、間近で見学することはできない。
貴賓がありますね^^

これも、国宝の本堂
曼荼羅堂とも言うそうです。


こちらは、西塔ですが・・・・
東塔・西塔(国宝)
- いずれも三重塔である。東塔は初重が通常どおり3間(柱が一辺に4本立ち、柱間が3つあるという意味)であるのに対し、二重・三重を2間とする特異な塔である(日本の社寺建築では、柱間を偶数として、中央に柱が来るのは異例)。これに対し、西塔は初重、二重、三重とも柱間を3間とする。また、屋根上の水煙(すいえん)という装飾のデザインを見ると、西塔のそれはオーソドックスなものだが、東塔の水煙は魚の骨のような形をした、変わったデザインのものである(ただし、創建当初のものではないらしい)。細部の様式等から、東塔は奈良時代末期、西塔はやや遅れて奈良時代最末期から平安時代初頭の建築と推定される。東西の塔にデザインや建築時期の違いは若干あるものの、近世以前の東西両塔が現存する日本唯一の例として、きわめて貴重なものである。
東西両方の塔が、造ったまんま残ってるのは、ここだけみたいですね。
この両方がいっぺんに見えるところ・・・・

ビューチフルでんな
今回の見たかったところは・・・・
奥の院

この辺は、まだ青葉が残ってましたが・・・・

この本堂の裏に、素晴らしい庭園が・・・
楼門(重要文化財)から西へ進みますと、石彫“くりから龍”を中心に現世を表現した渓流を右手に眺め、スロープをゆっくり上がっていくと浄土の世界が目前に広がります。阿弥陀如来像を中心に数多くの石仏が並び、阿弥陀仏の姿を写す極楽の池“宝池”があり、ニ上山を背景に當麻の自然を存分に取り入れた年中楽しんでいただける浄土庭園です。
こりゃ、また明日~~

日曜日です・・・・
天気も良さそうですし、
どこ行きます???
おしごとのみなさ~~ん・・・・
本日も、笑顔と気合で乗り切りまっしょい!
去年の同日の日記
http://blog.goo.ne.jp/takomusume97/d/20081115
おはようございます!
今日は、何の日??
- 二十四節気・雑節等
- 霜降
- 二十四節気の一つ 旧暦九月中気
- 霜始めて降る
- 七十二候の一つ(52候)。
- 電信電話記念日
- 1869年(明治2年)の9月19日(新暦では10月23日)に、東京・横浜間に日本で初の公衆電信線の架設工事が始められたことに由来する。1950年(昭和25年)に日本電信電話公社が制定。
- 津軽弁の日
- 津軽弁の日やるべし会が制定。 方言詩人・高木恭造の命日。
さて、昨日は奈良へ行ってきました。
毎週のように行ってますけどね
朝、早く平城宮跡は、霧に包まれ幻想的な雰囲気でした。

平城遷都1300年・・・来年ですからね。
平城宮跡も、工事が急ピッチで進んでます。
平城遷都1300年祭 http://www.1300.jp/
http://www.1300.jp/

朱雀門も、幻想的に浮かび上がって・・・

日の出も、しっかり拝めました

今回の目的は・・・・
東京・福岡と出張してはって165万人も集めた・・・
興福寺の阿修羅像さま
”お堂で見る阿修羅”と称した特別展が17日から・・・
早速行ってきました。
土日やと、すごい人なので、せっかく素浪人してるし平日に


お寺さんの紹介は、以前しましたのでパスしまして・・
http://blog.goo.ne.jp/takomusume97/d/20090203
ほんと、興福寺は国宝だらけ、見ごたえありますよ^^

今回は、特別やさかいに、拝観料も高い
大人1500円です。
うちの奥やんが、障害者手帳もってたので、付き添い一人と半額~
ラッキー


平日にもかかわらず、9時前には、この行列・・・
土日が怖いね。
いや~~、並んででも見る価値ありますよ^^
動画でも見て・・・・
http://www.asahi.com/video/news/TKY200910170196.html
美しいですね、見惚れます

是非、見に行ってください。
まずは、ここを見て勉強してから~~
興福寺HP http://www.kohfukuji.com/
http://www.kohfukuji.com/
興福寺の駐車場は900円と高いので、近くの猿沢池あたりが安いですよ~
では、
本日も、笑顔と気合で乗り切りまっしょい!
去年の同日の日記
http://blog.goo.ne.jp/takomusume97/d/20081023
おはようございます!
今日は、何の日??
- 下元(新暦)
- 元々は正月15日の上元、7月15日を中元、10月15日の下元をあわせて「三元」とする中国の習慣が伝わったもの。
- グレゴリオ暦制定記念日
- 1582年のこの日、ローマ教皇グレゴリウス13世がユリウス暦に代わってグレゴリオ暦を制定した。
- たすけあいの日
- 1965年(昭和40年)12月に開かれた全国社会福祉会議で決められた日で、日常生活での助け合いや、地域社会へのボランティア活動を積極的に進めることを呼びかける日。
- 新聞週間
- アメリカで1930年代から行われていた新聞の重要性、必要性を多くの人々に知らせる運動が1940年には全米に拡大。日本では新聞の普及と教育のためにGHQが新聞週間を提唱し、1947年(昭和22年)に愛媛新聞が初めて実施し、日本新聞協会が翌年から実施。当初は10月1日からの1週間だったが、台風シーズンと重なってしまうために1962年(昭和37年)から現在の日程に変更。
- マージャンの日
- (毎月第3木曜)
- 新聞少年の日
- 日本新聞協会が1962年(昭和37年)に制定。10月15日からの新聞週間内の日曜日を「新聞少年の日」「新聞配達の日」と、日本新聞協会が定めている。新聞の宅配制度の基盤となる新聞を配達する人々の労に感謝する日。
- 女人禁制破りの日
- 婦人運動家が提唱。 1867(慶応3)年、イギリス公使ハリー・S.パークが、夫人同伴で、当時女人禁制だった富士山に登りました。
さて、日曜日に訪れた・・・・石上神宮
いしがみ・・・ちゃいまっせ。
”いそのかみ”と読むそうです。


石上神宮(いそのかみじんぐう)は奈良県天理市にある神社。式内社(名神大社)で、旧社格は官幣大社(現在は神社本庁の別表神社)。中世には二十二社の中七社のひとつとされた。
別名、石上振神宮、石上坐布都御魂神社、石上布都御魂神社、石上布都大神社、石上神社、石上社、布留社、岩上大明神、布留大明神、等。付近で立教した、天理教の初期資料で、幕末 - 明治期に地元では『いわがみさん』と呼ばれていた事が判る。伊和大神との関係は不明。
尚、『日本書紀』に記された神宮は、伊勢神宮と石上神宮だけであり、その記述によれば、日本最古設立の神宮となる。
日本最古だそうです・・・

境内には、鶏ちゃんがあっちこっちに・・・

美しいでんな・・・
でもね、ちょろちょろ動くさかいに、ピンボケしまんねん

こちらでは、鶏ちゃんは神の使いだそうですよ


こりゃ、牛やな




楼門の棟木に「文保二年(1318)卯月二十九日、右奉二為 聖朝安穏 天長地久 社頭繁昌 興隆仏法 郷内泰平 諸人快楽一 所レ造如レ件」の墨書銘があり、鎌倉時代末期、後醍醐天皇が即位された頃の建立である。建築は、桁(けた)行二間二尺、梁(はり)間一間五尺、重層、入母屋造、檜皮葺(ひわだぶき)で上層は和様三手先、下層は二手先に組み、斗供間の蟇股と柱頭の天竺様の鼻の繰形に優れたものがある。柱は円柱で、全体の恰好も美しい。この楼門を一名鐘楼門とも称え、縁起書に(「楼門に洪鐘一口を懸、四天王像を鋳あらわせり、楼門前に鶏栖(けいせい)あり、岩上大明神の五大字を題す」)と記し、氏子有事の際、この鐘をついてしらしたようである。

風格ありまんな^^


楼門をくぐると・・・・

永保元年(1081)白河天皇が鎮魂祭のために宮中の神嘉殿を移建せられたものと伝えられ、その構造は壮重雄健で全国に現存する拝殿では最古のものである。文明2年(1470)貞享元年(1684)享保18年(1733)元文5年(1740)寛政10年(1798)安政6年(1859)の修復、上葺等による棟札六枚と共に国宝に指定されている。
国宝なんですね・・・

楼門の向かえ側に摂社。


難しい・・・
漢字ばっかしやがな
もうちょっと、わかるようにしてね・・・

この拝殿は、もと内山永久寺の鎮守住吉社の拝殿を大正3年7月に移建したもので、保延3年(1137)の建立といわれている。形式は割拝殿で中央に一間の通路があり、通路の両方の上には唐破風(からはふう)がつけられている。周囲の左右両側が板戸の両開きで前後両面は素木の格子戸になっている。この拝殿は、度々の改造を経て、現在の形となったといわれている。この変遷は、梁上の蟇股(かえるまた)に表れ、南北両側にあるものは、創建当時の様式である。建物全体は、軽快素朴、優美な感銘を与え現在の割拝殿中もっとも優れ、数少ない永久寺の建物の一つとして貴重な遺構である。
これまた国宝なんですね。

鹿が彫られてる・・・
さすが奈良^^

ここは、三輪明神と並んで、日本でも有数のパワースポット。
鳥居をくぐった瞬間、気持ちがす~~っと

いかがですか?
是非、訪れてくださいね

では、
本日も、笑顔と気合で乗り切りまっしょい!
去年の同日の日記
http://blog.goo.ne.jp/takomusume97/d/20081015
おはようございます!
- 二十四節気・雑節等
- 下弦
- 半月。月と太陽の黄経差が270°となる日。
- 鉄道安全確認の日
- 1874年(明治7年)に新橋で日本初の鉄道事故が発生したことによる。
- 「リンゴの唄」の日
- 1945(昭和20)年、戦後初めて制作・公開された映画『そよかぜ』が封切られた日。並木路子が歌う挿入歌「リンゴの唄」は戦後を象徴する大ヒットとなった。
- ウィンクの日
- 10と11を倒して見ると、ウィンクをしているように見えることから(オクトーバーウィンク)。 女子中学生の間ではやったまじないで、この日、朝起きた時に相手の名前の文字数だけウィンクをすると、片思いの人に気持ちが伝わるんだとか。
- 商店街の日
- (10月第2日曜日
今日は、何の日??
はてさて、すみよっさんの続きをば


住吉鳥居というそうですが・・・
なんかね、柱が四角いんですわ。
普通は、丸いですよね??
住吉鳥居
なるほど・・・・

本殿は、4つあります。
全て国宝だそうです

この門をくぐりますと・・・

第三本宮・・・



その右隣に・・・・






第三第四の奥に・・・・


第二本宮・・・


その奥に・・・

第一本宮・・・



正式には、一番奥の第一本宮から参拝するらしいのですが・・・
あの門をくぐれば、3.4とあるから、どうしても、3・4・2・1の順になりますわ^^
それでも、いいみたいですけどね^^
しかし、工事ばっかし・・・・
がっかりでござった

石舞台・・・
舞楽を奏でるところです。日本三舞台(住吉大社・厳島神社・四天王寺)のひとつでもあり、重要文化財に指定されています。毎年5月の卯之葉神事では、雅びでおごそかに舞楽が行なわれます。
四天王寺さんのほうが、大きかったな~~
こんなところで、すみよっさん終了~~
三連休の中日です。
どこ行かれます??
お仕事のみなさ~~ん・・・
本日も、笑顔と気合で乗り切りまっしょい!
去年の同日の日記
http://blog.goo.ne.jp/takomusume97/d/20081011
おはようございます!
今日は、何の日??
元、体育の日ですね^^
今日も、あっちこっちで運動会~
お父さん・お母さんは、参加するおりには、きっちり準備運動をば・・・

さて、こないだ大阪市内へ行ったので、久しぶりに近くにある住吉っさんに行ってきました。
でもね、なんか、工事だらけで・・・・・
せっかく行ったのに~~って感じでした。

路面電車の停留所の目の前・・・
大阪市内なのに、風情ありまっしゃろ^^

車で走るのは、やや怖いですよ^^
軌道敷の上は、がたがたして、車がつぶれそうです。

危ない~~
電車が急ブレーキ~~
あの車も、右折するんやったら、線路に入ったらあかんわ・・・
路面電車・・・また違った角度から大阪を見れて、楽しいですよ。
一度、乗ってくださいな

住吉大社
住吉大社(すみよしたいしゃ)は、大阪府大阪市住吉区住吉にある神社である。式内社(名神大社)、二十二社、摂津国一宮で、旧社格は官幣大社(現神社本庁の別表神社)。
地元では「すみよしさん」あるいは「すみよっさん」と呼ばれ、また毎年初詣の参拝者の多さでも全国的に有名である。
海の神である住吉三神(底筒男命、中筒男命、表筒男命)と息長足姫命(神功皇后)を祀り、「住吉大神」と総称される。住吉大神宮(すみよしのおおがみのみや)ともいい、当社で授与される神札には「住吉大神宮」と書かれている。大阪の住吉大社、下関の住吉神社、博多の住吉神社、の三社が日本三大住吉とされる。
HP http://www.sumiyoshitaisha.net/
http://www.sumiyoshitaisha.net/

あのでっかい石燈篭・・・・
住吉大社は昔から海上の無事を祈る神様として、万葉集や住吉神社神代記に歌が残っている。
奈良時代の遣唐使派遣の際には、必ず海上の無事を祈願している。
このように海上安全の守護神としての信仰は広がり、海上輸送がさかんになった江戸時代には、運送船業の関係者により、約600基の石燈篭が奉納されている。
なるほど・・・
航海の無事を祈って
600基もあるんですね。



文化やら安政やら天保やら・・・
江戸時代の元号が

びっくりですね^^
すみよっさんと言えば・・・・

太鼓橋が有名なにゃけど・・・

工事中でがっかり・・・

御鎮座1800年・・・・
奈良が、来年で遷都1300年祭でしょ。
それよりも500年前から~
そんな大事な大祭のための工事・・・しゃ~ないね^^

こっちから渡りまっさ^^

他から画像を拝借・・・

ほんと、美しいんですけどね。
また完成したら、行ってきまっさ^^

手洗いから・・・
屋根に、なんか虹がかかってまんな


続く・・・・
では、
本日も、笑顔と気合で乗り切りまっしょい!
去年の同日の日記
http://blog.goo.ne.jp/takomusume97/d/20081010











