オリジナルの「源氏物語」に変更
11月10日21時47分配信 毎日新聞
フジテレビで09年1月から木曜深夜のアニメ枠「ノイタミナ」で放送予定だった、「源氏物語」の世界を描くテレビアニメ「あさきゆめみし」のアニメ化が中止となり、「源氏物語」を原作としたオリジナル作品「源氏物語千年紀 Genji」を制作することに変更されたことが10日、分かった。宣伝を担当するアスミック・エースによると、監督の出崎統さんの制作上の意向のためという。
アニメは当初、79~93年に講談社の月刊マンガ誌「mimi」などで連載された大和和紀さんのマンガ「あさきゆめみし」を原作とする作品を制作する予定だったが、出崎監督の「『源氏物語』をきちんと描きたい」という意向から企画が変更されたという。出崎監督は「誰もが魅入ってしまう『源氏物語』は魔物である。自分自身の手で新しい表現の境地に挑んでみたい」とのコメントを発表している。
のだめ2期は1クールなんですね。
あの毎話必ずうまいところに納まる感じってのが
深夜に観てさあこれから寝るぜって時に非常に心地よかったのですが。
さてそれにしてもいわゆる「原作」以外に原作がないということは
今のアニメのことだからバリンボリンCGを駆使した壮麗なOP(予想)の序盤で
「原作 紫式部「源氏物語」」
とか、さながら「キッスは目にして 作曲:ベートーベン」を彷彿とさせる
なんか壮大なクレジットがされたり、あるいはそのOPの最後には光源氏を中心として
その周囲にあまたの女性キャラをはべらせて画面を引いてOP終了(予想)という段で
画面の下部にちょこんと
「製作 1001・2009 紫式部/「源氏物語千年紀 Genji」制作委員会」
みたいなテロップが表示される構図を一瞬想像してしたり、
挙句の果てには最近オーディオコメンタリーで原作者が登場するケースがあるので
昔よくあった「織田信長の肉声を再現したテレホンサービス」みたいな感じで
妙にメカメカしい紫式部の合成音声で「このシーンはギャグ顔しちゃだめでしょお!」
とか原作者視点で演出にダメを出す構図とかを想像してしまいはからずも興味津々ですよ。
ちなみに源氏物語自体の内容を深く掘り下げてネタにすることが出来ないのは
単純に源氏物語をよく知らないからですよ。
結局古文とかで度々登場する当作に対して、「これは女受けだよなぁ」と思いながら
文法便覧片手に現代語訳を作る作業に終始してましたねぇ。
そういや「女受け」で思い出したけど、いわゆる腐った方々向けのメンアンドメンみたいな
古典ってあるのかなぁ。平安時代のあのなんかねちっこい文学のトレンドから察するに
そういう文学があっても(現代人視点では)おかしくない気もまたするわけですが、
ひとまずなんでもカップリングを作っちゃう(ガチャピン×ムックとかもあるとかw)
腐った方々のことですから、そんな方々のアンテナに引っかかってないところをみると
やっぱりことのほかメンアンドメンの反道徳性的なものは強かったのでしょうか、
ちょっと興味津々ですが別段読みたいとは思いません(笑)
11月10日21時47分配信 毎日新聞
フジテレビで09年1月から木曜深夜のアニメ枠「ノイタミナ」で放送予定だった、「源氏物語」の世界を描くテレビアニメ「あさきゆめみし」のアニメ化が中止となり、「源氏物語」を原作としたオリジナル作品「源氏物語千年紀 Genji」を制作することに変更されたことが10日、分かった。宣伝を担当するアスミック・エースによると、監督の出崎統さんの制作上の意向のためという。
アニメは当初、79~93年に講談社の月刊マンガ誌「mimi」などで連載された大和和紀さんのマンガ「あさきゆめみし」を原作とする作品を制作する予定だったが、出崎監督の「『源氏物語』をきちんと描きたい」という意向から企画が変更されたという。出崎監督は「誰もが魅入ってしまう『源氏物語』は魔物である。自分自身の手で新しい表現の境地に挑んでみたい」とのコメントを発表している。
のだめ2期は1クールなんですね。
あの毎話必ずうまいところに納まる感じってのが
深夜に観てさあこれから寝るぜって時に非常に心地よかったのですが。
さてそれにしてもいわゆる「原作」以外に原作がないということは
今のアニメのことだからバリンボリンCGを駆使した壮麗なOP(予想)の序盤で
「原作 紫式部「源氏物語」」
とか、さながら「キッスは目にして 作曲:ベートーベン」を彷彿とさせる
なんか壮大なクレジットがされたり、あるいはそのOPの最後には光源氏を中心として
その周囲にあまたの女性キャラをはべらせて画面を引いてOP終了(予想)という段で
画面の下部にちょこんと
「製作 1001・2009 紫式部/「源氏物語千年紀 Genji」制作委員会」
みたいなテロップが表示される構図を一瞬想像してしたり、
挙句の果てには最近オーディオコメンタリーで原作者が登場するケースがあるので
昔よくあった「織田信長の肉声を再現したテレホンサービス」みたいな感じで
妙にメカメカしい紫式部の合成音声で「このシーンはギャグ顔しちゃだめでしょお!」
とか原作者視点で演出にダメを出す構図とかを想像してしまいはからずも興味津々ですよ。
ちなみに源氏物語自体の内容を深く掘り下げてネタにすることが出来ないのは
単純に源氏物語をよく知らないからですよ。
結局古文とかで度々登場する当作に対して、「これは女受けだよなぁ」と思いながら
文法便覧片手に現代語訳を作る作業に終始してましたねぇ。
そういや「女受け」で思い出したけど、いわゆる腐った方々向けのメンアンドメンみたいな
古典ってあるのかなぁ。平安時代のあのなんかねちっこい文学のトレンドから察するに
そういう文学があっても(現代人視点では)おかしくない気もまたするわけですが、
ひとまずなんでもカップリングを作っちゃう(ガチャピン×ムックとかもあるとかw)
腐った方々のことですから、そんな方々のアンテナに引っかかってないところをみると
やっぱりことのほかメンアンドメンの反道徳性的なものは強かったのでしょうか、
ちょっと興味津々ですが別段読みたいとは思いません(笑)














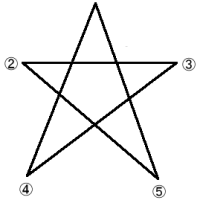
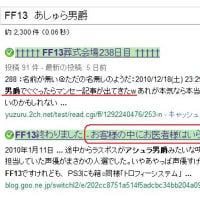




でもまあ出崎監督だから、きっと別物になるんじゃないかとは思ってましたが。
源氏物語は、ハーレムアニメとかギャルゲと同じと思うと分かりやすいですよね。
ツンデレもヤンデレもビッチも清純系もロリも全て取り揃えているので、源氏がモデルのギャルゲがあってもいいとさえ思っているのですが。
ちなみに腐向け目線で考えると「とりかえばや」とかはその要素があるかもですね。
あと、源氏は原作にもホモ描写はあるのですよ。
もちろんあちらの世界には源氏物語をネタにしている方々もいらっしゃいますぜ…
(もっとも国文学士様の前で大層な事は言えませんがw)
しかし改めてそう考えるとユーザの嗜好ってのは
実はこの1000年間殆ど変わらないともいえましょうか。
メンメン描写が既に存在してたことといい…
そしてそれをモチーフにした腐った方々の活動といい…