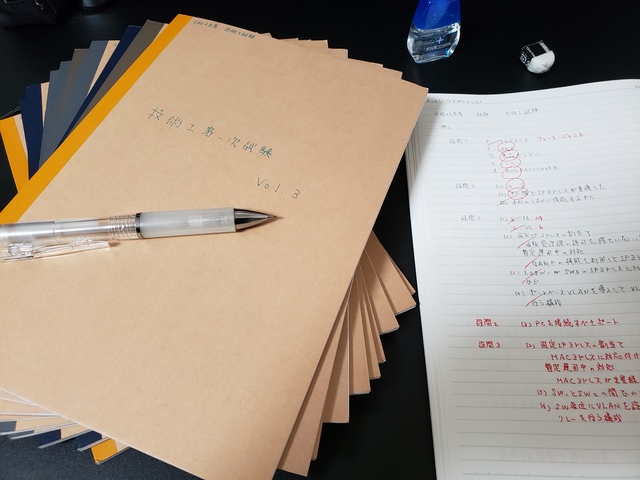2/8(土)は、久々の大雪で、大変だった。
何が大変だったかというと、
この日朝から第三級陸上特殊無線技士試験があったからだ。
行きはそれほど苦なく、試験会場にたどり着けたが、
帰りは散々だった。
だが、試験自体は問題無かったと思う。
解答例が発表されたら、自己採点する予定であるが、多分合格であろう。
頭を切り替えて、全経簿記能力検定3級が2/16(日)に控えている。
先週、Amazonで模擬問題+過去問題集を購入して、現在1回目の模擬試験
を解いてみた。
結果は、89点とまずまずの結果である。
だが、売上総利益の計算は、頭からスコーンと忘れているらしく、
売上高 - 仕入高
で求める傾向がある。
そうではなく、
売上高 - 売上原価(期首商品+仕入高-期末商品)
で求めなければならない。
ポイントは、この計算を商品有高帳から求めることが出来るかということである。
期首と期末の資産と負債情報、売上高、仕入高の情報から売上総利益を
求める問題(試験で言うと、問2あたり、仕訳の次の問題)は、比較的分かりやすい
が、商品有高帳から求める問題は、上記問2の問題を応用した形となるからだ。
まだ、1週間残されているので、しっかりと学習を進めていきたいと思う。
1/26(日)に受験した危険物取扱者試験乙種第2類の結果が、
2/5(水)発表され(てい)た。
結果は、
70%で合格
であった。
これで、危険物取扱者試験乙種は残り1つ(乙種第1類)
のみとなった。
2014年度1発目の合格である。
幸先好調といった感じである。
パラレル学習を習得するために、4つの試験勉強が同時並行
で進んだのと、やはり試験は独特の雰囲気の中で実施される
2点の影響で、点数はまぁ普通といった感じである。
とはいえ、国家試験であることは間違いないし、
国にまた1つ認めてもらえたという喜びに浸りながら、
今週末の第三級陸上特殊無線技士試験に臨みたいと思う。
パラレル学習が進む中、ブログの更新までケアが出来ておらず、
情報処理試験ネタは久々の更新となってしまった。
早いもので、2014年も1か月が終了した。
(こんなカウントの仕方してると、すぐ年をとってしまうのだが、、、)
それはさておき、こちらの状況をいつもの形式で報告したいと思う。
【午前Ⅰ・Ⅱ試験】
システム構成要素(13/17)
ソフトウェア(6/14)
ハードウェア(5/10)
ヒューマンインタフェース(4/4)
マルチメディア(2/4)
※括弧内の数字は、正答数/問題数を表している。
【午後Ⅰ試験】
H16春 問1
H17春 問2
H18春 問3
H20春 問2
【午後Ⅱ試験】
H17春 問2
H24春 問2 × 2回 (論文のブラッシュアップ)
問題文の読み込み
先週より、試験が立て続けにあることから、内容を吟味して学習を進めている。
今回は、
プロジェクトスコープマネジメント
プロジェクトタイムマネジメント
プロジェクト人的資源マネジメント
あたりの学習を進めた。
特に午後Ⅰ試験の問題は、こちらの内容を理解すると共に、午後Ⅱ試験のネタ
集めを目的としたところである。
例えば、自社の要員でなぜプロジェクト要員を計画せず、外部要員を調達する
ことにしたのか?といった問題が、午後Ⅱ試験で出題される。
その時に、自社の要員で本来は賄えるはずが、同時並行する他のプロジェクトに
要員をと取られており、外部要員を調達することとした。
とか、
調達する際に、主観で評価すると評価項目漏れや客観的な判断で、適切な委託先
を選定できなくなるから、チェックリストを設けた
そして、下請法に引っかからないようにするための工夫として、資本金をチェック項目
についかした
など、
使えそうなネタがてんこ盛りである。
結局、午後Ⅰ試験も午後Ⅱ試験も問われる内容はそれほど変わらない。
(当たり前といえば当たり前である。シラバスがあるんだから、、、)
とはいっても、口で言う程簡単ではなく、
午後Ⅱ試験では、良くある抽象的な話から、
具体的な話に落とし込むところにそのむずかしさがあると思っている。
しかも、2時間という時間的制約と問題文と設問の内容的制約が加わるのだから。
だから、事前にしっかりと準備することの大事さを改めて痛感した。
引き続き頑張っていきたいと思う。
いよいよ来週は、第三級陸上特殊無線技士試験日である。
先週は主に法規の問題を解いたが、今週は無線工学の学習に専念した。
学習ポイントは大体つかめた。
①オームの法則
②電力の計算
③合成抵抗と合成静電容量の計算(公式が逆になる)
④送信機と受信機
⑤IDC回路やスケルチなどの用語
①~③は、問題を繰り返すことで頭に叩き込みすることができる。
但し、④と⑤は暗記しないといけない。
現時点での解いた問に対するの正答率は、約88%である。
まずは、弱点を補うことで点数アップを図りつつ、細部にわたって、
試験日までに暗記できるところまで暗記して、試験に臨みたいと思う。
なにげに、油断すると足元をすくわれそうなので、しっかりと対策して、
この試験も刈り取りたいと思う。
以前の(全経簿記能力検定試験3級の学習(その1))記事で、
パラレル学習について記載した。
前回に比べ、習慣化が進んでいるのか、さほど大変という感じはしなくなってきた。
テキストは、
「全経簿記能力検定試験 公式テキスト 3級(ネットスクール)」
「全経簿記能力検定試験 公式問題集 3級(ネットスクール)」
を利用している。
この区分の試験対策本は、はっきり言って上記2つ+過去問題集しか私は見たことがない。
だが、非常に分かりやすく、体系立っていると思う良テキスト+問題集である。
これらの本を利用して学習を進めているのだが、ようやく全てを読破及び解くことが終わった。
こちらも、正答率は約98%位である。
これは、4級で築きあげたベースに、3級で追加となる勘定科目毎の仕訳と精算表作成前の
決算整理仕訳をしっかりと理解してきたからだ。
逆に言うと、これだけしっかりと理解すれば、
①仕訳問題で点が取れる。
②精算表や貸借対照表、損益計算書を作成する際に、
決算整理仕訳分だけの要素を加味して作り上げれば、
まるっと点数がもらえる。
やはり、基礎は大事だ。
土台の上に、追加で新しい知識を載せていくのは、そこまで難しくない。
少しずつ理解すれば、3級レベルの合格点に簡単に届くからだ。
本日、過去問題集でも買いに行って、試験に慣れておき、
確実に刈り取れるようにしていきたいと思う。