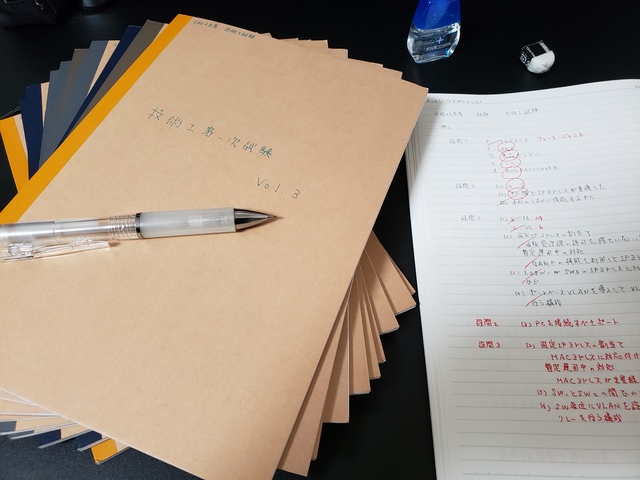今日はまたまた夜間作業のため、自宅でのんびり過ごしている。
今週からは本格的に論文対策として、手書き論文を書きだした。
早速本日書いてみた。
テーマは、「プロジェクト・スコープ・マネジメント」である。
私が理解した内容を簡単に説明すると、
プロジェクトが立ち上がってから、様々なフェーズで変更要求が発生するが、
その変更を、予算・品質・納期などの様々な観点から判断して要求を取込む
か否かを判断して、管理すること
である。
要は、担当者レベルで勝手に要求を受け入れたりすると、想定外に影響が大きく、
納期遅延や品質低下、予算超過を招くから、しっかりとPMが管理して下さいね
ということである。
情報処理技術者試験で求められるのは、上記で説明した一般論(抽象的な内容)
を具体的に記述することである。
その具体的にというのが一番難しいのだが、問題文の状況を踏まえて、あなたは
どのようなプロジェクト遂行中に発生した変更要求を取込むもしくは取り込まなかった
のかを記述しなければならない。
最低限、以下の要素は必須である。
・回答(設問に対する解答)
例:私は○○が必要だと判断した。
・根拠(なぜそのような回答となったのか)
例:なぜならば、○○を実施しないと△△となるからである。
・具体例
例:例えば、□□を行うことを怠ると、想定外の作業が発生し、△△になってしまう
上記の3つを含めた形で、プロジェクト・スコープ・マネジメントの論述をしようとすると、
プロジェクト遂行中に発生した変更要求に対して、
(回答)私は、変更管理委員会(以下、CCB)に変更要求の受け入れ可否の判断
をかけるようにした。
(根拠)なぜならば、担当者ベースで変更要求を受け入れると、納期・品質・コスト
の影響が発生してしまうからだ。
(具体例)例えば、担当者は軽微な要求だと思って受け入れた結果、システム全体
に影響を与える改修であることが判明し、想定外の作業が発生すること
で予算の超過や納期遅延が発生するなどの問題が発生することが
考えられるからだ。
だから、私はCCBを通じて、プロジェクトで変更要求の受け入れ可否を判断すること
とした
などである。
上記の例は、かなりチープな内容であるが、それでもこれに気付かない受験者は結構
多いそうである。
なので、論文対策実施時は、上記の3要素を常に意識した論述をするように、常日頃
から意識していきたいと思う。
今週は、色々と学習が進められた。
今週からは、いつものフォーマットに従って、
進捗報告をしてみたいと思う。
【午前試験】
240/345(69.6%)
【午後Ⅰ試験】
H25春 問3
【午後Ⅱ試験】
過去問題の読み込み
平成7年~平成18年(3問×12年=36問)
論文対策本
1巡目完了
大体、70%位は現在の知識でカバー出来てことになる。
弱点分野(基礎理論、コンピュータシステム)も把握できたので、
ここら辺を強化すれば、75%以上は点数が確保できるであろう。
今回で3回目となるプロジェクトマネージャ試験であるが、
そろそろ合格したい。
だが、合格したいと思う気持ちが強くなればなるほど、
プレッシャを感じる方も多いのではないだろうか?
まずは、プロジェクトマネージャの基礎をしっかりと体に
叩き込まないと、変化球に対応できない。
私の経験上、間違いなく言えることは、
本番試験では、いつもはやらかさないようなミスを犯したり、
精神的に追い詰められたりする。
当然である。
準備をしていっても、それが的を外されるのだから。
的を外されても、午後Ⅰ試験では90分、午後Ⅱ試験では120分
で問題を理解し、設問に答えることをしなければならない。
この時、最後に信じることができるのは、自分自身が今まで学習し、
頭に叩き込んだ内容である。
これだけは裏切らない。
努力した分だけ自分に返ってくる = 答案用紙にアウトプットできる
と思っている。
だから、しっかりと準備を進めたいとおもう。
基礎を抑えるレベルまでもっていくことが、
当面の学習目標である。
来週からは、実際に論文を書いてみよう!!
今日はまたまた夜勤のため、自宅でのんびりしている。
午前試験対策も後半を迎えてきている。
現在は、約450問中300問解答。正答数は207問であるため、
現時点での正答率は、69.0%である。
ゆっくりと正答率が上がってきている。
ここで、ひとつ感じたことをお伝えする。
高度区分を1つでも保有していた受験者が、午前Ⅰ試験免除の
有効期限切れにより、午前Ⅰ試験から受験しなければならなくなった
ケースを考える。
この時、大半の人は、午前試験対策をやらねばと思うだろう。
ここに注意した方が良いのでは?と思う落とし穴がある。
それは、午前試験対策本の最初の方は、
基礎理論 や コンピュータシステム
などの、比較的学習してから時間が経過した分野が掲載されている
ケースが多い点である。
ここで正答率が上がらず、行き詰ると、折角対策本の中盤以降に
現れる自分が得意とする分野(例えば、合格した試験区分に該当する分野や
直近まで受験対策をしていた試験区分に該当する分野)が待ち構えてて、
点も稼げるのに、やる気の低下から、学習をやめてしまう。
このようなことって、以外に多いのではないだろうか?
実際の情報処理技術者試験の午前Ⅰ試験は、所詮30問しか出題されず、
基礎理論やコンピュータシステムに関する問題もせいぜい2~3問程度だと
割り切れば、学習当初点数が取れなくても、全然問題ない。
まずは、過去問題を解くことで、ぼんやりと傾向がつかめる。
そこから、確実に点が取れる分野とそうではない分野を切り分けることで、
効率的に学習が進められる。
具体的には、選択肢の内容がすべて理解できているものは、もう解くのをやめて、
正答できなかった問題に対して、午前試験対策本などで知識を補強する
といった感じだ。
高度区分のメインどころは、
午後Ⅰ試験 と 午後Ⅱ試験
だと思っている。
いかに、
「午前試験は効率良く合格点を取り、午後試験の対策を打つか」
だとも思っている。
そして、その試験区分の午前Ⅱ試験~午後Ⅱ試験までは、問われ方が
違うだけで、求められている知識はそれほど変わらないと思う。
なので、午前試験の一部で躓いて、そのあと学習が進まないのは非常に
もったいない話だと思うので、もしこのような悩みを抱えている方がいれば、
是非参考にして頂ければと思う。
ちなみに、私はブログを通じて、論文試験対策を行っている。
まだまだの部分は多々あるが、
・主張
・根拠
・具体例
・入れられるところは、定量的数値を書く
を意識してアウトプットし続けることで、この癖を自然と身につける作戦である。
「プロジェクトマネージャの学習(その2)」から2週間ぐらいが経過してしまった。
この間に、午前試験対策を実施。
現在は、約450問中217問解答。正答数は138問であるため、
現時点での正答率は、63.6%である。
微妙な感じである。
分野別にみると、
基礎理論
コンピュータシステム
が苦手のようだ。
逆に、私はつい先日までSAの受験対策をしていたこと、SCとDBに合格している
ことから、
データベース
ネットワーク
情報セキュリティ
システム開発
関連は、正答率が高かった。
やはり、高度区分を受験すればするほど、基礎理論とコンピュータシステムからは
遠ざかっていくため、自分の弱点を見直すことが出来た。
ちなみに、エンべデッドスペシャリストなんかだと、基礎理論やコンピュータシステム
関連から非常に良く出題されることから、この試験区分を受験することもおもしろそうだ。
まずは、春試験にPMを受験するため、あくまでも午前対策としての学習にとどめるが、
またひとつ楽しみを見つけた気がした。
やはり、過去に分からなかった部分でも、自分自身のスキルが上がるにつれて分かる
ことが増えてくる。
例えば、コンピュータシステムや基礎理論を知らないと、組み込みシステムのような制約
の強い基板上に、システムを構築するには、このような基礎知識が大前提にあって、
どのように効率良くリソースを使って実現するかなどが重要になってくるなどだ。
(漠然としているが、、、)
引き続き、学習を進めていきたいと思う。
今日からは、論文対策も開始した。
やることがたくさんあった方が、実は効率良くダラダラ感無く学習が進められるため、
しっかりと集中して取り組んでいきたいと思う。
平成25年度 秋期 情報処理技術者試験でシステムアーキテクトを受験した。
ここで、ひとつ課題が明らかになった。
以前にも
で記載したが、午前試験で問われる知識レベルが低下している。
そこで、午前Ⅰ試験でも午前Ⅱ試験でも対応できるように、
今回は、午前レベルの知識を再習得することに決めた。
早速、
「情報処理教科書 春期 高度試験午前Ⅰ・Ⅱ 2014」
を購入。
問題数は、ざっくり450問位だろうか?
現時点で80問位解いてみたが、
案の定、45%位の正答率しか取れなかった。
無理もない。
今までは、午前Ⅰ試験を免除し続けてきたため、
基礎理論やコンピュータシステムのレベル3程度の問題から
長年遠ざかっていたからだ。
そして、この分野の問題は、私の中では苦手なレベルである。
しっかりと学習を進めて、自分自身の下地を築き上げたいと思う。
ただ、以前と違うこと。
それは、新しい知識を習得することへの楽しさが以前にも増した点だ。
しっかりと自分の弱点を把握して、そこからしっかりと頭に叩き込み、
平成26年度 春期 情報処理技術者試験に臨みたいと思う。
ちなみに、タイトルにもある通り、次はPM受験を予定している。