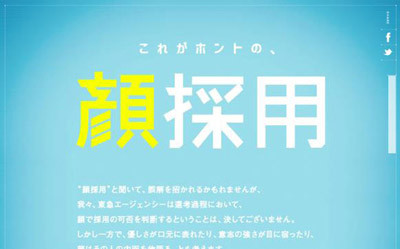「10日で大阪の治療院を開業して3年、本当にいろいろありましたが、これを機に故郷の治療院も再開させたい」と語るのは、大阪市東住吉区「かとう鍼灸治療院」の院長、加藤大助さん(44)。「大阪の」という言葉があるが、本来であれば故郷で治療院を続け、大阪に住んで治療院を開業することはなかった。あの東日本大震災の原発事故が起きなければ。
家族は全員無事も近くで原発事故が
[写真]友人らに支えられここまで来れたと話す加藤大助さん(右)と清恵さん夫妻=大阪市東住吉区で
福島県南相馬市で鍼灸治療院を経営していた大助さんは、妻の清恵さん(40)と娘3人と地元で暮らしていた。同院は内科医をしている加藤さんの父親が所有する家の敷地内に建てられており、みんなで仲良く暮らしていたという。「京都にある大学で鍼灸などを習い、大阪府寝屋川市内でも学んだことを生かし2年ほど働いてました。地元へ戻って病院に勤務。その時に受付をしていた妻と知り合い17年前に結婚し、鍼灸院を開業して生活していたんです」
3人の娘に恵まれ、愛する地元で幸せに暮らしていた。だが、そんな暮らしを突然、大きな揺れの悪夢が襲った。2011年3月11日に発生した東日本大震災だった。鍼灸院の休診時間で横になっていた時、突然の激しい揺れに目が覚めた。「最初横揺れが起こり、すぐにおさまると思ったらそれが縦揺れに変わって、はめ込み式のタンスから中の物が全部出てきました」
一方、清恵さんは自宅リビングで当時3歳の3女とすごしていた。最初の揺れで庭へ避難。揺れがおさまり、リビングに戻ると、自分と3女がいた場所に大きな食器棚が倒れガラスも散乱していた。
自宅の中はめちゃくちゃになったが、家族は全員無事だった。しかし、テレビのニュースの内容に驚くばかり。そして、距離にして約20キロの地点にある東京電力の福島第一原子力発電所の事故を知り、大助さんは着の身着のままで妻子とともに車で遠くの方へ避難した。
思うように避難できず、大阪の友人から連絡
テレビやラジオから聴こえる被害状況や原発事故の内容を聞き、妻子や妻の妹家族と車で避難。「とにかく遠くへ」と福島市内を目指した。「原発事故の情報や被ばくされた方の数が増えていると聞いて、子どもたちを守らなくてはと必死で逃げました」。最初は宮城県の仙台市へ行こうとしたが、津波被害のため道路が通れないと聞き行き先を福島市内にしたという。
だが、福島市内も混乱状態で車も動けない。市民会館へたどりついたが、そこはもう避難してきた地元の人など多くの人が集まっていた。小さな子どもがいることから、大助さんはほかへの避難を模索。そこで「福島空港が避難所として開放されている」と聞き、即座に向かった。
同空港へ着くと、臨時便に行列ができていた。「飛行機での避難」を考え、親類が静岡県内に別荘を持っていたためそこへ向かうことを考え、徹夜で行列に並び東京へのチケットを手に入れた。だが、その日に長野県でも地震が発生。清恵さんや子どもたちも怖かったため、再び避難先を探した。
そんな時、大学時代の同級生の妻が「大阪で文化住宅をキープしたよ」と連絡をくれた。だが、2日以内に本人がサインしないとそれが無効になってしまう。そこで、清恵さんと子どもらが先に大阪へ向かった。大助さんは両親のもとへ戻ろうとしたが、同級生が「奥さんや子どもさんが来ても、なにもしらない大阪ではわからないだろうから一緒に来てくれ」と助言してくれたため、再びチケットの行列に並び翌日に大阪へ向かった。
家や仕事を世話してくれた大阪の友
[写真]故郷・南相馬に残した治療院の再開を目指すと語る加藤大助さん
大阪市住之江区のいわゆる文化住宅に来たが、風呂・ガスともにナシの状態。「住めるだけでもありがたい」とすごしていたが、子どもたちは突然の生活環境の違いに辛さを覚えていた。そんな時、父親がマンションを持っているという同級生が「ワンルームが隣同士で2部屋空いたのでおいで」と声をかけてくれた。家族5人でそこへ引っ越し、約8か月すごすことになる。
住む場所は確保。だが、収入がないため大助さんはコンビニやガソリンスタンドのアルバイト求人などに申し込もうとしたが、学生時代の同級生らが「鍼灸の仕事は、手を使わなかったら感覚がなくなってしまう。なんとかするから」と声をかけてくれ、3~4か所で同業者の手伝いをできるように段取りを組んでくれた。
そして、その手伝いであちこちへ移動し、たまたま大阪市東住吉区の地下鉄田辺駅を利用しようとした時、目の前のビルの窓にあった「空店舗」の看板が目に入った。
その瞬間「ここでならやれるかもしれない」という直感がよぎり、すぐに申し込んだ。「子どもたちのことを考えると、南相馬の現状では連れて帰れない。自分だけが南相馬へ帰って治療院を再開することもできない。もうここで暮らしていくしかないと考え、腹をくくりました」
避難から約1年たった2012年3月10日、東住吉区で「かとう鍼灸治療院」を開業した。地下鉄・田辺駅の真ん前ということもあり、今では地元の人が訪れ、中には南相馬で通っていた人が来てくれることもあるという。そして、きょう10日で開業から丸3年を迎えた。子どもらも当初は環境の変化に動揺したこともあったが、今では元気に学校へ通っているという。
大阪で開業3年の決意・南相馬の治療院を再開へ
「今こうしていられるのは、支えてくれた友人たちのおかげです」と大助さん。3年がたち、地元にもとけこんでいるが「まだ正直、食っていくのが精一杯なんで頑張らなければ」と日々奮闘。清恵さんも子育てをしながら、受付で支えてくれている。「ほんと妻や子どもたちにも感謝です。よくあの状況で文句ひとつ言わず頑張ってくれたので」
開業3年を迎え、新たな決意も口にした。「やはり故郷の治療院のことは、1日も忘れたことがありません。多くの患者さんに支えられてましたし。だから4月から、南相馬の治療院再開に向けて動こうと思うんです」
4月からは月に1週間ほど南相馬へ戻り、治療院を任せられる人を探し再開させたいという。そして、大阪と南相馬で治療院を回していくのが目標だという。「父親は内科医として故郷へ残り、一時期はやむなく東京へ避難したけど、避難指定解除になったら即戻り患者さんを診てるんです。僕もこの3年を機に再開に向けて頑張りたい」。再開の計画を聞いた地元の人たちからは「待ってるよ」という声もあるという。
今でも経営は大変だが「一歩ずつ進んで行かなければ。子ども3人をしっかり育てなくちゃいけないし」と前向きで気合い十分の大助さん。きょうも故郷への想いを胸に患者さんの治療にあたる。
地図URL:http://map.yahoo.co.jp/maps?lat=34.62815600045654&lon=135.52584563912777&z=16
本記事は「THE PAGE」から提供を受けております。
著作権は提供各社に帰属します。