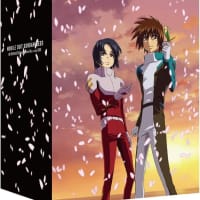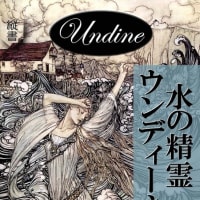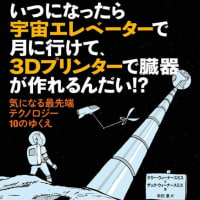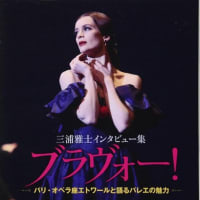何度聴いても、なんてカッコいい曲なんだろう
ということはともかくとして、ボウイのこの曲がラジオから流れてきて久しぶりに聞いた時――「♪疑うことをいつからやめたのさ、セオリー通りじゃ、Oh!No No!とても堪らないぜ。鏡の中のマリオネット、あやつる糸を断ち切って。鏡の中のマリオネット、自分のために踊りな」……って、なんだかまるで未来のアンドロイドのことを歌ってるようにも聴こえるなあ――なんてつい、思ってしまったわけです(^^;)
それで、チェスでも将棋でも碁でも人間に勝てるようになったAIでも、いわゆる「サリーとアン問題」を解くまでにとても時間がかかった――ということだったと思います。このことは前にもどこかで軽く触れた記憶があるのですが、それとは少し別のこととして、「アンドロイドは自我に目覚めるか」、「仮に目覚めたとして、人間はそのことに本当に気づけるか」という問題があると思うわけです。それで今回はそもそも、「では人間はいつ自我/自意識(セルフアウェアネス)に目覚めたのか」ということについて、ちょっと書いてみたいと思いましたm(_ _)m
今から約二百万年前、わたしたち人類のご先祖さまであるホモ・ハビリスが地上に現れた時……彼らは「賢い脳は持っていたが心は空白」だったそうです。ホモ・ハビリスは230万年前から140万年前にかけて生きていたと考えられ、脳が大きくなったことでアウストラロピテクスより利口だったとか。ホモ・ハビリスは打製石器によって動物を狩るなど、手先のほうも相当器用だった。でも、わたしたちのイメージとしては――このくらいですでに、「ウホウホ? 」くらいのことは互いにしゃべって意思疎通をはかっており、自我の芽生え、心のようなものはすでにあった……みたいに勝手に想像しますよね(^^;)
」くらいのことは互いにしゃべって意思疎通をはかっており、自我の芽生え、心のようなものはすでにあった……みたいに勝手に想像しますよね(^^;)
なので、「賢い脳は持っていたが心は空白」と言われると、何かこう「ん? 」と思ってしまう。でも、仮説としてはどうも次のようなことらしいのです
」と思ってしまう。でも、仮説としてはどうも次のようなことらしいのです

>>昔々、人間の祖先となる動物がいた。彼らには意識がなかった。それは、これらの動物が脳を持っていなかったということではない。彼らが物事を知覚し、賢く、複雑な動機によって突き動かされたのは確かで、彼らの内部を調節するメカニズムは多くの点で私たちのものと変わらなかった。だが彼らには、そのメカニズムを覗きこむすべがなかったと言われている。彼らは賢い脳を持っていたが、心は空白だった。彼らの脳は感覚器官から情報を受け取って処理しただろうが、彼らの心は、それに伴う感情をまったく意識しておらず、彼らの脳は空腹感や恐怖などに駆られただろうが、彼らの心は、それに伴う感情をまったく意識しておらず、彼らの脳は自発的な活動を企てただろうが、彼らの心は、それに伴う意志をまったく意識していなかっただろう……。ということで、人間の祖先となる動物たちはそんな風に暮らし、自分自身の行動に対する内なる説明にまるで気づいていなかった。
「賢い脳を持ってはいるが、心は空白」は、ホモ・ハビリスの本質を捉えているようだ。
(「神は、脳がつくった」E・フラー・トリー先生著、寺町朋子先生訳/ダイヤモンド社より)
さて、アンドロイドが自我に目覚めるの「自我」というのはようするに、自己認識能力である――ということを先にちょっと書いておいて、お話を進めたいと思いますm(_ _)m
ホモ・ハビリスの次の進化段階がホモ・エレクトスで、こちらは「自分がわかる自己」という種だった模様。ホモ・エレクトスはホモ・ハビリスよりも大きな脳を持ち、動物の皮を衣服として用いたり、火を操っていたと言います。また、互いに助けあって共同生活を営んでいたらしい……と同時に、共同での狩りや生活のためにはなんらかの形によるコミュニケーションが必要だったと思われるものの、この当時言語がどの程度発達していたかは活発な議論が今も続いているとか。
さて、ホモ・エレクトスはホモ・ハビリスよりもさらに高度な大型動物を狩るための木を削った槍を作り、火を制御し、アフリカを出てイギリスからインドネシアにまで進出したらしい(スゴイ!! )
)
そして、この段階におけるホモ・エレクトスの「自己認識」がどのようなものだったかなのですが、そのあたりの進化は緩やかなものだったのではないか……とのことです。そもそも自分を認識するとは何かというと、なんか当たり前すぎるほど当たり前な気もしますが、自己認識=「私が存在していることがわかること」、「『私がいる』と感じること」と定義されるとか。
とはいえ、この自己認識がなければ他者認識というものも生まれないわけで、そうした意味でまず「わたし」がいなければ、「あなた」という存在もありえない……ということでもある。そして、ホモ・エレクトスは自己認識を持っていたと思われるが、他者が何を考えているかについてまではよく気づいておらず、自分について内省的に考えることもできなかった――という段階だったそうです。
さて、次に古代型ホモ・サピエンス(ネアンデルタール人)ですが、小学生か中学生くらいの頃に、「ネアンデルタール人は死者に花を手向けるなど、優しい心を持っていた」みたいに習った記憶のある方は多いと思います。ここで人類は「思いやりのある自己」を持つまでに進化したらしい


ここからようやく、「サリーとアン課題」について引用させていただこうと思いますm(_ _)m
>>子どもに心の理論があるかどうかの評価に用いられる標準的な筋書に、「サリーとアン課題」というものがある。この課題では、絵か人形を用いて、子どもたちに次のような場面を見せる。部屋にサリーとアンがいて、部屋にはボール、蓋つきの籠、蓋つきの箱がある。サリーがボールを籠に入れて部屋を出ていく。サリーがいなくなってから、アンがボールを蓋つきの籠から取り出して蓋つきの箱に入れる。その後、サリーが部屋に戻ってくる。ここで子どもたちは質問される。サリーがボールを探すのはどこでしょう?
この問いに正しく答えるためには、子どもはボールが箱に入っていることを知っていても、サリーはアンがボールを移し換えたのを見ていないので、ボールが籠に入っていると誤って思いこんでいることを理解しなくてはならない。このように他者の心を推測することは一次の心の理論と呼ばれる。
(「神は、脳がつくった」E・フラー・トリー先生著、寺町朋子先生訳/ダイヤモンド社より)
ええと、チェスや将棋や碁の世界においては、人間の名手が相手でさえ勝ちまくったAIですが、この「心の理論」においては、なかなかアンの持っている箱の中を探すまでに至らなかった……ということなんですよね。普通であれば、自分がいない間にアンがどこか別の場所へ隠したと疑うことくらいは誰でもするし、そちらを調べようともすると思う。でも、AIはしまったはずの場所にボールがなくても、アンの箱を調べようとまではしない――ここを越えるのにAIはとても時間がかかり、その後ディープラーニングによって進化したところ、ようやくこの段階を越えることが出来たのみならず、ChatGPTのように賢くなった……ということでした
さて、ネアンデルタール人についてのまとめ

>>およそ20万年前には、ホミニン(ヒト族)のネアンデルタール人は現代ホモ・サピエンスより大きな脳を持っていた。彼らは利口で、自己認識も他者認識も身につけていたらしい。両方の能力を持ったおかげで、ネアンデルタール人は食物の獲得や交戦、取引、子孫作りにおいて進化的にかなり有利になっただろう。そのわけは、彼らが他者の行動について考えたり予測したりする能力を持っていたと考えられるからだ。
しかしネアンデルタール人には、自分の考えについてまとめるための内省能力や、過去と現在の事細かなことを活かして将来の計画を立てる能力が、まだ欠けていたようだ。
10万年前には、ホミニン(ヒト族)が類人猿の祖先たちから分かれて590万年ほどが経っていた。それは、分岐から現在に至る期間の99%近くを占める。残りの1%あまりにあたるわずか10万年で、ホミニンが、神々を祀るためのアンコールワットやシャルトル大聖堂などの記念建造物を築き、戯曲の『マクベス』やオラトリオの『メサイア』を書き、月まで飛行することなど、ありそうもないではないか?だが驚くべきことが起ころうとしていた。
(「神は、脳がつくった」E・フラー・トリー先生著、寺町朋子先生訳/ダイヤモンド社より)
では、次が初期ホモ・サピエンスなのですが、>>「ホモ・サピエンスの人口はネアンデルタール人よりはるかに速く増えた」とのことで、「ネアンデルタール人が、新たにやって来た隣人たちにとてもかなわなかったのは明らかだ」。さらに、「ホモ・サピエンスが繁殖で成功を収めたのは、「仲間のあいだで賢い個体がさらなる賢さのために絶えず選ばれるという、とめどない圧力」があってのことだった……ということらしく。
初期ホモ・サピエンスは、ネアンデルタール人よりももっと向こう、インドネシアより先を目指したのみならず、貝殻の装飾品を身に着けたり、体に装飾したり、体にフィットした服を着たり……「他者から自分がどう思われているか」を意識していたのではないかと推測されるということでした(こうしたことがさらに進化した我々人類の間において、「グッチ」や「カルティエ」といった品を身に着けることに繋がっているのではないか……と考えるとなかなか面白いのでないでしょうか・笑)。
そして、この「自分が他者からどう思われているか」というのがようするに、「自分の心を見つめる自己」(内省的自己意識)ということだそうです。
>>子どもは、「サリーとアン課題」によって示されるように、四歳ごろから他者の考えを意識し始める。そして、少なくとも一部のホミニン(ヒト族)が、やはりこの能力をおよそ20万年前に獲得し始めた可能性がある。その次のおもな認知能力は、子どもが六歳ごろから身につけ始めるもので、一般に二次の心の理論と呼ばれる。
「二次の心の理論」とは何を意味するのだろう?「サリーとアン課題」では、サリーが部屋を出ていったあとに、アンがボールを籠から取り出して箱に入れた。だから、ボールを移されたところを見ていなかったサリーは、ボールが籠に入っていると思っていた。そして、「サリーは、ボールが籠に入っていると(誤って)思っている」、とアンは思っていた。これが「一次の心の理論」、すなわち、他者が考えていることを認識すること(「Aさんは〇〇と思っている」、と考えること)だ。
しかし、もしアンが知らない内にサリーが窓から部屋のなかを覗いており、アンがボールを籠から取り出して箱に入れるのを見ていたとすると、状況は変わる。「サリーとアン課題」では、子どもにこんな質問が出される。「アンは、サリーがボールをどこで探すと思うでしょう?」。これは「二次の心の理論」を測定するテストだ。なぜ「二次」なのかと言えば、ある他者が考えていると別の他者が考えていることについて考えること(「Aさんは〇〇と思っている、とBさんは思っている」、と考えること)が含まれており、情報の階層が一つ増えているからだ。
今あげたケースでは、アンは、ボールを箱に移したときにサリーが窓から部屋のなかを覗いていたのを見ていなかったので、「サリーはボールが籠に入っていると思っている、とアンは(誤って)思っている」ということを、子どもは理解しなくてはならない。ほとんどの子どもでは、六歳くらいにならないと、この認知能力の獲得が始まらない。
さらに高次の心の理論を持っているかどうかについて、子どもを調べることもできる。これまでの筋書を使えば、たとえば次のような展開が考えられる。もし、アンがボールを籠から箱に移すのをサリーが窓から覗いていたことを、サリーの知らない内にアンが気づいていたら、どうなるか?この場合、「サリーは、ボールが箱に入っていると思っている」とアンは思うだろう。なぜなら、ボールを箱に移したのをサリーに見られたからだ。
しかし、サリーは窓から部屋を覗いたときにアンから見られていたことを知らなかったので、「サリーはボールが籠に入っていると思っている、とアンは思っている」とサリーは(誤って)思うだろう。心の理論の筋書は、当事者の一人がもう一人について誤って思っている情報をつけ加えることによって、さらに複雑になることもある。
この分野の研究者によれば、一次の心の理論は、他者が考えているとある人が考えることの単純な人間のやり取りを表すものだが、「それでは社会的交流を十分に捉えることはできない」という。社会的な会話のほとんどには、「人びとの考えについての、ほかの人びとの考えを考慮したり(二次的信念)、さらには、人びとの考えについての、ほかの人びとの考えについての、人びとの考えについて考えること(より高次の信念)を考慮したときに初めてきちんと理解される心と心のやり取りが含まれる」。これが、きわめて複雑な社会的交流の中核をなすものだ。
二次の心の理論を身につけるためには、自分を対象として見ることが求められる。それは、単に鏡を見て自分を認識するということではなく、自分がほかの人びとにとってどう見えるか、自分がほかの人びとからどう見られるか、さらには自分がほかの人びとからどう見られるかについて自分がどう考えるかについて、考えることができるということだ。それには、自分について考える自分について考えることが含まれる。要するに、それは内省的自己意識ということだ。
(「神は、脳がつくった」E・フラー・トリー先生著、寺町朋子先生訳/ダイヤモンド社より)
さらにここからヒトは、現在のわたしたちである「現代ホモ・サピエンス~時間を認識する自己~」へと進化してゆくわけですが……いわゆる現代病の根のあたりにあるものは、初期ホモ・サピエンスが進化して獲得したもの――そのあたりから生じているような気がしませんか?(^^;)
貝殻などで身を飾ったりしていたということは、衣食住に関して若干余裕がないと考えたり作ったりも出来ないことでしょうし、自分の体にフィットした服を着たりするようにもなってきたということは……このあたりからだんだん、たとえば金ならぬ「物を持ってる奴」と「あまり持ってない奴」とにちょっと階級が分かれるなど、こうしたことが今わたしたちの間にもある貧富の差の根源あたりにありそうに思うと、なかなか「ふうむ」と考えさせられるところがあるような気もしたり。
また、「人にどう見られるか・思われるか」と気にしだしたのがこの頃だとすれば――いわゆる我々の間に蔓延している現代病、「そんなつもりで言ったんじゃないのに、こう誤解された 」、「わざと悪いほうに取られて言いふらされた
」、「わざと悪いほうに取られて言いふらされた 」など、「あの人にこう思われているらしい
」など、「あの人にこう思われているらしい 」、「そんなこと思ってないのに、こう思っていると思われている」など、人間関係における「♪ややこしや~」問題は、大体のところこのあたりからはじまってたんじゃないかな~なんて(^^;)
」、「そんなこと思ってないのに、こう思っていると思われている」など、人間関係における「♪ややこしや~」問題は、大体のところこのあたりからはじまってたんじゃないかな~なんて(^^;)
なんにしても、「神は、脳がつくった」は、人間が神を創りだすにはそこまでこのように脳が進化しなければならなかった……という過程について語られている本であって、決してAIに関しての本ではないものの、わたしが個人的に思うに――現在のAIが人間でいうところの「一次の心の理論」を乗り越えた結果、ChatGPTのように賢くなったのだとしたら、次なる課題はもしかしてこの「二次の心の理論」を得ることなのかなって思ったんですよね。そして、もしAIやアンドロイドがこの「二次の心の理論」を得ることが出来たとしたら、「彼らはデジタルゾンビではなく、確かに心を持っている」……というのか、果たしてそのことを否定できるのか、していいのか――ということが問題になってくるのではないかと、そのように思った次第であります。。。
ただ、わたしが思うにですね……イアン・マキューアン先生が『恋するアダム』の中で描いておられるように、アンドロイドさんたちはこの人間の世の醜く穢れたありように絶望し、自ら命を絶つというのか、機能停止に陥る、とにかく初期モデルの間でそのようなことが続出した場合、「彼らをさらに進化させねばならぬ」と人間が考えることが果たして正しいことなのか――そうした問題も出てくるのではないかと、そんなふうに思った次第であります
それではまた~!!
永遠の恋、不滅の愛。-【13】-
ロドニー・ウエストの死体が海岸に浮かんでいるのを発見したのは、アーサー・ホランド博士だった。ホランド博士はクリストファー・ランド博士の死後、数日はその死を悼むように過ごしていたが、その後は再び海岸沿いのホワイトサンドを走ったりするようになり――早朝、ホランド博士がランニングしていると、壮年の男性が倒れているのを発見したわけだった。
ロドニーの体は何度となく波に洗われているところで、発見時、すでに息はなかったものの、ホランド博士は医師として心臓マッサージや人口呼吸など、蘇生措置を行い……それからハッとしたということだった。クレイグ医師の地下の医療室に救急医療カプセルがあったのを思いだし、一秒でも速くそちらへ搬送できれば助かる可能性が万にひとつはあるかもしれない――そう考え、ホランド博士は大急ぎでホテルのほうへ戻ってきた。
話を聞いたミロスは、ボーイのルカとマルスに担架を用意するよう指示し、筋骨逞しい黒い肌の彼らはホランド博士の案内で、ロドニーの体を急いでクレイグ医師の元まで運んだという。だが結果は、ロドニーがおそらくは断崖のどこかから身を投げ、五時間以上は時が経過していたろうというものであり……心臓が停止して二~三時間以内であればどうにかなった可能性もある。だが、彼の肉体はすでに死を迎え、蘇生するのは不可能な段階に入っているということだった。
実をいうとこの前日の夜、ロドニーと最後に過ごしていたのは俺だった。俺はここのところずっとそうだったように、あの三老人についてこうした可能性もあればああいった可能性もあるといったように考えたり、あるいはそのことをランド博士の死と結びつけ、突飛な捜査を脳内で展開してみたりと――そんなことで忙しく頭を働かせてばかりいた。けれど、ロドニーから「今夜はちょっと飲もうぜ」と言われた時、そうした考えのすべてが一時的に吹っ飛んだのだ。
というのも結局、すべては憶測の域を出ないどころか、ほとんどありえない妄想とも言える領域のことを俺は何度となく頭の中でこねくり回していたのだったし、ロドニーからそう言われてある意味ハッとしたのだった。確かにそんなことより、バカンス先で知りあった素晴らしいプロテニスプレイヤーと話でもしたほうがよほど有益な時の使い方だと、そんなふうに思い直したわけである。
けれど、後になってみればわかる……ロドニーは間違いなく俺を選び、俺にだけ話したいことがあったのだ。だから俺はそのことを彼の死後、心から後悔した。よく考えてみれば確かにその時ロドニーはいつもと少し様子が違ったのだし、そのことにもし気づけていれば、違う結末もあったのではないかということ――ゆえに、ロドニー・ウエストが死んでしまって以降は、俺はそのことで頭の中が占められるあまり、『人間そっくりのヒューマノイド当てクイズ』自体、本当にどうでもよくなってしまったのだ。
『最近、女房とあまりうまくいってないんだ』
俺たちは昨晩の八時半くらいからロドニーの部屋で飲みはじめ、俺がそちらの部屋を出たのが十二時過ぎくらいのことだった。クレイグ医師は四大大会(グランドスラム)で優勝したこともある偉大なテニスプレイヤーの遺体を検視したとはまるで思ってない様子で――それがノーベル賞受賞者であれ、素晴らしいプロテニスプレイヤーであれ、死んでしまえば同じ肉塊だというような冷徹な眼差しにより彼は解剖しているように見えた。そして俺から前夜の様子などについて詳しく聞くと、クレイグ医師は妙に納得していたようだった。クレイグ医師曰く、「体にある打撲傷のように見えるものは崖から落ちた時に岩の角などでぶつけたものでしょうな。遺体の所見から、死亡推定時刻は午前一時から三時くらいの間……と考えていましたが、あなたの話を聞いて大体間違ってないだろう確信しました」とのことである。
『奥さんっていうと、以前は同じようにプロのテニスプレイヤーだったレイチェル・ロノスさんだよね?』
俺はその後、プエルトリコやバハマ諸島へ行った時、ネットが使える環境へ戻っても――特段フランチェスカやロドニーのことは調べなかった。唯一、ジェイムズ・ホリスター博士やアーサー・ホランド博士やクリストファー・ランド博士のことについては何度となく検索をかけたが、特にこれといって本当に欲しい情報については提示されなかったのである。ホリスター博士についてはSNSの更新が止まっていることもなく、そもそもそれは会社のスタッフが投稿するもののようで、博士の個人的な投稿については止まっているというそれだけのようだった。ホランド博士は家族のSNSに本人が登場していないようだ……と感じはしたが、去年とか数か月前に父親と写したのだろう写真については投稿があったり、特段日付のないものだと、アーサー・ホランドはもしや「今」とか「きのう」とか「おとつい」、もしかして三番目の前妻の家を訪れ、子供と過ごしたのだろうか――と見た人が勘違いしてもまるでおかしくなかったことだろう。
そして、肝心のクリストファー・ランド博士だが、博士の死は今のところ公表されてはいないようで、不思議なことにランド博士は今もまだ生きているようだった。ということは、この『本物の人間そっくりのヒューマノイド当てクイズ』が終了後、博士の家族の元へはCIAからでも極秘に連絡がいくということなのかどうか……。
『うん。俺とレイと弟のシドは、同じテニスアカデミー出身なんだ。コートのある敷地内に学校と寮が併設されてるような環境で、十三くらいの頃からずっと一緒に過ごしてきた。正確には俺が十三でレイが十四か。彼女は俺と違って学校の成績のほうも良かったから、テニスについては才能の萌芽があっても勉強のほうは落ちこぼれといった俺とは……ちょっと距離のある感じだった。その後、弟のシドニーが同じアカデミーへやって来た。俺とシドはふたつ違いだから、その頃には俺とレイは高校生に上がるところで、シドはまだ中学生といったところでな。わかるだろ?十代の頃のふたつ違いは大きい。レイは学校でも目立つタイプで、コーチたちも将来は花形選手になると信じて大切に育てていた。ほら、あんまり若い頃に花開きすぎちまうと、その後燃え尽き症候群になってテニスやめちまったりとか、よくある話だろ?その点、確かにレイは成績も良かったから、厳しいテニス界に一足速く身を投じるよりも、まずは学業に専念すべきかどうかで迷っていたわけだ。優等生によくある話だが、俺はといえばその真逆で、俺からテニスを取ればなんにも残らないからな。それでブルドッグみたいにがっしり噛みついて離れなかったわけだよ。俺とレイは同学年だったから、そんな時、彼女が俺に話しかけてきたんだ。二年ちょっとくらい、お互い顔は知っててもそんなに親しく話したことはない――みたいな関係性だったから、俺にしてみればちょっとしたチャンスだった。というのも、俺は心の底から恋してるっていうのとは違ったが、レイは女子選手の花形で、将来はスタープレイヤーになるのが約束されてるようなものだったからな。みんなが彼女に憧れていた……そしてそれは弟のシドにしてもそうだったわけだ』
レイチェル・ロノスはその後、ジュニア・チャンピオンとして優勝はしたが、プロとしてデビューしたのは十九歳、彼女が希望した大学へ入学したあとのことだったらしい。プロデビュー後の活躍は目覚ましく、多くの大会で準優勝(全豪オープン)、あるいはベスト4(全仏オープン)やベスト8(ウィンブルドン大会)……など、プロ二年目で四大大会のひとつで優勝し(全米オープン)、四年目にはグランドスラムを制する成績を残し、引退後は同じプロテニスプレイヤーのロドニー・ウエストと結婚したわけだった。
『確かに弟は小さい頃からテニスの神童としてもてはやされていたし、兄貴の俺のほうの才能が<そこそこ>と見なされているのとはまったく違う、破格の注目のされ方だった。で、レイと同じく品行方正で誰に対しても礼儀正しく優しい……なあ、テディ。俺の言いたいことがわかるか?シドはずっとレイのことが好きだったんだ。ふたりはほとんど双子みたいに性格がよく似ていた。だが、レイはどんなに慕われてもずっとシドのことを弟のように扱ってきたし、ほら、マスコミでもずっと言われてきたように俺とシドは全然似てない。俺が自分の髪の毛をずっと黒くしてたのはシドのブロンドと同じじゃつまらんと思ったからさ。このへん、髪の色や髪型については俺の場合、毎年色々な変遷があったわけだが、ある部分それは容貌のいい弟に対するコンプレックスが多少なり関係してたからなんだ。俺は素行が悪かったもんで――時々寮を抜けだしては夜の街へ繰り出すといったような――そっち方面に関しても少しばかり進んでるといえば進んでいたかもしれない。温室育ちのシドとは違って、ロッカールームで他の選手と悪ふざけしたりとか……まあ、なんかそんな感じだった。女子たちの間では人気ゼロでも、男連中の間では何故か人気の高い中心人物――といった意味では唯一、レイも俺に対して一目置いてたという意味でな』
『俺はあんまり、マスコミの書きたてることを真に受けないタイプだと思うんだけど……』俺はロドニーの部屋のキャビネットにあったウィスキーを氷で割って飲んでいた。俺の部屋に酒はなかったが、ロドニーの部屋にはワインセラーがあったのみならず、高級な銘柄の酒瓶が随分棚に並んでいたものである。『ロドニーとシドニーのウエスト兄弟は仲が悪いって話、あれは本当だったのかい?』
『本当だとも』と、ロドニーはスコッチグラスを揺らして笑った。『むしろそのことを隠したがってたのはオレじゃなく、品行方正な優等生であるシドのほうだったんだぜ。それで、「ここ一年くらい家で顔を合わせることがあっても口も聞いてねえな」とか、オレが本当のことをマスコミのインタビューで言ったりすると、あいつは自分の優等生イメージに傷がつくと思ってのことだろう、そういうのが物凄く嫌みたいだった』
とはいえ、テニスの大会で当たった時、兄のロドニーは弟のシドニーに一度も勝ったことはないのだ。タイブレークを破ったあとの、シドニーの頬に浮かんだ酷薄な笑み……カメラがもし嘘をつかないものならば、彼は間違いなく血の繋がった兄をこてんぱんにのしてやることに快感を覚えていたようだった。
『じゃあ、もしかして仲が悪くなった原因というのはもしかして……?』
俺の知る限り、ウエスト兄弟の仲が悪いのは、レイチェル・ロノスを奪いあってのことである――といったゴシップ記事というのは見かけた記憶がない。だが、もしかしたらシドニーはあの整った美貌の裏に、ずっとそうした兄に対する憎しみを押し隠してきたということなのだろうか?
『こう言って理解してもらえるかどうかわからないが、世の中には血を分けあって生まれた兄弟だというのに、何故か致命的に気が合わない者同士として生まれついた……そんなことがあるものなのさ。テニスのコーチだった親父は、オレが四歳の頃からテニスの英才教育を施そうと考え、オレはたぶん結構いいセンいってたはずだと自分でも思うんだよ。ところがだな、弟のシドのほうがオレよりもっと才能がありそうだと睨んだ親父は、オレとシドを競わせようとしたんだ。そのこと自体はオレも悪いことだとは今も思ってない。女子というのはどうかわからんが、男の場合は特に近くに能力の拮抗した選手のいたほうが、ライバルに負けたくないとして才能が伸びるもんだっていうからな。オレはその後、ただの弟の相手をするちょうどいいヒッティング・パートナーとして踏み台にされそうだと感じ、おふくろに頼んで有名なテニスアカデミーへ入学することにした。シドのほうがあんなに顔もよくて成績も素晴らしく、テニスの才能もずば抜けた天才だとかっていうんでなかったら……オレはただの中途半端な甘ったれ小僧だったから、実家を出たいとはまでは考えなかったろう。だが、このまま家にいるよりは他人に囲まれてテニスの才能を第一優先に伸ばすといった環境に身を置いたほうが幸せだったんだ、その時点においてはな』
俺は黙ってちびちびウィスキーを飲んだ。夜になっても気温はさして下がりもせず、エアコンは効いていたが、ロドニーは窓を開けっぱなしにしていたので、部屋の空気は妙に生ぬるいままだった。この時窓から流れてくるように聴こえた潮騒の音を、何故か俺は妙にはっきり覚えている。
『それなのに、何故そうした犠牲を強いた当の本人が同じアカデミーへやって来るんだ?もちろん、無邪気な優等生の弟はその時点では気づいてなかったろう……オレはおまえの顔を見たくないからこそ家を出たんだぞ、なんてことにはな。けどまあ、生まれて初めての親元を離れての寮生活だ。シドも相当心細かったらしく、オレはいい兄貴という仮面を被って、時にはあいつを守ってやることさえした。その後、シドがレイの練習してるところを見て――いつになく熱心な目つきをしてたもんで、(はは~ん)と気づいたわけだ。オレもレイのことは気になっていたが、当時それはまだ恋と呼べるほどのものじゃなかった。というより、弟が自分の鏡でも見るみたいに、まったく自分と同じ傾向、性格的にも似たタイプの女を好きになってるのを見て……ヘドが出そうだとさえ感じた。もちろん、実際のところ人間はそんなものだし、それの何が悪いってこともない気はするんだがな』
『その後、一体何があったんだい?』
俺はソファに座ったまま、壁にかかったマティスの絵を見た。「赤い部屋(赤のシンフォニー)」――確か、この絵は最初緑に塗っていたのをその後、何か理由があって赤に変えたということだった。だが、俺はその昔美術書か何かで読んだ肝心なその理由についてど忘れしてしまっていた。
『さてな。レイチェル・ロノスのような女は高嶺の花であるとして、オレは最初から彼女が自分に振り向いてくれる可能性があるとは……あまり考えてなかったわけだ。ところがだな、それが何故かはわからんが、彼女はプロになるべきかそれとも学業を大切にすべきか迷ってるといった話をオレにしてきたわけだ。それまでほとんど口を聞いたこともないことを思うと、「なんでオレ?」ってな話だ。で、オレは当時自分が思ったり感じたりしてたことをオレなりに誠意を込めて話したわけだ。「自分には惨めなまでにテニスしかない」とか、「もし他に道があったら、オレならまずそちらの可能性を試す。テニスは必ずしもそこまで将来を保証してくれるようなスポーツじゃない」、「まあ、君ほど才能があったら両立してバランスも取ってうまくやってくんだろうけど」とかなんとか、大体そんな話だ。他に、これはそれまで誰にも話したことのないことだったが、弟のシドにコンプレックスがあるとか、そんな話もしたんだよ。よくわからんが、なんとなくそんな雰囲気だったから……そしたらレイチェルの奴、妙に共感したみたいだった。それはオレがまったく期待してなかった反応だったが、「でもあなた、弟の彼のこと、とてもよく面倒みてるじゃないの。えらいわ」とかいう話でな。オレはその時ちょっと(女ってのはもしかしてこういうのに弱いのか?)と思ったりもした。簡単にいえば弱いところや傷を見せるってことだが、確かに彼女も周囲から色々なことを期待されたり、優等生の型に嵌められてるといったような息苦しさがあったんだろう。オレはレイの将来を思って、そう羽目を外すような道に彼女を誘ったりはしなかったが、テニスがダメでも勉強がダメでも、他にも道はある――みたいなことを、少しだけ教えたんだ。だって、魂それ事体はとても自由でどこへでも行けるってのに、可能性を狭めてるのはむしろオレたち自身のほうなんだからな……』
『そういうのが女性に効くっていうのは、なんかわかる』と、俺も同意した。『それでロドニーは、たぶんその時すぐにレイチェルと恋人関係になったってわけでもないんだろ?でも彼女はそれであればこそ、ロドニーのことをずっと忘れずに覚えていた……といったような印象だ。それで、どういった過程があってレイチェルさんとは結婚したんだい?俺はジャーナリストとはいえ、普段はそんなに大した詮索好きってわけでもないんだ。だけど、ロドニーがその奥さんとうまくいってないってことは、そのことで何か話したいのかと思って……』
『まあ、話せば長くなることなんだがな』と、バルコニーの外の闇を眺めるようにして、ロドニーは微かに皮肉な笑みをその時浮かべていた。『オレはレイのほうに多少なり「その気がある」とはまるで思っていなかった。ところがだな、大学へ進学後もずっとオレの言葉が支えだったとかなんとか、あとからそんな話をされて――お互いプロだった間につきあうことになった。マスコミに関係を隠すのは大変だったが、ある意味そんなことも愛しあう若いカップルには刺激だったかもしれない。とにかく、結婚するって正式に決まった段階でお互いの両親に紹介することになって……オレは初めて実家のほうにレイチェルのことを連れていった。当然、弟のシドのことも呼んだ。そのさ、確かにオレとシドは兄弟としていまいちしっくりいってなかったかもしれん。けど、弟の初恋の相手を用意周到に奪うことで復讐しようと考えるほど……オレは腹黒くもなければ、そこまで色々考えられるほど頭もよくないわけだよ。だが、シドのほうではそう思わなかったようだ。レイはそのことに気づかなかったようだが、「オレたち、結婚することにしたんだ」と言った時のシドニーのあの顔……それはオレがあいつに対してずっと感じていたことをはっきり表したのにも似た顔だった。でもそれもほんの一瞬のことでな、シドはいつもの明るいアイドル精神を発揮して、「おめでとう!」と言った。とにかく、オレとシドの間はその日を境にはっきり変わったんだ。それまではオレのほうが無理してあいつと普通にしゃべったりなんだりしてるって関係性だったのに、今度は立場が逆転した。とはいえ、今ではあいつにも美人のカミさんがいるし、ウィンブルドン大会七連覇だの、四大大会優勝計三十一回だの……オレがあいつの豪邸までいって、そういう記念のカップだなんだ、「ウオーッ!!」と叫んで狂ったように叩き壊さないのが不思議なほど――テニス界の帝王としての地位を極めたんだ。なんにしても、レイと結婚して以降、オレとシドはマスコミを前にして表面上は仲良くしてるように見えたり、不仲説を否定はしていても、関係性のほうはまったくもって冷えきっていたわけさ』
確かに、シドニー・ウエストの妻は元世界ユニバースのモデルで、物凄い美人だった。また、SNSを見れば彼らのヘドが出そうになるほど幸福そのものの生活を垣間見ることが出来る……なんて思うのは、やっぱり俺の心がちょっとひねくれ曲がってるせいなのだろうか?
『でも、そうしたことももう何年も昔の話で……今ロドニーと奥さんのレイチェルさんの関係がうまくいってないのは、弟の天才テニスプレイヤーは関係ないってことでいいんだよな?』
『いや、関係あるのさ。シドとレイが不倫関係を結ぶようになって以降って意味ではな』
俺は驚くあまり、バカラのグラスを危うく取り落とすところだった。ガチャリとガラスのテーブルの上にそれをのせると、急いで氷を入れ、ウィスキーを注ぐ。
『そんな……ふたりともそういうタイプの性格じゃないっていうか……いや、俺はどちらのこともよく知ってるわけじゃないけど……』
『そうなんだよ。シドは家庭を壊すタイプの男なんかでは絶対にない。毎年お義理でクリスマスカードすら送らなくなって久しいが、それでもそういうことはオレにもよくわかる。確かに、元を正せばオレが悪いって話ではあるのさ。結婚後に、本気じゃない小さい浮気ってのがあって、女ってのは絶対的な証拠があるわけじゃなくても、何故かそういうことには気づいてしまう不幸な生き物らしくてな。よくこう言う女がいるだろ?「家庭にさえ持ち込まなければいいのよ」とか、「わたしが気づかなければいいわ。だってそれなら浮気してないのと同じことだもの」っていう女が……とはいえ、彼女たちは大抵の場合気づいてる。口ではそう言いながらも猟犬並みの鼻の良さによって夫の浮気には必ず敏感に気づく。オレは決定的な証拠がありでもしない限り、絶対にシラを切り通したしな。でもその後、レイは何かの拍子にシドに相談したんだ。で、シドは相当親身になってレイの話を聞いてたんだろう。その頃にはもうシドは結婚して子供も大きくなっていた。でもあの優等生の、絶対道を踏み外さない奴が、今では不倫の甘い蜜ってやつにどっぷり浸かり込んでるわけだ……オレはな、男のそういう話をあまり信じる気はないんだが、シドの場合は確かに本当にそうなのかもしれないと思う。つまり、あの元世界ユニバースの美人の奥方のことは、他の恋人候補の中で一番容姿と経歴が申し分ないと思ったから結婚相手として選んだっていうんだ。ようするに、相手の女は低学歴のアバズレだがどうにも惹かれてしょうがないとか、あいつにはそういう経験がまるきりないんだな。そこで本当に条件だけで相手を選んで交際し、それから「彼女なら申し分ない」とかいうクソみたいな理由で結婚したんだろう。だから、本当に最初から本能で惹かれることの出来る稀有な相手に悩みを相談された時……オレは――あいつがオレに復讐したかったんだとは思わない。ただ、本人自身がびっくりしたのさ。こんなにも恋愛とセックスと不道徳に溺れることができる自分って奴に、中年のいい年になってからようやく気づいたという意味でな。で、それはあいつだけじゃなくレイも同じだった。シドの奥さんに関しては、SNSの投稿を見ていて思うに、気づいていても気づかない振りを徹底するつもりのようだな。さてこの話、第三者として冷静に聞いていて、テディはどう思う?』
『どう思うって……問題は部外者である俺がどう思うとか考えるかじゃないよ。ついでにいうと、レイチェルさんと弟のシドニーのこともどうでもいい。友達であるロドニー、君がこの問題をどう乗り越えるかってことのほうが大事だってことだ』
(ああ、そうか)と、俺は初めて妙に合点がいった。おそらく彼のような人間が百万ドルという金に興味があるわけでもないのに、わざわざこんなオカドゥグ島くんだりまでやって来たのは――そうした問題すべてに一時的にせよ背を向け、逃げたかったからではないだろうか?
『はははっ。やっぱりおまえ……テディ、おまえは大した奴だよ』と、グラスの最後の飲み残しをぐいっとやって、ロドニーは笑った。『オレはな……すごく不思議なんだが、シドに対してはあまり怒りが湧いてこないっていうか、あいつも苦しい立場だろうなという気がする。だって、今まで信じられないくらいクリーンなイメージで売ってきたスポーツ選手だってのに、こんなスキャンダル、あいつのヤワな優等生メンタルで耐えられるものなのかどうか……奥さんのセドナはマスコミの前でさめざめ泣いて、徹底的に自分はひどい被害者なのだという振りをし続けるだろう。シドの奴、誰もが羨むような美人と結婚しちゃいるが、実際は結構カワイソウなんだぜ。結婚指輪に三億とか、「アタマおかしいのか?」としか俺には思えんが、豪邸の内装のほうも彼女が拘りに拘って一切妥協しなかったって、おふくろからはそう聞いた。もし離婚なんぞしようものなら、ガキふたりの養育費含め、一体いくらふんだくられることになるのか……レイのほうは最初はオレに対するあてつけではじまった関係でも、今じゃもうオレとは必要最低限でさえ口も聞きたくないらしい。だがどう思う?オレとレイが離婚したところで……シドの奴はますます苦しくなるってだけだ。そこで、オレは今回のこのうさんくさい『本物のヒューマノイド当てクイズ』ってのに参加することに決めたわけだよ。そうともさ……百万ドルなんかもらったところで、オレの深刻な人生の問題は全然解決なぞしない。だが何か、ちょっとくらい生きるヒントでももらえるんじゃないかとそんな気がしたのかもな。何かこう、直感的に』
『ヒントなら、たぶんあったんじゃないか?』
俺はバルコニー側にあるロドニーの座る椅子の隣に座って言った。窓の外の闇の中から、潮騒の音だけが静かに響いてくる。
『ほら、ヒューとトムとメアリーのお三方を見てみろよ。結局みんな、最後はあんなふうになるんだ。フランチェスカの話じゃあ、トムとジュリアのジョーンズ夫妻は、お互いにどっちかが速く死ぬよう心から願っていた関係性らしいぜ。そしてそれはヒューとメアリーにしても同様なんだ。片方が先に死ねば、保険金含め結構な大金が転がりこんでくる……ジュリアさんっていうのは、夫の横暴やモラハラに耐えに耐えたといった結婚生活だったらしく、夫のトムが死んだら十年ほども長生きして、夫のいない世界で自由に生きることが心からの望みだったらしい。そしてメアリーはそんな彼女の手を握りしめ、「こんなところで死んじゃあ駄目よ」と最後まで励ましたらしいんだが、寄る年波と病いには打ち勝てなかったんだろう。メアリーはメアリーで、同様に夫から踏みつけにされるような人生だったから、ヒューが死ねば大金が手に入り、その後はせめても自由に生きられる……といった予定でいるつもりらしいぞ。ふたりの女性とも、金のことでは夫のほうががっしり握ってるといった家庭生活だったらしく、俺もメアリーが介護ロボットのシノブのことをこっそりつねってるところを見たが、その気持ちもわかろうというものだ。ほら、今はよく言うだろ?「人間の男女の間に今も愛は燃えているか?」なんて特集が雑誌で組まれたりさ……つまり、セックスドールがいて性的な満足を得られるのみならず、料理や掃除なんかも彼女が全部やってくれるんだ。女性にしても、恋愛経験豊富な女性でさえ、ある程度の年になったら人間の男なんかと一緒にいるより、主夫ロボットと暮らしていたほうがよほど幸せだ――となったり。一昔前はそれでも、「そんなの人間らしい生活とは言えないし、不自然だ」とか、そうした人々に対して「人間として欠陥があるからロボットを代わりにして満足しているのだろう」だのいうくだらん議論があったっていうよな?でももう時代は変わったんだ。何が普通で常識で正しいのかなんて……もう誰にも定義なんか出来ない。そしてそういう中で俺も、ええと、今のところ作る気はなくとも、俺の子孫なんかも生きていくしかないんだよ』
『まあ、確かにそうだな』と、ロドニーはもう一度皮肉げに笑った。『これはオレが直感的に思ってることなんだが、あのじいさんとばあさんはたぶん、若い頃から相当<老い>ということに対して気を配って生きてきたんだろう。大体今、百四十歳とかそれ以上生きてるご老人っていうのは……若い頃から長生きできるよう、若さを維持できるよう遺伝子治療を受けてたり、高額な薬を飲み続けてたりとか、そうした基本的に金のある人たちだものな。すでに金持ちと貧乏人の間でそうした寿命格差が生まれているわけだが、あの老人たちからはあんまり健全な印象を受けもしなければ、幸福そうにも見えないというあたり――長寿=幸福とも限らんということなんだろうな』
『そりゃそうだよ。ほら、スウィフトの「ガリバー旅行記」に、ストラルドブルグっていう不老不死の人がたまに生まれる、ブログディンナグって国をガリバーが訪ねる場面ってのがあるんだけどさ、自分の血族に純粋に愛着を持てるのもせいぜいが孫の代くらいまでで、その後は容貌も醜くなる一方で、性格のほうもひねくれ曲がって手に負えなくなる……みたいな話でね。不老不死の人間なんかもしいたとしたら、本人も大して幸せでないし、周囲の人はもっと迷惑だ、政府も生涯に渡って年金やらなんやら最低限の生活費を支給しなきゃならないし、社会的にも邪魔な存在だってことなんだよな。でも今は、その昔SF小説なんかで不老不死が売られていたみたいに……まだ実現はしていないにせよ、科学的にそれも不可能ではないという見通しが出てきてるんだ』
『ほう。というか、オレも科学系のドキュメンタリーなんかでそうした話は聞いたことがある。そのストラルドブルグって不死人は、老人として醜く老いていく一方なのかもしれんが、肉体を若く保つ――のにも現行、やはり限界があるわけだよな。となれば、自分の意識をもうひとつの人工ニューロンか何かで出来た脳のほうへ移植し、それ以外は交換可能なアンドロイドの体を使用すれば……一応理論上、その人物は永遠に生きることが出来るとかなんとか』
『うん。実際にはさ、その人工ニューロンの脳に意識を発生させるって研究が元になってるんだけど……ちょっとその、安全性のほうが倫理的にどうかってことで、そうした成功例が存在するとはまだ言われてない。でもまあ、すでにずっと前からあるアンドロイドの疑似意識プログラムをそこに置き換えるって実験自体は成功してるわけだから、実はこの地球上のどこかにはすでに<永遠の生命>を持つ人類が存在してるんじゃないか……みたいに言われてたりはするんだよね』
そうなのである。俺がロドニーに簡潔に語ったような延長線上に<永遠の生命体>なるものが存在するのであれば、被験者が続出していておかしくないように感じられるだろう。だが、自分の脳――言い換えれば、『<わたし>そのもの』をもうひとつの人工ニューロンの脳に接合できたところで、失敗した場合、彼/彼女の心・精神・魂は一体どうなったのか、誰にも確認も取れなければ責任も取れないだろうこと、この場合の手術の失敗は病気による胃や他の臓器移植の失敗とは根本的に意味が異なることから……闇の世界ではわからないにせよ、少なくとも表の医療界ではタブーとされ、禁止されることになったのだ。また、生きた人の意識のデータ化研究によって、死ぬ少し前に別のクラウドに意識データをアップロード、その後、新しいアンドロイドの体の脳にダウンロードする研究も行われたが、「自分はどうなってもいい」というその道の研究者夫妻が試してみたというケースが一件だけ公表されている。だが、この夫の心・精神・魂の総合データと思われるものは、確かにデータとして現在もクラウドに存在するものの――そのプログラムの羅列はヒトゲノムのようには解読することが不能な、今も誰にもどうにも出来ないバグのようなものとして保存されたままであるという。また、夫のアンドレイ・キンスキーの懇願によって実行キーを押した妻のラリッサ・キンスカヤは自責の念に悩まされ、その後拳銃自殺をはかったということである。
『まあ、そうまでして長生きしたいとはオレは思わん側の人間ではあるが……どうなんだろうな。それでも細胞が若返る薬ってやつをオレもレイもずっと飲んできたし、そのせいで実際の年齢以上に若く見えるって部分は間違いなくある。また、その薬の効果ですらも追いつかず、百歳を越えてあのじいさん・ばあさんみたいに老いさらばえてきたとしても……やっぱり、それならそれで一日でも長く生きたいと、そうした望みを人を持つものなんだろうか』
――この言葉は、この日の夜のうちに断崖から身を投げたロドニーの口から出たものであることを思うと……彼は本当はどういう気持ちだったのか、俺には想像することさえ出来ない。奥さんとの不仲や、彼女と弟シドニーとの浮気といった問題があったにせよ、俺の知る限りロドニー・ウエストという人物は自殺する道を選ぶとまでは思えない。だが、俺はそれまでの間も『実はクリストファー・ランド博士は他殺ではないのか』との可能性が、モーガン・ケリー同様五パーセントはあるのではないか……とずっと疑ってきたにも関わらず、『実はロドニーは自殺などではなく、誰かに殺されたのではないか』と考えることが出来なかった。つまり、彼の死にショックを受けるあまり、自殺とは到底思えないが、かといって殺したとすれば一体誰が――と思考の網をさらに展開させられるほど、俺は心と頭を働かせられる余力が残っていなかったのだ。
とにかく俺は、医療カプセル内に入ったロドニーの遺体と対面すると、ショックのあまり泣き崩れた。そして、自分の部屋で三日ほど落ち込んで過ごしたのだが、それはミカエラやフランチェスカも同様だったようである。メアリーとヒューのアンダーソン夫妻とトム・ジョーンズはロドニーとさして親しく話す間柄というのではなかったし、彼ら三人がクリストファー・ランド博士が死んだと聞いた時同様、さして動じてないように見えたとしても……俺はさして驚かなかった。『なんという心の冷たい老人どもだ』と感じもしなかったし、むしろ彼らの立場にしてみれば、せっかく見飽きた介護施設からバカンスへやって来たのに若い連中がふたりも立て続けに死んじまってまったく迷惑だ……と感じたとしても無理はない、といったようにも思った。ただ、廊下で介護ロボットであるシノブが、おそらく俺の生体情報をスキャンし、栄養状態が落ちていると感じたのだろう。「本当にお気の毒に。そのお悲しみ、お察ししますわ」などと、憐れみに満ちた聖母マリアのような眼差しを向けてきたというのが、何やら俺には妙に印象的だったというそれだけである。
そして俺が、自室のベッドにて『そのお悲しみ、お察ししますわ』というシノブの言葉を心の中で反芻し、そのことを何故奇妙と感じるのか――頭の中で思考を転がしていた時のことだった。
>>続く。