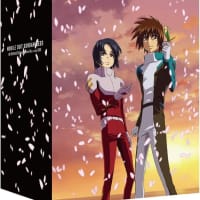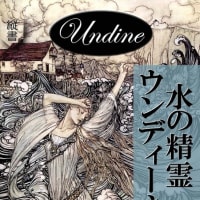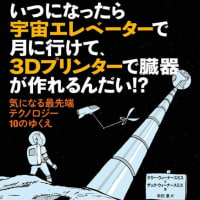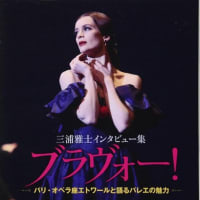(※海ドラ「カサンドラ」に関してネタばれ☆があります。一応念のため、ご注意くださいませm(_ _)m)
ネットフリックスで「カサンドラ」という全6回のドラマを見ました♪
>>家族とともに1970年代のスマートホームに引っ越してきたサミラ。長い間眠りについていたヴァーチャルアシスタントを息子が再起動したことで、サミラの好奇心は疑惑へと転じていく。
というのがネトフリにあるあらすじで、主人公のサミラは四人家族のお母さん。他に夫ダーヴィトと息子フィンと娘ジュノがいて、前に住んでいたところはサミラのお姉さんが自殺したことから……「心機一転やり直そう!」といった気持ちで、こちらのスマートホームへ引っ越してきた →
→ 。
。
もっとも、彼らはそこが時代の最先端をゆくスマートホームだったから引っ越してきたというわけではなく、家自体は1970年代に建てられもので、それからすでに五十年も経過していたというあたり、建物自体はかなり古い。なんというか、そこにトップ画のようなヒト型家事アンドロイドのようなものがくっついていて、彼女は<家>そのものと同化しているに等しく、家中にあるモニターに顔だけ映ってることが多かったりもして、ちょっと不気味……。
とはいえ、もちろんサミラたちはカサンドラに人間に相当するような<心>まであるとは思っておらず、展開としてはサイコスリラーで、カサンドラは本来なら家の女主人であるサミラが孤立するように動きます ジュノはまだ小学生くらいで幼く、カサンドラは悪意のないように装いつつも、ママであるサミラが「こう言ってた」的なことを言って自信を失わせたり、その後彼女を喜ばせることをして、ジュノの心を掴んでいく。
ジュノはまだ小学生くらいで幼く、カサンドラは悪意のないように装いつつも、ママであるサミラが「こう言ってた」的なことを言って自信を失わせたり、その後彼女を喜ばせることをして、ジュノの心を掴んでいく。
カサンドラはサミラが閉所恐怖症であることがわかると、彼女を狭い部屋に閉じ込めて出られないようにしたり、「妻」であり「母親」である彼女に成り代わろうという意志のあることをはっきりサミラに見せつけます。何分ビジュアルのほうが「モニターに顔が映ってるだけ 」の旧式タイプであるだけに(いえ、造形としてはそこがすごくいいのですけども・笑)、最初はただの偶然であると思おうとするものの、カサンドラの悪意があまりにはっきりしたものであることに、サミラがまず最初に気づく。
」の旧式タイプであるだけに(いえ、造形としてはそこがすごくいいのですけども・笑)、最初はただの偶然であると思おうとするものの、カサンドラの悪意があまりにはっきりしたものであることに、サミラがまず最初に気づく。
でもカサンドラは、他の家族に巧みな形で心の囲い込みのようなことを行ってますから、「カサンドラはおかしい」的なことを言っても、最初は軽く受け流されてしまう。そして、こちらの2020年代に起きていることと大体平行する形で、元は生身の人間だったカサンドラが生きていた1970年代に「何が起きたのか」が語られるという形式なのですが、視聴者的に「も、もしかしてそうなのかな…… 」と薄々感じつつ、途中ではっきりわかる回があるわけです。
」と薄々感じつつ、途中ではっきりわかる回があるわけです。
カサンドラの旦那さんは科学者で、実はある研究を行っていて……と、こう書くと何やらありがち設定なのですが、ドラマを見てるこっちとしては「だって、まだ1970年代でしょ? 」といった感じで、つい油断(?)しているため――実はカサンドラが死ぬ前に自分の脳の意識に当たるものを機械のほうへ移した……とわかる段になると、ちょっと驚きます
」といった感じで、つい油断(?)しているため――実はカサンドラが死ぬ前に自分の脳の意識に当たるものを機械のほうへ移した……とわかる段になると、ちょっと驚きます
そして、自分的に「何故カサンドラはそこまでしたのか」ということには、二段式の理由があったように見ていて思いました もともとの機械になる前のカサンドラは、大体のところ彼女が生きていた時代の女性が経験するだろう苦しみや悲しみを経験しています。簡単にいうと夫の浮気やらなんやら、そこは目を瞑れたにしても、夫が息子に対して本当の意味では無関心だったりと……また、カサンドラがガンになったのは間違いなく夫が原因であることが見ている側にはわかるんですよね
もともとの機械になる前のカサンドラは、大体のところ彼女が生きていた時代の女性が経験するだろう苦しみや悲しみを経験しています。簡単にいうと夫の浮気やらなんやら、そこは目を瞑れたにしても、夫が息子に対して本当の意味では無関心だったりと……また、カサンドラがガンになったのは間違いなく夫が原因であることが見ている側にはわかるんですよね

そんな人生の色々を経験したカサンドラが、機械に脳内の意識を移すことまでして守ろうとしたものはなんだったのか……おそらくここがこのドラマの一番のキモではないでしょうか ←
← 。
。
サミラは最終的に、カサンドラが仕組んだことにより娘の同級生を殺そうとした事故の張本人ということで、彼女は精神病院へ入院することになります。そして、残された家族のダーヴィトとフィンとジュノの三人は家の中でカサンドラに監禁・管理されるということに。
家族全員で「もう一度やり直そう!」と思ってやって来たのに、その家におかしな家事アンドロイドがくっついていたことで……とんだことになったサミラたち一家。スマートホームの電源的なものを切っても動作を停止することのないカサンドラは、ダーヴィトにもフィンにもジュノにも、買い物など、自分が許可した以外では外出を許さず、母のサミラと携帯で話すことさえ禁じています
冒頭で、カサンドラの元の家族が、家で同じような監禁下へおかれ、車で逃げだそうとしたところ、事故に遭う場面があることから
 ……カサンドラが夫とその愛人とふたりの間に出来た赤ちゃん、それにカサンドラの息子を殺したのだろうか――といったように見えるシーンがありますが、このあたりの謎についても最後のほうでわかることに。
……カサンドラが夫とその愛人とふたりの間に出来た赤ちゃん、それにカサンドラの息子を殺したのだろうか――といったように見えるシーンがありますが、このあたりの謎についても最後のほうでわかることに。
このあたり、カサンドラは一人息子のことが心配で、自分の意識を機械に移してまで生き続けようとしたのか……と最初は思うのですが(カサンドラの一人息子はいじめっ子を殺し、彼女はその後始末までしている)、彼女にはもうひとつ、それ以上の理由があったのでした


物語は最後の最後、ちゃんとぎりぎり救いがあるような形で終わったように思われますし、ドラマ内に流れる全体的な雰囲気含め、とても好感の持てる、直感的に「好き 」と感じられる作品だったと思います。
」と感じられる作品だったと思います。
そして自分的に、見た動機というのが実は、「家事ロボット?ええと、じゃあ洗濯とか掃除してるところは想像できるけど、料理って具体的にどうするんだろ? 」と思ったことだったり(^^;)
」と思ったことだったり(^^;)
↓に出てくる旧式ロボットのシズカに関していえば、手首のところだけ部品交換したりとか、体も伸び縮みしたり……といったイメージはあったのですが、実際にカサンドラが手首の部品を換えて包丁で野菜切ったりするのを見て――ビジュアル的に「おお!そういうことか 」と思ったような次第であります♪
」と思ったような次第であります♪
それではまた~!!
永遠の恋、不滅の愛。-【30】-
――こうして俺は、完全にひとりぼっちになった。もちろん、最愛の女性を失い、ぬいぐるみやらおもちゃやらを受けとるべき赤ん坊も遠く離れてしまったとはいえ……離婚したにせよ両親は生きているし、親友や友達であれば何人かはいた。だが、俺はこの時この上もなく孤独で、それが誰でもいいから泣いて縋りたいほど、心が完全に空っぽだったのだ。
「シズカ、おまえが人間だったら良かったのにな……」
キッチンで充電中の家事ロボットにそう呟いてしまい、俺は苦笑した。今は自分好みにカスタマイズしたアンドロイドをガールフレンドやボーイフレンドにしている人間などいくらでもいるし、それで人生の幸福度が上がるなら、俺はそれはいいことではないかと考えている。だがやはり、大学のアンドロイド工学科などという場所にいて、一から身体内部の機械を組み立て、プログラムしたことがあるせいだろう。俺はそういった種類の恋人や友人を持ちたいと思ったことが一度もなかったのである。
だが、今ならばよくわかる。シズカがもし旧式のロボットでなく、人間によく似た女性の容姿をしていたら――俺は彼女に心の慰めを求めたことだろう。クオリアのないデジタルゾンビでもなんでもいい。優しくあたたかい言葉をかけてくれ、思いやりのある態度を見せてくれるなら、本物の愛なぞなくてもいい。それに近い疑似的なものを与えてくれるなら……俺はそれが本当の人間じゃなくてもいいから慰めが欲しいと、心からそう願う人の気持ちが初めてわかった。
そしてこの翌日――つまりは、七月の十三日ということだが、メールボックスに、>>オカドゥグ島より愛をこめて。という奇妙なタイトルのメールが届いているのに気づいた。俺はそこでミカエラとの愛を深めたことを思いだし、今となっては懐かしい思いでそのメールを開いていた。
>>やあ、テディ。久しぶりだね。
ぼくがだれかわかるかな?あのあと、君とミカエラ・ヴァネリがどうなったか、失礼ながらぼくは時折君の家の家事ロボット――シズカを通して覗き見ることがあったんだ。
覗き見る、なんて言っても、トイレやバスルームや夜に寝室のほうをちらと覗くといったような下劣なことでは当然なくってね。何かのことで困ってないかどうか、定期的に観察することが時にあるといった程度のことさ。移民局での審査も、途中から担当官が変わって、突然ラクに話が通じるようになっただろう?それもこちらでちょいと裏から手を回せば簡単に出来る程度のことに過ぎない……ああ、べつに恩着せがましい言い方をするつもりはないんだ。
単に、これもたまたま偶然――きのう、シズカの目を通して見たところ、テディ、君は一家団欒の最中のようだった。最初、てっきりぼくは「ああ、誰か親しい人でも招いて食事中なのかな」と思ったものだよ。ところが、よく見てみるとどうも違う。ディアナ・レジェンテとエルネスト・アーウィンがそこにいたことまではまあいい……けれど、会話を聞いているうちに流石にぼくも気づいたよ。ミカエラは以前の君が愛した精神が幼いほうのミカエラではなく、オペラ座のエトワールとしてのミカエラ・ヴァネリなのだということにね。
この時、ぼくがどのくらい驚いたか……いや、テディ、君のほうがぼくなんかよりずっと愕然としたことだろうね。その後、暫くただ黙って会話を聞くうち、ミカエラ・ヴァネリは恋人のエルネスト・アーウィンと元の鞘へ戻るらしいといったこともわかった。
そこでだ、親愛なるテディ。もう一度こちらへやって来る気はないかい?オカドゥグ島までやって来るのが面倒なら、アメリカ国内にある我々が拠点としている場所でもいいし……一度、直接会って話せないだろうか?
よろしく頼む。
ノア・フォークナー博士が送信してきたメールに、俺はすぐ返信した。何故なのだろう。ミカエラと出会った場所へもう一度行きたかった。まるでそこへ行けば俺の愛したミカエラがいて、もう一度愛しあえるような気がした。もちろんそんなはずはないとわかっている。とにかく、俺はこの時オカドゥグ島へもう一度戻りたくて仕方なかったのだ。
>>絶妙なタイミングでメールをくれたこと、心から有難く思う。
正直なところ、ミカエラのことではすっかり打ちのめされて、俺は今精神的にすごく参ってる。心が空っぽになって、もう何をする気にもなれないくらい……俺のような人間が、あなたのような人にとってどういった意味で有益なんだろうかとは、一年前にあなたと会った時から思ってはいた。けれど、今の俺にとっては本当に何もかもがどうでもいい。
もしフォークナー博士、あなたが何か俺にさせたい仕事があるなら、喜んでそれをしたいと思っている。
こちらこそ、よろしく頼む。
次に、さして時間を置かずにメールを送ってきたのはフォークナー博士ではなくミロスだった。今度はマイアミ空港ではなく、カナダのトロント空港へ向かえとのことだったから、俺はその通りにした。そしてトロントからキューバのハバナ入りをし、ホセ・マルティ空港から例のプライヴェート・ジェットでオカドゥグ島へ向かったわけである。
「お久しぶりです」
実際に直接会う前から、デバイス越しに顔と顔を合わせていたとはいえ――ミロスのことを懐かしい友人のように感じている自分に、俺はちょっと驚いたかもしれない。
「ミロス、君が迎えにきてくれて嬉しいよ」
俺は彼と握手し、抱擁を交わすことすらして、それからジェット機のほうへ乗り込んだ。今回は俺ひとりきりだったが、約一年ほど前、自分の座席の前にロドニー・ウエストが、通路を挟んだその隣にフランチェスカ・レイルヴィアンキが、さらに一番前の座席にはモーガン・ケリーがいて……最後に、ミカエラがミロスと一緒に乗り込んできた時のことを思いだした。
俺はそうしたあれこれについて思い返すうち、自然と瞳に涙が滲んだ。ロドニーはもういないし、あの時間をもう一度繰り返すことも二度と出来ない……けれど、ミカエラは確かに俺の隣の座席に座っている気がした。そして、腰につけたポーチからお菓子を取り出し、俺に選ばせようとした時のことを――まるでついこの間のことのように俺は思いだすことが出来た。
(ミカエラはいたんだ。確かにここに、間違いなく……)
オカドゥグ島へ到着すると、前に泊まったのと同じ二階の部屋へ行きたいとミロスに頼んだ。部屋のほうは模様替えがされているでもなく、前と同じだった。ただひとつ違うことと言えば……ミカエラとの部屋の間のドア、そこにかかっていた金鎖がなくなっていたことくらいだったろうか。
そのレリーフの施された白い扉を開くと、ミカエラと初めて結ばれたベッドがある。けれど、そこには俺のいた部屋とは違って、ジョルジュ・デ・キリコの『通りの神秘と憂愁』はなかったのだ。代わりに、何故かルノワールの『ピアノに寄る少女たち』という絵が掛かっている。
(どうしてなんだろう。俺が元いた部屋には変わらず、ダ・ヴィンチの絵が掛かってるっていうのに……)
無論、一年前のあの日、滞在客が去ってのち、絵を飾っておく意味のほうは確かになくなったことだろう。あるいは別の宿泊客がやって来るなり、バカンスへ出ていた研究員たちが戻ってくるなりして、模様替えが行われたとしてもまるで不思議ではない。けれど俺はもう一年も前のことになるというのに、ここの部屋が模様替えもされず、金の鎖と鍵がしっかり掛かったままだったとしたら――ミカエラは記憶が戻るでもなく、今も俺と幸せに暮らしていたのではないかと、そんな意味のないことを思うばかりなのだった。
(馬鹿だな……そんなはず、あるわけもないのに……)
ミカエラがかつて眠っていたベッドに突っ伏すと、俺は思う存分泣いた。声を押し殺すことさえしなかった。今になってみると後悔することばかりだ。俺はここへやって来た初日から、ミロスにでも頼んでミカエラとの間にある鎖と鍵を解いておいてもらうべきだったのに。
(しかも俺はあの時、あのミカエラに対して『少なくとも5パーセントくらいは人間そっくりのアンドロイドである可能性がある』なんて考えていたんだからな。今にして思えばまったく笑っちまうような話だ……)
ノア博士もミロスも、暫くの間俺のことを放っておいてくれた。そして、旅の肉体的疲労の蓄積や、泣いたことによる感情の解放といったこともあってか、俺が少しの間眠って目覚めると――すでにあたりは深い暗闇に包まれていたのだった。
俺はこののち、明るい廊下のほうへ出ると、妙にしーんとしていて幽霊でも出そうなホテルの中を、中央階段を下りてフロントのほうへ向かった。そこではミロスが、今はもう隠す必要のないPC画面に向かい、何かの仕事をしているところだった。
「そういや、ここはインターネットが一切使えないっていうのはそもそも最初から嘘だったんだよな」
「いえ、あながちそうとも言い切れません」と、ミロスは相変わらず人好きのする笑顔を浮かべて言った。「ミラー様が滞在当時も、地下の研究施設では部分的に使っていましたし、ここは外部からのウイルス攻撃といったものが及ばない特殊な設計がされていますから、回線自体が一般的なそれとは違いがあるのです。ところで、そろそろお腹がすいたことでしょう。コックたちに何か用意させましょうか?」
「ああ、うん……なんかすまないね。一年前のあの時もそうだけど、なんか無銭飲食するだけして、宿泊料も踏み倒して出ていった客って感じだものな。かといってそれ相応の金を支払うにしても、それはフォークナー博士がくれた百万ドルの中から僅かに戻すみたいな話だし……」
「いえ、ミカエラさまの御記憶が戻られたのは残念なことですが、それ以外ではノア博士はあなたがこちらへ来られたことを大変喜んでおられます。ミラー様と共同でお仕事のほうへ取り掛かられるのは、早くても約百年ほどのちのことになるのでないかと、そう想定しておられたようですから……」
俺はこの時、ミロスの顔の表情を見て(大したものだな)と、あらためて感心した。ミロスは悲しみと戸惑いの入り混じったような、そして心からの同情を感じさせる、巧みな顔の表情をしていたからだ。いわゆる<不気味の谷>を越えるひとつ手前のバージョンだとはとても思えぬくらい。
この瞬間、一体どこで会話というのか、連絡しあったものかはわからないながら、ミロスはマスターであるフォークナー博士の意図をキャッチし、壁にデジタル表示された時刻のほうを指し示した。
「ノア博士が、一緒に同じ部屋のほうでお食事しながら話したいとのことでございます。それで、よろしかったでしょうか?」
「あ、ああ。もちろんいいよ……」
ホテル内は不気味なくらいしんと静まり返っていた。俺たちが約一年前に滞在した時でも、宿泊客は全部で十一名と少なかったものだ。それでも、アンドロイドとはいえ従業員がいたりと、「人の気配がなんとなくする」というだけで、雰囲気のほうは随分違ったものだ。
「差し支えなかったらでいいんだけどさ」と、俺はミロスと一緒にエレベーターへ乗り込みながら言った。あの時には表示が隠されていた地下へと続くボタンを、彼はデジタルキーによって操作している。「ここへは普段、どのくらい人がいるものなんだい?つまり、地下にある研究施設の人たちっていうのは、おそらくあの時同様バカンスで外に出てるってことなんだろ?でも、普段その全員が揃った場合には……」
「結構、いらっしゃいますよ」人数についてはっきり把握しているのは間違いないのに、何故かミロスは曖昧な言い方をした。「大体、三十人くらいは……おそらくこれから、アップルゲート博士がそのあたりのことについても説明されるでしょう。あれを一体何人とカウントすべきなのか、数字に強いはずのコンピュータである私にも、少々理解の難しいところがありますもので……」
俺はてっきり、オカドゥグ島の地下施設というのは、大体地下の一階、あるいは二階部分にそれぞれ研究に関するフロアが存在するのだろうと想像していた。だが、エレベーターが相当深くまで潜っていくように感じ――次第に焦りを覚えはじめた。確かに、今や民間の核シェルターでさえ、三十数階分の地下マンションを提供しているほどなのだから、彼らの最新鋭の科学技術をもってすればなんらの造作もないことなのかもしれない。だがやはり俺は、地震や津波といった自然災害に見舞われた場合どうするのだろうと、そんなことが心配だったのである。
「大丈夫ですよ」と、ミロスは何か問われる前から、俺の顔色から言いたいことを察したようだった。あるいは、スカウトされ、初めてここへやって来た研究員というのは同じことを疑問に思うものなのだろうか?「ここは人工島なんです。最初から、地盤その他選び抜いた場所に島を作り、地下施設を設けるという前提で緻密な計算のもと建設がされています。それでも不慮の事故その他、あるいは避けられぬ自然災害が生じた場合においても――万一の緊急避難経路や、究極、島自体の破壊についても十分考慮がされていますから、ミラー様が不安をお感じなる必要はありません」
「う、うん……そりゃそうなんだろうけど、まあようするに心理的な問題なんだろうな。ミロスはダンテの『神曲』なんて知ってる?」
「はい、もちろん。こちらの施設の二階にある図書室にもありますし、私の情報データベースにも蔵書として存在しますから」
「それのさ、ダンテがウェルギリウスの案内で地獄を案内されるところがなんとなーく頭の隅のほうに思い浮かぶわけ。もちろん俺がこれから向かうのは地獄なんかじゃない。それよりもずっといい、科学技術研究所だっていうことはわかってるんだけど……」
「では、私がウェルギリウスで、ミラー様がダンテということですね」
「う、う~ん。なんかそんな言い方されると照れるけどさ……」
そんな話をしているうちに、エレベーターは地下何階層分になるかもわからぬ場所へ到着した。扉が開くと同時、暗闇の中に自動で明るい光がもたらされると、そこは細長い長方形の廊下だった。そしてその横のほうにオレンジブラウンの、よく磨き込まれた――俺の中の感覚としては、それは教会のドアを連想させるような扉だったのである。
「今度は、昔やったRPGゲームの陸の孤島にある地下室って感じだな」
「それは、どういったことでございましょうか?」
不思議そうな顔をしているミロスに、俺は肩を微かに竦めて笑ってみせた。一秒間に十億回以上もの情報処理が可能な頭脳でも、今の俺の言葉に関連する項目はなかったのだろうと思うとなんだかおかしかったのだ。
「いや、俺たち人間は君たち賢いアンドロイドと違って、記憶の中のゴミみたいなもんをなんでも結びつけて考えがちだってだけの話だよ。ほら、ここの廊下は他のどこにも通じてなくて、この部屋のドアはこのエレベーターからしかやって来れないんだろ?とりあえず、今俺の視覚で見た感じとしちゃそうだ。でも、壁の向こうには他に研究室や、研究員たちの私室や休憩室とか、色々あるってことなんだろうなと思って……」
「ああ、そういう意味ならばわかります。ただ、ここはノア博士にとって本当に特別な場所なんですよ。他の研究員たちでも、ここへ来たことのある方はほとんどいらっしゃらないと思います。ゆえに、私にはわかります。博士がどのくらいミスター・ミラーに信頼と期待を寄せているのかといった、そうしたことが……」
ミロスはそう言ったが、もしかしたらただの特殊な同情かもしれないと俺は思っていた。最愛のミカエラを失い、俺が今どれほど失意のどん底にいるかと想像し、彼にとっての特別な場所で少しくらい話でもしようかという、何かそういったような。
だが、通された部屋のほうは何か「特別」といったこともなく、極めて質素かつ平凡だった。ソファとカウチと袖椅子がそれぞれひとつずつあり、他にはあまり高価そうに見えない木製のテーブルがあるきりだった。けれど、そこには一応ワインと二客のグラスがあり、ホタテとサーモンのカルパッチョ、トマトとチーズのブルスケッタ、カプレーゼサラダ、バーニャカウダ、チキンのハーブソテー、チキンカチャトーレ、鮭のワイン蒸し……などが並んでいたものである。
「テディ、君が前に滞在中に食べていたものや、他にも食べたいものがあればなんでもミロスに頼めばいい。そしたらここまで運んでくれるから」
「え、ええ。今回はお招きいただきまして……」
壁のひとつは3Dシアターになっていた。今、そこではミカエラ・ヴァネリが――今まるで目の前にいるかのような存在感で、ふたつのバーの間で何かのヴァリエーションを踊っている。これも、世界的コリオグラファーとして有名なひとり、ロジェ・ヴァランタンがバレエの女神のために捧げた作品だということだった。バレエのわかる人間にとっては非常に難易度の高いことがわかるらしいが、俺のような素人には、やはりある程度ストーリー性がないとそのあたりについてはさっぱりということになる。
「まあそう堅い挨拶は必要ないよ。僕と君の仲じゃないか」
ノア博士はこの日も白衣を着ており、その下にはくたびれたようなワイシャツと、下にはベージュのチノパンを履いていた。
「テディ、君にとって今ミカエラの姿を見るのがつらいなら……何か映画か、くだらない環境音楽でも流しつつの芸術映像を見るとか、そんなふうにしたほうが良かったかな?」
「いえ、お気遣いは無用です。俺も、バレエのことはわからないながら、ミカエラの踊ってる姿を見るのは好きなんですよ。彼女の記憶が戻って唯一もし純粋に感謝できるとしたら、その点かもしれません……これほどの才能を、俺ひとりが独占するためだけにミカエラのことを縛ってはいけなかったのだと、理性で納得できるのはバレエに関することだけですから」
「そうか。もし、ミカエラ・ヴァネリがひとりの人間の中に生じた別人格ということでなかったら――我々にも打つ手はいくらもあったと思うんだ。たとえば、ニューヨークのテディの部屋には、まだミカエラのDNA……髪の毛でも、口を拭いた時ティッシュにつけた口紅でもなんでもいいが、そうしたものからクローンを作ること自体は可能だ。だが、今のミカエラ・ヴァネリの脳のコピーを作ったところで、その中からテディ、君の愛したミカエラの人格のみを取り出すといったことは非常に難しいか、不可能に近いことだとウェリントン博士や他の精神分析医は言うんだね」
「いえ、わかっています。そんな形ででも俺の愛したミカエラが甦ってきてくれたらどんなにいいかとは望みますが、それはしてはいけないことですから」
「…………………」
ここで、沈黙が落ちた。もちろん、今や俺にもよくわかっている。ここではそうした非合法の、ほとんど人体実験かそれに近い研究すら行われているのだろうということは。けれど、そうと認めることはつらかったが、俺が愛していたミカエラが消えたことには意味があり、『こうなるべくしてなった』ことも、少しくらいであれば理解できなくもなかったからだ。
「テディ、君は二重人格や多重人格といったものを信じるかね?」
「ええ。医学的に証明されているという言い方はなんですが、実際に会ったことはないにせよ、そうした精神状態を持つ人がいるといったことは本で読んだことがありますよ。発症の理由としては、幼少時に負ったトラウマが原因である場合が多いとか……」
(それがミカエラのこととどう関係するのだろう?)と、俺は少しばかり不思議に感じた。昔読んだことのあるノンフィクション本によると、親などから性的虐待を受け、その耐え難い記憶を別人格を生みだして押しつけることで……オリジナルの人格はそのことをすっかり忘れ去っているという、そうした原理だったように記憶している。
「僕は思うんだがね……ミカエラ・ヴァネリは幼少時からバレエの天才少女として騒がれ、ほとんど健全な少女時代のようなものがなかったのだよ。一にバレエ、二にバレエ、三四もバレエなら五もバレエ……といったような生活。本人もそのことに納得していたにせよ、別の見方をすれば非常に窮屈で異常な十代だったとも思うわけだ。『バレエのことなんかすっかり忘れて、一夏パーッと旅行でもして楽しみた~い!!』と思ったことが一度もない――なんていうことはなかったんじゃないかな。また、これがもし実の両親が相手であれば『わたしもうバレエなんてイヤっ!!』とか、我が儘を言ってレッスンさぼったりといったこともあったに違いない。けれど、バレエの才能ゆえに見出され引き取られたことから、それじゃなくても自分に厳しい彼女のことだ。自分の精神を十代の頃より抑圧しに抑圧してきた……なんていうふうには想像したことさえなかったんじゃないだろうか?」
「ミカエラが頭を打って記憶を失った時、バレエのことをまったく忘れて覚えていなかったのは、そうした部分もあったのではないかという精神分析ですか?」
「まあ、大体のところウェリントン博士による分析なんだがね。確かに、なんにも覚えてなければもう踊らなくていい……無意識のうちにもミカエラ・ヴァネリが深層意識でそう感じた可能性というのはあるんじゃないだろうか。けれど、妊娠してホルモンバランスが乱れたといった生理学的なことの他に、妊婦っていうのはとにかくじっとしてなきゃならないだろうし、バレエどころか日常動作にも何かと苦労やいつも以上の疲労を伴う。深層意識で眠っていてじっとしているミカエラと、表層意識に出ているミカエラとの間に……何か意識としてクロスするものがそのあたりであったんじゃないだろうか。妊婦なんだから仕方ないとか、この状態でいるのもあともう少しの我慢とか、そう頭ではわかっていても――この今の面倒な状態を誰かに押しつけたいとまでは言わないにせよ、代わってくれるなら別の誰かに出産の面倒なとこだけお願いしたいわとか、そういう……」
「ええ、わかります。俺だってずっとそうしたことは考えていましたから……だから、そもそも最初から避妊には気を遣って、子供なんて持たないという選択をすべきだったんじゃないかと思ってみたり。でも結局、関係なかったのかもしれない。深層意識のほうにいた元のミカエラは『もう十分休んだし、バレエを踊りたい』とずっと思っていたのかもしれない。その機が熟したら、彼女はやっぱり元の記憶を取り戻したということなのかどうか……結局のところ、すべてはわからないことです」
「今は色んなことについてシミュレーションできる科学技術があるのに、なんとも悩ましいことだと、僕も心からそう思うよ」
ノア博士は、心からの同情を込めた眼差しをしていた。現代では、今我々が認識する現実の他にも――ある意味無数の数の地球が存在する。つまり、もうひとつの地球をデジタルな仮想世界において再現することで、『ある選択をした場合、地球はどうなるか』という研究が、多くの大学や民間の研究施設で行われている。簡単にわかりやすく言ったとすれば、バタフライ・エフェクトというやつだ。たとえば、このままアマゾンの密林がどんどんなくなっていったとして、何パーセントの樹木が失われた時、地球の他の場所ではどのような影響が出るかなど、自然環境に関するシミュレーションの他に、戦争抑止のためなどにもよく用いられる。「このまま二か国間で戦争になった場合、最終的にどういうことになるか」というシミュレーションモデルを提示することで――なるべく早く戦争を終わらせるか、和平交渉するための手段として用いられることが多い。
また、個人のプライヴェートな生活においても、Aという女性や男性と結婚した未来と、Bという男性や女性と結婚した未来ではどう違うのか……といったシミュレーションを、体験しようと思えばできるらしい。またこれは時間をスキップしてある程度先の未来を覗き見ることも出来るということだった(とはいえ、これはあくまでゲームに近いものであり、結局のところ今の現実世界において同じ選択をしたところで同じ未来になるとは限らない――といった程度のことではあるようだ)。
「フォークナー博士、実は俺……あなたの下で仕事がしたいんです。ミカエラがいなくなってしまってから、心が空っぽに近い状態になっちゃって、いくら『これじゃいけない』と思ってみても、何もする気になれなくて……でも、アンドロイド工学については大学で学びましたし、ここの最先端技術に追いつくにはもっと勉強が必要でしょうが、その点については一生懸命がんばります。ですから……」
「そうか。じゃあまあ、そのあたりについてはおいおい順に説明していこうかなと思うよ」と、ノア博士は嬉しそうな顔をして言った。彼は普段は無表情で、死んだような目をしているところがあるのだが、そのかわり、口角を上げて笑ったりすると(今博士は本当に嬉しいんだな)と感じられ、こちらまで嬉しくなるほどだった。「何もアンドロイドに関することだけに限らない。ここの施設を一通り見学するなりなんなりして、自分なりに興味を持てたことについて研究というのか、何かそんなふうにしてもらえたらと思うんだ。まあ、そのことひとつに拘らず、飽きたら今度は別のことを研究テーマにしようとか、そんなことでもまるで構わないしね。とにかく、今の人生の終わり頃にでも、意識データを次の肉体に移し替えることを選ぶなら……時間のほうはたっぷりあるわけだから」
「…………………」
俺自身は今のところ、そんな先のことまでは考えられなかった。ただ、ミカエラのいない人生を送っていくのが今はつらくてならず、そこから逃げたいというそれだけだった。
(それに、今はこの一度きりの人生だけでもう自分は十分だと思っていたとしても……死というものが目前に迫ってきたとしたら――やはりその不安や恐怖から逃れたいあまり、俺はそうした誘惑に負けてしまうのだろうか……)
「いや、いいんだ。ここへ招かれた人々というのはね、いくつかパターンはあるが、大体のところ複雑な心理状態を経験して次の生をどうするかについて決定する。だから、そんなことについてもおいおい考えていけばいいことだから、今の段階で僕のほうで色々助言することは控えておくよ。それより……」
特に何か手動でスイッチを操作したということもないのに――『眠れる森の美女』のバレエシーンが消え、そこは突然にして宇宙空間へと切り換わった。しかも、正面部分の壁だけではない。天井部分も床も、左右両方の壁も、三百六十度、境目のない宇宙だった。その中で俺とノア博士とは、それぞれソファに座ったまま、テーブルの上の食事をつまんではワインを飲んでいるのだった。
「テディ、これから君に手伝ってもらおうと思っている我々の組織について、簡単にレクチャーしておこうかと思う」
俺は思わず、ごくりと喉を大きく鳴らしてワインを飲んでいた。トマトとチーズのブルスケッタも、ホタテとサーモンのカルパッチョも、チキンのハーブソテーもとても美味しかった。思わずげっぷが出そうになり、抑えるのに苦労したくらい。
「まあ、それはもしかしたら、我々は何者か、僕という人間とは一体なんなのかということの説明でもあるかもしれない。テディも知ってのとおり、僕はもう三十年以上も前に一度死んだ人間だ。そしてその最初の人生においては、ノーベル賞を受賞した著名人であったにせよ、特にその後半生は犬猫といった動物、それにアンドロイドだけに心を許す、カワイソウな老人として世に覚えられて死亡したというね。だが、実際の僕のほうは裏の科学組織の長として、非常に忙しい日々を過ごしていたんだ。何より、自分の死が刻一刻と迫っていたことから、どうにかして自分の意識を次の新しい脳組織に移植して生き延びねばならないと焦ってもいたしね……その実験がどうなったかについては、前にも一度説明したね。僕はこうして一度死を経験し、まずは一旦別の仮の肉体のほうで甦ることに無事成功した。一応、これで理論上は永遠の生命を得たとも言えたかもしれないが、まだ技術としては不十分でね。そのことについてはその後も研究を重ね、ついには現在のように安全性の高いところまでやって来ることが出来たわけだ。そして僕は、ダ・ヴィンチが飛行機を作ったり潜水服のアイディアを持っていたりしたように、他にも研究したいことが山のようにあったんだ。また、そのためには優秀な助手が必要でもあったから、『これは』という人物のことをスカウトすることにしたわけだ。どこから誰をどうやってと君は思うかもしれない。大体のところはね、テディ、君のところのシズカをハッキングした時のように、ロボットやアンドロイドの目や耳や記録を使って調査するんだ。また、こんなことを僕がひとりで出来るはずもなく、大抵のことはアンドロイドたちに手伝ってもらうわけだが、それでもあらゆる問題の最終決定を下すだけでも当時から大変だったものだ……そこで僕は、第二、第三の『僕』のコピーを作って対応することにしたんだ。そして、第二、第三、第四、第五……の『僕』が得た情報を、最終的にオリジナルである自分にフィードバックする。そんなことが可能なのかと思われるかもしれないが、可能だということはテディ、君には当然わかっているね?」
「ええ。その、こんな言い方はなんですが、博士もご承知のとおり、それはそれほど突飛なアイディアではありません。人間ひとりの脳ではそうした並列情報処理に限界があったにせよ、我々の外にハードディスクドライブがあれば……十分可能なことです」
そしてこの時俺が思っていたことというのが実は、前に俺とここオカドゥグ島で対応してくれたノア博士は何番目の彼であり、今目の前にいる彼と同一人物なのかどうかということだったかもしれない。結局、そのような形で情報を何人もの『ノア・フォークナー』が共有しているのであれば――それが七番目だろうと、百飛んで五番目であろうと、どちらでも同じということではあるにせよ。
「その通りだ。僕が自分のことを多少なり特殊であると自負するのはね、そうしたことが理論上は一応可能であるとされていたにせよ、誰も実際はそこまですることもなく出来もしなかった時代、誰にも知られぬ形でそれを実行へ移した点かもしれない。でも当時はとにかく信頼できる人材が今以上に乏しかったものでね、その上時間もないとなれば、他に手がなかったのだよ。テディ、君はもしかしたら僕のことを『そんな恐ろしい奴だったのか。なんという気味の悪い奴だ』と思うかもしれないが……」
「いえ、それはありません」と、俺はきっぱりした口調で言った。「最初に会った時から、俺のあなたに対する好意と尊敬は変わりありません。また、今聞かされていることも、予想していたわけではありませんが、実際のところもっと凄いことがここの研究所では行れているのだろうと想像していました。また、ここの科学研究機関の総裁というか、総責任者であるノア・フォークナー博士の下で働くということは、表の世界から姿を消し、裏の世界で生きることを意味しており、こちらの世界を垣間見てから「やっぱり表の世界へ戻りたいや」というくらいなら……その程度の覚悟しかないのなら、俺は今ここへ来ていません」
ノア博士の人柄への好意、というのは本当のことだった。最初に相手と話した時の第一印象というのは、確かに絶対のものとまでは言えない。だが、俺はそうした勘が当たるほうだった。むしろ、第一印象の悪い人間でも『いや、そんなことを思うのはいけない』とか、『彼もよく知ればきっといい点が……』と頑張ってつきあううち、それが良いほうに転じた例のほうが極めて少ない。ゆえに、俺は自分のこの勘が外れ、ノア・フォークナーのことを「コイツ、実はただの怪物じゃないか」――と時が経つにつれ感じるようになったにせよ、それはそれでいいと思っていたのだ。
「そうか。ただ、ひとつこのことだけはわかって欲しいんだ。僕だって、今の何人もの世界中に散らばる自分を統合している自己……などというものになりたくてなったわけじゃないんだ。今だって、それが最適解だと思っているわけでもない。単に、過去のある時点においてはそれ以外打つ手がなかったというそれだけの話でね。この犠牲については、自分で選んだことなのだから犠牲などと呼ぶことも出来ない――また、そのように選択したのは自分なのだから、神でさえも恨むことは出来ない。ここが、なんとも今という時間と空間を生きる僕のつらいところかな。かといって、ここのいくつにも分かれている科学組織部門について、そのすべての責任者が僕というわけでもない。たとえば、サイバー関係についていえば、アンドロイドだけでも事足りるとも言える。それでも何かあった時のための抑止機関として、頂点に立っているのは人間である必要があるけどね……また、ここに密接した機関として裏の諜報機関というものもある。今から約一年前にスカウトしたモーガン・ケリーは、実に優秀な指揮官として今もそこで働いてくれているよ」
「彼女、元気なんですね。良かった……あと、幸せかどうかもわかるといい気もするけれど、そんなことはどう定義するかにもよるといったところかな」
「そうだね。モーガンはいまや特段もう一度結婚して幸せになりたいとか、そうした一般的な望みを持っているというわけでもなさそうだし……仕事が一番面白くてそれが生き甲斐になってはいるようだ、とは言えるかな」
モーガンは、自分を助けてくれた神の正体を知ることが出来たのだろう。そして、その裏のCIAとも言うべき組織で働くことに生き甲斐と喜びを覚えているというのなら――それが一番ではないかと、俺はそんな気がしていた。
>>続く。