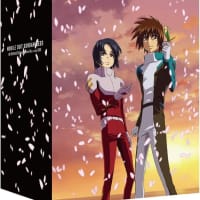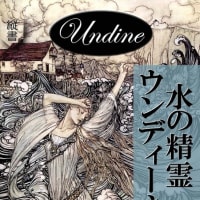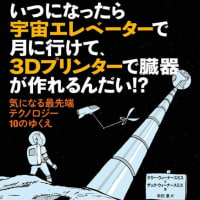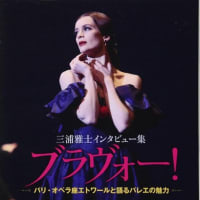>>萩尾さんと同居するようになった後、増山さんと3人で一緒に映画、コンサート、美術展など様々な文化的な場所によく出かけるようになりました。たびたび映画を観にいったのは、池袋駅の東口にあった「文芸坐」です。3本ぐらいを同時上映するので、それを全部観るわけです。
帰りに喫茶店でお茶を飲みながら、おしゃべりをしました。同じものを見ても、考えることや感じることは全然違うので、学ぶことがとても多かったです。ふだんは、萩尾さんのことは「モーさま」、増山さんは「ノンたん」、私は「ケーコタン」と呼び合っていました。
1971年に描いた私の短編『ガラスの迷路』では、合唱部の11人の仲間の中に、2人の名前を流用した「増山典子」「萩尾英」「高見望都」という人物を登場させました。私ですか?「飯塚恵子・ケーコタン」として登場させました。
(『扉はひらく いくたびも』中央公論新社より)
>>『みんなでお茶を』は、シリーズもののファンタジーSFの3作目でした。この作品の仲良し精霊のキャラクター3人のうち、2人は増山さんと竹宮先生をモデルにしていました。主人公のダーナは萩尾の理想的冒険型モデルとでも言いますか、私ができないことやってもらっていたのです。描きながら、もうこのシリーズは描けないなと気がつきました。
仲良し精霊の3人キャラクターというのが辛かったからです。描く前に気がつけよ、と、自分で突っ込みました。
でも、好きなキャラクターだったので、動かせるかもしれないと思ったのですね。ネームまではできましたが、絵に入るとため息ばかりついてしまいました。このシリーズは続きがありましたが、以後、描いていません。
ああ、私はやっぱり、今後は二人に会うのは無理だな、と思いました。
(『一度きりの大泉の話』萩尾望都先生著/河出書房新社より)
『ガラスの迷路』が収録された、竹宮惠子SF短篇集1「告白」と、『精霊狩り』シリーズが収録された『10月の少女』をそれぞれ購入して読みました。そうです。ただ、『一度きりの大泉の話』と『扉はひらく いくたびも』に上記のように書いてあったがゆえに買ったのでした

『ガラスの迷路』は1971年10月発表で、『精霊狩り』シリーズは3作あって、第1作目は1971年5月、第2作目の「ドアの中のわたしの息子」は、1972年2月、第3作目の「みんなでお茶を」は1974年2月発表です。
ちなみに、おそらく竹宮先生が当時、本当に盗作されたと思っていたらしい『11月のギムナジウム』は1971年11月発表、大泉サロンの解散が1972年11月ごろなのかなって思います。「一度きりの大泉の話」の第2章のタイトルに、「大泉の始まり――1970年10月」とあって、「少年の名はジルベール」に、大泉サロンと呼ばれていた長屋は二年契約で、契約が切れる時に別の場所へ引っ越すことを竹宮先生は決断された、みたいにあるので →
→
そして、萩尾先生が竹宮先生と増山さんが引っ越した先のOSマンションに呼びだされ、盗作疑惑をかけられたのが1973年の3月半ばごろ……ということだったので、『精霊狩り』シリーズの第3作目は、完全に仲違いしてしまったあとの、最後の原稿ということなのかなって思います
で、わたしが萩尾先生の作品を順番に読んでいこうと思うに当たって、『10月の少女』を次に選んだのは、まずこの『精霊狩り』が収録されているということと、他に『一度きりの大泉の話』にも言及のある、『あそび玉』という作品が収録されているという、このふたつの理由がありました。ちょっと、『あそび玉』に関しては竹宮先生の代表作である『地球へ……』という作品の設定と似たところがあるので、これはまた別の記事であらためて書こうと思っていますm(_ _)m
なんにしても今回は、とりあえず『ガラスの迷路』と『精霊狩り』シリーズのことについてのみ、話を絞りたいと思っていたり。じゃないといつも通り無駄に文章が長くなる気がするので(^^;)
わたしがこのふたつの作品に注目したのは、竹宮先生と萩尾先生の関係がうまくいっている時期、その頃お互いをどんなふうな存在として捉えていたか……みたいに、多少わかるところがあるかなと思ったからなんですよね。相手の存在を漫画の登場人物として描くということは、「わたしはあなたをこういう感じの人として見てますよ 」とわかることでもあるし、またその作品は当然相手も読むわけですから、そのあたりの配慮もあるんじゃないかな……と思ってのことでした。
」とわかることでもあるし、またその作品は当然相手も読むわけですから、そのあたりの配慮もあるんじゃないかな……と思ってのことでした。
で、ですね。結果として言うと、一番面白かったのは増山法恵さんの人物造形です(笑)。『ガラスの迷路』のほうには、増山典子という女の子、またもうひとり、のんちゃんと呼ばれている女の子も、増山さんがモデルなのかなと思われ……で、『精霊狩り』シリーズのほうでは、増山さんはリッピという女の子として登場するんですよね。そして、この作品中で描かれてるイメージって、わたしが『一度きりの大泉の話』と『少年の名はジルベール』で読んだ増山さんイメージとまさにドンピシャ☆でした(^^;)
そして、萩尾英(えい)くんは男の子なのですが、ハンサムで「正義の味方くん」と呼ばれていたりします。これはたぶん、竹宮先生が最初、萩尾先生のことを「男の人かもしれない」と思っていたことに由来するものなのではないでしょうか。そして、萩尾英という名前から連想される容姿をした男の子といった感じがします。
そしてもうひとりの萩尾先生がモデルと思われる、高見望都(たかみもと)さんは――萩尾先生の天然っぷりが伺えるようなキャラでないかと思いました(笑)。というのも、高見望見さんというキャラは、11人いる合唱部員のひとり、佐藤順一くんと、かみあわない会話をしていたりするからなのでした。
佐藤順一くん:「きのう食べたサンマ悪くてあたっちゃってさ」
高見望都さん:「そう言えばもうすぐ秋ね。空が高くてロマンチック!」
……こうした感じの会話のかみあわなさ(?)は、おそらく大泉サロンがはじまった頃から萩尾先生に見られる現象だったのではないでしょうか(つまり、竹宮先生はそれをうまく捉えて表現されたのではないかと思われます・笑)。
それはさておき、この『ガラスの迷路』、「一度きりの大泉の話」のほうにも言及があって、そちらで萩尾先生はこんなふうに書いておられます。
>>竹宮先生はその頃、『週間少女コミック』に載せる『ガラスの迷路』のネームをやっておられました。原稿のベタとか消しゴムかけのお手伝いをしたと思います。お手伝い中は、部分・部分のページがやって来るので、全体の話がわかりません。完成した作品を読んだのは週刊誌に掲載されてからです。それは夢の世界を彷徨う何か悲しい少年の話でした。シュールで少し難しかったです。「難しい題材だと思うけど、ぐいぐい引き込んで読ませてしまう、すごいなあ」と思いました。
(『一度きりの大泉の話』萩尾望都著/河出書房新社より)
わたし個人の『ガラスの迷路』の感想はというと――とりあえず、話のほうに整合性がないと思うんですよね(^^;)冒頭で須田マモルくんという12歳の病弱な男の子が、心臓発作を起こして死んでしまう。で、このマモルくんという男の子、先天性心臓疾患を持っていて、病院のほうでも家でも閉じこもりきりの生活で、庭のオブジェの11個だけを友達にして育った子でした。そしてこの死んだはずのマモルくん、突然学校に姿を現し、11人の合唱部員の生徒のことを家に招待します。この11という符号があるゆえに、そのあたりのことが作中で明かされるのかと読者としては期待してしまいますが、そんなこともなく……この11人のことを色々知っていると思しきマモルくんは、工藤ちよ子が萩尾英のことを好きだということをバラしてしまい、怒った増山典子ちゃんに引っぱたかれてしまいます。
>>「友だちに……なろうですって。その友だちをどんなにキズつけたか……あなたわかってるの!?親友同士のあいだでは知ってても言っちゃいけない公然の秘密がある――それも知らず、なにが友だちになりたいよ!あなたは友だちのつくりかたを知らないの!?」
この言葉にぐっさり傷つくマモル。確かに、ずっと病院や家に閉じこもってばかりいた彼の人生では、友達の作り方がわからなくても無理はありません。その後、11人はガラスの迷路に走りこむマモルくんの姿を追いかけますが、結局のところ追いつけず……この日の夜、11人は同じ夢を見、そのことをお互いに電話で連絡を取り合って知ります。その夢とは、マモルくんが出てきて三時三十六分プラットホーム――といったように告げるという夢です(ちなみに、この時刻はマモルくんが冒頭で死亡したとされる時刻です)。
11人は学校が終わると同時、まっすぐ駅へと向かいます。三時三十六分に出る電車などないのですが、そこで11人は見ました。白い人に抱かれて眠る、マモルくんの姿を……そしてこの、何かぼやっと霞んだような、しなやかな体つきの女性(天使?)に抱かれて、マモルくんは来るはずのない電車に乗って逝ってしまうのでした。。。
――ざっとかいつまんで言ったとすれば、こんな感じのお話です。お話のほうに整合性はないのですが、何故か不思議と心に残るお話だと思いました。そして、この続篇に『扉はひらく いくたびも』という、再びマモルくんが主人公のお話があるのですが、こちらもお話に整合性のほうはありません。『ガラスの迷路』のほうでそのあたりストーリーで失敗したので、こちらではそのあたりの回収をしようという試みがあるかと思いきや、特にそんなこともなく――マモルくんはまたしても友だちを得られず失敗する……何か、そうした悲しい孤独を背負ったまま終わります。
でも不思議と、この「悲しい孤独」という部分が、「なんとなくいいな」と思いました。12歳で亡くなった男の子が、「友だちが欲しい」と願っているにも関わらず、結局のところ果たされずに終わってしまう……ジョバンニとカムパネルラの別れのような悲しみではなく、他の子供たちはみんな大人になってゆくのに、自分は永遠にそこから置いていかれてしまうという悲しみ。
さて、『ガラスの迷路』の感想のほうが長くなってしまいましたが、『精霊狩り』のほうはなんていうかまあ、主人公のダーナが萩尾先生で、同じ精霊の友だちにリッピとカチュカという女の子がいます。で、リッピに関しては、『ガラスの迷路』の増山典子さんと同じく、わたしの頭の中にあった「増山法恵さんってきっとこんな感じの人では? 」といったイメージと、ばっちり合致しています。一方、カチュカのほうは眼鏡をかけた少し地味目の女性かな??といったイメージなのですが、カチュカのことはとにかく好きです
」といったイメージと、ばっちり合致しています。一方、カチュカのほうは眼鏡をかけた少し地味目の女性かな??といったイメージなのですが、カチュカのことはとにかく好きです
それで、ですね。わたしこの『精霊狩り』シリーズを読んで、竹宮先生のことが好きになりました。萩尾先生の目から見た竹宮先生って、こんな感じの性格の人だったっていうことなんだろうなあ……と思ったら、まあ、簡単にいえば、お互い関係がうまくいってる間はこのくらい心を許してたんだろうな、みたいに思ったんですよね(^^;)
「一度きりの大泉の話」も、「少年の名はジルベール」も、その後関係が破綻してしまうとわかっているせいか、そこに至る前段階においてはすっごくとっても仲が良かった――みたいにはあえて書かれていないというだけで、実際はこのくらいお互いに気を許しあってたんだろうなあ、みたいに思ったというか。
>>それで増山さんに連絡をしました。両親を説得できたので上京できる。竹宮先生にも説明した。これから家を探したい、できれば、今年中ぐらいに引っ越せれば良いと思う。そう言うと増山さんは「それなら私が、二人が住めるような良い物件を探すから任せて。竹宮さんとも話して、ちゃんと見つけておくから」と、あっという間に「いいところが見つかったのよ!うちのすぐ近くなの!」と連絡をくれました。
なんと、増山さんは、自分の家の斜め向かいにある貸家を見つけたのでした。あの、キャベツ畑のそばの。貸家は2階建ての家で、小さな前庭がありました。畑の中に点在する長屋にも建売の住宅にも、よく庭がついていました。なんだか長閑でした。「ねえ、早く、引っ越してらっしゃいよ!」
とにかくこれで上京の準備はできました。
>>大泉の家は2階建ての半長屋で1階が4畳半、台所、風呂、トイレ、2階が3畳と6畳、前庭付き、家賃と食費を竹宮先生と私で折半することに決まりました。
小さな前庭は日当たりが良く、花や野菜を植えたら良く育ちそうでした。増山さんは八百屋や肉屋や豆腐屋など近所の店を教えてくれたり、細々した生活の買い物の手伝いなどをしてくれました。私たちが住む長屋の居心地も良かったのでしょう。増山さんは毎日のように遊びに来ました。食事をし、泊まっていきました。
2階の6畳に布団を並べ、私たちはぎゅうぎゅう布団に潜り込んで、眠り込むまでおしゃべりしました。
(『一度きりの大泉の話』萩尾望都先生著/河出書房新社より)
なんていうか、「一度きりの大泉の話」と「少年の名はジルベール」を読み比べて思うのは、竹宮先生と増山さんは「少年愛(BL)」のことで双子のように方向性が一致していたのかもしれません。また、おふたりはこのことを<運命>といったようにもおっしゃっています。でも、読者という第三者として読む分には……萩尾先生だって竹宮先生と増山さんにとって<運命>だったはずだし、その後嫉妬や盗作疑惑といったような複雑な問題が出てくるまでは――そのままいったとすれば「わたしたち三人の出会いは本当に運命だったよね!」と、今もそう言ってたはずなのです。
でも、何故そうならなかったかについては、この2冊の本を読めばわかることとはいえ……「一度きりの大泉の話」を読んでから「少年の名はジルベール」を読むと、竹宮先生がこの本を書いて発表できたのは、増山さんがいらっしゃったからじゃないかなと思いました。何故かというと、増山さんがいなくて「少年の名はジルベール」を発表した場合、もしかしたら萩尾先生か、萩尾先生が今も親しくしておられる漫画家先生の誰かから、「ん?そーだったっけ? 」みたいに疑問を呈される可能性がないとは言えない気がする、というか。でも、竹宮先生にとっては増山さんさえ味方でいてくれて、「でもわたしたちの間ではこーだったわよね?」と話しあえれば、多少そうした攻撃があっても全然平気でいられるという、そうした部分があったんじゃないかな……と思ったりしたんですよね(^^;)
」みたいに疑問を呈される可能性がないとは言えない気がする、というか。でも、竹宮先生にとっては増山さんさえ味方でいてくれて、「でもわたしたちの間ではこーだったわよね?」と話しあえれば、多少そうした攻撃があっても全然平気でいられるという、そうした部分があったんじゃないかな……と思ったりしたんですよね(^^;)
なんにしても、例によって長くなってしまったのでそろそろ終わらせようと思うのですが(汗)、『10月の少女』に収録されている「十年目の鞠絵」については、実は「10年目の(増山)法恵」といったようにも読める気がする――とか、他にも書きたいこと色々あったのですが、そのあたりについてはまた、いずれ機会があったらということにしたいと思いますm(_ _)m
それではまた~!!