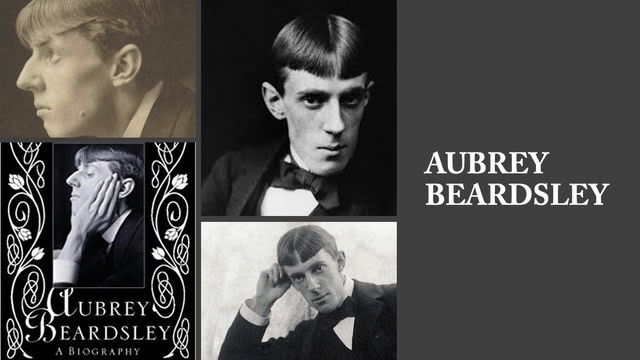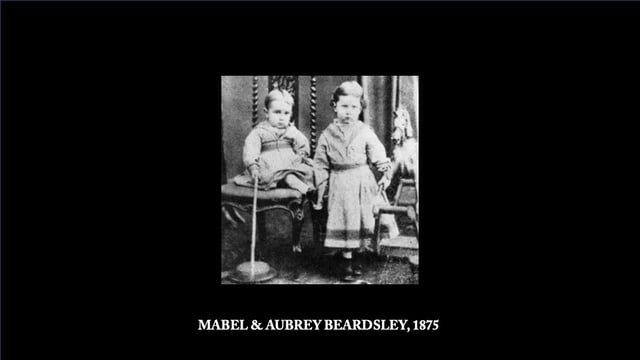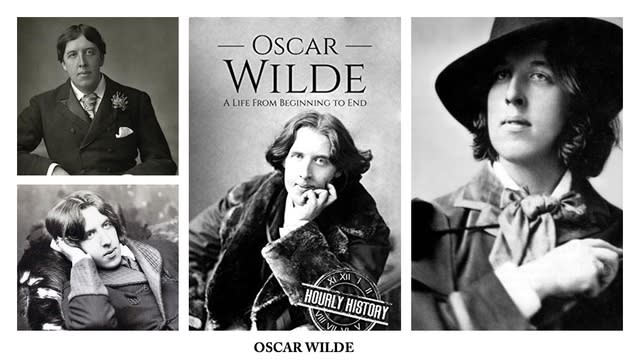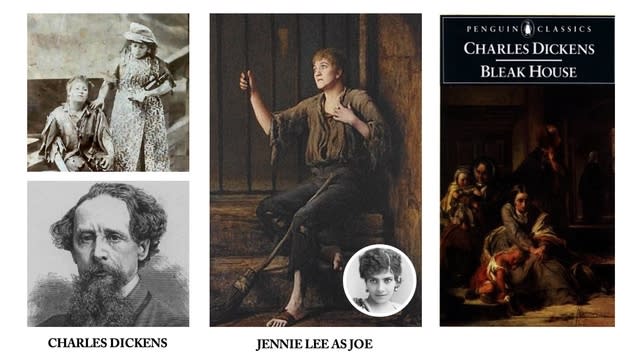春休みが終わり、ゴールデンウィークが始まる前の4月の平日の午後、ディズニーランド好きの妻にいざなわれ、ディズニーランドに行ってきました。その日はそれほど混んでいなかったので、人気の「美女と野獣」など数々のアトラクションを待ち時間があまりなく見ることができました。
その中で、「ファンタージーランド・フォレストシアター」で行われていた「ミッキーのマジカルミュージックワールド」というショーも観ることができました。森の中の劇場という雰囲気なのですが、中は1500人くらいが収容できる本格的な劇場でした。約25分くらいのパフォーマンスも想像以上に素晴らしく、ダイジェスト版のミュージカルを観ている感じでした。
全席指定なので、行列に並ぶという必要はないのですが、劇場の建物の前が小さな広場になっています。ディズニーランドは、いろんな物語が随所に散りばめられているのですが、実はこの広場の壁面に飾られている演劇ポスター、これをじっくり眺めずに素通りしてしまうのは非常にもったいないと思いました。
私はディズニーに関してはそんなに詳しいわけではないのですが、大学で英文学を専攻していたし、演劇は自分でも学生時代、シェイクスピア劇で舞台にも立ったこともあり、ミュージカルや演劇もいろいろ観ておりました。
そんな私にとって、ここに飾られている演劇ポスターはそれぞれが魅惑的な芸術作品でした。これに興味を持った人がどれくらいいるのかわかりませんが、そのまま見過ごされてしまうのが忍びないので、このポスターについて語っておきたいとおもいます。
壁面に飾られているのは、過去に上演された演目ということなのか、これから上演予定の演目なのかはわかりませんが、森の中のこのシアターがこの国(ファンタジーランド)の演劇の中心地であるという演出なのだと思いました。
“Cat on a Hot Thin Roof” (熱い薄屋根の猫)

このポスターには、『おしゃれキャット』のマリーが描かれていますが、実は『熱いトタン屋根の猫』という演劇作品へのオマージュとなっています。
オリジナル作品のタイトルは、“Cat on a Hot Tin Roof”(日本語では『熱いトタン屋根の猫』)。『ガラスの動物園』や『欲望という名の電車』で有名なアメリカの劇作家、テネシー・ウィリアムズによる戯曲です。1955年にニューヨークで初演され、ピューリッツァー賞を受賞しています。
癌で余命いくばくもない米国南部の大富豪の農園主。同性愛の恋人を失った次男は酒に溺れ、妻は愛を取り戻そうと悩む。長男とその妻は父の財産を狙い、農園主の誕生日に集まってくるという話。1958年にエリザベス・テイラー、ポール・ニューマンの主演で映画化されている作品です。
こちらが映画のビデオクリップです。
このポスターによれば、この戯曲を演じるのは、『おしゃれキャット』に登場する子猫のマリーということです。『おしゃれキャット』(原題: The Aristocats)は1970年に公開されたアニメーション映画で、日本では1972年に公開されています。
この映画のビデオクリップはこちらです。
この映画ではまだあどけない子猫のマリーなのですが、『熱い薄屋根の猫』が彼女のデビュー作となり、いきなり円熟した女性の役を演じるというギャップがいいですね。タイトルの“Tin Roof”(トタン屋根)が“Thin Roof”(薄い屋根)となっているところがミソです。
ポスターのタイトルの左下に、小さめの文字で“Love,Betrayal, Shoddy Architecture, This play has it all!”(愛と裏切り、そしてしょぼい建築構造。このお芝居にはその全てがある!)と書かれています。「薄い屋根」なので、「しょぼい建築構造」なんですね。
“Pigmalion” (ピグマリオン)

『クマのプーさん』に登場するピグレットというキャラクターが描かれていますが、バーナード・ショーの演劇作品『ピグマリオン』へのオマージュになっています。
オリジナルのタイトルは“Pygmalion”で、アイルランド出身の英国の作家バーナード・ショーが1912年に書いた戯曲です。1938年に映画化されていますが、その後、舞台ミュージカルとなったのが、『マイフェアレディ』で、オードリー・ヘプバーン主演で映画化されています。『マイフェアレディ』の原作がバーナード・ショーの『ピグマリオン』だったのですね。
こちらが映画『ピグマリオン』のビデオクリップです。
この「ピグマリオン」という話の原作は、ギリシャ神話の、彫刻に恋してしまうキプロス王の話(彫刻に命が吹き込まれ人間の女性に変身する)なのですが、心理学で「ピグマリオン効果」という言葉も使われます。他者から期待されると学習効果が向上するということですね。
このポスターでは、“Pygmalion”の“Pyg”が“Pig”という綴りになっています。主演はピグレットということですが、このピグレットというのは、ピンクの耳の子ブタのぬいぐるみで、プーさんの親友なのですね。プーさんやクリストファー・ロビンといっしょに、100エーカーの森に住んでいると言われています。こちらがピグレットが登場している動画です。
この左上にフクロウが描かれていますが、『ピグマリオン』の中で登場する言語学者のヒギンズ教授の役だと思います。『クマのプーさん』の中に登場するフクロウは、プーさんたちといっしょに100エーカーの森に住んでいて、物知りで、長老的な存在と言われています。こちらがフクロウが登場するビデオクリップ。
子豚のピグレットがフクロウの指導を受けてどのような淑女に変身していくのか見ものです。
“Who’s Afraid of the Big Bad Wolf?” (狼なんか怖くない)

これは、“Who’s Afraid of Virginia Woolf?”(バージニアウルフなんて怖くない)という戯曲のパロディーかと思っていたら、ディズニーの『三びきの子ぶた』の中で歌われる“Who’s Afraid of the Big Bad Wolf”(おおかみなんか怖くない)のほうが先だったのですね。
“Who’s Afraid of Virginia Woolf?”(ヴァージニアウルフなんて怖くない)というのは、エドワード・オルビー(Edward Albee)の有名な戯曲で、1962年にブロードウェイで初演された作品です。
二組の夫婦の偽善的な関係が描かれていて、1963年にトニー賞を受賞、20世紀アメリカ演劇の代表的な作品のひとつと言われています。1966年にはエリザベス・テイラー、リチャード・バートン主演で映画化され、同年のアカデミー賞で五部門を獲得した作品です。
こちらがその映画のビデオクリップです。
ちなみにヴァージニア・ウルフというのは、1882年生まれの英国の小説家で、モダニズム文学の代表的存在と言われていますが、本人はフェミニストでレズビアンで、59才で入水自殺をした人物です。

で、ディズニーのポスターに登場しているビッグバッドウルフなのですが、ディズニーの『三匹の子ぶた』(Three Little Pigs)に登場する悪役キャラクターです。『三匹の子ぶた』は1933年に公開されたアニメーション短編映画ですが、ビッグバッドウルフはその後、『赤ずきんちゃん』(1934)、『オオカミは笑う』(1936)、『働き子ぶた』(1939)に等にも出演しています。
こちらは『三匹の子ぶた』のビデオクリップです。
“King John” (キング・ジョン)

“King John”(ジョン王)はウィリアム・シェイクスピアが書いた歴史劇で、あまり有名作品ではないのですが、日本では、蜷川幸雄氏がシェイクスピア全作上映を目指し、吉田鋼太郎氏が途中からその遺志を引き継いだ「彩の国シェイクスピア・シリーズ」の第36弾作品として上演される予定だったのが 『ジョン王』でした。コロナ禍で、2020年6月に予定されていた公演は中止になってしまったので、幻の演目になってしまいましたが。
こちらがそのプロモーション動画です。
ディズニーのポスターの「ジョン王」ですが、主演がプリンス・ジョンとなっています。プリンス・ジョン(Prince John)は、映画『ロビン・フッド』に登場する悪役で、イングランド王子という設定です。家臣である蛇のサー・ヒスの催眠術を利用し、国王である兄のリチャード王を一時的に追い出して自分が臨時の王になるのですが、税金を取ることしか考えていないという人物。ここで活躍するのがロビン・フッドなんですね。
『ロビン・フッド』(Robin Hood)は、1973年公開の長編アニメーションで、日本では1975年に公開されています。こちらがそのプロモーション動画。
ポスターの上部に、“Love, Deceit and Taxes”(愛、裏切り、そして税金)と書いてありますが、アニメの中でプリンス・ジョンが税金の取り立てが大好きだったことを意味しているのですね。
これら4つのポスターは架空の演目なのですが、実際に見てみたくなりますね。劇場ポスターといえどこんなに深いストーリーがあるのを知ると、時を忘れて鑑賞していたいです。
その中で、「ファンタージーランド・フォレストシアター」で行われていた「ミッキーのマジカルミュージックワールド」というショーも観ることができました。森の中の劇場という雰囲気なのですが、中は1500人くらいが収容できる本格的な劇場でした。約25分くらいのパフォーマンスも想像以上に素晴らしく、ダイジェスト版のミュージカルを観ている感じでした。
全席指定なので、行列に並ぶという必要はないのですが、劇場の建物の前が小さな広場になっています。ディズニーランドは、いろんな物語が随所に散りばめられているのですが、実はこの広場の壁面に飾られている演劇ポスター、これをじっくり眺めずに素通りしてしまうのは非常にもったいないと思いました。
私はディズニーに関してはそんなに詳しいわけではないのですが、大学で英文学を専攻していたし、演劇は自分でも学生時代、シェイクスピア劇で舞台にも立ったこともあり、ミュージカルや演劇もいろいろ観ておりました。
そんな私にとって、ここに飾られている演劇ポスターはそれぞれが魅惑的な芸術作品でした。これに興味を持った人がどれくらいいるのかわかりませんが、そのまま見過ごされてしまうのが忍びないので、このポスターについて語っておきたいとおもいます。
壁面に飾られているのは、過去に上演された演目ということなのか、これから上演予定の演目なのかはわかりませんが、森の中のこのシアターがこの国(ファンタジーランド)の演劇の中心地であるという演出なのだと思いました。
“Cat on a Hot Thin Roof” (熱い薄屋根の猫)

このポスターには、『おしゃれキャット』のマリーが描かれていますが、実は『熱いトタン屋根の猫』という演劇作品へのオマージュとなっています。
オリジナル作品のタイトルは、“Cat on a Hot Tin Roof”(日本語では『熱いトタン屋根の猫』)。『ガラスの動物園』や『欲望という名の電車』で有名なアメリカの劇作家、テネシー・ウィリアムズによる戯曲です。1955年にニューヨークで初演され、ピューリッツァー賞を受賞しています。
癌で余命いくばくもない米国南部の大富豪の農園主。同性愛の恋人を失った次男は酒に溺れ、妻は愛を取り戻そうと悩む。長男とその妻は父の財産を狙い、農園主の誕生日に集まってくるという話。1958年にエリザベス・テイラー、ポール・ニューマンの主演で映画化されている作品です。
こちらが映画のビデオクリップです。
このポスターによれば、この戯曲を演じるのは、『おしゃれキャット』に登場する子猫のマリーということです。『おしゃれキャット』(原題: The Aristocats)は1970年に公開されたアニメーション映画で、日本では1972年に公開されています。
この映画のビデオクリップはこちらです。
この映画ではまだあどけない子猫のマリーなのですが、『熱い薄屋根の猫』が彼女のデビュー作となり、いきなり円熟した女性の役を演じるというギャップがいいですね。タイトルの“Tin Roof”(トタン屋根)が“Thin Roof”(薄い屋根)となっているところがミソです。
ポスターのタイトルの左下に、小さめの文字で“Love,Betrayal, Shoddy Architecture, This play has it all!”(愛と裏切り、そしてしょぼい建築構造。このお芝居にはその全てがある!)と書かれています。「薄い屋根」なので、「しょぼい建築構造」なんですね。
“Pigmalion” (ピグマリオン)

『クマのプーさん』に登場するピグレットというキャラクターが描かれていますが、バーナード・ショーの演劇作品『ピグマリオン』へのオマージュになっています。
オリジナルのタイトルは“Pygmalion”で、アイルランド出身の英国の作家バーナード・ショーが1912年に書いた戯曲です。1938年に映画化されていますが、その後、舞台ミュージカルとなったのが、『マイフェアレディ』で、オードリー・ヘプバーン主演で映画化されています。『マイフェアレディ』の原作がバーナード・ショーの『ピグマリオン』だったのですね。
こちらが映画『ピグマリオン』のビデオクリップです。
この「ピグマリオン」という話の原作は、ギリシャ神話の、彫刻に恋してしまうキプロス王の話(彫刻に命が吹き込まれ人間の女性に変身する)なのですが、心理学で「ピグマリオン効果」という言葉も使われます。他者から期待されると学習効果が向上するということですね。
このポスターでは、“Pygmalion”の“Pyg”が“Pig”という綴りになっています。主演はピグレットということですが、このピグレットというのは、ピンクの耳の子ブタのぬいぐるみで、プーさんの親友なのですね。プーさんやクリストファー・ロビンといっしょに、100エーカーの森に住んでいると言われています。こちらがピグレットが登場している動画です。
この左上にフクロウが描かれていますが、『ピグマリオン』の中で登場する言語学者のヒギンズ教授の役だと思います。『クマのプーさん』の中に登場するフクロウは、プーさんたちといっしょに100エーカーの森に住んでいて、物知りで、長老的な存在と言われています。こちらがフクロウが登場するビデオクリップ。
子豚のピグレットがフクロウの指導を受けてどのような淑女に変身していくのか見ものです。
“Who’s Afraid of the Big Bad Wolf?” (狼なんか怖くない)

これは、“Who’s Afraid of Virginia Woolf?”(バージニアウルフなんて怖くない)という戯曲のパロディーかと思っていたら、ディズニーの『三びきの子ぶた』の中で歌われる“Who’s Afraid of the Big Bad Wolf”(おおかみなんか怖くない)のほうが先だったのですね。
“Who’s Afraid of Virginia Woolf?”(ヴァージニアウルフなんて怖くない)というのは、エドワード・オルビー(Edward Albee)の有名な戯曲で、1962年にブロードウェイで初演された作品です。
二組の夫婦の偽善的な関係が描かれていて、1963年にトニー賞を受賞、20世紀アメリカ演劇の代表的な作品のひとつと言われています。1966年にはエリザベス・テイラー、リチャード・バートン主演で映画化され、同年のアカデミー賞で五部門を獲得した作品です。
こちらがその映画のビデオクリップです。
ちなみにヴァージニア・ウルフというのは、1882年生まれの英国の小説家で、モダニズム文学の代表的存在と言われていますが、本人はフェミニストでレズビアンで、59才で入水自殺をした人物です。

で、ディズニーのポスターに登場しているビッグバッドウルフなのですが、ディズニーの『三匹の子ぶた』(Three Little Pigs)に登場する悪役キャラクターです。『三匹の子ぶた』は1933年に公開されたアニメーション短編映画ですが、ビッグバッドウルフはその後、『赤ずきんちゃん』(1934)、『オオカミは笑う』(1936)、『働き子ぶた』(1939)に等にも出演しています。
こちらは『三匹の子ぶた』のビデオクリップです。
“King John” (キング・ジョン)

“King John”(ジョン王)はウィリアム・シェイクスピアが書いた歴史劇で、あまり有名作品ではないのですが、日本では、蜷川幸雄氏がシェイクスピア全作上映を目指し、吉田鋼太郎氏が途中からその遺志を引き継いだ「彩の国シェイクスピア・シリーズ」の第36弾作品として上演される予定だったのが 『ジョン王』でした。コロナ禍で、2020年6月に予定されていた公演は中止になってしまったので、幻の演目になってしまいましたが。
こちらがそのプロモーション動画です。
ディズニーのポスターの「ジョン王」ですが、主演がプリンス・ジョンとなっています。プリンス・ジョン(Prince John)は、映画『ロビン・フッド』に登場する悪役で、イングランド王子という設定です。家臣である蛇のサー・ヒスの催眠術を利用し、国王である兄のリチャード王を一時的に追い出して自分が臨時の王になるのですが、税金を取ることしか考えていないという人物。ここで活躍するのがロビン・フッドなんですね。
『ロビン・フッド』(Robin Hood)は、1973年公開の長編アニメーションで、日本では1975年に公開されています。こちらがそのプロモーション動画。
ポスターの上部に、“Love, Deceit and Taxes”(愛、裏切り、そして税金)と書いてありますが、アニメの中でプリンス・ジョンが税金の取り立てが大好きだったことを意味しているのですね。
これら4つのポスターは架空の演目なのですが、実際に見てみたくなりますね。劇場ポスターといえどこんなに深いストーリーがあるのを知ると、時を忘れて鑑賞していたいです。