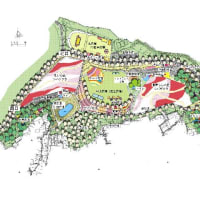庭のつつじが満開。「きれいだね。真っ赤もいいね」
母は前々から老人ホームから自宅に帰りたいといっていた。
帰宅祝いにと、新しく1本つつじを買うことにした。パジャマを買ってやったって、鉢植えの花でも買ってやったって、それほど長い感激はないだろう。庭に一本上等なものを、それが真っ赤に咲くつつじだった。
農家であったので庭は比較的広い。
庭にはいろんな種類のつつじがある。昔からのものもあるが、私も出かけたついでに財布に見合った植木を買ってきた。いつの日か、つつじが多くなった。名前は知らない。
紫色がさめるとピンクが真っ盛りになる。そして、赤。次は白が順番を待っている。
庭の手入れに来てもらっている千代田町の植木屋さんに存在感のある「赤いつつじ」を昨年の暮れに頼んでおいた。
「お袋が帰ってくるときまでに、ここから眺められる場所に真っ赤に咲かせたいんだよ。少々値がはってもいい。何か、心が躍るようなものを見つけてきてくれませんか」
「家で死にたいね。ここ(老人ホーム)でも良くやってもらっているけどやはり家がいい」92歳の母は帰るその日を心待ちにしていた。
燃えるような赤いつつじが咲いた。居間のカーテンを開ければ、否が応でも目の前に迫る真っ赤なつつじ。
淡い色が高齢者には似合う、お年寄りはそう思っている。着るものも見るものも自然にそうなる。
でも、見るものは燃えるような、刺激的なものだってけっこういける。
「赤がきれいだね」
庭を見ていつもそう言うのを聞いて、こっちが満足している。
小さな部屋での生活、スケジュール通りの生活からの開放がそう言わせているのだ。
食事とか風呂とか、洗濯とか不便なことがあっても、だれにも束縛されない自由を取り戻したことへの満足感があるのだろう。
「昨日はテレビのお守り。だれともしゃべらなかった」
本当は、つつじは刺身のつまのようなもの。いくら景色がきれいであっても、それは心の癒しにはならない。他愛のないことでも会話の相手役になってやることが「刺身」なのだ。高齢者が元気に生きる、というのは人とのふれあいが不可欠なのである。
「後期高齢者はいじめられている。杖をつきながらでも、車椅子に乗ってでも国会前でデモをしたらいい。そういう自由な行動が高齢者を元気にさせる」
みのもんたの「朝ズバ!」で瀬戸内寂静さんと渡辺淳一さんが言っていた。
高齢者が思い抱く色は何? アンケートの結果、「黒」が多かった。黒や灰色は悲しくなる色である。後ろ向きの色である。
瀬戸内さんの思い抱く色は「赤」、渡辺さんは「ピンク」であった。
赤は闘う色でありピンクなど暖色は希望の色である。為政者は高齢者に対して赤やピンクの気持ちにさせることが務めではないかと思う。黒の気持ちにさせるのは政策のどこかに誤りがあるのではないか。
何の不自由もない生活と思っていたが、実際の母の心は灰色であったのかもしれない。
「薮塚のYさんがスイカを持ってきてくれて、とてもおいしかった」
カーテンが開いているときは「ちょっと立ち寄ってくれ」という合図。役所に出かけるときは網戸を開けて「元気?」と言葉をかけてから車に乗る。
「たまには線香でもあげていったら!」あがってしゃべっていけ、ということだ。
連休であるし、別に用事があるわけでもない。あがりこんだ。
大好物のスイカをいただいたことを報告したかったようだ。
「めい(私の孫の名前)はいい子だね。昨日もここに来て線香あげて、絵をかいて・・、字もうまくなって」
孫が連休で帰ってきていた。「おおばば、好き」といわれてすごくうれしいようだ。やりたいことを勝手にやらせておくからおおばばが気にいっているようで、かならず立ち寄る。
仏壇に線香をあげて、手を合わせていくのが「いい子だね」の理由のひとつ。母は先祖のことをすごく気にする。
庭の花を摘んできて、茶碗に水をいれて花をさしていったという。
そんな他愛のない話であった。
そして、この日は「生まれてはじめてのこと」をしてしまった。
母の背中を洗ってやったのである。
「ちえの(私のいとこ)が連休明けてからくるというんだけど。風呂に入らなくても死にはしないから・・」
ちえのさんは東京に住んでいるが、月の半分くらい太田に帰ってくる。家庭菜園の耕作、収穫のためである。そのとき、母を風呂に入れてくれている。
「(風呂は)身内がいい」といっているので、すっかりちえのさんに甘えてしまっている。
「3日も入っていないの? いれてあげようか」
「そんなことしてもらったらお天道様が西から上がるよ」
「気にすることないよ。今から入れば、まだ暖かいし。お湯をいれて・・」
「温度は39度に設定してあるから、蛇口をひねればだいじょうぶ。悪いね。背中がかゆいんだ、ほんとは」
母の裸を見るのははじめてだった。背中は白く、とはいえ農業で鍛えた体はしっかりとしていた。
どういうわけか、照れくささもなかった。親子というのは不思議なものだ。
「おじいさんをいつも風呂にいれてやったが、だんだんやせていって・・。もともとやせ型だったから、最後にいれてやったときは骨と皮。でも、後生がよかった。寝込んでから2週間だった。お父さんも1週間。私も、もう迎えに来てもらってもいいのだが・・」
祖父も父も88歳で逝った。そのことを思ってのことだろう。
足はいくらか弱って、杖をつくことも多くなった。でも、耳はちゃんと聞き分けられるし、頭もしっかりしている。上毛新聞のパズルをまだやっているのだから。
「おせん(母の名前)がこの家を守っていかなければと、まだ生かさせてくれているのだろうね」
「足を温かくしてないととたんに具合が悪くなってしまう」
椅子に座って自分で下着をはいていたが、右足がうまくタイツに入らない。タイツを拡げて右足に入れてやった。
「さっぱりした」満足げな様子を見て、とてもうれしかった。
いつものようにマッサージ椅子に腰をかけたお袋をみて「こんなことだったら、いつでもやってあげるよ」と心の中でつぶやいた。