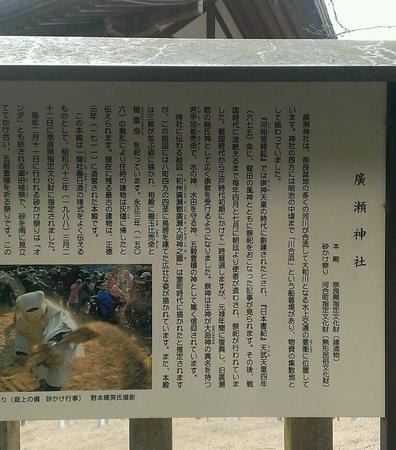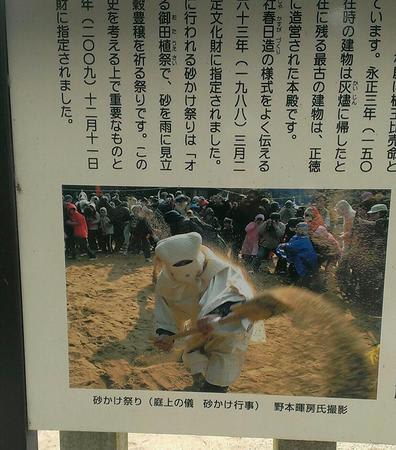ずいぶん前の話になるんですが、念願のチャリを買いまして、今日は初乗りしてみました。

郡山城跡を中心に市街を走りました。

郡山城跡。


五左衛門坂。
高坊主という背丈二メートル、目も口もない妖怪が住んでいたとされる場所です。

それから市街を通り抜け、源九郎稲荷神社から金魚資料館へ。


源九郎稲荷神社。狐の伝説で有名な神社です。お約束、チャリを入れてみた(笑)。





マーブルに似てるな(笑)。

そういや全然話は変わるんですが、庭木を剪定していたら、鳥の巣を見つけました。

これってもしかして、以前にうちで巣立った鳥の巣だったのかも。


郡山城跡を中心に市街を走りました。

郡山城跡。


五左衛門坂。
高坊主という背丈二メートル、目も口もない妖怪が住んでいたとされる場所です。

それから市街を通り抜け、源九郎稲荷神社から金魚資料館へ。


源九郎稲荷神社。狐の伝説で有名な神社です。お約束、チャリを入れてみた(笑)。





マーブルに似てるな(笑)。

そういや全然話は変わるんですが、庭木を剪定していたら、鳥の巣を見つけました。

これってもしかして、以前にうちで巣立った鳥の巣だったのかも。