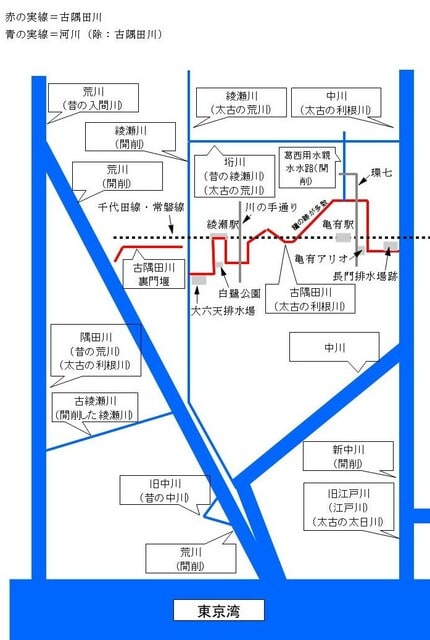久々の本郷台地は、概ね、ブラタモリの本郷台地の回をなぞる小旅である。すなわち、地下鉄千代田線の根津駅から出発し、藍染川に寄り道をした後、弥生土器ゆかりの地を訪ね、湯島天神に詣った後、本郷三丁目辺りの坂(菊坂、炭団坂、鎧坂)を堪能し、樋口一葉宅跡を訪れて御茶ノ水に出るルートである。最初に全体のルート図を掲げておこう。黒の細点線が踏破ルートである。

根津駅の地上に出ると不忍通りと言問通りの交差点がある。本郷台地が目的なら言問通りを西に帝国大学方面に上るところだが、今回は寄り道をする。言問通りを逆方向に東に向かう。しばらく下りで、最初の信号の地点が一番低く、そこから台東区に入って上りになる。上っているのは上野台地である。

すなわち、信号の地点が本郷台地と上野台地の間の谷間であり、谷を作ったのが藍染川である。信号を左折して、今は暗渠となっている藍染川の上を歩く。川名の由来は、川の水が藍染に使われていたからである。そうした藍染屋さんが今も残っている。

気が済んだから寄り道はおしまい。言問通りに戻って帝国大学方面に坂を上る。

すると、左手に「弥生式土器発掘ゆかりの地」の碑が現れた。

弥生時代の「弥生」こそがこの弥生である。ただし、この碑の建っている処が発掘現場でないことは、線路沿いの大森貝墟の碑が大森貝塚があった場所でないことと同様である(Vol.8参照)。ただし「ここかも」という場所が帝国大学の敷地内にあり、発掘現場であることを示すプレートがあり、その脇が崖になっているというので、崖下から拝もうと上ってきた坂を下りて横道に入ると、なるほどそこは崖下である。

崖上は本郷台地であり、帝国大学は台地の上にあるのである。下々の私が最高学府を見上げ、最高学府が下々の私を見下ろすというのは世の中のありようと一致している。ブラタモリでは「『でかい樹』の辺りにプレートがある」と言っていたからここら辺だと思うのだが、放送時から10年経過していて、テレビで見た風景からだいぶ変わってしまっていて、いまいち確信が持てない(三田段丘のときもそうだった)。ま、しかし誤差20メートルの範囲内であることは確かだろう。
そのまま崖下を縫って湯島天神に向かう。途中、旧岩崎庭園が現れた。

まことに広大な敷地である。そう言えば、上野台地を王子に向かって歩いたときは途中に旧古河庭園が現れて、あっちも広大であった。まっことお金持ちはいるものである。こうした広大な土地のほんのひとかけらでもあれば私のような下々の者は十分生活できるのである。
そうこうするうちに湯島天神に通じる石段(天神石坂)に到着。

湯島天神がある処も本郷台地の上である。すなわち、最高学府も、天神様も、いと高き処におわすのである(あと、縄文人、弥生人も高い処に住んでいた。遺跡や貝塚が見つかるのは高台である)。世の中の多くの人は階段を見るとげんなりするようだが、私は逆に燃えるタチ。中学んときの陸上部の練習で、こうした階段を何度も駆け上ったものである。だが、無理をして痛風が出ても困るので、駆け上りはせず歩いて上って台地の上(天上)に出た。湯島天神は梅が綺麗だと聞いていたが、既に多くが散っていたのは残念だった。

境内の大判焼屋さんが閉まっていたのも残念だった。

カムカムエヴリバディで深津絵里が毎日焼いている回転焼きは、イコール今川焼きであり、イコール大判焼きである。
さて、下々の私も今はいと高きところ(本郷台地上)にいるわけで、せっかくだからしばらくは台地上をうろつくことにし、春日通りを西に進むと本郷三丁目交差点にぶち当たった。交叉するのは中山道である。この中山道に向かって立つと、さっき根津で見た言問通り同様、少し下ったらすぐ上っているのが分かる。

この下ってる坂が見送り坂で、上ってる坂が見返り坂である。中山道を旅する人を送ってきた人がここで見送り、旅人が見返す坂である。
その二つの坂の境目から左(西)に下る坂がある。菊坂である。

言問通りの低くなっているところが谷間で藍染川が流れていたごとく、二つの坂の境目(一番低い処)は谷間であり、谷間を作るのは川である。すなわち、ここにも川が流れていたのであり、菊坂はその川跡なのである。この菊坂を下ると、菊坂コロッケを売ってるお肉屋さんが現れた。

ここのコロッケを購入することも今回の小旅の目的の一つである。3個購入。ひっきりなしに客が来るのはここら辺の名物である証しである。
さて、このすぐ先から、菊坂に平行して一本南側を通る小径を行く。というのも、樋口一葉の旧宅跡はその小径に面している。

この一角のどこかが樋口一葉宅跡である。先ほど、菊坂を下り既に台地から降りているから、今いるのは谷底である。奥の階段は、ここ(谷底)から台地上に上る階段である(後で下ることになる)。
さらに、ここら辺の有名な坂も、菊坂の一本南の小径とつながっている。炭団坂(炭団=炭を丸めた燃料)もそうだし、

鎧坂もそうである。

先に書いたとおり、谷底に降りているから坂はみな上り坂である。この鎧坂を上る途中に鬱蒼とした路地があり、暗い中をくねくね行くと崖下に降りるような階段が現れる。


これが、先ほど見た樋口一葉宅跡の一角の奥に見えた階段である。
これで、今回予定した場所はすべて見た。帰途につくべく新御茶ノ水駅を目指す。途中、後楽園遊園地の観覧車の最上部が見えた。

後楽園が近くなんだな。半世紀近く前にときどき通っていた真砂図書館もここら辺だったんだな。

そして、神田川にかかる聖橋を今回は下から見上げる(今回は見上げてばかり)。

聖橋とくれば、中央線と総武線と丸の内線の交叉を見たいところ。一応、三線の車両を一枚に収めることはできたが、

総武線(右上隅の黄色いラインの入った車両)はホームに停車中である。走行中の三線を一枚に収めることが究極の目標である。
因みに、お寺の敷地内を「境内」と言うが、神社の場合は何て言うんだろう?と思ったら「境内」でよいらしい(大辞林)。それから、「あいぞめ」と入力すると多くの場合「愛染」と変換されるが、変換率で言うと「藍染」と「愛染」ではどちらが高いのだろうか。私の世代では断然「愛染恭子」の「愛染」だと思うのだが。