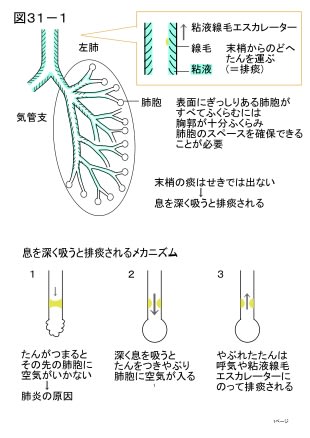なお、「姿勢保持のために広背筋が収縮している場合」も、よい姿勢のときに比べ「微細な作業を行う際の、肩甲骨のわずかな動き」が出にくくなります(詳しくは「広背筋短縮と腱板断裂の関係」の項を参照)。
軽作業の際、肘や手で体を支えると「姿勢保持のために広背筋が収縮する」ことになりやすいです(図20-2 ×4を参照)。
そのためか、書道や食事のマナーでは「背すじをのばし(短背筋群を収縮させ)、机に肘や手をつかない(ついたとしても肘や手に体重をかけない)」よう指導されることが多いです。
しかし、一旦「姿勢保持のために広背筋が収縮するくせ」がついてしまうと、肘や手をつこうがつくまいが、作業をしようがしまいが、広背筋が収縮してしまいやすくなります。
ですから、子供のうちから「姿勢保持のために広背筋が収縮するくせ」をつけないようにすることが肝心です。
そのためには「鍛えたい筋肉が未発達な子供のうちから、座位を長時間とったり、書字など難しい作業をしすぎたりしないこと」が大切です。
「書字の極意1」の①~③を行うのも有効です。
しかし、それでも「姿勢保持のために広背筋が収縮するくせ」がついてしまった場合は、「腕の力を抜く練習」を行うとよいです(詳しくは「腕の力を抜く練習」の項を参照)。
ちなみに、「書字など、主に利き手のみが動く作業」が多い人の場合、広背筋や腹斜筋の収縮(短縮)は左右非対称に起こりやすいです。
たとえば右利きの場合は、「左大殿筋や左短背筋群を収縮させ、左半身のみを安定させることによって、右肩甲骨~右手の動きを自在にする」という体の使い方をする人がいます(注1)。
つまり、本来は「中枢(体幹中心部)の安定&末梢の自在」とすべきところを「左半身の安定&右半身の自在」としてしまうのです。
しかし、大殿筋や短背筋群は左右ともに収縮した方が安定するので、左大殿筋+左短背筋群だけでは不足なことが多いです(注2)。
そのため、結局は、左広背筋や左腹斜筋まで収縮してしまうのです。
すると、左肩甲骨~左手は動きにくくなってしまうので、ピアノなど、両手を繊細に動かす作業のとき困ります。
それに、左肩や左腰を傷めやすくなります(「鍛えたい筋肉と緩めたい筋肉」の項を参照)。
ですから、やはり「中枢(体幹中心部)の安定&末梢の自在」とした方がよいです。
そのためには、座位の際は「左右の坐骨に均等に体重をかけ、背すじを伸ばし、左右大殿筋・短背筋群を収縮させる」よう意識します(注3)。
ただし、ここで急きょ左右の坐骨に均等に体重をかけようとすると、思わぬ落とし穴があります。
大殿筋や短背筋群は抗重力筋なので、体重が多くかかると発達する傾向があります(注4)。
ですから、体の使い方が「左半身の安定&右半身の自在」となっていた人は、大殿筋の厚みも左>右となっている場合が多いのです(注5)。
大殿筋の厚みが左>右となっている人が、座位で左右の坐骨に均等に体重をかけようとすると、骨盤が右に傾き右に転がりそうになるため、余計体を左に傾けざるをえなくなってしまう場合があるのです(図32-2 ×2を参照)。
しかし、だからといって右坐骨に体重をかけることをやめてしまうと、ますます左大殿筋は発達し、右大殿筋は退化してしまうことになります。
ですから、大殿筋の厚みが左>右となってしまった場合は、「座位で右坐骨の下に折りたたんだタオルなどを入れ、大殿筋の厚さ不足を補った上で、左右の坐骨に均等に体重をかける」とよいです。
そうしていると、しだいに右大殿筋も発達してくるので、そうなってきたらタオルを薄くしたり取り除いたりします。
ちなみに、体の使い方が「左半身の安定&右半身の自在」となっている人は、脳が「左に傾けている姿勢」を正中位だと勘違いしてしまうためか、視野も左にずれてしまうことがあります。
すると「細長いフランスパンを横に置き、中央を真二つに切ったつもりなのに、右の方が1㎝位長く切れてしまう」などということが起こりやすくなります(注6)。
また、「メガネの右上角を壁や柱にぶつけてしまう」といったことが起こる場合もあります。
「左に傾けている姿勢」だと、頭も左側が突出することになるため、左側をぶつけやすくなりそうにも思えますが、視野も左に偏っているので、不注意になっている右側をぶつけやすくなるようです。
それに、図32-1 ×1を見ても分かりますが、「左に傾けている姿勢」だと、目の位置も左より右の方が高くなります。
その目の位置から水平線を見ると、視線はいつもやや右下へいくことになるためか、右上への注意が向きにくくなってしまうようです。
ですから、そのような場合は、ときどき「背すじを伸ばし、あごを引き、顔は正面を向いたまま、右斜め上を見る」とよいです(必要であればタオルを入れ、左右の坐骨に均等に体重をかけながら行ってください)。
そうすると、脳からスイッチが入るようで、「右大殿筋や右短背筋群が収縮しやすくなる」という利点もあります(注7)。
ただし、これはやや混乱する話なのですが、体の使い方が「左半身の安定&右半身の自在」だからといって、必ずしも広背筋や腹斜筋の収縮(短縮)が左>右となるとは限りません。
なぜなら、体重を左坐骨に多くかけている人は、その分大殿筋や短背筋群の発達も左>右となっているからです。
右坐骨は荷重が少ないものの、その分右大殿筋や右短背筋群(鍛えたい筋肉)も退化しているので、右広背筋や右腹斜筋(緩めたい筋肉)が手伝いすぎて過労→短縮しやすいといえます。
よって、広背筋や腹斜筋の短縮は左<右となっている場合も多いのです(注8)。
腹斜筋の短縮に左右差があるか否かは、鏡を見ながら口を大きく開けてみると予測がつきます。
口を大きく開けると、下顎は、より短縮の強い方に引かれます。
よって、左よりも右腹斜筋の短縮が強い場合、下顎は右に引かれることになります(注9)。
すると、上前歯の中央線に比べ下前歯の中央線の位置が、右にずれてしまうことになります(注10)。
(注1)全員がこのようなゆがみ方になるわけではありませんが、このようなゆがみ方になる人が多いです。
現代人は、受験など書字の機会(つまり利き手ばかり使用する機会)が多いためか、左右のゆがみがある人はとても多いです。
(注2)本来は左右の大殿筋+短背筋群が収縮すべきところを主に左だけが収縮することになるので、エネルギー消費↓となり太りやすいという欠点もあります。
(注3)「左半身の安定&右半身の自在」としている人は、体重を左坐骨に多くかけたり、体を左に傾けたりしている場合が多いです。
(注4)ただし、血行が悪かったりする場合は、体重が多くかかったからといって大殿筋や短背筋群(鍛えたい筋肉)が発達するとは限りません。
それらの代わりに腹斜筋・広背筋・脊柱起立筋群・腰方形筋など(緩めたい筋肉)が過労→短縮してしまう場合もあります。
(注5)大殿筋の大きさに左右差があるかどうかは、うつぶせになり、左右の大殿筋を同じくらい収縮させながら触ってみると分かります。
(注6)脳血管障害の後遺症(半側空間無視)でも似たような症状が出ますが、その場合は1㎝よりも大きくずれることが多いようです。
(注7)左右の脊柱筋を触りながら右斜め上を見ると、休んでいた右脊柱筋が収縮するようになるのが分かります(ただし、右脊柱筋がひどく退化している場合は分かりにくいです)。
(注8)「左広背筋や左腹斜筋は短縮していない」という意味ではなく、「左より右の短縮の方がひどい」という意味です。
(注9)右腹斜筋だけでなく、右首の筋の短縮が強い場合も、下顎は右に引かれることになります。
(注10)上前歯の中央線と下前歯の中央線の位置を比べてみると、下顎が右(もしくは左)にずれているか否かを判別しやすいです。
ひどくずれている人は、口を開く前からずれている場合もあります。