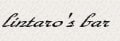このブログは、基本的なところは思い出ブログである。音楽やプロレスの話もするが、身近なところで言えば、主として酒と旅について書いてきた。
これは、日常的な自分の趣味が酒と旅だったからに他ならないが、その酒と旅という趣味が脅かされる事態となって久しい。言うまでもなく、コロナ禍のせいだ。
僕は居酒屋が大好きだが、一応、酒は引きこもっていても呑める。だが、旅にはなかなか出られない。
この新型コロナウィルス、COVID‑19というやつは、まことにやっかいな感染症である。どんどん変異していくため実態をつかみにくいが、とにかく恐るべき感染力であるということ。人はみなマスクをして手洗い消毒を行い密を避け換気をしアクリル板を立て対策した。そのため、僕などは年に2,3回は風邪を引いていた弱い人間だったのだが、あれ以来一切風邪なんぞ引いていない。どころか、例年猛威をふるうインフルエンザまでもが、日本からほぼ撲滅されてしまった。いかに、従来型の風邪やインフルエンザが、感染力において雑魚だったかということか。それでもCOVID‑19は第6波だの第7波だのと襲ってくる。
もちろん、厳しい病気であるということは間違いないが、さらに社会をややこしくしているのは、ワクチンの接種有無は除いたとしても、人によって感染症状に大きく差があり、「無症状」なる状態もかなりの場合出てしまうということ。これは困る。
自分がリアルタイムで感染しているかどうかがわからない。インフル君にも潜伏期間はあったが、その比ではない。自分が媒体者となっているかもしれない怖さ。最初は検査抑制論もあり(今もある)、近い距離で頻発し出したときは本当に自衛に徹した。僕は、今はワクチンも打ち、仮に感染しても死に至ることはおそらくないだろう。だが、同居人である妻には基礎疾患がある。油断できない。
なので、旅にはなかなか出られない。
コロナ禍の中で、いろんなことを考えていた。
政府は「GoToトラベル」というよくわからない施策を打ち出した。そんな税金を投じて感染拡大に寄与することをせずとも感染症が収束すれば人はまた旅に出るさ、現に2022年は「行動制限のない夏」というキャッチコピーだけでこんなに人は動いてるじゃないか(全然収束してないけど)。
そんな政治的な話はまた分断を煽ることにも繋がるので措く。僕がこのキャンペーンを見ていて思ったのは、旅とは、僕がしてきた旅行とはいったいなんだったのかということだ。
基本的に、GoToトラベルという施策は、指定旅行代理店を通じてのパッケージツアーに「半額税金で補助するよ」というもの。ネット予約のホテル代も対象になる場合があるが、いずれにせよ、ふらり旅派にはほぼ寄与しない。
僕は、旅行代理店を使ったことは過去に、新婚旅行で外国に行ったときくらいである。厳密にいえば修学旅行や社員旅行とかは代理店が入っていたのだろうけれども、個人の旅行では代理店に世話になる発想がなかった。
税の再分配の不均衡さについては、例えばふるさと納税などと同じで、今に始まったことではなく、ここで語ることでもない。それよりも。
僕が趣味にしていた、大好きな国内旅行は、世間的には旅行という範疇ではなかったのだろうか。自転車を漕ぎ、周遊券や18きっぷを大いに活用し、野宿をしたり夜汽車に乗ったりクルマで車中泊をするような旅は。
そして、連想は続く。
若かった頃。よくユースホステルを泊まり歩いていた時代に、いわゆる「ベテランの旅人」に遭遇することがあった。もう何年もバイトしつつ旅を続けているような人たち。
たいていはいい人で、これから行く先の見どころなどのアドバイスをくれたり、旅の面白い話をしてくれたりする。ネットもない時代、そうした口コミは有難い。だが、時々は面倒くさい人もいたりした。
「あーあ、あそこ行ったの(笑)。有名ってだけのとこだったろう? 本当にいいのはその奥なのにね」「知床の真価は夏じゃわからんよ。冬を見ずして語るなかれだ」「東雲湖も行ったことないんじゃ話になんない」「今日どこで泊まるかなんて夕方になんないと決められないじゃん」「最初にスケジュール決めてその通り動くなんてシロート」うっせーよ!
うざいベテランには本当に閉口するが、そういう鼻持ちならない人がよくいうセリフがあった。
「旅と旅行とは違うんだよ。わかる?」
くだらない話で、彼の人たちはつまりスケジュール管理された団体旅行等をバカにし、あれは旅ではない、我々がやっている風来坊的な在り方こそが本当の「旅」だと言いたかったのだろう。言葉遊びとしても、対象を見下している段階で品がないし、なにより的外れに気取っている様には、こっちまで恥ずかしくなってくる。
こうしたつまんない話は、いまから約40年前にチラホラと聞こえていた言説であり、とっくに記憶の奥底に沈んでいた。いまこんなこと言う人なんていないだろう。僕だって、「旅」と「旅行」を特に気取って使い分けたりはしていない。
しかしながら、コロナ禍は人を鬱にする。そんなはるかむかしの話まで記憶の沼から掬い上げ、あろうことにか「もしかしたら旅行と旅とは違うものなのか?」などと思いはじめる。嫌味なベテランの馬鹿説まで肯定しはじめた。GoToに該当するのが旅行で、恩恵をうけないのが旅か。こんなことを考えたりするのは、精神がやられている証拠である。
これはいかんな。いかんのはわかっているが、こういう時にさらに考えたくなるのが僕の悪癖である。
まずは日本国語大辞典を引く。「旅行」は第一義として「旅に出ること」となっている。当然だろう。旅と旅行は基本的には同義だ。しかし注釈をみると、「視察、観光、保養、社寺参拝などの目的で、よその土地にでかけて行くこと」と。「目的」が出てきた。日国辞典は「旅」についても詳細に解説しているが、そのなかに目的に関する文言はない。
だがあくまで辞書の説明であって、目的アリが旅行でナシが旅とはさらに言えない。そもそも、人の行動にはほぼ目的があるというのが僕の持論であって、旅にも目的はあるはず。その目的が具体的事象ではなくとも「失恋を癒しに」「ストレス解消」だって目的だ。あてもなくふらりと旅に出た、と言えば目的がないみたいだが、実は深層に「現実逃避」という目的がある。
しかしながら、旅行と旅の違いがここに出ているような気もする。「あてもなくふらりと旅行に出てみたんだけど…」ってなんか座りが悪い。ふらりと出るのは語感からして旅だよなあ。また人数もあって「ひとり旅」はあっても「ひとり旅行」とは言わないな。「個人旅行」という言葉はあるけどそれは団体旅行との対比であって、必ずしも一人を意味しない。定義は難しい。
だいたい「たび」というのは古来からある日本語だろう。万葉集の「旅にしあれば椎の葉に盛る」は有間皇子のであるが、この場合、旅と詠んでいるが実際は「連行」であって…話がそれすぎますな。
比して「旅行」はそもそも外来語。いつから日本に入っていたのか。知識層は別として、日葡辞書には「リョコウ」という項目が既にある。意味は「タビニユク」。室町期には口語として広まっていた。
江戸時代には、旅と旅行は使い分けられていたんだろうか。東海道中膝栗毛はどうだったかな。
このあと僕は辞書や文献にハマって数時間。全てをここに書くわけにもいかない。例えば神輿の渡御にともなう「御旅所」という言葉なんかは実に興味深いのだが、措いて。
分厚い漢和辞典なども見たのだけれど、旅という字は、「㫃(ハタアシ 旗の意味)」に「从(二人もしくは多数の人)」からなっていて、旌旗の下に集まる大軍のことらしい。おーそうだったのか。具体的には500人で一旅となるそうな。前から、軍隊用語で連隊とか師団とか旅団とか出てきて、他はともかく何で「旅」なんだろうと思っていたのだが、旅とはそもそも軍隊のことだったのか。その軍隊は列を組んで移動するので、そこから「たび」の意味が生じた由。
じゃ中国だと、旅という文字に団体の感じがしてくるのかなあ。「旅懐」「旅情」「旅愁」なんて言葉も漢和辞典にはあったので、そうではないのかもしれないけど。
そもそも旅にもいろいろあるわけで、「たび」「旅行」に全てを負わせるのは大変なのではないか。例えば英語だとTripだのJourneyだのTourだのSafariだのVoyageだの…Travelももちろんある。もう少し日本語もなんとかならないか。
旅の定義は、狭くは居住地を離れて他の場所へゆくこと、としていいだろう。さすれば、他にも言葉はある。
いちばんつまんないのは「出張」だろうな。楽しそうではない。
最近は「遠征」という言葉もつかう。最初は軍隊用語だったのかな。「ヒマラヤ遠征」なんて用法を経て、今なら例えば、ミスチルの福岡ドーム公演に行くのは「遠征」という言葉を用いる。
「巡礼」もある。宗教用語だが、転じて今はロケ地やアニメの舞台をめぐる旅の意味となった。これはたぶん、「聖地」という言葉が先に、ゆかりの地を示すために生まれたんだろう。そして聖地巡礼。日本には近い意味で「遍路」という言葉もあったのだが、それは採用されなかった。語感かな。
「放浪」も旅の一形態としてつかうな。さすらい。前述のうざいベテラン旅人なら「あなたのは旅ではなくむしろ放浪でしょう」と言えば喜ぶにちがいない。「彷徨」もあるが、声に出してもベテラン旅人に教養がないと伝わらない可能性もある。
そうして思えば「流離」「流浪」とどんどんデラシネ的要素が増す。これは旅だろうか。「居住地を離れて…」というより居住地がそもそも無いような。映画「砂の器」で親子が流れ流れてゆく光景を思い出す。広義ではこれも旅の一形態かもしれないが。
「漂泊」は使わないかな。芭蕉は「漂泊の思いやまず」片雲の風に誘われて東北へ旅に出たのだけど。
言葉あそびはこのくらいにしようか。飽きてきた。GoToなんかどうでもよくなってきたが、出張、遠征、巡礼くらいまでは補助がもらえただろうか。「GoTo放浪」「GoTo漂泊」なんてギャグでもつかえない。
僕もいい歳になって、若かった頃のようにのべつ幕無しに旅行に出ているわけでもない。せいぜい夏に少し長い旅、そして年末に妻の実家の帰省にかこつけて幾泊か動く。あとは、2、3泊の旅を何回か、といったところ。虫養いみたいなものだ。
2019年は、夏に身体を悪くしてしまいほぼ旅に出られなかった。それでも年末には癒えていたので、少し動いた。
成田には、真夜中についた。
早暁、お不動さんに参拝しようと思っている。関東の人がこぞって初詣にゆく成田山新勝寺には、僕はまだ行ったことがなかった。
夜明けまで4,5時間ある。ホテルに泊まるほどでもなく、ネットカフェに入ろうと思ったのだが、満員で断られた。そうか、成田空港の早朝便を待つ人でいっぱいなのだ。仕方なく、深夜営業のラーメン屋で軽く呑み、駅前のマクドで時間を潰した。これではGoToには引っかからない(そもそもコロナ禍以前の話だが)。
白々としてきたので新勝寺へ。何日か後にはごった返すはずの成田さんも、今は誰もいない。
そのあと、水郷と伊能忠敬で有名な佐原を散策。さらに香取神宮。利根川を渡って鹿島神宮を細かく歩き、鹿島臨海鉄道に乗って水戸へ。
以前、このブログでも書いたが、尊王攘夷と水戸学についてはかなり詰めて勉強したことがある。そのときから水戸をゆっくり歩きたかったのだが機会を得られずにいた。
史跡中心にじっくりと歩き、幕末に思いを馳せ、黄昏時になったので、最後に偕楽園へとやってきた。
ここに来るのは、約30年ぶりとなる。あの時は、梅が盛りだった。関東に住んでいた女友達と一緒だった。
僕はそのとき、彼女に言った。「結婚しようか」と。
今は冬。閑散としている偕楽園のベンチに座り、昔のことを思い出していた。思いついて、既に先に実家へ帰っている妻にメールをした。今、偕楽園にいる、と。
返信には、特に感慨深いことは何も書かれてなかった。内容を要約すれば「あっそう」。まあそうだよな。時はよどみなく流れている。僕は莞爾として、夜の水戸の町へと繰り出した。
なかなかいい旅をしたと思った。あちこち旅をしてきたけれど、北関東はあんまり歩いていない。関西人あるあるだろう。来年はどこへ行こうか。今回は成田から始めたが、同じパターンで佐野あたりまで来ておいて、早暁厄除け大師、そして栃木、足利、桐生、前橋なんてコースがいいんじゃないか。若いころ萩原朔太郎にはまったことがある。渡良瀬橋の上で森高千里も歌おう。そんな鬼が笑うようなことをぼんやりと考えていたら、そのあとすぐ新型コロナウィルスが世界を席巻してしまった。
生活が、変わった。
あれから長らく、外で呑むということをしていない。宴席ではなく一人で呑む、あるいは同居人となら問題ないだろうけれども、それならわざわざ出かけなくてもいい。そして「ウィルス家に持ち込みたくない脳」をぼんやりと外向けに匂わせる。いやーもう何年も外で呑んでないよ。
こうした「過剰に恐れる馬鹿なオヤジ」という緩いアピールが、歯止めになる。いまや緊急事態宣言の頃のような雰囲気は全くなく、普通にあちこちで宴会は行われているが、そういう席には元来行きたくないのであって、うまく断る口実ともなっている。この歳になって、今更コミュニケーションをはからずともよく、嫌われたり陰口を叩かれてももう何も支障はない。守るべきものは、他にある。
ただ、旅には行きたい。
僕の両親も、妻の両親もまだ健在である。人生90年時代。永らえてくれているのは有難いことだが、疾患だらけの高齢者がコロナ禍を迎えるというのも、なかなか大変である。
妻は年に2回は帰省していたが、それも出来ない。感染の心配もさることながら、田舎には「村人の視線」というものがある。おいそれとは行けないのだ。
僕と田舎の義兄で相談して、リモート環境を整えた。なので週に一度は、母娘がテレビ電話で話している。しかしそういうことを続けると、つのる思いもまた増幅したりするのはわかる。歳を重ねれば気弱にもなる。生きてるうちにはもう会えないのかい?
とうとう妻は帰省を決断した。そして、正月でも盆でもないシーズンオフに、一人空路で東北へと向かった。直前にPCR検査をして、僕が空港まで車で送り、向こうでは兄に空港に来てもらい、最低限ドアtoドアで。
滞在は半月程度だったが、後からみればちょうど波と波の間だった。うまい時期に動いたと言える。果たして、次はいつになるか。
ところで、「出張」「遠征」「放浪」「流離」などと同様、「帰省」もまた旅の一形態か。さっきは忘れていたな。
僕も旅に出たいのだが。
我慢の限界にきた。
結局、感染は人を媒体にしておこる。なら、人に会わなければよかろう。
個人で旅をするようになって何十年。目的は、他の人と同様に主として観光である。しかしながら、若い頃に有名観光地などはずいぶんと行った。今はむしろ、目的が「素晴らしい風景をみる」ではなく「その場所に立って思いを馳せる」に移行してきている。分類すれば「歴史散策」「文学散歩」か。観光は観光だが、あまり一般には需要がないところを細かく歩いて喜んでいる。時期は問わない。シダレザクラやラベンダーも目的にしていない。写真を撮っているのは石碑や墓がほとんどだ。
前述した旅行においても、例えば藤田東湖生誕の碑の前で佇んでいるのは僕くらいである。同じ碑でも、観光客が行列を作る宗谷岬の日本最北の碑とは様相が全く異なる。また、新年になれば何万人の初詣客でギュウギュウの成田山新勝寺だって、年末の夜明けには僕一人しかいない。梅の咲いていない冬の夕方の偕楽園を歩いているのは僕だけだ。そもそも、そういう旅行をしているのである。
あとは、列車に乗らずに自家用車で(ガソリンはしっかり消毒してセルフで)、「土地のうまいものと酒」さえ切り捨ててしまえば、いくらでも旅はできるのではないか。
そうして僕はシーズンオフ、車に食料と酒と自炊道具と布団を積み、2泊3日のショートトリップに出た。
夜明け前、大阪湾に沿うように南下した。堺をすぎ、早朝の和泉国一宮の大鳥神社に参拝して、観光を始める。泉大津のロシア人墓地などは、あまり人も来ない。岸和田城を車中から眺め、いくつか古墳を過ぎて、泉佐野の樫井古戦場跡へ。ここには塙団右衛門の墓もある。
和歌山に入り、加太の深山砲台跡へとゆく。ここが、本日の午前中のメイン。友が島の砲台は有名だが、こちらは比較的マイナーである。しかし壮観。細やかに見て歩く。
淡島神社にも立ち寄ろうとしたが人が多そうに見えたのでパスし、今度は山に向かって進路をとる。
伊太祁󠄀曽神社や粉河寺などあちこち寄りつつ、高野山の麓まできた。
九度山の眞田庵は2度目なので一瞥にとどめ、慈尊院や丹生酒殿神社などに時間をとり、そこから山へ。丹生都比売神社(ここの板碑は見たいと思っていた)を経由して、高野山の結界の中へと入る。
高野山は2度目なのだが、以前来た時には宝物館を中心にした寺院観光だったため、今回はじっくり歩いてみたかった。有難いことに、高野山には参拝客向けの大型駐車場がいくつもある。清潔なトイレもある。そこに車を止め、車中泊とする。連泊の予定。
日も暮れたころ、持参した酒を飲み、缶詰などをいくつも空けて一人宴会。この旅行では飲食店はもちろん、スーパーにさえ寄る予定はない。ちょっと徹底してみようと思った。まあね、高野山の町に泊まる人はだいたいが宿坊であり、夜の飲食店は少ない。酩酊して就寝。
翌朝。夜明け前から読経が聞こえてくる。さすが高野山。僕は湯を沸かし、一杯のコーヒーを喫する。この時間が本当に好き。
夜が完全に明けたら高野山の町を歩き回る。史跡だけではなく、人々が暮らす路地などにも入りこんでみる。山頂の台地がそのままひとつの自治体であり、小中高大と学校が揃い、数々の寺院が中心ながら、生活の色も濃く、なんだか離島を旅しているような感覚になる。楽しい。比叡山延暦寺とはそこが違う。
半日は、奥の院の墓石群で過ごす。ここは飽きない。時間を忘れる。日が暮れるまでずっと墓を巡り続ける。
翌日。行きは和泉、和歌山経由だったので帰りは河内経由。千早赤阪村の楠木正成関係の史跡や、西行終焉の地弘川寺などあちこちを回り、夕刻には自宅へ戻った。
接触無しでも旅は可能だな。確かにガス以外金はつかっていないし、料金のかかる施設にも入っていない。経済を回す、というGoTo的視点でゆけばけしからんと言われるだろうが、そもそも平時の旅とやってることはあまり変わらないし、申し訳ないが日本経済の為に旅に出たいわけでもない。
困ったことは、風呂に入れないことくらい。たいていは一日の観光が終われば、どこかの温泉に寄ってあふうぅぅ…というのが楽しみだったのだが、それを今回は省いた。濡れタオルで体を拭けばそれなりにさっぱりはするが、物足りない。
それ以外は、だいたい満足である。いい旅をした。
調子に乗った僕は、また旅に出た。今度は丹後半島を中心として2泊3日。これも前回同様、非接触を旨とした旅である。
立ち寄っているところは、山椒大夫の安寿姫の塚とか、静御前生誕の地とか、細川ガラシャ夫人の幽閉地とか。全然他の観光客と出会わない。
しかしマイナー観光地(失礼)だけではない。丹後最大の景勝地である「日本三景」天橋立にも、実は行った。
結局これも、方法と時間帯なのである。天橋立といえば「股のぞき」であり、たいていの観光客は山に登る。そして、観光スポットは駅のある南西側に集中している。日本三文殊である智恩寺があり、大天橋が架かる。それに付随して門前町があり、旅館が林立し土産物屋が並ぶ。
股のぞきは昔やったことがあるのでパスし、日も暮れたあと、逆の北東側、籠神社のあたりからアプローチした。大砂州の根もとあたりに小さな駐車場があり、そこで一夜を明かした。
そして早朝。天橋立縦断ウォーキングを試みた。約3.6km。朝5時から歩いている人などいない。さわやかな松並木の散歩。この巨大砂州は、日本の道100選ともなっている。また砂州の途中に鎮座する橋立明神の脇には、名水100選の「磯清水」もある。
小一時間かけて大天橋を渡り智恩寺まで来ても、6時くらい。それでもさすが日本三景、ぼつぼつ観光客が姿を見せてきた。頃合いになったので、僕は踵を返して戻った。
「非接触」「感染防止策の徹底」などと大上段に構えずとも、こんな旅ならなんら問題はない、と思う。前述したように、もともとの今の僕の旅のスタイルを大きく変えているわけではない。そもそも日常生活のほうがよっぽど感染機会が多く、危険といえる。
メシと風呂だけは少し難ではあるが、2度目の旅は、買い出しを解禁した。高野山の旅は山上2泊だったが、今度は日本海沿岸2泊である。スーパーで刺身くらいは買う。やっぱり新鮮なものはうまい(笑)。食べているのはもちろん車中である。
こんなふうに、自分の交通手段を用いての旅だと、ほぼリスクは回避できる。だが、電車に乗って自由に旅をする、というところまでは、まだリスク無しには難しい。
もうひとつ、考えることがある。
「旅と旅行とは違う」と同じ文脈で語られることが多い言説がある。曰く、
「旅ってやっぱり出会いだよ」
出会い。もちろん広義には「素晴らしい風景に出会う」「おいしいものに出会う」なども含まれるだろうが、意味合いの大半は、人との出会いを指すだろう。うざい旅人なら「出逢い」と書けとか言うだろう。
僕も、旅の中での人との出会いについては、数多くの思い出をブログ内で書いている。
幾多の場面で、いろんな人に助けられたし、いろんな人と笑ったし、いろんな人と語り合った。それは人生においてかけがえのない追憶として今も胸に生きている。人生が思い出の集合体であるとするならば、旅における彼の人たちとの出会いがもしも無かったとすれば、僕の人生なんて本当にスカスカだったろう。現実的に見ても、今の妻とも出会ったのは旅の空の下であり、旅がなければ人生そのものが別のものになっていたはずだ。
利己的に言えば、今の僕にはもう特に出会いは必要ない。ひとり旅であれば、ここ何年も非接触の旅をしていたのと同じだった。もうこの歳になれば、寂しくもない。むしろ気楽であって、誰とも出会わない旅を謳歌していた。なので、コロナ禍においても少しの修正と考え方の変更によってなんとかなった。
しかし、もしも僕の青春時代がコロナ禍だったとすれば。
本当にゾッとする。もちろんこれは旅行に限ったことではなく、旅行をしなくとも青春時代は大きく形を変えていただろうし、また「もしも僕の青春時代が戦時下だったなら」などというifとも通じるものがあるが、今の若者はどう思って日々を過ごしているのだろうか。
無論のこと、今の若い人の価値観は僕とは異なるだろうし、また若者にも多様性がある。さらに時代が違う。「もしも僕の青春時代にスマホとネット環境があったなら」というifも考えたくなる。でも可能性が狭められているのは間違いない。なんとか充実した青春を送ってくれ、と切に願う。
もはや、もとの世界に戻ることはないのだろうか。なんだか、今の様相をみていると絶望的な気もしている。検査の充実と、インフルエンザにおけるタミフルのような特効薬があれば、とは思うが、同じコロナウィルスである風邪の特効薬もないのにこれは相当に難しい。おそらく、なし崩し的にこのまま日常を取り戻したふりをして生きていくのだろう。
思い切り利己的に考えれば、家族の内臓疾患が寛解し、さらに身内から高齢者がいなくなったときが、ひと段落なのだろう。しかし、その頃には僕も高齢者になっているような。さすれば、自らを切り捨てる哲学を持たなくてはならなくなる。
電車に乗って駅弁を食べたり酒を呑んだりすることが、何か人に影響を及ぼす可能性のない世の中に、いつかは戻ってほしい、と願っている。空を見上げてため息ひとつ。
これは、日常的な自分の趣味が酒と旅だったからに他ならないが、その酒と旅という趣味が脅かされる事態となって久しい。言うまでもなく、コロナ禍のせいだ。
僕は居酒屋が大好きだが、一応、酒は引きこもっていても呑める。だが、旅にはなかなか出られない。
この新型コロナウィルス、COVID‑19というやつは、まことにやっかいな感染症である。どんどん変異していくため実態をつかみにくいが、とにかく恐るべき感染力であるということ。人はみなマスクをして手洗い消毒を行い密を避け換気をしアクリル板を立て対策した。そのため、僕などは年に2,3回は風邪を引いていた弱い人間だったのだが、あれ以来一切風邪なんぞ引いていない。どころか、例年猛威をふるうインフルエンザまでもが、日本からほぼ撲滅されてしまった。いかに、従来型の風邪やインフルエンザが、感染力において雑魚だったかということか。それでもCOVID‑19は第6波だの第7波だのと襲ってくる。
もちろん、厳しい病気であるということは間違いないが、さらに社会をややこしくしているのは、ワクチンの接種有無は除いたとしても、人によって感染症状に大きく差があり、「無症状」なる状態もかなりの場合出てしまうということ。これは困る。
自分がリアルタイムで感染しているかどうかがわからない。インフル君にも潜伏期間はあったが、その比ではない。自分が媒体者となっているかもしれない怖さ。最初は検査抑制論もあり(今もある)、近い距離で頻発し出したときは本当に自衛に徹した。僕は、今はワクチンも打ち、仮に感染しても死に至ることはおそらくないだろう。だが、同居人である妻には基礎疾患がある。油断できない。
なので、旅にはなかなか出られない。
コロナ禍の中で、いろんなことを考えていた。
政府は「GoToトラベル」というよくわからない施策を打ち出した。そんな税金を投じて感染拡大に寄与することをせずとも感染症が収束すれば人はまた旅に出るさ、現に2022年は「行動制限のない夏」というキャッチコピーだけでこんなに人は動いてるじゃないか(全然収束してないけど)。
そんな政治的な話はまた分断を煽ることにも繋がるので措く。僕がこのキャンペーンを見ていて思ったのは、旅とは、僕がしてきた旅行とはいったいなんだったのかということだ。
基本的に、GoToトラベルという施策は、指定旅行代理店を通じてのパッケージツアーに「半額税金で補助するよ」というもの。ネット予約のホテル代も対象になる場合があるが、いずれにせよ、ふらり旅派にはほぼ寄与しない。
僕は、旅行代理店を使ったことは過去に、新婚旅行で外国に行ったときくらいである。厳密にいえば修学旅行や社員旅行とかは代理店が入っていたのだろうけれども、個人の旅行では代理店に世話になる発想がなかった。
税の再分配の不均衡さについては、例えばふるさと納税などと同じで、今に始まったことではなく、ここで語ることでもない。それよりも。
僕が趣味にしていた、大好きな国内旅行は、世間的には旅行という範疇ではなかったのだろうか。自転車を漕ぎ、周遊券や18きっぷを大いに活用し、野宿をしたり夜汽車に乗ったりクルマで車中泊をするような旅は。
そして、連想は続く。
若かった頃。よくユースホステルを泊まり歩いていた時代に、いわゆる「ベテランの旅人」に遭遇することがあった。もう何年もバイトしつつ旅を続けているような人たち。
たいていはいい人で、これから行く先の見どころなどのアドバイスをくれたり、旅の面白い話をしてくれたりする。ネットもない時代、そうした口コミは有難い。だが、時々は面倒くさい人もいたりした。
「あーあ、あそこ行ったの(笑)。有名ってだけのとこだったろう? 本当にいいのはその奥なのにね」「知床の真価は夏じゃわからんよ。冬を見ずして語るなかれだ」「東雲湖も行ったことないんじゃ話になんない」「今日どこで泊まるかなんて夕方になんないと決められないじゃん」「最初にスケジュール決めてその通り動くなんてシロート」うっせーよ!
うざいベテランには本当に閉口するが、そういう鼻持ちならない人がよくいうセリフがあった。
「旅と旅行とは違うんだよ。わかる?」
くだらない話で、彼の人たちはつまりスケジュール管理された団体旅行等をバカにし、あれは旅ではない、我々がやっている風来坊的な在り方こそが本当の「旅」だと言いたかったのだろう。言葉遊びとしても、対象を見下している段階で品がないし、なにより的外れに気取っている様には、こっちまで恥ずかしくなってくる。
こうしたつまんない話は、いまから約40年前にチラホラと聞こえていた言説であり、とっくに記憶の奥底に沈んでいた。いまこんなこと言う人なんていないだろう。僕だって、「旅」と「旅行」を特に気取って使い分けたりはしていない。
しかしながら、コロナ禍は人を鬱にする。そんなはるかむかしの話まで記憶の沼から掬い上げ、あろうことにか「もしかしたら旅行と旅とは違うものなのか?」などと思いはじめる。嫌味なベテランの馬鹿説まで肯定しはじめた。GoToに該当するのが旅行で、恩恵をうけないのが旅か。こんなことを考えたりするのは、精神がやられている証拠である。
これはいかんな。いかんのはわかっているが、こういう時にさらに考えたくなるのが僕の悪癖である。
まずは日本国語大辞典を引く。「旅行」は第一義として「旅に出ること」となっている。当然だろう。旅と旅行は基本的には同義だ。しかし注釈をみると、「視察、観光、保養、社寺参拝などの目的で、よその土地にでかけて行くこと」と。「目的」が出てきた。日国辞典は「旅」についても詳細に解説しているが、そのなかに目的に関する文言はない。
だがあくまで辞書の説明であって、目的アリが旅行でナシが旅とはさらに言えない。そもそも、人の行動にはほぼ目的があるというのが僕の持論であって、旅にも目的はあるはず。その目的が具体的事象ではなくとも「失恋を癒しに」「ストレス解消」だって目的だ。あてもなくふらりと旅に出た、と言えば目的がないみたいだが、実は深層に「現実逃避」という目的がある。
しかしながら、旅行と旅の違いがここに出ているような気もする。「あてもなくふらりと旅行に出てみたんだけど…」ってなんか座りが悪い。ふらりと出るのは語感からして旅だよなあ。また人数もあって「ひとり旅」はあっても「ひとり旅行」とは言わないな。「個人旅行」という言葉はあるけどそれは団体旅行との対比であって、必ずしも一人を意味しない。定義は難しい。
だいたい「たび」というのは古来からある日本語だろう。万葉集の「旅にしあれば椎の葉に盛る」は有間皇子のであるが、この場合、旅と詠んでいるが実際は「連行」であって…話がそれすぎますな。
比して「旅行」はそもそも外来語。いつから日本に入っていたのか。知識層は別として、日葡辞書には「リョコウ」という項目が既にある。意味は「タビニユク」。室町期には口語として広まっていた。
江戸時代には、旅と旅行は使い分けられていたんだろうか。東海道中膝栗毛はどうだったかな。
このあと僕は辞書や文献にハマって数時間。全てをここに書くわけにもいかない。例えば神輿の渡御にともなう「御旅所」という言葉なんかは実に興味深いのだが、措いて。
分厚い漢和辞典なども見たのだけれど、旅という字は、「㫃(ハタアシ 旗の意味)」に「从(二人もしくは多数の人)」からなっていて、旌旗の下に集まる大軍のことらしい。おーそうだったのか。具体的には500人で一旅となるそうな。前から、軍隊用語で連隊とか師団とか旅団とか出てきて、他はともかく何で「旅」なんだろうと思っていたのだが、旅とはそもそも軍隊のことだったのか。その軍隊は列を組んで移動するので、そこから「たび」の意味が生じた由。
じゃ中国だと、旅という文字に団体の感じがしてくるのかなあ。「旅懐」「旅情」「旅愁」なんて言葉も漢和辞典にはあったので、そうではないのかもしれないけど。
そもそも旅にもいろいろあるわけで、「たび」「旅行」に全てを負わせるのは大変なのではないか。例えば英語だとTripだのJourneyだのTourだのSafariだのVoyageだの…Travelももちろんある。もう少し日本語もなんとかならないか。
旅の定義は、狭くは居住地を離れて他の場所へゆくこと、としていいだろう。さすれば、他にも言葉はある。
いちばんつまんないのは「出張」だろうな。楽しそうではない。
最近は「遠征」という言葉もつかう。最初は軍隊用語だったのかな。「ヒマラヤ遠征」なんて用法を経て、今なら例えば、ミスチルの福岡ドーム公演に行くのは「遠征」という言葉を用いる。
「巡礼」もある。宗教用語だが、転じて今はロケ地やアニメの舞台をめぐる旅の意味となった。これはたぶん、「聖地」という言葉が先に、ゆかりの地を示すために生まれたんだろう。そして聖地巡礼。日本には近い意味で「遍路」という言葉もあったのだが、それは採用されなかった。語感かな。
「放浪」も旅の一形態としてつかうな。さすらい。前述のうざいベテラン旅人なら「あなたのは旅ではなくむしろ放浪でしょう」と言えば喜ぶにちがいない。「彷徨」もあるが、声に出してもベテラン旅人に教養がないと伝わらない可能性もある。
そうして思えば「流離」「流浪」とどんどんデラシネ的要素が増す。これは旅だろうか。「居住地を離れて…」というより居住地がそもそも無いような。映画「砂の器」で親子が流れ流れてゆく光景を思い出す。広義ではこれも旅の一形態かもしれないが。
「漂泊」は使わないかな。芭蕉は「漂泊の思いやまず」片雲の風に誘われて東北へ旅に出たのだけど。
言葉あそびはこのくらいにしようか。飽きてきた。GoToなんかどうでもよくなってきたが、出張、遠征、巡礼くらいまでは補助がもらえただろうか。「GoTo放浪」「GoTo漂泊」なんてギャグでもつかえない。
僕もいい歳になって、若かった頃のようにのべつ幕無しに旅行に出ているわけでもない。せいぜい夏に少し長い旅、そして年末に妻の実家の帰省にかこつけて幾泊か動く。あとは、2、3泊の旅を何回か、といったところ。虫養いみたいなものだ。
2019年は、夏に身体を悪くしてしまいほぼ旅に出られなかった。それでも年末には癒えていたので、少し動いた。
成田には、真夜中についた。
早暁、お不動さんに参拝しようと思っている。関東の人がこぞって初詣にゆく成田山新勝寺には、僕はまだ行ったことがなかった。
夜明けまで4,5時間ある。ホテルに泊まるほどでもなく、ネットカフェに入ろうと思ったのだが、満員で断られた。そうか、成田空港の早朝便を待つ人でいっぱいなのだ。仕方なく、深夜営業のラーメン屋で軽く呑み、駅前のマクドで時間を潰した。これではGoToには引っかからない(そもそもコロナ禍以前の話だが)。
白々としてきたので新勝寺へ。何日か後にはごった返すはずの成田さんも、今は誰もいない。
そのあと、水郷と伊能忠敬で有名な佐原を散策。さらに香取神宮。利根川を渡って鹿島神宮を細かく歩き、鹿島臨海鉄道に乗って水戸へ。
以前、このブログでも書いたが、尊王攘夷と水戸学についてはかなり詰めて勉強したことがある。そのときから水戸をゆっくり歩きたかったのだが機会を得られずにいた。
史跡中心にじっくりと歩き、幕末に思いを馳せ、黄昏時になったので、最後に偕楽園へとやってきた。
ここに来るのは、約30年ぶりとなる。あの時は、梅が盛りだった。関東に住んでいた女友達と一緒だった。
僕はそのとき、彼女に言った。「結婚しようか」と。
今は冬。閑散としている偕楽園のベンチに座り、昔のことを思い出していた。思いついて、既に先に実家へ帰っている妻にメールをした。今、偕楽園にいる、と。
返信には、特に感慨深いことは何も書かれてなかった。内容を要約すれば「あっそう」。まあそうだよな。時はよどみなく流れている。僕は莞爾として、夜の水戸の町へと繰り出した。
なかなかいい旅をしたと思った。あちこち旅をしてきたけれど、北関東はあんまり歩いていない。関西人あるあるだろう。来年はどこへ行こうか。今回は成田から始めたが、同じパターンで佐野あたりまで来ておいて、早暁厄除け大師、そして栃木、足利、桐生、前橋なんてコースがいいんじゃないか。若いころ萩原朔太郎にはまったことがある。渡良瀬橋の上で森高千里も歌おう。そんな鬼が笑うようなことをぼんやりと考えていたら、そのあとすぐ新型コロナウィルスが世界を席巻してしまった。
生活が、変わった。
あれから長らく、外で呑むということをしていない。宴席ではなく一人で呑む、あるいは同居人となら問題ないだろうけれども、それならわざわざ出かけなくてもいい。そして「ウィルス家に持ち込みたくない脳」をぼんやりと外向けに匂わせる。いやーもう何年も外で呑んでないよ。
こうした「過剰に恐れる馬鹿なオヤジ」という緩いアピールが、歯止めになる。いまや緊急事態宣言の頃のような雰囲気は全くなく、普通にあちこちで宴会は行われているが、そういう席には元来行きたくないのであって、うまく断る口実ともなっている。この歳になって、今更コミュニケーションをはからずともよく、嫌われたり陰口を叩かれてももう何も支障はない。守るべきものは、他にある。
ただ、旅には行きたい。
僕の両親も、妻の両親もまだ健在である。人生90年時代。永らえてくれているのは有難いことだが、疾患だらけの高齢者がコロナ禍を迎えるというのも、なかなか大変である。
妻は年に2回は帰省していたが、それも出来ない。感染の心配もさることながら、田舎には「村人の視線」というものがある。おいそれとは行けないのだ。
僕と田舎の義兄で相談して、リモート環境を整えた。なので週に一度は、母娘がテレビ電話で話している。しかしそういうことを続けると、つのる思いもまた増幅したりするのはわかる。歳を重ねれば気弱にもなる。生きてるうちにはもう会えないのかい?
とうとう妻は帰省を決断した。そして、正月でも盆でもないシーズンオフに、一人空路で東北へと向かった。直前にPCR検査をして、僕が空港まで車で送り、向こうでは兄に空港に来てもらい、最低限ドアtoドアで。
滞在は半月程度だったが、後からみればちょうど波と波の間だった。うまい時期に動いたと言える。果たして、次はいつになるか。
ところで、「出張」「遠征」「放浪」「流離」などと同様、「帰省」もまた旅の一形態か。さっきは忘れていたな。
僕も旅に出たいのだが。
我慢の限界にきた。
結局、感染は人を媒体にしておこる。なら、人に会わなければよかろう。
個人で旅をするようになって何十年。目的は、他の人と同様に主として観光である。しかしながら、若い頃に有名観光地などはずいぶんと行った。今はむしろ、目的が「素晴らしい風景をみる」ではなく「その場所に立って思いを馳せる」に移行してきている。分類すれば「歴史散策」「文学散歩」か。観光は観光だが、あまり一般には需要がないところを細かく歩いて喜んでいる。時期は問わない。シダレザクラやラベンダーも目的にしていない。写真を撮っているのは石碑や墓がほとんどだ。
前述した旅行においても、例えば藤田東湖生誕の碑の前で佇んでいるのは僕くらいである。同じ碑でも、観光客が行列を作る宗谷岬の日本最北の碑とは様相が全く異なる。また、新年になれば何万人の初詣客でギュウギュウの成田山新勝寺だって、年末の夜明けには僕一人しかいない。梅の咲いていない冬の夕方の偕楽園を歩いているのは僕だけだ。そもそも、そういう旅行をしているのである。
あとは、列車に乗らずに自家用車で(ガソリンはしっかり消毒してセルフで)、「土地のうまいものと酒」さえ切り捨ててしまえば、いくらでも旅はできるのではないか。
そうして僕はシーズンオフ、車に食料と酒と自炊道具と布団を積み、2泊3日のショートトリップに出た。
夜明け前、大阪湾に沿うように南下した。堺をすぎ、早朝の和泉国一宮の大鳥神社に参拝して、観光を始める。泉大津のロシア人墓地などは、あまり人も来ない。岸和田城を車中から眺め、いくつか古墳を過ぎて、泉佐野の樫井古戦場跡へ。ここには塙団右衛門の墓もある。
和歌山に入り、加太の深山砲台跡へとゆく。ここが、本日の午前中のメイン。友が島の砲台は有名だが、こちらは比較的マイナーである。しかし壮観。細やかに見て歩く。
淡島神社にも立ち寄ろうとしたが人が多そうに見えたのでパスし、今度は山に向かって進路をとる。
伊太祁󠄀曽神社や粉河寺などあちこち寄りつつ、高野山の麓まできた。
九度山の眞田庵は2度目なので一瞥にとどめ、慈尊院や丹生酒殿神社などに時間をとり、そこから山へ。丹生都比売神社(ここの板碑は見たいと思っていた)を経由して、高野山の結界の中へと入る。
高野山は2度目なのだが、以前来た時には宝物館を中心にした寺院観光だったため、今回はじっくり歩いてみたかった。有難いことに、高野山には参拝客向けの大型駐車場がいくつもある。清潔なトイレもある。そこに車を止め、車中泊とする。連泊の予定。
日も暮れたころ、持参した酒を飲み、缶詰などをいくつも空けて一人宴会。この旅行では飲食店はもちろん、スーパーにさえ寄る予定はない。ちょっと徹底してみようと思った。まあね、高野山の町に泊まる人はだいたいが宿坊であり、夜の飲食店は少ない。酩酊して就寝。
翌朝。夜明け前から読経が聞こえてくる。さすが高野山。僕は湯を沸かし、一杯のコーヒーを喫する。この時間が本当に好き。
夜が完全に明けたら高野山の町を歩き回る。史跡だけではなく、人々が暮らす路地などにも入りこんでみる。山頂の台地がそのままひとつの自治体であり、小中高大と学校が揃い、数々の寺院が中心ながら、生活の色も濃く、なんだか離島を旅しているような感覚になる。楽しい。比叡山延暦寺とはそこが違う。
半日は、奥の院の墓石群で過ごす。ここは飽きない。時間を忘れる。日が暮れるまでずっと墓を巡り続ける。
翌日。行きは和泉、和歌山経由だったので帰りは河内経由。千早赤阪村の楠木正成関係の史跡や、西行終焉の地弘川寺などあちこちを回り、夕刻には自宅へ戻った。
接触無しでも旅は可能だな。確かにガス以外金はつかっていないし、料金のかかる施設にも入っていない。経済を回す、というGoTo的視点でゆけばけしからんと言われるだろうが、そもそも平時の旅とやってることはあまり変わらないし、申し訳ないが日本経済の為に旅に出たいわけでもない。
困ったことは、風呂に入れないことくらい。たいていは一日の観光が終われば、どこかの温泉に寄ってあふうぅぅ…というのが楽しみだったのだが、それを今回は省いた。濡れタオルで体を拭けばそれなりにさっぱりはするが、物足りない。
それ以外は、だいたい満足である。いい旅をした。
調子に乗った僕は、また旅に出た。今度は丹後半島を中心として2泊3日。これも前回同様、非接触を旨とした旅である。
立ち寄っているところは、山椒大夫の安寿姫の塚とか、静御前生誕の地とか、細川ガラシャ夫人の幽閉地とか。全然他の観光客と出会わない。
しかしマイナー観光地(失礼)だけではない。丹後最大の景勝地である「日本三景」天橋立にも、実は行った。
結局これも、方法と時間帯なのである。天橋立といえば「股のぞき」であり、たいていの観光客は山に登る。そして、観光スポットは駅のある南西側に集中している。日本三文殊である智恩寺があり、大天橋が架かる。それに付随して門前町があり、旅館が林立し土産物屋が並ぶ。
股のぞきは昔やったことがあるのでパスし、日も暮れたあと、逆の北東側、籠神社のあたりからアプローチした。大砂州の根もとあたりに小さな駐車場があり、そこで一夜を明かした。
そして早朝。天橋立縦断ウォーキングを試みた。約3.6km。朝5時から歩いている人などいない。さわやかな松並木の散歩。この巨大砂州は、日本の道100選ともなっている。また砂州の途中に鎮座する橋立明神の脇には、名水100選の「磯清水」もある。
小一時間かけて大天橋を渡り智恩寺まで来ても、6時くらい。それでもさすが日本三景、ぼつぼつ観光客が姿を見せてきた。頃合いになったので、僕は踵を返して戻った。
「非接触」「感染防止策の徹底」などと大上段に構えずとも、こんな旅ならなんら問題はない、と思う。前述したように、もともとの今の僕の旅のスタイルを大きく変えているわけではない。そもそも日常生活のほうがよっぽど感染機会が多く、危険といえる。
メシと風呂だけは少し難ではあるが、2度目の旅は、買い出しを解禁した。高野山の旅は山上2泊だったが、今度は日本海沿岸2泊である。スーパーで刺身くらいは買う。やっぱり新鮮なものはうまい(笑)。食べているのはもちろん車中である。
こんなふうに、自分の交通手段を用いての旅だと、ほぼリスクは回避できる。だが、電車に乗って自由に旅をする、というところまでは、まだリスク無しには難しい。
もうひとつ、考えることがある。
「旅と旅行とは違う」と同じ文脈で語られることが多い言説がある。曰く、
「旅ってやっぱり出会いだよ」
出会い。もちろん広義には「素晴らしい風景に出会う」「おいしいものに出会う」なども含まれるだろうが、意味合いの大半は、人との出会いを指すだろう。うざい旅人なら「出逢い」と書けとか言うだろう。
僕も、旅の中での人との出会いについては、数多くの思い出をブログ内で書いている。
幾多の場面で、いろんな人に助けられたし、いろんな人と笑ったし、いろんな人と語り合った。それは人生においてかけがえのない追憶として今も胸に生きている。人生が思い出の集合体であるとするならば、旅における彼の人たちとの出会いがもしも無かったとすれば、僕の人生なんて本当にスカスカだったろう。現実的に見ても、今の妻とも出会ったのは旅の空の下であり、旅がなければ人生そのものが別のものになっていたはずだ。
利己的に言えば、今の僕にはもう特に出会いは必要ない。ひとり旅であれば、ここ何年も非接触の旅をしていたのと同じだった。もうこの歳になれば、寂しくもない。むしろ気楽であって、誰とも出会わない旅を謳歌していた。なので、コロナ禍においても少しの修正と考え方の変更によってなんとかなった。
しかし、もしも僕の青春時代がコロナ禍だったとすれば。
本当にゾッとする。もちろんこれは旅行に限ったことではなく、旅行をしなくとも青春時代は大きく形を変えていただろうし、また「もしも僕の青春時代が戦時下だったなら」などというifとも通じるものがあるが、今の若者はどう思って日々を過ごしているのだろうか。
無論のこと、今の若い人の価値観は僕とは異なるだろうし、また若者にも多様性がある。さらに時代が違う。「もしも僕の青春時代にスマホとネット環境があったなら」というifも考えたくなる。でも可能性が狭められているのは間違いない。なんとか充実した青春を送ってくれ、と切に願う。
もはや、もとの世界に戻ることはないのだろうか。なんだか、今の様相をみていると絶望的な気もしている。検査の充実と、インフルエンザにおけるタミフルのような特効薬があれば、とは思うが、同じコロナウィルスである風邪の特効薬もないのにこれは相当に難しい。おそらく、なし崩し的にこのまま日常を取り戻したふりをして生きていくのだろう。
思い切り利己的に考えれば、家族の内臓疾患が寛解し、さらに身内から高齢者がいなくなったときが、ひと段落なのだろう。しかし、その頃には僕も高齢者になっているような。さすれば、自らを切り捨てる哲学を持たなくてはならなくなる。
電車に乗って駅弁を食べたり酒を呑んだりすることが、何か人に影響を及ぼす可能性のない世の中に、いつかは戻ってほしい、と願っている。空を見上げてため息ひとつ。
目先のことに埋もれて心が茫々としてくる。何かを見失っているように思う。この漠とした不明瞭さはいったい何だろうか。
心の焦点があわない日々が続く。
今年は秋から冬にかけて、葬式によく出た。
冠婚葬祭の中でも葬式は前触れなく行われるもので、なんともいたしかたないのだが、3ヶ月で4回は多くないかい? どうしてみんなそう足早に逝ってしまうのか。
なんだかどうも葬儀会場にばかり足を運んでいたような気がする。葬式は今、都市部ではほとんどが専門の葬儀会場で執り行われるので、お宅へ伺ったりすることは、ほぼない。無味乾燥であるような気もするが、時代だろうか。
どこも同じようなつくりであるため、ふと錯覚を起こし「先週も来たな」とか思ってしまう。
話が変わるが、こういう葬儀会場が増えてきたのはいったいいつごろからなんだろう。
高度成長期だろうか。家の主流がマンションなどの集合住宅となれば、そこで葬式をするわけにもゆくまい。寺院で執り行うこともあっただろうが、非檀家の核家族の割合が高くなればお寺さんでの葬式も難しくなっていく。
僕の祖父母の時代は、まだ自宅葬だった。家に祭壇が作られ、そこから出棺した。まだまだ昭和の時代のこと。ただ母方の祖母は長命し、亡くなったのは平成になってからで、葬儀は斎場で行われた。時代が変わったのだ。
今は老人人口が多くなり、葬儀会場がどんどん新設されているように思える。介護施設と並んで盛況なビジネスとなっているのではないだろうか。もしかしたら過当競争になっているかもしれない。新聞にも毎日のように斎場のチラシが入っている。
電話による勧誘も多い。とある日に僕が電話に出れば「セレモニーホール○○ですが」と。あちらも仕事でやっていることで大変だろうとは思うが、葬儀の予定などを訊ねられるのは気分の良いものではない。妻に尋ねると、平日もあちこちからかなり掛かってきているようで、電話に出るのが嫌になったと言う。
11月には叔父が死んだ。急死だった。
父の弟だが、これで6人兄弟の長兄である父も、三人の弟を失ったことになる。
さすがに父の落ち込みは見ていて辛くなるほどで、最も年長である自分が何故生きているのか、などという。もう一人の弟も、今は車椅子でしか動けない。僕からすれば、他の叔父たちと違い酒も煙草もやらずストイックに過ごしてきた父は長生きしてもらわねば困るのだが、本人としてはいたたまれないのだろう。
叔父の葬儀も、やはり会場で行われた。
慟哭を聞くのは、辛いものだ。
葬儀が始まると、音楽が流れた。どこかで聴いたことがあるのだが、すぐには思い出せない。「これ、何の曲やったかな?」と僕が独り言のように言うと、隣にいた叔母(父の妹)が「ロッホ・ローモンドや」とすぐに言ってくれた。あっそうか。
スコットランド民謡の名曲だが、こういう澄んだ美しいメロディは、もしかしたら葬儀に合うのかもしれないと思って聴いていた。聴くうちに、涙が出た。
ただ、叔父が指定したわけではあるまい。葬儀場が用意していたものだろう。血管が破れ救急車の車中ではもう既に意識が無かった叔父が、そんなことまで遺言をしたはずがない。
葬式に音楽を流す、というのは、おそらく葬儀場が始めたことではないか。自宅葬の頃は、そんな習慣は無かったのではないかと思う。つたない経験からの話で、実際はそうではないかもしれないが。あれ、キリスト教の葬儀では讃美歌が流れるのだったっけ。「主よ御許に近づかん」というのは、フランダースの犬の最終話を観て泣いた世代の僕としては、馴染みなのだけれど。しかし仏式だと、読経だよなあ。
最近は自宅葬においても音楽は流れるようで、以前とある田舎で葬儀に参列したとき、出棺の際になんとも言えない悲しい曲が流れた。曲名はわからない。インストだがどちらかといえば演歌調の曲で、ただ悲しみを助長させるだけに思えた。ああいうマイナー調の曲はどうなのかと思う。おそらく互助会が用意したのだろうと思うが、例えば結婚式の花束贈呈で「かあさんのうた」が流れるようなものだ。
ただ、葬儀に音楽が定着していることはわかった。
別の機会。「自分の葬式にどういう音楽を流したいか」という話題が妙に盛り上がった。主体は若い人で、葬儀に音楽は当たり前の世代らしい。
驚くことにその場にいただいたいの人はもう決めているようで、尾崎豊がいいだの「私は絶対にハナミズキ」だのと言っている。そうか。
僕は、そんなこと考えたこともなかった。叔父の葬儀の前で、ロッホローモンドなどもまだ聴いてない。尋ねられたのだが気の利いた答えも言えず窮して「どうせ自分は死んどるんやしそれを聴くこともできんやないか」などと冷や水を浴びせるようなことを言ってしまった。場の空気もみず誠に申し訳ない。
僕は、葬式自体が必要ないと思っている。
昨年、別ブログで村落墓地の連載をしたため、民俗学的に葬儀というものの歴史と実態についてかなり様々な書籍を読んだ。考えるに、現在の葬儀というものは江戸時代の檀家制度、寺請制度の名残で、そんなものは僕個人には関係ない。信仰心もなく、死んで浄土に行くとも地獄に落ちるとも思えないので、戒名とかはどうでもいい。
夏に、内臓にヘンなものが見つかって入院した。僕も死を考え、妻に「葬式はせんでええぞ。金がかかりすぎる。どうしてもと周りがやかましく言うなら、とにかく最低ランクでやって。金は残せ」と言ったら、妻が「縁起でもないことを」と怒った。
そのときも、さすがに音楽までは考えなかった。
葬式にふさわしい音楽とは、なんだろうか。
おそらくは、インストがいいのだろうと思う。そしてきれいな曲で、マイナー調でないほうがいい。葬式と言ってすぐに思いつくのはショパンの葬送行進曲だが、これが掛かっていたのを聴いたことがない。おそらく、生々しすぎるのだろう。
まあクラシックか。「G線上のアリア」とか「亡き王女のためのパヴァーヌ」とか。ラヴェルは実際に聴いたことがある。
歌詞があるものは、相応ではないような気がする。まあ洋楽であればいいか。言葉の意味がわからないほうがいい。ロッホローモンドは、そういう意味でもふさわしい気がしてきた。もっとも、僕が実際に聴いたのはインストだったけれど。
もっと明るくゆくなら、カントリーの名曲「Will The Circle Be Unbroken」がある。加川良さんのカバー(その朝)や、なぎらさんのカバー(永遠の絆)が有名だが、やはりここは原曲か。
will the circle be unbroken
by and by load by and by
there's a better home a-waiting
in the sky, lord, in the sky
やっぱりダメだな。なんか泣きそうになる。
ハンバートハンバートの「大宴会」なんかもいいとは思うんだけれど、こういうのはBGMになりにくいからやっぱりふさわしくないかな。
今は、自分が死ぬときに、どんな音楽が流れていたらいいか、を茫洋とした心のままに考えている。
葬儀は必要ないし、もしも自分の葬儀がなされたとしても、僕はそれに出席していないのだから、どうでもいいと言える。
いちばん好きな歌を聴きながら逝くかな。そうなると「他愛もない僕の唄だけど」とかになるけど、なんか違うな。
終焉を迎えるときに去来するものとは何だろうか。
それは、自分自身にとっては、追憶しかないと思っている。
おそらく「思い出」だけが、最後に残るものだ。あの世が信じられない以上、歩んできた足跡だけが僕には残される。そのめぐる追憶というものが幸せなものであったならば、莞爾として人生を終えることが出来る。
そのとき、僕が独りであれば、もう何も思い残すことはない。
僕には子供がいないため、心配なのは妻だけだ。彼女を残してゆくのは忍びない。つまり妻より一日でも長生きすればいい。だから、老いるまで何としても生き延びなければならない。
そしてこの世を去ったあとは、いったい何が残るだろうか。
墓標などいらない。骨なんかは産業廃棄物でいいと思っている。そもそも、子孫がいない僕の墓など一瞬で無縁となる。だいたい墓を建ててくれる人などいるのだろうか。甥や姪に金を置いて死ねば建ててはくれるだろうが、無駄なことだ。
近親者や友人が、まだそのときにいるとすれば、彼らに多くは望まない。すぐに忘れ去られるのも寂しいから、なんとなしにあんな男がいたと記憶の片隅に置いておいてくれればいい。
功成り名を遂げた一部の人とは違い、僕も含めた市井の人間は、居なくなれば語り継がれることなどない。だから、僕が居なくなって、さらに僕のことを直接知っている人も居なくなれば、僕という概念上の人間もまたこの世から消える。
そこまで思いめぐらして、べーやんの「忘れな詩」が浮かんできた。
もしも私がうたい終わってギターをおいてこの場所を遠く去る時に
誰一人うしろ姿にふり向く人はいないとしても それでいい 想い出一つ残せれば
この詩を書いた中村行延さんは、今どうしてらっしゃるのかなあ。公式サイトも消えている。行延さんが出なくなってから「きらきらアフロ」も見なくなった。喫茶店を閉店したあと、就職されたというような話はおっしゃられていたが…おそらくはどこかで歌っておられるとは思うのだけれど。
けれどあなたの青春のどこかの季節に まぎれもなく私がそこにいたことを
いつまでも いつまでも 忘れないでいてほしい
あなたにだけは この詩 忘れないでいてほしい
忘れないで欲しい、というのは、本音ではあるけれど、そこまで強くは望んでいない。何かの機会に、思い出してもらえる存在であったならいいな、という程度。そんな気持ちを、べーやんの歌に託したいという思いが、今はある。
そしてそれは、逆に今を生きる僕の気持でもある。
今年も、何人もの人を見送ってきた。僕の人生に強く影響を与えてくれた人、優しくしてくれた人、力になってくれた人。僕は、あなたたちのことを生涯忘れない。いつまでも、いつまでも、僕の追憶の中に生き続けてもらう。
でも、もうあえないんだな。さびしいね。
心の焦点があわない日々が続く。
今年は秋から冬にかけて、葬式によく出た。
冠婚葬祭の中でも葬式は前触れなく行われるもので、なんともいたしかたないのだが、3ヶ月で4回は多くないかい? どうしてみんなそう足早に逝ってしまうのか。
なんだかどうも葬儀会場にばかり足を運んでいたような気がする。葬式は今、都市部ではほとんどが専門の葬儀会場で執り行われるので、お宅へ伺ったりすることは、ほぼない。無味乾燥であるような気もするが、時代だろうか。
どこも同じようなつくりであるため、ふと錯覚を起こし「先週も来たな」とか思ってしまう。
話が変わるが、こういう葬儀会場が増えてきたのはいったいいつごろからなんだろう。
高度成長期だろうか。家の主流がマンションなどの集合住宅となれば、そこで葬式をするわけにもゆくまい。寺院で執り行うこともあっただろうが、非檀家の核家族の割合が高くなればお寺さんでの葬式も難しくなっていく。
僕の祖父母の時代は、まだ自宅葬だった。家に祭壇が作られ、そこから出棺した。まだまだ昭和の時代のこと。ただ母方の祖母は長命し、亡くなったのは平成になってからで、葬儀は斎場で行われた。時代が変わったのだ。
今は老人人口が多くなり、葬儀会場がどんどん新設されているように思える。介護施設と並んで盛況なビジネスとなっているのではないだろうか。もしかしたら過当競争になっているかもしれない。新聞にも毎日のように斎場のチラシが入っている。
電話による勧誘も多い。とある日に僕が電話に出れば「セレモニーホール○○ですが」と。あちらも仕事でやっていることで大変だろうとは思うが、葬儀の予定などを訊ねられるのは気分の良いものではない。妻に尋ねると、平日もあちこちからかなり掛かってきているようで、電話に出るのが嫌になったと言う。
11月には叔父が死んだ。急死だった。
父の弟だが、これで6人兄弟の長兄である父も、三人の弟を失ったことになる。
さすがに父の落ち込みは見ていて辛くなるほどで、最も年長である自分が何故生きているのか、などという。もう一人の弟も、今は車椅子でしか動けない。僕からすれば、他の叔父たちと違い酒も煙草もやらずストイックに過ごしてきた父は長生きしてもらわねば困るのだが、本人としてはいたたまれないのだろう。
叔父の葬儀も、やはり会場で行われた。
慟哭を聞くのは、辛いものだ。
葬儀が始まると、音楽が流れた。どこかで聴いたことがあるのだが、すぐには思い出せない。「これ、何の曲やったかな?」と僕が独り言のように言うと、隣にいた叔母(父の妹)が「ロッホ・ローモンドや」とすぐに言ってくれた。あっそうか。
スコットランド民謡の名曲だが、こういう澄んだ美しいメロディは、もしかしたら葬儀に合うのかもしれないと思って聴いていた。聴くうちに、涙が出た。
ただ、叔父が指定したわけではあるまい。葬儀場が用意していたものだろう。血管が破れ救急車の車中ではもう既に意識が無かった叔父が、そんなことまで遺言をしたはずがない。
葬式に音楽を流す、というのは、おそらく葬儀場が始めたことではないか。自宅葬の頃は、そんな習慣は無かったのではないかと思う。つたない経験からの話で、実際はそうではないかもしれないが。あれ、キリスト教の葬儀では讃美歌が流れるのだったっけ。「主よ御許に近づかん」というのは、フランダースの犬の最終話を観て泣いた世代の僕としては、馴染みなのだけれど。しかし仏式だと、読経だよなあ。
最近は自宅葬においても音楽は流れるようで、以前とある田舎で葬儀に参列したとき、出棺の際になんとも言えない悲しい曲が流れた。曲名はわからない。インストだがどちらかといえば演歌調の曲で、ただ悲しみを助長させるだけに思えた。ああいうマイナー調の曲はどうなのかと思う。おそらく互助会が用意したのだろうと思うが、例えば結婚式の花束贈呈で「かあさんのうた」が流れるようなものだ。
ただ、葬儀に音楽が定着していることはわかった。
別の機会。「自分の葬式にどういう音楽を流したいか」という話題が妙に盛り上がった。主体は若い人で、葬儀に音楽は当たり前の世代らしい。
驚くことにその場にいただいたいの人はもう決めているようで、尾崎豊がいいだの「私は絶対にハナミズキ」だのと言っている。そうか。
僕は、そんなこと考えたこともなかった。叔父の葬儀の前で、ロッホローモンドなどもまだ聴いてない。尋ねられたのだが気の利いた答えも言えず窮して「どうせ自分は死んどるんやしそれを聴くこともできんやないか」などと冷や水を浴びせるようなことを言ってしまった。場の空気もみず誠に申し訳ない。
僕は、葬式自体が必要ないと思っている。
昨年、別ブログで村落墓地の連載をしたため、民俗学的に葬儀というものの歴史と実態についてかなり様々な書籍を読んだ。考えるに、現在の葬儀というものは江戸時代の檀家制度、寺請制度の名残で、そんなものは僕個人には関係ない。信仰心もなく、死んで浄土に行くとも地獄に落ちるとも思えないので、戒名とかはどうでもいい。
夏に、内臓にヘンなものが見つかって入院した。僕も死を考え、妻に「葬式はせんでええぞ。金がかかりすぎる。どうしてもと周りがやかましく言うなら、とにかく最低ランクでやって。金は残せ」と言ったら、妻が「縁起でもないことを」と怒った。
そのときも、さすがに音楽までは考えなかった。
葬式にふさわしい音楽とは、なんだろうか。
おそらくは、インストがいいのだろうと思う。そしてきれいな曲で、マイナー調でないほうがいい。葬式と言ってすぐに思いつくのはショパンの葬送行進曲だが、これが掛かっていたのを聴いたことがない。おそらく、生々しすぎるのだろう。
まあクラシックか。「G線上のアリア」とか「亡き王女のためのパヴァーヌ」とか。ラヴェルは実際に聴いたことがある。
歌詞があるものは、相応ではないような気がする。まあ洋楽であればいいか。言葉の意味がわからないほうがいい。ロッホローモンドは、そういう意味でもふさわしい気がしてきた。もっとも、僕が実際に聴いたのはインストだったけれど。
もっと明るくゆくなら、カントリーの名曲「Will The Circle Be Unbroken」がある。加川良さんのカバー(その朝)や、なぎらさんのカバー(永遠の絆)が有名だが、やはりここは原曲か。
will the circle be unbroken
by and by load by and by
there's a better home a-waiting
in the sky, lord, in the sky
やっぱりダメだな。なんか泣きそうになる。
ハンバートハンバートの「大宴会」なんかもいいとは思うんだけれど、こういうのはBGMになりにくいからやっぱりふさわしくないかな。
今は、自分が死ぬときに、どんな音楽が流れていたらいいか、を茫洋とした心のままに考えている。
葬儀は必要ないし、もしも自分の葬儀がなされたとしても、僕はそれに出席していないのだから、どうでもいいと言える。
いちばん好きな歌を聴きながら逝くかな。そうなると「他愛もない僕の唄だけど」とかになるけど、なんか違うな。
終焉を迎えるときに去来するものとは何だろうか。
それは、自分自身にとっては、追憶しかないと思っている。
おそらく「思い出」だけが、最後に残るものだ。あの世が信じられない以上、歩んできた足跡だけが僕には残される。そのめぐる追憶というものが幸せなものであったならば、莞爾として人生を終えることが出来る。
そのとき、僕が独りであれば、もう何も思い残すことはない。
僕には子供がいないため、心配なのは妻だけだ。彼女を残してゆくのは忍びない。つまり妻より一日でも長生きすればいい。だから、老いるまで何としても生き延びなければならない。
そしてこの世を去ったあとは、いったい何が残るだろうか。
墓標などいらない。骨なんかは産業廃棄物でいいと思っている。そもそも、子孫がいない僕の墓など一瞬で無縁となる。だいたい墓を建ててくれる人などいるのだろうか。甥や姪に金を置いて死ねば建ててはくれるだろうが、無駄なことだ。
近親者や友人が、まだそのときにいるとすれば、彼らに多くは望まない。すぐに忘れ去られるのも寂しいから、なんとなしにあんな男がいたと記憶の片隅に置いておいてくれればいい。
功成り名を遂げた一部の人とは違い、僕も含めた市井の人間は、居なくなれば語り継がれることなどない。だから、僕が居なくなって、さらに僕のことを直接知っている人も居なくなれば、僕という概念上の人間もまたこの世から消える。
そこまで思いめぐらして、べーやんの「忘れな詩」が浮かんできた。
もしも私がうたい終わってギターをおいてこの場所を遠く去る時に
誰一人うしろ姿にふり向く人はいないとしても それでいい 想い出一つ残せれば
この詩を書いた中村行延さんは、今どうしてらっしゃるのかなあ。公式サイトも消えている。行延さんが出なくなってから「きらきらアフロ」も見なくなった。喫茶店を閉店したあと、就職されたというような話はおっしゃられていたが…おそらくはどこかで歌っておられるとは思うのだけれど。
けれどあなたの青春のどこかの季節に まぎれもなく私がそこにいたことを
いつまでも いつまでも 忘れないでいてほしい
あなたにだけは この詩 忘れないでいてほしい
忘れないで欲しい、というのは、本音ではあるけれど、そこまで強くは望んでいない。何かの機会に、思い出してもらえる存在であったならいいな、という程度。そんな気持ちを、べーやんの歌に託したいという思いが、今はある。
そしてそれは、逆に今を生きる僕の気持でもある。
今年も、何人もの人を見送ってきた。僕の人生に強く影響を与えてくれた人、優しくしてくれた人、力になってくれた人。僕は、あなたたちのことを生涯忘れない。いつまでも、いつまでも、僕の追憶の中に生き続けてもらう。
でも、もうあえないんだな。さびしいね。
最近、駅弁を食べる機会が何度かあった。この1ヶ月で3回。
これを多いと見るか少ないと見るかは、マニアのいる世界でもあり何とも言えないが、僕は昨年末まで、たぶん一年以上駅弁を食べていなかった。ずいぶんご無沙汰してしまったものだと思う。
別に駅弁離れ、というつもりもなくただ機会がなかっただけだと一応は考えてみる。そうだよなあ。別に駅弁が嫌いになったわけでもなし。でも思い返してみると、ここ14~5年は昔と比べてかなり利用回数が減ったように思われる。どうしてかなあ。
まずは旅に出ることが少なくなったというのが第一義的にあるのはもちろんだと思うけれども、他にもいくつか要因があるように思う。
ひとつは、僕が新幹線・特急列車に乗る機会を減らしているということ。旅行に行くときの交通機関の選択としてどんどん車のパーセンテージが上がっていることに加え、遊びであまり速い列車に乗らなくなっている。以前は「時間を金で買う」という意識が強かったが、移動も旅行の楽しみであるに間違いは無く、今はよく普通・快速列車に乗る。新幹線というのは、車窓風景が均質的なので飽きる。あれは出張用だ。在来線のほうが楽しい。
ところが鈍行列車の車内というのは、今は食事をする場所ではなくなっている。
田舎の路線でも、座席はベンチシートが増えた。あの席では弁当などは実に食べにくい。また快速列車は前向き座席が多いが、近郊線なので混雑する。立っている人からじろじろ見られるのもまた食事に相応しくない。
また他に、食事の選択肢が増えたということ。
それでも特急に乗る機会もあるにはあって、特急列車は座席にテーブルもついていて弁当を食べるに不自由はないが、乗車するのはターミナル駅から、ということが多く、食事をテイクアウトするのに駅弁だけではなくデパ地下やエキナカなど目移りして、そっちのほうがコスパが良いことが大半なので困ってしまう。昔は長い汽車旅だと、駅弁か立ち食いそばくらいしか選択肢がなかったものだが。
さらに、昔と比べて駅弁が手軽に手に入りやす過ぎる、ということがある。
昔からデパートの催事で「駅弁大会」というものは盛んにあって、現地に行かなくても手に入ったものだったが、それがさらに昨今はスーパーなどでも企画されるようになった。僕が住む徒歩圏内のスーパーでも、年に何度も各地方の名物駅弁を特集して販売している。そうなると、逆に買わなくなるのである。
この心理を説明するのは難しい。いつでも手に入ると思うと購買意欲が失せるという心理を。
例えば別のことで書くと、僕は名古屋に多い「コメダ珈琲店」という喫茶店の「シロノワール」という大きなデニッシュパンにソフトクリームを乗っけてシロップをかけて食うというデザートが好きで、名古屋に昔住んでいたときにハマり、その後名古屋を離れて後も愛知県に行くことがあれば必ず探して食べていた。ところが、そのコメダ珈琲店が全国チェーン展開を始め、とうとう僕の最寄駅のそば、つまり徒歩5分くらいのところにも開店してしまった。そうなると、もう行かなくなるのである。東海地方に行っても「うちの近所で食べられるものを何もここでわざわざ」と思い、また地元の店にも「また今度ね」と思って行かない。結局、地元に店が開店してから一度もシロノワールを食べていない。
つまるところ今までも「せっかくここまで来たんだから食べよう」という心理が働いていたのだろう。駅弁についても同じ。例えば鳥取に行けば「元祖かに寿しを食べなくちゃ」とかつてはやはり思ったが、今はスーパーの広告に載っていると、鳥取で食べなくてもいいかと思い、また駅弁をスーパーで買わなくてもいいだろう、とも思ってしまう。
駅弁を食べていない言い訳に字数を使いすぎた。思い出話を書く。
初めて駅弁を食べたのはいつだったかということを思い返すと、小学校一年のときに家族旅行で南紀に海水浴へ行ったときの帰りだった。今にして思えばおそらく、田辺駅で購入したのだろう。普通の幕の内弁当だったと記憶している。
これがうまかった。
家族で列車に長時間乗るときは、たいてい母親は弁当を作る。この旅行も、行きはおかんが作ったおにぎりや卵焼きを車内で食べたのだろう。だが帰りはそういうわけにはいかない。で、駅弁の登場となったのだが、とにかく子供にはモノ珍しい。それに僕は幼少時からネリモノが大好きで、そこに入っていたカマボコなどがもう嬉しくてしかたがなかった。
しかし、その後は長らく駅弁を食べる機会がなかった。食べたかったのだけれど。
子供の頃、うちの書棚に保育社のカラーブックスシリーズの一冊である「駅弁旅行」という本があった。これはカラーブックスだから一種の駅弁の写真集である。
これを、僕は何度も何度も、それこそ舐めるように読み、眺めた。そして憧れた。うまそうだな。石井出雄氏の文章も魅力的で、この本はいま僕の手元にはないのだが(既に絶版であるようで、実家にはまだあるのではないかと思うが)、その記述のひとつひとつまで思い出すことが出来る。
ちょっと検索してみるとどうも昭和42年発行で、改訂版もその後出たようだが、僕が見ていたのは42年度版。なので、今はもう無い弁当も多いだろう。したがって、その本に載っていた駅弁で今も販売しているものは、なんせ50年ほども前からずっとロングセラーになっているものだから、もう駅弁界のレジェンドと言ってもいいだろう。
厚岸の「かきめし」。森の「いかめし」。長万部の「かにめし」「もりそば弁当」。八戸の「小唄寿司」。大館の「鶏めし」。高崎の「鳥めし弁当」「だるま弁当」。横川の「峠の釜めし」。千葉の「やきはま弁當」。横浜の「シウマイ弁当」。大船の「鰺の押寿司」「サンドイッチ」。静岡の「鯛めし」。富山の「ますのすし」。神戸の「肉めし」。岡山の「祭すし」。三原の「たこめし」。広島の「しゃもじかきめし」。宮島口の「あなごめし」。鳥取の「かに寿し」。松山の「醤油めし」。折尾の「かしわめし」。人吉の「鮎ずし」。適当に挙げているが、これらは当時、本当に憧憬の弁当だった。
大人になったら食べよう。そう思い続けていた。
だが、駅弁というものは、高い。現在、駅弁の値段は普通に1000円を超えている。もちろん、昔はそんなにはしなかったが、当時の物価と照らし合わせると高価であったことには違いはない。
駅弁初の「1000円弁当」として「しゃぶしゃぶ弁当松風」が売り出されたことがニュースになったのを今も記憶しているが、それはまだ僕が小学生ではなかったか。つまり40年くらい前に既に1000円超えの弁当が発売されたということは、通常の駅弁すら5~600円はしていたのだろう。そして、その後も値段は上がってゆく。
大学生から周遊券を使った汽車旅を始めるが、金銭的には切り詰めた旅行であり、とても手が出るものではなかった。当時の日記を見ても駅弁を買った記録がない。ただ逡巡した記憶は、何度もある。
今ではあまり見かけなくなったが、当時は駅弁はよくホームで「立ち売り」をしていた。首から弁当が入った大きな箱をストラップで吊るし、大きな声で「べんとぉー べんとぉー」と声を出す。立ち売りのおじさんの声はだいたい練れたいい声で、僕は子供の頃よく聴いた、大徳寺の托鉢のお坊さんの声を思い出した。
その立ち売りのおじさんが北海道の長万部駅で憧れの「かにめし」を担いで売っているのを見た。列車の停車時間に思わず駆け寄ったのだが、その「700円」の値札にどうしても躊躇する。僕はおじさんの前でしばらく立ち尽くしてしまった。
「買うの? 買わないの?」おじさんは僕に言った。おそらく営業妨害だったのだろう。ごめんなさい。あわてて僕は立ち去った。
そんな幾度かの記憶がある。
社会人となって、一応フトコロに小銭は持てるようになった。僕は、旅に出るたびに駅弁を求めた。
ただ、これは僕にとっては一種の「文学散歩」だったような気がする。子供の頃に憧れたレジェンド弁当を食べてみたい。そんな思いが強かった。したがって、食べたら必ず弁当の掛け紙は持って帰る(峠の釜めしは当然ながら容器も持ち帰る)。
もちろんロングセラーの弁当というものは、うまいから生き残っているのであり、味は当然折り紙つきである。だが、当時は味よりもやはり「経験したい」という思いが強かったと思う。高崎でとりめしを食べたときには大変旨いと思い、もう一度食べたいとは思ったが、次回に機会があったときはやはり「だるま弁当」を買ってしまった。こっちも食べてみたいじゃない。で、包み紙は持ち帰る。コレクター的要素が強くなってきた。
なので、複数回食べた弁当はそんなに多くない。例外的に金沢の「お贄寿し」と福井の「越前かにめし」はよく食べたが、これには出張がからんでいる。純粋に旅行先で食べたとは言えない。
また、例えばその頃小淵沢駅で「元気甲斐」という弁当がTVの企画によって売り出され、大変に評判を呼んでいた。とにかくうまいらしい。だが、僕はそういう新しい弁当には一瞥もくれず「高原野菜とカツの弁当」を買った。こっちのほうが歴史があるから。何というか、面倒くさい男だった。もちろん高原野菜カツ弁当もうまかったし、後になって食べた元気甲斐も上等だったが。
そのうちに、結婚する。妻が僕の駅弁の掛け紙のコレクションを見て「これ何? 」と言った。
僕がかくかくしかじかと説明すると、僕の趣味にはほぼ興味を示さない妻が、これには乗ってきた。僕の歴史の話などはいつも耳を塞ぐ妻だが、食べ物となると違うらしい。また、妻にも多少の蒐集癖はあり(飽きやすいのだが)、駅のスタンプなども集めている。
そのため、二人で旅行に出ればそこに「駅弁」を組み込むことが多くなった。
しかし、これは僕にとっては堕落の一歩だったと思っている。
僕は、とにかく子供の頃に憧れた、レジェンド級の駅弁を食べたいと思って動いている文学散歩的食べ歩きである。なので、明治時代から続く静岡の鯛めしや大船の鰺の押寿司などは何よりも優先すべき弁当であり、伝統と歴史を重んじている。
ところが妻はそうではない。何よりも「おいしいかどうか」を重視する(当然だが)。なので、雑誌の特集やTVなどはよくチェックし、評判の駅弁を食べたいと言う。
僕は新しく発売された「黒田如水弁当(仮)」や「山里のこだわり弁当(仮)」などといったものには全然興味がない。うまいにこしたことはないが、うまい、うまくないは別問題としているので、チョイスに齟齬が生じる。
そりゃ女房が推薦する弁当はうまいですよ。池田の「十勝牛のワイン漬ステーキ辨當」なんてのはびっくりするくらいうまかったなあ。僕は昭和40年代以前からある弁当を主にターゲットにしているので、こういうのは誘われなければ食べなかったと思う。おそらく僕の食べた中では5本の指に入ると思われ、その点においては妻に感謝なのだが、もうひとつ問題がある。
このステーキ弁当は、実は車で買いに行っているのである。北海道は池田駅に止まる列車も少なく、完全予約制となっていて途中下車でフラリと買えない(今はどうなのかな…20年くらい前の話)。なので、電話して車でお店に行って、どこかの景色のいい場所で食べた。
駅弁は、列車で食べてこそ。車窓を見つつ味わうものであると頑固に信じる実に面倒くさい男である。なので、うまかったのは抜群にうまかったが「駅弁を食べた」という気が全くしない。普通にレストランのテイクアウトである。
妻にとっては、食べてうまくて掛け紙を持ち帰ることが出来ればそれでよいので、その後も車で購入に走ることが多くなった。ことに北海道などは列車の便が悪いので、どうしてもそうなることが多い。
なんだかなあと思うのである。
そうしているうちに妻はついに禁断の場所である「デパートの催事」に手を出した。そうなると食べる場所は、我が家の茶の間である。旅情など一切介在しない。
「だってこうでもしないと進まないじゃない」
「あんた駅弁が全国に何種類あると思てんのや。2000種類できかへんぞ。3000くらいあるかもしれん」
「えーそんなにあるの」
「だいたい全部食べようなんてはなから無理な話なんや。新しいもんはどんどん出てくるし。コレクションはいいがコンプリートは一生かかっても無理や」
妻は、その後憑き物が落ちたように駅弁に興味を失った。飽きたのかもしれない。そういう僕も、レジェンド弁当をある程度食べ終え、徐々にペースが落ちた。そのうちに前述の理由などが重なり、もう駅弁に目の色を変えることはなくなってしまった。
しかし駅弁というものはなかなか味わい深いものであって、こうしてたまに食べると、旅情とともにいろんなことをまた思い出すのである。
この話は、最初は「駅弁で呑む」という記事のマクラにするつもりで書き始めたのだが、思わず長くなってしまったのでここまでにする。呑む話はまた次の機会に。
これを多いと見るか少ないと見るかは、マニアのいる世界でもあり何とも言えないが、僕は昨年末まで、たぶん一年以上駅弁を食べていなかった。ずいぶんご無沙汰してしまったものだと思う。
別に駅弁離れ、というつもりもなくただ機会がなかっただけだと一応は考えてみる。そうだよなあ。別に駅弁が嫌いになったわけでもなし。でも思い返してみると、ここ14~5年は昔と比べてかなり利用回数が減ったように思われる。どうしてかなあ。
まずは旅に出ることが少なくなったというのが第一義的にあるのはもちろんだと思うけれども、他にもいくつか要因があるように思う。
ひとつは、僕が新幹線・特急列車に乗る機会を減らしているということ。旅行に行くときの交通機関の選択としてどんどん車のパーセンテージが上がっていることに加え、遊びであまり速い列車に乗らなくなっている。以前は「時間を金で買う」という意識が強かったが、移動も旅行の楽しみであるに間違いは無く、今はよく普通・快速列車に乗る。新幹線というのは、車窓風景が均質的なので飽きる。あれは出張用だ。在来線のほうが楽しい。
ところが鈍行列車の車内というのは、今は食事をする場所ではなくなっている。
田舎の路線でも、座席はベンチシートが増えた。あの席では弁当などは実に食べにくい。また快速列車は前向き座席が多いが、近郊線なので混雑する。立っている人からじろじろ見られるのもまた食事に相応しくない。
また他に、食事の選択肢が増えたということ。
それでも特急に乗る機会もあるにはあって、特急列車は座席にテーブルもついていて弁当を食べるに不自由はないが、乗車するのはターミナル駅から、ということが多く、食事をテイクアウトするのに駅弁だけではなくデパ地下やエキナカなど目移りして、そっちのほうがコスパが良いことが大半なので困ってしまう。昔は長い汽車旅だと、駅弁か立ち食いそばくらいしか選択肢がなかったものだが。
さらに、昔と比べて駅弁が手軽に手に入りやす過ぎる、ということがある。
昔からデパートの催事で「駅弁大会」というものは盛んにあって、現地に行かなくても手に入ったものだったが、それがさらに昨今はスーパーなどでも企画されるようになった。僕が住む徒歩圏内のスーパーでも、年に何度も各地方の名物駅弁を特集して販売している。そうなると、逆に買わなくなるのである。
この心理を説明するのは難しい。いつでも手に入ると思うと購買意欲が失せるという心理を。
例えば別のことで書くと、僕は名古屋に多い「コメダ珈琲店」という喫茶店の「シロノワール」という大きなデニッシュパンにソフトクリームを乗っけてシロップをかけて食うというデザートが好きで、名古屋に昔住んでいたときにハマり、その後名古屋を離れて後も愛知県に行くことがあれば必ず探して食べていた。ところが、そのコメダ珈琲店が全国チェーン展開を始め、とうとう僕の最寄駅のそば、つまり徒歩5分くらいのところにも開店してしまった。そうなると、もう行かなくなるのである。東海地方に行っても「うちの近所で食べられるものを何もここでわざわざ」と思い、また地元の店にも「また今度ね」と思って行かない。結局、地元に店が開店してから一度もシロノワールを食べていない。
つまるところ今までも「せっかくここまで来たんだから食べよう」という心理が働いていたのだろう。駅弁についても同じ。例えば鳥取に行けば「元祖かに寿しを食べなくちゃ」とかつてはやはり思ったが、今はスーパーの広告に載っていると、鳥取で食べなくてもいいかと思い、また駅弁をスーパーで買わなくてもいいだろう、とも思ってしまう。
駅弁を食べていない言い訳に字数を使いすぎた。思い出話を書く。
初めて駅弁を食べたのはいつだったかということを思い返すと、小学校一年のときに家族旅行で南紀に海水浴へ行ったときの帰りだった。今にして思えばおそらく、田辺駅で購入したのだろう。普通の幕の内弁当だったと記憶している。
これがうまかった。
家族で列車に長時間乗るときは、たいてい母親は弁当を作る。この旅行も、行きはおかんが作ったおにぎりや卵焼きを車内で食べたのだろう。だが帰りはそういうわけにはいかない。で、駅弁の登場となったのだが、とにかく子供にはモノ珍しい。それに僕は幼少時からネリモノが大好きで、そこに入っていたカマボコなどがもう嬉しくてしかたがなかった。
しかし、その後は長らく駅弁を食べる機会がなかった。食べたかったのだけれど。
子供の頃、うちの書棚に保育社のカラーブックスシリーズの一冊である「駅弁旅行」という本があった。これはカラーブックスだから一種の駅弁の写真集である。
これを、僕は何度も何度も、それこそ舐めるように読み、眺めた。そして憧れた。うまそうだな。石井出雄氏の文章も魅力的で、この本はいま僕の手元にはないのだが(既に絶版であるようで、実家にはまだあるのではないかと思うが)、その記述のひとつひとつまで思い出すことが出来る。
ちょっと検索してみるとどうも昭和42年発行で、改訂版もその後出たようだが、僕が見ていたのは42年度版。なので、今はもう無い弁当も多いだろう。したがって、その本に載っていた駅弁で今も販売しているものは、なんせ50年ほども前からずっとロングセラーになっているものだから、もう駅弁界のレジェンドと言ってもいいだろう。
厚岸の「かきめし」。森の「いかめし」。長万部の「かにめし」「もりそば弁当」。八戸の「小唄寿司」。大館の「鶏めし」。高崎の「鳥めし弁当」「だるま弁当」。横川の「峠の釜めし」。千葉の「やきはま弁當」。横浜の「シウマイ弁当」。大船の「鰺の押寿司」「サンドイッチ」。静岡の「鯛めし」。富山の「ますのすし」。神戸の「肉めし」。岡山の「祭すし」。三原の「たこめし」。広島の「しゃもじかきめし」。宮島口の「あなごめし」。鳥取の「かに寿し」。松山の「醤油めし」。折尾の「かしわめし」。人吉の「鮎ずし」。適当に挙げているが、これらは当時、本当に憧憬の弁当だった。
大人になったら食べよう。そう思い続けていた。
だが、駅弁というものは、高い。現在、駅弁の値段は普通に1000円を超えている。もちろん、昔はそんなにはしなかったが、当時の物価と照らし合わせると高価であったことには違いはない。
駅弁初の「1000円弁当」として「しゃぶしゃぶ弁当松風」が売り出されたことがニュースになったのを今も記憶しているが、それはまだ僕が小学生ではなかったか。つまり40年くらい前に既に1000円超えの弁当が発売されたということは、通常の駅弁すら5~600円はしていたのだろう。そして、その後も値段は上がってゆく。
大学生から周遊券を使った汽車旅を始めるが、金銭的には切り詰めた旅行であり、とても手が出るものではなかった。当時の日記を見ても駅弁を買った記録がない。ただ逡巡した記憶は、何度もある。
今ではあまり見かけなくなったが、当時は駅弁はよくホームで「立ち売り」をしていた。首から弁当が入った大きな箱をストラップで吊るし、大きな声で「べんとぉー べんとぉー」と声を出す。立ち売りのおじさんの声はだいたい練れたいい声で、僕は子供の頃よく聴いた、大徳寺の托鉢のお坊さんの声を思い出した。
その立ち売りのおじさんが北海道の長万部駅で憧れの「かにめし」を担いで売っているのを見た。列車の停車時間に思わず駆け寄ったのだが、その「700円」の値札にどうしても躊躇する。僕はおじさんの前でしばらく立ち尽くしてしまった。
「買うの? 買わないの?」おじさんは僕に言った。おそらく営業妨害だったのだろう。ごめんなさい。あわてて僕は立ち去った。
そんな幾度かの記憶がある。
社会人となって、一応フトコロに小銭は持てるようになった。僕は、旅に出るたびに駅弁を求めた。
ただ、これは僕にとっては一種の「文学散歩」だったような気がする。子供の頃に憧れたレジェンド弁当を食べてみたい。そんな思いが強かった。したがって、食べたら必ず弁当の掛け紙は持って帰る(峠の釜めしは当然ながら容器も持ち帰る)。
もちろんロングセラーの弁当というものは、うまいから生き残っているのであり、味は当然折り紙つきである。だが、当時は味よりもやはり「経験したい」という思いが強かったと思う。高崎でとりめしを食べたときには大変旨いと思い、もう一度食べたいとは思ったが、次回に機会があったときはやはり「だるま弁当」を買ってしまった。こっちも食べてみたいじゃない。で、包み紙は持ち帰る。コレクター的要素が強くなってきた。
なので、複数回食べた弁当はそんなに多くない。例外的に金沢の「お贄寿し」と福井の「越前かにめし」はよく食べたが、これには出張がからんでいる。純粋に旅行先で食べたとは言えない。
また、例えばその頃小淵沢駅で「元気甲斐」という弁当がTVの企画によって売り出され、大変に評判を呼んでいた。とにかくうまいらしい。だが、僕はそういう新しい弁当には一瞥もくれず「高原野菜とカツの弁当」を買った。こっちのほうが歴史があるから。何というか、面倒くさい男だった。もちろん高原野菜カツ弁当もうまかったし、後になって食べた元気甲斐も上等だったが。
そのうちに、結婚する。妻が僕の駅弁の掛け紙のコレクションを見て「これ何? 」と言った。
僕がかくかくしかじかと説明すると、僕の趣味にはほぼ興味を示さない妻が、これには乗ってきた。僕の歴史の話などはいつも耳を塞ぐ妻だが、食べ物となると違うらしい。また、妻にも多少の蒐集癖はあり(飽きやすいのだが)、駅のスタンプなども集めている。
そのため、二人で旅行に出ればそこに「駅弁」を組み込むことが多くなった。
しかし、これは僕にとっては堕落の一歩だったと思っている。
僕は、とにかく子供の頃に憧れた、レジェンド級の駅弁を食べたいと思って動いている文学散歩的食べ歩きである。なので、明治時代から続く静岡の鯛めしや大船の鰺の押寿司などは何よりも優先すべき弁当であり、伝統と歴史を重んじている。
ところが妻はそうではない。何よりも「おいしいかどうか」を重視する(当然だが)。なので、雑誌の特集やTVなどはよくチェックし、評判の駅弁を食べたいと言う。
僕は新しく発売された「黒田如水弁当(仮)」や「山里のこだわり弁当(仮)」などといったものには全然興味がない。うまいにこしたことはないが、うまい、うまくないは別問題としているので、チョイスに齟齬が生じる。
そりゃ女房が推薦する弁当はうまいですよ。池田の「十勝牛のワイン漬ステーキ辨當」なんてのはびっくりするくらいうまかったなあ。僕は昭和40年代以前からある弁当を主にターゲットにしているので、こういうのは誘われなければ食べなかったと思う。おそらく僕の食べた中では5本の指に入ると思われ、その点においては妻に感謝なのだが、もうひとつ問題がある。
このステーキ弁当は、実は車で買いに行っているのである。北海道は池田駅に止まる列車も少なく、完全予約制となっていて途中下車でフラリと買えない(今はどうなのかな…20年くらい前の話)。なので、電話して車でお店に行って、どこかの景色のいい場所で食べた。
駅弁は、列車で食べてこそ。車窓を見つつ味わうものであると頑固に信じる実に面倒くさい男である。なので、うまかったのは抜群にうまかったが「駅弁を食べた」という気が全くしない。普通にレストランのテイクアウトである。
妻にとっては、食べてうまくて掛け紙を持ち帰ることが出来ればそれでよいので、その後も車で購入に走ることが多くなった。ことに北海道などは列車の便が悪いので、どうしてもそうなることが多い。
なんだかなあと思うのである。
そうしているうちに妻はついに禁断の場所である「デパートの催事」に手を出した。そうなると食べる場所は、我が家の茶の間である。旅情など一切介在しない。
「だってこうでもしないと進まないじゃない」
「あんた駅弁が全国に何種類あると思てんのや。2000種類できかへんぞ。3000くらいあるかもしれん」
「えーそんなにあるの」
「だいたい全部食べようなんてはなから無理な話なんや。新しいもんはどんどん出てくるし。コレクションはいいがコンプリートは一生かかっても無理や」
妻は、その後憑き物が落ちたように駅弁に興味を失った。飽きたのかもしれない。そういう僕も、レジェンド弁当をある程度食べ終え、徐々にペースが落ちた。そのうちに前述の理由などが重なり、もう駅弁に目の色を変えることはなくなってしまった。
しかし駅弁というものはなかなか味わい深いものであって、こうしてたまに食べると、旅情とともにいろんなことをまた思い出すのである。
この話は、最初は「駅弁で呑む」という記事のマクラにするつもりで書き始めたのだが、思わず長くなってしまったのでここまでにする。呑む話はまた次の機会に。
今年(2014年)は、珍しく僕の住んでいるところでも12月半ばに雪が降った。
北陸に住んでいた頃は、12月どころか11月でも降雪があったものだが、西日本の平野部ではまずそういうことはない。爆弾低気圧、なんて言葉も出てきた。先んじて寒波がおそったため、例年のクリスマス寒波は来ず、今は比較的穏やかに推移しているが。
過去の寒かった年のことを思い出す。
北陸に住んでいたときは「三八豪雪」「五六豪雪」というえげつない雪害が半ば伝説的に語られていて、二階から外に出たとかいろんな話を聞いたものだが、その頃は京都に居たので全く覚えがない。ただ、昭和58年の暮れから59年にかけて降り出したいわゆる「五九豪雪」は、日本海側だけではなく山を越えて太平洋側でも降雪があったために、よく記憶している。
この年は、大学受験の年だった。
生来の怠け癖のせいか、受験というものをずっと薄くしか意識してこなかった。
もちろん怠惰な性格のためであって、これを学校のせいにしてしまうと「馬鹿者」と言われてしまうのだが、なんとなく高校生活においてはずっと「進学」ということが遠い世界のように僕には思えていた。
僕が住んでいた地域の公立高校には、当時、学校間格差というものがなかった。「十五の春は泣かせない」という言葉を今もおぼえているが、当時の京都の公立高校は「高校三原則(小学区制・総合制・男女共学)」を堅持していて、公立であれば近所の高校へ進学することになっていた(これが小学区制)。そのため公立高校のレベルはどこも同じで、高校入試も特に苦労した記憶も無く、その高校に入ればアタマのいいヤツからそうでないヤツまで様々なレベルの生徒が混在していた。ガリ勉から不良まで雑多で、制服も無くそれは面白い高校生活だったが、こと進学ということに関しては学校としてはあまり手を打っていなかったというのが実情だったろう。そりゃしょうがない。同じクラスの中に、国立大学を目指すヤツもいれば植木屋を目指すヤツもいたのだから。特別な授業など出来ない。
なので進学のための勉強は、個人に委ねられていた。レベルの高い勉強をしたいヤツは予備校や塾に通う。
僕は怠惰な性格なので、そういうことを放置して青春時代を謳歌していた。ぼんやりと大学に行きたいとは思っていたが、特別なことは何もしていなかったと言っていい。そうして、いつしか3年生になっていた。
夏に、模試をいくつか受けた。
そこで、これではダメだということを思い知らされた。歯が立たないのである。尻に火が付いた。
しかし火はすぐに熾火となってしまう。こりゃ今からじゃ間に合わないんじゃないか。そしてすぐに、一年浪人すればなんとかなるかも、というところに思考が飛んでゆく。
親にそのことを言うと「阿呆か」と言われた。そんな経済的余裕はないぞと。兄弟も居て、教育費だけでパンクしてしまうではないか。現役でどっか入ってくれ。最も望ましいのは、家から通える学費の安い国公立大学であると言う。
しかし地元の国立と言えば京大である。そんなんは逆立ちしても無理や、あんたらの息子やでオツムのレベルくらい想像がつくやろ、と言うと、せめて安めの私立なら良い、しかし地方へやるのは無理だから、家から自転車で通えるところにしろ、と。
18歳の僕は、岐路に立たされていた(遅いっつーの)。
僕は、数学が致命的なほどに出来ない。
ならば私立文系ということになるが、これもアタマを抱えることになる。英語が不得手なのだ(数学と英語が出来ないで進学を考えるなど身の程知らずも甚だしい)。
ただ、国語と日本史は、模試では結構いい成績をとっているのである。古文も得意だし、当時から歴史ヲタクだった。しかし偏りが大きすぎた。
私立文系の入試の形態は、大学により様々である。だが、困ったことに多くは英語の比率が大きい。英語200・国語100・社会100とか。英語150・国語150・社会100なんてのも。これでは受からない。その中で、英語国語社会で100点づつの300点満点の大学があった。それがどういう天の配剤か「自転車で通える大学」だった。そして、その大学は大学野球でいつも応援していてファンであり、父の母校だった。
狙いは定まった。
しかし定まっただけで、そこから受験モードに急に切り替わったわけではない。夏休みの宿題は9月1日に始め、試験は一夜漬けを得意としてきた僕だ。とりあえず問題集などを買い込んだが、なかなか勉強に手がつかない。ついTVを見てしまう。
そうしているうちに、秋も過ぎ冬を迎えようとしていた。
学校の授業は、あいかわらず平常営業である。特に受験体制ではなく教科書を追っている。僕は微分積分などどうでもいいので、内職をしていた。机の下の「試験に出る英単語」を暗記している。他にもそういうヤツはいっぱいいた。教師も黙認していた節がある。そのうち、欠席が目立つようになってきた。授業より受験勉強を優先しているのだろう。
欠席という手もあるか。出席日数を計算すると、このあと2学期全休しても落第にはならないようである。僕は、ちょっと籠ろうと思った。
その年、親父が滋賀県で中古の家を購入していた。
京都の家は借家であり、仕事もありそのまま住み続けていたが、いずれ定年後のことを考えて安い家を買ったらしい(だから貯金が無くて浪人を許さなかったのか)。したがってその家は現状空家だった。
その家は、電気水道ガスは何とか通じていたが、電話もTVもまだ無かった。余計なものは何も無い。意志の弱い僕には大変好都合である。TVがあるとつい見てしまう。
12月も初旬を過ぎた頃、僕は親父の車にストーブと小さなコタツ、布団、参考書と問題集、食料を積んで、その家に送ってもらった。そして、自ら篭城を始めた。
その家に年末まで20日間ほど居たのだが、よく生活していたなと自分でも思う。何食ってたんだろう。ほとんど記憶がない。冷蔵庫も無かったはず。外出もしなかったし、おそらくカップラーメンばかり食べていたのではないか。二度ほど親が来たが、食料と着替えを置いていったくらいだっただろう。だいたい電話も無く(もちろんケータイもない)、僕の人生であそこまで世俗を外れたことはなかったように思う。
雨戸も閉めたまま。だんだんいつが昼か夜かもわからなくなっていた。眠くなったら寝る。ハラが減ったら何か食う。あとはひたすら、勉強。
ただ、ここが僕の意志の弱いところなのだが、ラジオだけは小さいのを持ち込んでいた。疲れたら、スイッチを入れた。唯一の娯楽だったか。
AMしか入らないラジオだったが、音楽は流れていた。
よく聴こえてきたのは、松田聖子の「瞳はダイヤモンド」。小泉今日子の「艶姿ナミダ娘」。そして山下達郎の「クリスマス・イブ」。
映画色の街 美しい日々がきれぎれに映る
いつ過去形にかわったの
これらを聴くと、あの孤独を感じる間もなかった受験勉強の頃が思い出される。それはそれで、充実した日々だったと今になって思う。
夕暮れ抱き合う舗道 みんなが見ている前で
あなたの肩にちょこんとおでこをつけて泣いたの
トイレに行こうとして、ふと窓の外を見た。
雪が降り積もっていた。全然気が付いていなかった。ここまで積もった雪をあまり見た記憶がなかった。冷えるはずだ。空からはまだ絶え間なく白い雪が降り続いている。
心深く秘めた想い 叶えられそうもない
街角にはXmas tree 銀色の煌き Silent night Holy night
このうたは、あれから30年以上過ぎたのに、まだ命脈を保っている。僕にとっては、このうたはやはり1983年12月のうたとして鮮烈に記憶に残っている。
年が明けると、すぐに共通一次試験。無駄とは知りつつ、マークシートだものどう転ぶかわからないので、一応受験した。
結果、惨敗。100点満点の日本史の点数を200点満点の数学Ⅰの点数が大幅に下回るという恐ろしい結果となった。しょうがない。さあもう本命に絞っていこう。
そして、その本命の受験日。また雪が降った。この冬は本当によく降った。
僕は自転車で受験会場である大学へ向かったのだが、路面は凍結しており、途中坂道で思い切り滑り横転し、腕を痛めた。だがそんなことは言っていられない。動揺しつつも、何とか受験会場には間に合った。
試験は、全然出来た気がしなかった。難しすぎた。駄目だ。やはり、付け焼刃の勉強では追いつかなかったか。僕は憔悴して空を見上げた。雪が少し小降りになってきた。
それから合格発表までの数日間のことをまた思い出す。
2月以降、もう学校も授業などはやっていない。だから行ってもしょうがないのだが、なんとなく顔を出すと、受かったヤツ、落ちたヤツらが報告に現れる。予備校の相談もしている。その悲喜交々とした様を見ているのも、まだ着地していない僕にはしんどかった。3月になればすぐに卒業式がある。就職組や合格組は様々に相談をしているが、輪に入る気にもなれない。
僕はこれからどうなってゆくのだろう。先行きが見えず足が地に付かないこの中途半端な「あわあわ」とした気持ち。それは今まで味わったことのない時間だった。
僕は、ひとりで街へ映画を見に行った。アニメーション「うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー」が封切りとなったので、ラムちゃんのファンだった僕は、せめてこれくらいは見ようと思った。
映画は、傑作だった。非常に面白かった。公開は二本立てで、併映は吉川晃司主演のアイドル映画だったのだが、入替制でないのをいいことに吉川君の映画の間は居眠りをして、2回見た。映画など頭に入るかな、と最初は思っていたのだが、しばしそういうことは忘れた。
外に出れば、もう暗くなっている。吉川晃司の映画を挟んで3本見たことになるので、ずいぶん時間も過ぎていた。
空を見ると、また細かな白いものが舞っている。
僕の頭の中ではずっと映画のエンディングテーマだった「愛はブーメラン」が繰り返し流れていた。
今 あの娘の細い腰 手を回した 悲しいわ これっきりね
今 想い出永遠に消しましょうか ため息で So long in my dream
そのときの繁華街の風景を今もよくおぼえている。ポケットに手を突っ込みながら、帰りのバス停へ向かうでもなく、うつろな目で歩いた。
湧き起こる「あわあわ」とした気持ちを「愛はブーメラン」がいっとき押し流す。そしてまた再び空虚感が襲ってくる。
今、同じような状況に至っても、こんな気分にはなるまい。若かったのだろう。アーケードから出ると、また雪。
もしか もしか 愛はもしかして 放り投げたブーメラン
大学には奇跡的に合格していた。当日僕は合格発表を見に行く気にもならずフテ寝していたが、母と妹が見に行ったらしい。叩き起こされた。そして、春が来た。
今も、あの気持ちが揺れた冬のことを懐かしく思い出すときがある。
北陸に住んでいた頃は、12月どころか11月でも降雪があったものだが、西日本の平野部ではまずそういうことはない。爆弾低気圧、なんて言葉も出てきた。先んじて寒波がおそったため、例年のクリスマス寒波は来ず、今は比較的穏やかに推移しているが。
過去の寒かった年のことを思い出す。
北陸に住んでいたときは「三八豪雪」「五六豪雪」というえげつない雪害が半ば伝説的に語られていて、二階から外に出たとかいろんな話を聞いたものだが、その頃は京都に居たので全く覚えがない。ただ、昭和58年の暮れから59年にかけて降り出したいわゆる「五九豪雪」は、日本海側だけではなく山を越えて太平洋側でも降雪があったために、よく記憶している。
この年は、大学受験の年だった。
生来の怠け癖のせいか、受験というものをずっと薄くしか意識してこなかった。
もちろん怠惰な性格のためであって、これを学校のせいにしてしまうと「馬鹿者」と言われてしまうのだが、なんとなく高校生活においてはずっと「進学」ということが遠い世界のように僕には思えていた。
僕が住んでいた地域の公立高校には、当時、学校間格差というものがなかった。「十五の春は泣かせない」という言葉を今もおぼえているが、当時の京都の公立高校は「高校三原則(小学区制・総合制・男女共学)」を堅持していて、公立であれば近所の高校へ進学することになっていた(これが小学区制)。そのため公立高校のレベルはどこも同じで、高校入試も特に苦労した記憶も無く、その高校に入ればアタマのいいヤツからそうでないヤツまで様々なレベルの生徒が混在していた。ガリ勉から不良まで雑多で、制服も無くそれは面白い高校生活だったが、こと進学ということに関しては学校としてはあまり手を打っていなかったというのが実情だったろう。そりゃしょうがない。同じクラスの中に、国立大学を目指すヤツもいれば植木屋を目指すヤツもいたのだから。特別な授業など出来ない。
なので進学のための勉強は、個人に委ねられていた。レベルの高い勉強をしたいヤツは予備校や塾に通う。
僕は怠惰な性格なので、そういうことを放置して青春時代を謳歌していた。ぼんやりと大学に行きたいとは思っていたが、特別なことは何もしていなかったと言っていい。そうして、いつしか3年生になっていた。
夏に、模試をいくつか受けた。
そこで、これではダメだということを思い知らされた。歯が立たないのである。尻に火が付いた。
しかし火はすぐに熾火となってしまう。こりゃ今からじゃ間に合わないんじゃないか。そしてすぐに、一年浪人すればなんとかなるかも、というところに思考が飛んでゆく。
親にそのことを言うと「阿呆か」と言われた。そんな経済的余裕はないぞと。兄弟も居て、教育費だけでパンクしてしまうではないか。現役でどっか入ってくれ。最も望ましいのは、家から通える学費の安い国公立大学であると言う。
しかし地元の国立と言えば京大である。そんなんは逆立ちしても無理や、あんたらの息子やでオツムのレベルくらい想像がつくやろ、と言うと、せめて安めの私立なら良い、しかし地方へやるのは無理だから、家から自転車で通えるところにしろ、と。
18歳の僕は、岐路に立たされていた(遅いっつーの)。
僕は、数学が致命的なほどに出来ない。
ならば私立文系ということになるが、これもアタマを抱えることになる。英語が不得手なのだ(数学と英語が出来ないで進学を考えるなど身の程知らずも甚だしい)。
ただ、国語と日本史は、模試では結構いい成績をとっているのである。古文も得意だし、当時から歴史ヲタクだった。しかし偏りが大きすぎた。
私立文系の入試の形態は、大学により様々である。だが、困ったことに多くは英語の比率が大きい。英語200・国語100・社会100とか。英語150・国語150・社会100なんてのも。これでは受からない。その中で、英語国語社会で100点づつの300点満点の大学があった。それがどういう天の配剤か「自転車で通える大学」だった。そして、その大学は大学野球でいつも応援していてファンであり、父の母校だった。
狙いは定まった。
しかし定まっただけで、そこから受験モードに急に切り替わったわけではない。夏休みの宿題は9月1日に始め、試験は一夜漬けを得意としてきた僕だ。とりあえず問題集などを買い込んだが、なかなか勉強に手がつかない。ついTVを見てしまう。
そうしているうちに、秋も過ぎ冬を迎えようとしていた。
学校の授業は、あいかわらず平常営業である。特に受験体制ではなく教科書を追っている。僕は微分積分などどうでもいいので、内職をしていた。机の下の「試験に出る英単語」を暗記している。他にもそういうヤツはいっぱいいた。教師も黙認していた節がある。そのうち、欠席が目立つようになってきた。授業より受験勉強を優先しているのだろう。
欠席という手もあるか。出席日数を計算すると、このあと2学期全休しても落第にはならないようである。僕は、ちょっと籠ろうと思った。
その年、親父が滋賀県で中古の家を購入していた。
京都の家は借家であり、仕事もありそのまま住み続けていたが、いずれ定年後のことを考えて安い家を買ったらしい(だから貯金が無くて浪人を許さなかったのか)。したがってその家は現状空家だった。
その家は、電気水道ガスは何とか通じていたが、電話もTVもまだ無かった。余計なものは何も無い。意志の弱い僕には大変好都合である。TVがあるとつい見てしまう。
12月も初旬を過ぎた頃、僕は親父の車にストーブと小さなコタツ、布団、参考書と問題集、食料を積んで、その家に送ってもらった。そして、自ら篭城を始めた。
その家に年末まで20日間ほど居たのだが、よく生活していたなと自分でも思う。何食ってたんだろう。ほとんど記憶がない。冷蔵庫も無かったはず。外出もしなかったし、おそらくカップラーメンばかり食べていたのではないか。二度ほど親が来たが、食料と着替えを置いていったくらいだっただろう。だいたい電話も無く(もちろんケータイもない)、僕の人生であそこまで世俗を外れたことはなかったように思う。
雨戸も閉めたまま。だんだんいつが昼か夜かもわからなくなっていた。眠くなったら寝る。ハラが減ったら何か食う。あとはひたすら、勉強。
ただ、ここが僕の意志の弱いところなのだが、ラジオだけは小さいのを持ち込んでいた。疲れたら、スイッチを入れた。唯一の娯楽だったか。
AMしか入らないラジオだったが、音楽は流れていた。
よく聴こえてきたのは、松田聖子の「瞳はダイヤモンド」。小泉今日子の「艶姿ナミダ娘」。そして山下達郎の「クリスマス・イブ」。
映画色の街 美しい日々がきれぎれに映る
いつ過去形にかわったの
これらを聴くと、あの孤独を感じる間もなかった受験勉強の頃が思い出される。それはそれで、充実した日々だったと今になって思う。
夕暮れ抱き合う舗道 みんなが見ている前で
あなたの肩にちょこんとおでこをつけて泣いたの
トイレに行こうとして、ふと窓の外を見た。
雪が降り積もっていた。全然気が付いていなかった。ここまで積もった雪をあまり見た記憶がなかった。冷えるはずだ。空からはまだ絶え間なく白い雪が降り続いている。
心深く秘めた想い 叶えられそうもない
街角にはXmas tree 銀色の煌き Silent night Holy night
このうたは、あれから30年以上過ぎたのに、まだ命脈を保っている。僕にとっては、このうたはやはり1983年12月のうたとして鮮烈に記憶に残っている。
年が明けると、すぐに共通一次試験。無駄とは知りつつ、マークシートだものどう転ぶかわからないので、一応受験した。
結果、惨敗。100点満点の日本史の点数を200点満点の数学Ⅰの点数が大幅に下回るという恐ろしい結果となった。しょうがない。さあもう本命に絞っていこう。
そして、その本命の受験日。また雪が降った。この冬は本当によく降った。
僕は自転車で受験会場である大学へ向かったのだが、路面は凍結しており、途中坂道で思い切り滑り横転し、腕を痛めた。だがそんなことは言っていられない。動揺しつつも、何とか受験会場には間に合った。
試験は、全然出来た気がしなかった。難しすぎた。駄目だ。やはり、付け焼刃の勉強では追いつかなかったか。僕は憔悴して空を見上げた。雪が少し小降りになってきた。
それから合格発表までの数日間のことをまた思い出す。
2月以降、もう学校も授業などはやっていない。だから行ってもしょうがないのだが、なんとなく顔を出すと、受かったヤツ、落ちたヤツらが報告に現れる。予備校の相談もしている。その悲喜交々とした様を見ているのも、まだ着地していない僕にはしんどかった。3月になればすぐに卒業式がある。就職組や合格組は様々に相談をしているが、輪に入る気にもなれない。
僕はこれからどうなってゆくのだろう。先行きが見えず足が地に付かないこの中途半端な「あわあわ」とした気持ち。それは今まで味わったことのない時間だった。
僕は、ひとりで街へ映画を見に行った。アニメーション「うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー」が封切りとなったので、ラムちゃんのファンだった僕は、せめてこれくらいは見ようと思った。
映画は、傑作だった。非常に面白かった。公開は二本立てで、併映は吉川晃司主演のアイドル映画だったのだが、入替制でないのをいいことに吉川君の映画の間は居眠りをして、2回見た。映画など頭に入るかな、と最初は思っていたのだが、しばしそういうことは忘れた。
外に出れば、もう暗くなっている。吉川晃司の映画を挟んで3本見たことになるので、ずいぶん時間も過ぎていた。
空を見ると、また細かな白いものが舞っている。
僕の頭の中ではずっと映画のエンディングテーマだった「愛はブーメラン」が繰り返し流れていた。
今 あの娘の細い腰 手を回した 悲しいわ これっきりね
今 想い出永遠に消しましょうか ため息で So long in my dream
そのときの繁華街の風景を今もよくおぼえている。ポケットに手を突っ込みながら、帰りのバス停へ向かうでもなく、うつろな目で歩いた。
湧き起こる「あわあわ」とした気持ちを「愛はブーメラン」がいっとき押し流す。そしてまた再び空虚感が襲ってくる。
今、同じような状況に至っても、こんな気分にはなるまい。若かったのだろう。アーケードから出ると、また雪。
もしか もしか 愛はもしかして 放り投げたブーメラン
大学には奇跡的に合格していた。当日僕は合格発表を見に行く気にもならずフテ寝していたが、母と妹が見に行ったらしい。叩き起こされた。そして、春が来た。
今も、あの気持ちが揺れた冬のことを懐かしく思い出すときがある。
「恥の多い生涯を送って来ました」
もちろん太宰治の有名な一節だが、その太宰は「人間失格」を書き終えて、自死を選んだ。39歳の誕生日を迎える数日前。
僕も同年齢にして、「死」というものを意識するようになったことを記憶している。無論のこと太宰とは異なり自ら死を選ぼうなどとは微塵も考えてはいなかったが、少なくとも人生は有限である、ということをはっきりと認識したように思う。
それには様々な要因があったのだが、同時に「自分史」というものを無性に記したくなった。自分史といえば大仰でありそんな大層なものではないが、自分の軌跡を、その追憶の断片をどこかに残しておきたくなった。
ブログというツールを知ったのはいつだったか。
はっきりとは憶えていないが、それまでWeb上で日々雑感を書いていた日記ツールに限界を感じはじめた頃、おそらく2004年の夏くらいではなかったか。下書きが出来る(執筆に時間をかけられる、また推敲・修正も可能)、字数制限が厳しくない、活字の大きさ等紙面上の自由さやデザインの選択幅の大きさなど、非常に魅力を感じた。
ただ、しばらくは使用に踏み切ってはいなかった。
その頃、日記ツールやBBSなどをWeb上で運営していた以外に、僕はHPを作りたいと思い、その準備をコツコツと行っていた。これがつまり、人生が有限であると気付いた僕が書き残そうと思った自分史にあたる。
しかしそれは公表するまでには至らなかった。少し身体を悪くしてしまい、そのため長時間座って作業を続けることが叶わなくなった。
では、書き溜めていた文書、またこれから書こうと温めていた思いをどうやって吐露してゆくか。
僕は、ブログツールを使おうと思った。それが、このブログにあたる。
2004年も暮れに差し掛かった頃、僕はとりあえず最初の記事を書いた。以後、昔話を中心として記事を積み重ね、これでちょうど10年になる。
この10年というもの、ずっとブログを書いてきた。途切れることなく。稼動させたブログサービスはいくつもある。僕の中の引き出しはとうに空っぽになり、つまり内面にもうネタは無く、自分史という段階は超え、今はもう好奇心に引っかかったものを引きずり出し調査して思考して書くという状況になっている。それでも飽かず、書くことに多くの時間を費やしてきた。
僕にとってのこの10年とはいったいなんだったのだろうか。そんなことを今考えている。
厳しく見れば、それはただの浪費だったのかもしれない。
この費やした時間というものを、もっと有効活用していれば、と人は言うだろう。事実、いくらWeb上に書き続けても、それは何も生み出していないに等しい。
だが、それでも書いてきた。
そして、いつしかこれは僕の「墓標」であると思うようになった。
人は、いつか死ぬ。
そして、死んだ人の軌跡というものは、史上に残る事績を成したひとにぎりの群像を除いては、何も残らない。多くの市井の人々は、忘れ去られてゆく。
例えば子孫や親しい友人は、彼らのことを憶えているかもしれない。だがそれらの人々の人生も有限であり、人は死んだ瞬間から、忘却の波に呑まれていく運命にある。
市井の人が生きてきた証しというものは、極端なことを言えば墓標しか残らない。しかしその墓標すら現代社会においては、建立も難しい時代となっている。そして仮に墓を建てても、祭祀者が途絶えれば終る。
ふつうの人は、何も残らない。
まして、その故人が何を思い、どのように人生を積み重ねてきたかということなどは、その人の脳内にしか存在しないもの。
生きるということは、そういうことなのだ。
彼らが育まれ、努力し、恋をし、幾多のことに感動し、辛いことを潜り抜け、褒められ励まされ、愛情を注ぎ、笑ったり泣いたりしてきたことは、全て無になる。
もちろん、それは自明のことである。消失することに対して抗うことは出来ない。銅像を建てたり、小惑星に名前を冠したりしても、その人の思い、その人の追憶というものは残らない。
ただ、こうして書くことは、銅像よりも彼の人の追憶を留めておくことにはならないだろうか。
Webというものに自分を表現することが可能になってから、しばらく経つ。
以前は、自分の思いを吐露したものを残しておくことは、ごく限られた人にしか不可能だった。作家になるか、あるいは芸術家になるか。自伝を書ける人は幸いである。いくら史上に残る大物であっても、伝記をしるされたり小説の題材になったりするのは、自分の思いを残したとは言いがたい。
今は、誰でもこうして書ける。自分の思考を公表できる。いい時代になったと思う。
同時に、恥を晒しているという見方も出来る。内面を公表するというのはそういうことで、だからHNで書いている。
あらためて昔の記事を読むと、耳まで赤くなる。恥の多い人生であったとつくづく思う。
それでも、こうして自分の軌跡を残しておけるのは、幸せなことだと感じている。
ブログサービスに限れば、例えば日本においては今世紀に入ってから隆盛し、歴史はそろそろ15年になる。
既に管理人がこの世にいないブログも数多くあるだろう。震災のときに「更新が止まったブログ」のことが話題になったが、そんなブログは数多いに違いない。さすればそれは、サーバー上に残る彼の人の墓標であることになる。
願わくは、いつまでも残しておいてやってほしい、と思うのである。無縁仏として片付けてしまわずに。先方も商売でやられていること、難しいとは思うが、何とかならないものかと思う。
わたしは今日まで生きてみました
時にはだれかの力を借りて
時にはだれかにしがみついて
わたしは今日まで 生きてみました
そして今 私は思っています
明日からも こうして生きて行くだろうと
「今日までそして明日から」を聴きながら、またいろんなことを考える。
僕は、いつまで書いてゆけるだろう。
自分的に「虎は死して皮を残す」程度のことは、もう書いたと思っている。だからといって、終了宣言には踏み出せない。それをするには、僕はどうも書くことが好きすぎるようだ。
しかし、書こうと思ってもなかなか書けなくなってきた。
かつて量産していた時代は、いくらでも書きたいことがあった。そういう蓄積や衝動がなくなったことは確かにある。そして同時に、筆力の衰えも感じる。言葉が流れ出てこなくなった。脳の硬直化か。体力の衰えと同様のものを感じている。
でも、書きたいな、まだ。頻度は落ちたとしても。
ブログを始めた頃は、まさか10年後もこうして僕が「凛太郎」としてWeb上に棲息しているとはとても想像がつかなかった。そして今も、将来のことは全く見えない。例えば、還暦を迎えても書いているなんてイメージは全然持てない。
今後何が起こるかは、わからない。
でもしばらくは、道はまだ続いているみたいだ。
終了宣言もしないし、生涯ブロガー宣言もしない。ただ道が続いているなら、少しづつでも歩いてゆくか。そんな心境かな。
けれど それにしたって
どこで どう変わってしまうか
そうです 分からないまま生きてゆく
明日からの そんなわたしです
わたしは今日まで生きてみました
わたしは今日まで生きてみました
そして今 わたしは思っています
明日からもこうして 生きてゆくだろうと
そんな感じで、まだ凛太郎はWeb上に居ます。
もちろん太宰治の有名な一節だが、その太宰は「人間失格」を書き終えて、自死を選んだ。39歳の誕生日を迎える数日前。
僕も同年齢にして、「死」というものを意識するようになったことを記憶している。無論のこと太宰とは異なり自ら死を選ぼうなどとは微塵も考えてはいなかったが、少なくとも人生は有限である、ということをはっきりと認識したように思う。
それには様々な要因があったのだが、同時に「自分史」というものを無性に記したくなった。自分史といえば大仰でありそんな大層なものではないが、自分の軌跡を、その追憶の断片をどこかに残しておきたくなった。
ブログというツールを知ったのはいつだったか。
はっきりとは憶えていないが、それまでWeb上で日々雑感を書いていた日記ツールに限界を感じはじめた頃、おそらく2004年の夏くらいではなかったか。下書きが出来る(執筆に時間をかけられる、また推敲・修正も可能)、字数制限が厳しくない、活字の大きさ等紙面上の自由さやデザインの選択幅の大きさなど、非常に魅力を感じた。
ただ、しばらくは使用に踏み切ってはいなかった。
その頃、日記ツールやBBSなどをWeb上で運営していた以外に、僕はHPを作りたいと思い、その準備をコツコツと行っていた。これがつまり、人生が有限であると気付いた僕が書き残そうと思った自分史にあたる。
しかしそれは公表するまでには至らなかった。少し身体を悪くしてしまい、そのため長時間座って作業を続けることが叶わなくなった。
では、書き溜めていた文書、またこれから書こうと温めていた思いをどうやって吐露してゆくか。
僕は、ブログツールを使おうと思った。それが、このブログにあたる。
2004年も暮れに差し掛かった頃、僕はとりあえず最初の記事を書いた。以後、昔話を中心として記事を積み重ね、これでちょうど10年になる。
この10年というもの、ずっとブログを書いてきた。途切れることなく。稼動させたブログサービスはいくつもある。僕の中の引き出しはとうに空っぽになり、つまり内面にもうネタは無く、自分史という段階は超え、今はもう好奇心に引っかかったものを引きずり出し調査して思考して書くという状況になっている。それでも飽かず、書くことに多くの時間を費やしてきた。
僕にとってのこの10年とはいったいなんだったのだろうか。そんなことを今考えている。
厳しく見れば、それはただの浪費だったのかもしれない。
この費やした時間というものを、もっと有効活用していれば、と人は言うだろう。事実、いくらWeb上に書き続けても、それは何も生み出していないに等しい。
だが、それでも書いてきた。
そして、いつしかこれは僕の「墓標」であると思うようになった。
人は、いつか死ぬ。
そして、死んだ人の軌跡というものは、史上に残る事績を成したひとにぎりの群像を除いては、何も残らない。多くの市井の人々は、忘れ去られてゆく。
例えば子孫や親しい友人は、彼らのことを憶えているかもしれない。だがそれらの人々の人生も有限であり、人は死んだ瞬間から、忘却の波に呑まれていく運命にある。
市井の人が生きてきた証しというものは、極端なことを言えば墓標しか残らない。しかしその墓標すら現代社会においては、建立も難しい時代となっている。そして仮に墓を建てても、祭祀者が途絶えれば終る。
ふつうの人は、何も残らない。
まして、その故人が何を思い、どのように人生を積み重ねてきたかということなどは、その人の脳内にしか存在しないもの。
生きるということは、そういうことなのだ。
彼らが育まれ、努力し、恋をし、幾多のことに感動し、辛いことを潜り抜け、褒められ励まされ、愛情を注ぎ、笑ったり泣いたりしてきたことは、全て無になる。
もちろん、それは自明のことである。消失することに対して抗うことは出来ない。銅像を建てたり、小惑星に名前を冠したりしても、その人の思い、その人の追憶というものは残らない。
ただ、こうして書くことは、銅像よりも彼の人の追憶を留めておくことにはならないだろうか。
Webというものに自分を表現することが可能になってから、しばらく経つ。
以前は、自分の思いを吐露したものを残しておくことは、ごく限られた人にしか不可能だった。作家になるか、あるいは芸術家になるか。自伝を書ける人は幸いである。いくら史上に残る大物であっても、伝記をしるされたり小説の題材になったりするのは、自分の思いを残したとは言いがたい。
今は、誰でもこうして書ける。自分の思考を公表できる。いい時代になったと思う。
同時に、恥を晒しているという見方も出来る。内面を公表するというのはそういうことで、だからHNで書いている。
あらためて昔の記事を読むと、耳まで赤くなる。恥の多い人生であったとつくづく思う。
それでも、こうして自分の軌跡を残しておけるのは、幸せなことだと感じている。
ブログサービスに限れば、例えば日本においては今世紀に入ってから隆盛し、歴史はそろそろ15年になる。
既に管理人がこの世にいないブログも数多くあるだろう。震災のときに「更新が止まったブログ」のことが話題になったが、そんなブログは数多いに違いない。さすればそれは、サーバー上に残る彼の人の墓標であることになる。
願わくは、いつまでも残しておいてやってほしい、と思うのである。無縁仏として片付けてしまわずに。先方も商売でやられていること、難しいとは思うが、何とかならないものかと思う。
わたしは今日まで生きてみました
時にはだれかの力を借りて
時にはだれかにしがみついて
わたしは今日まで 生きてみました
そして今 私は思っています
明日からも こうして生きて行くだろうと
「今日までそして明日から」を聴きながら、またいろんなことを考える。
僕は、いつまで書いてゆけるだろう。
自分的に「虎は死して皮を残す」程度のことは、もう書いたと思っている。だからといって、終了宣言には踏み出せない。それをするには、僕はどうも書くことが好きすぎるようだ。
しかし、書こうと思ってもなかなか書けなくなってきた。
かつて量産していた時代は、いくらでも書きたいことがあった。そういう蓄積や衝動がなくなったことは確かにある。そして同時に、筆力の衰えも感じる。言葉が流れ出てこなくなった。脳の硬直化か。体力の衰えと同様のものを感じている。
でも、書きたいな、まだ。頻度は落ちたとしても。
ブログを始めた頃は、まさか10年後もこうして僕が「凛太郎」としてWeb上に棲息しているとはとても想像がつかなかった。そして今も、将来のことは全く見えない。例えば、還暦を迎えても書いているなんてイメージは全然持てない。
今後何が起こるかは、わからない。
でもしばらくは、道はまだ続いているみたいだ。
終了宣言もしないし、生涯ブロガー宣言もしない。ただ道が続いているなら、少しづつでも歩いてゆくか。そんな心境かな。
けれど それにしたって
どこで どう変わってしまうか
そうです 分からないまま生きてゆく
明日からの そんなわたしです
わたしは今日まで生きてみました
わたしは今日まで生きてみました
そして今 わたしは思っています
明日からもこうして 生きてゆくだろうと
そんな感じで、まだ凛太郎はWeb上に居ます。










 クリックで各カテゴリの
クリックで各カテゴリの