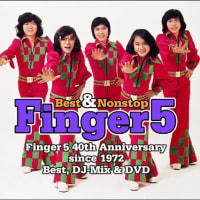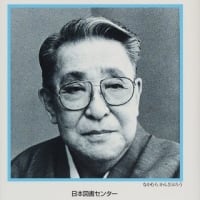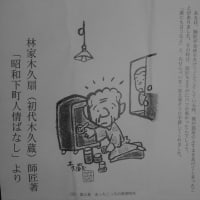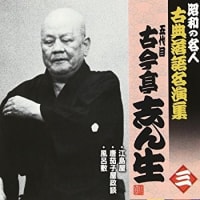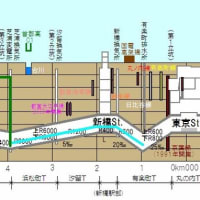げんしろ
「原子炉」ではなく「げんしろ」・・「寄席の席亭が入場人員の頭数を意図的に少なく勘定し、噺家へのワリの支払いを減らす」ことをいった。今では「誤魔化す」ことをいうらしい。
かねがね、往時の生活振り・・例えば、噺家の生活に就いても調べてみたいと思い、資料を集めているが、なかなか進捗しない。偶々、資料がある部分に関し纏まったので、非常に雑駁なものだが、とりまとめてみた。(本稿は、あくまでも“横丁の隠居噺”であって、「考察」の類ではありません)
1887(明治20)年頃の寄席の給金表(ワリ)
三代目柳枝 金4厘 春風亭柳橋(二代目) 金3厘5毛
禽語楼小さん 金4厘 三遊亭金馬(後、小圓朝)金3厘
談洲楼燕枝(初代) 金4厘 永瀬徳久(五代目むらく)金3厘
古今亭今輔(三代目) 金3厘5毛 三遊亭遊三(初代) 金3厘
枝太郎(四代目左楽) 金3厘 三遊亭圓遊(初代) 金5厘
春風亭柳条 金3厘 三遊亭橘之助 金4厘
三遊亭円太郎(ラッパ) 金4厘
以上はスケ(助演)料金で、トリの場合は、この二倍。圓遊だけ5厘貰っているが、彼の人気は盛大であった。圓遊の師匠・圓朝は勿論これ以上だったと推測される。残念ながら、圓朝、圓馬、圓喬、圓右の資料はない。なお、当時の寄席の木戸銭は、4銭。
ワリ4厘というのは客一人分だから、百人入る寄席なら、40銭になる。当時は、四~五軒の寄席を掛け持ちするのが常識だから、結構の収入になる。人気が出れば、お座敷の収入もプラスされる。月給に換算すれば、かなりの実入りになったろう。
ここで比較のため、1886(明治19)年の他の職業の収入や物価をみてみよう。
内閣総理大臣(伊藤博文) 月給800円=年俸9600円
内大臣 月給600円=年俸7200円
各省大臣 月給500円=年俸6000円
巡査(東京府以外) 月給12円
巡査(東京府以外、12年以上勤続) 月給15円
今日新聞(東京新聞) 一部 1銭
朝日新聞 一部 1銭5厘
浅草仲見世店賃(間口九尺奥行き二間) 3円80銭(1ヶ月)
万年筆 50銭(1本)
料理屋「魚十」 向島堤下
「小鉢、椀盛り、刺身など料理一式」 30銭
天麩羅「鈴木」 南品川2丁目 上:6銭、中:4銭、下:2銭
引手茶屋「堀川」 新吉原 貸座敷1名様1円30銭 遊女揚げ代、
料理三種、お酒四本付
当時の物価と現在を単純に比較するのは難しいが、仮に1銭を100円とすると、新聞が100~150円、仲見世の店賃が3万8000円、巡査の月給は12万円。「万年筆」「魚十」「堀川」などは、何となく理解できる。
人気噺家の収入は、決して悪くはないどころか、かなり羽振りが良かったのではないだろうか。4銭の木戸銭は、その後物価の上昇とともに上がったが、席亭も苦しかったのではないだろうか。この頃は、七三で七を芸人が持っていったらしい(その後、六四を経て五五になったと聞く)。だから「げんしろ」したくなる気持ちも分かるね。
注:資料は ①平凡社「落語の世界」今村信雄と②東京新聞3月7日朝刊に依った。
平成17年3月17日 B
「原子炉」ではなく「げんしろ」・・「寄席の席亭が入場人員の頭数を意図的に少なく勘定し、噺家へのワリの支払いを減らす」ことをいった。今では「誤魔化す」ことをいうらしい。
かねがね、往時の生活振り・・例えば、噺家の生活に就いても調べてみたいと思い、資料を集めているが、なかなか進捗しない。偶々、資料がある部分に関し纏まったので、非常に雑駁なものだが、とりまとめてみた。(本稿は、あくまでも“横丁の隠居噺”であって、「考察」の類ではありません)
1887(明治20)年頃の寄席の給金表(ワリ)
三代目柳枝 金4厘 春風亭柳橋(二代目) 金3厘5毛
禽語楼小さん 金4厘 三遊亭金馬(後、小圓朝)金3厘
談洲楼燕枝(初代) 金4厘 永瀬徳久(五代目むらく)金3厘
古今亭今輔(三代目) 金3厘5毛 三遊亭遊三(初代) 金3厘
枝太郎(四代目左楽) 金3厘 三遊亭圓遊(初代) 金5厘
春風亭柳条 金3厘 三遊亭橘之助 金4厘
三遊亭円太郎(ラッパ) 金4厘
以上はスケ(助演)料金で、トリの場合は、この二倍。圓遊だけ5厘貰っているが、彼の人気は盛大であった。圓遊の師匠・圓朝は勿論これ以上だったと推測される。残念ながら、圓朝、圓馬、圓喬、圓右の資料はない。なお、当時の寄席の木戸銭は、4銭。
ワリ4厘というのは客一人分だから、百人入る寄席なら、40銭になる。当時は、四~五軒の寄席を掛け持ちするのが常識だから、結構の収入になる。人気が出れば、お座敷の収入もプラスされる。月給に換算すれば、かなりの実入りになったろう。
ここで比較のため、1886(明治19)年の他の職業の収入や物価をみてみよう。
内閣総理大臣(伊藤博文) 月給800円=年俸9600円
内大臣 月給600円=年俸7200円
各省大臣 月給500円=年俸6000円
巡査(東京府以外) 月給12円
巡査(東京府以外、12年以上勤続) 月給15円
今日新聞(東京新聞) 一部 1銭
朝日新聞 一部 1銭5厘
浅草仲見世店賃(間口九尺奥行き二間) 3円80銭(1ヶ月)
万年筆 50銭(1本)
料理屋「魚十」 向島堤下
「小鉢、椀盛り、刺身など料理一式」 30銭
天麩羅「鈴木」 南品川2丁目 上:6銭、中:4銭、下:2銭
引手茶屋「堀川」 新吉原 貸座敷1名様1円30銭 遊女揚げ代、
料理三種、お酒四本付
当時の物価と現在を単純に比較するのは難しいが、仮に1銭を100円とすると、新聞が100~150円、仲見世の店賃が3万8000円、巡査の月給は12万円。「万年筆」「魚十」「堀川」などは、何となく理解できる。
人気噺家の収入は、決して悪くはないどころか、かなり羽振りが良かったのではないだろうか。4銭の木戸銭は、その後物価の上昇とともに上がったが、席亭も苦しかったのではないだろうか。この頃は、七三で七を芸人が持っていったらしい(その後、六四を経て五五になったと聞く)。だから「げんしろ」したくなる気持ちも分かるね。
注:資料は ①平凡社「落語の世界」今村信雄と②東京新聞3月7日朝刊に依った。
平成17年3月17日 B