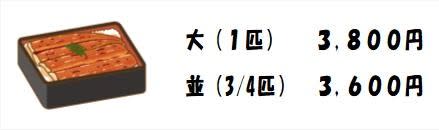2023年12月28日
これは11月分のつぶやきです。
今日は多くの職場で仕事納めですね。今日は職場の大掃除、明日からは家の大掃除という人も多いでしょうね。
今回はゴミ出しの話題です。
ゴミはいつもおばさんが出してくれるので、おじさんはたまにしかゴミステーションに行くことはありません。といってもゴミステーションは近くなので出かけるときはよく前を通ります。
ここは上にワイヤーが張ってあってカーテンのようにリングに吊したネットを開けてゴミを入れます。
ネットにはフックが付いていてそれを外して開けて、閉めたらフックをひっかけます。ただそれだけですが、少し手間に感じます。またフックの下の方のネットがきちんと閉まっていなかったらそれを直さないといけません。
30年ほど前に勤めていた職場の宿舎には何もなかったので、地面にそのまま置いていました。
でもカラスなどがゴミを散らかすのを防ぐためにゴミステーションが作られました。職場に勤めていた大工さんに作ってもらったようで、コンパネ製の立派な物でした。
しかしその蓋が重かったのでです。幅が180センチ、高さが90センチ位だったと思います。せめて蓋だけでも穴をたくさん開けていればもっと軽く開けられたのに雨のことを考えたのでしょうか。
もうひとつ、出すときは問題ないのですが深いので収集が大変だっただろうと思います。
一時期実家で生活をしていたことがあります。そのときは100メートルほど離れた場所に直接置いていました。実家を出た後で近くにゴミステーションが設置されました。
すぐ近くになったので、時々帰ったときにゴミステーションだなと思ってみていました。
でも、いつも収集日に帰るわけでもないし、収集時間が過ぎています。そのため生もの以外は出さずにためていました。
先日朝早く出て帰った日が収集日だったので、ためておいたゴミをおばさんが出しました。
そして発見したのです。おばさんに言われておじさんも試してみると蓋を開けるのがとても軽いのです。
それだけではありません。蓋を開けると前が下がるのです。それで出すときもゴミを大きく持ち上げなくて良いので高齢者には優しいと思います。、何よりも収集が楽だと思いました。


蓋を持ち上げると固定されます。ゴミを出したら取っ手を引いて閉めるだけです。今のところのようにフックをかけたり外したりの手間はありません。
南京錠をかけられるようになっているので収集日以外のゴミ出しを防ぐこともできます。
でもこの地域はきちんとルールを守っているのでその必要はありません。
ゴミステーションもきれいに保たれています。
たかがゴミステーションと言われるかもしれませんが、便利さだけでなく住民の気持ちも美しく護ってくれていると感じました。
おじさんからの動画のお知らせ
マウスの両方のボタンを押すと、サイズ変更のハンドルにカーソルが移動します。
枠を3×3に9等分して、ハンドルの含まれる部分で両ボタンを押します。
中央だと回転操作になります。
「おじさんとおばさんのつぶやき」
「つぶやき」の目次
「家を建てるなら」の目次