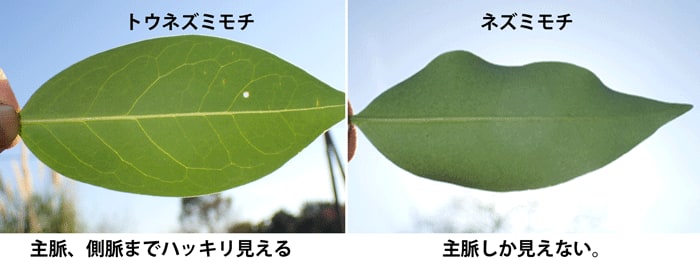園のホームページ植物豆知識の所に、「古事記に出ているガガイモ」を載せてありますので、莢実が自然に開くのを撮りたいと考えましたが、自然ではなかなか開かず諦めかけていました。

一月近くもなかなか開かず、このままの状態でぶら下がっていました。
昨日、莢実がぶら下がっている場所に行ってみたら、数個ある莢実の一つが裂けて種を飛ばし始めたところでした。竹林の高いところにぶら下がっているし、風が吹くと竹は揺れて、なかなか上手く撮影出ませんでした。引き寄せようとしても,とても手は届かず,思案顔で立ち尽くしていたら、散歩中の男性が、竹を倒して下さったので、間近で撮る事が出来ました。謝謝です。

風の中に立ち、暫く、様子を観察。中の種子は綿毛にくっついて、飛んでいってしまいました。 そして残ったのは、莢実の外側だけになりました。

これがアメノカガミ船になるのですね。長さ10cm、深さ2.5cmの小さな小さな舟。この舟に乗ったスクナビコの丈は如何ほどだったのでしょう。ガガイモの莢を船に見立て、小さな神様を乗せて登場させるとは!! 『日本書紀』には、“粟の茎によじのぼり、それにはじかれて常世国へ渡っていった"とあるので、相当小さかったのでしょう。おそらく当時は至る所にガガイモは有ったのだろうと思えるのですが、それにしても古代の人の想像力には感服します。
大穴牟遅神(オオムナデ=大国主命)に協力して国造りされた小さな神、少彦名命(スクナビコ)は体が小さくて敏捷、忍耐力、総じて知恵の神と称されている。神仙術(方術士)の元祖でもあり、禁厭(まじない)の得意技を持つとされています。病気の治療及び薬の知識に抜きん出ていた。国土建設、疾病平癒、産業振興、民心の安定を司る。土木業、建設業、医業、薬業、醸造業、殖産業、農業、漁業、商業の守護神であるようです。(ウキィペディア参照)
ハッキリとそう書かれているのではなく、文中から推して、大国主の命は五穀豊穣・商売 繁盛・縁結びなどの神様、少彦名命は医業・薬・温泉・酒造の神様と云う評価をされて今日へ至っているようです。
ガガイモから話がとんだ方へいってしまいましたが、こんな事を想像すると植物に興味湧かないかしら?