
大水の時、いつ水が引き始めるか?鵜匠や船頭に教えられた。長良川 鵜飼屋に暮らして教わった川のみかた。
鵜飼が行われる長良川。岐阜城の反対側となる右岸に鵜匠が住む鵜飼屋がある。鵜飼屋と川の間には堤防が築かれ、車や人が川に通えるように門が開かれ、金属製のゲートが付けられている。普段は開いているその門、陸閘(りっこう)のゲートは川の水位が高くなると閉鎖して水を防ぐ仕組みになっていた。
私達は平成4年、鵜飼屋の地先、片端に陸閘のある川に面したマンションに住み始めた。
鵜飼屋での最初の夏、上流で大雨が降った。水の高さが気になって川を見ていると鵜匠や船頭さん十人ほどが川沿いの道に集まっている。なにを見ているのかと様子を伺っていると、ある一瞬、全員が各自の家に帰って行った。同時に水はこれ以上高くはならないという判断をしたらしい。
翌年、水位が高くなる時を待ち構えて、鵜飼屋の人たちと並んで水面を見ていた。どうやら、流れの一番早い部分を見ているようだ。つぶやきが聞こえる「まだやな」やがて「よっしゃ」と誰ともなく声がして、そこにいた全員がそろって帰っていった。
私には何が起こったのかが全くわからなかった。親しくなっていた鵜匠の山下純司さんに聞いてみたが「波の形や」と、返って来た言葉がまた謎であった。
三年目の梅雨、その年は雨が多く川が増水する機会も多かった。水面に近い高さから見ていると、流れの中心には、先の部分が鋭角になった波が集まっているのが見えてきた。その波は水位が上昇している間は中央、そして岸よりへと位置を変えては白く砕けて流れている。波頭がやがて同じ所にとどまるように見えた瞬間、波頭から角がとれて、柔らかな丸みを帯びたような状態になった。
「あっ」と思った時、傍らの山下さんが言った。「そうや、これ以上水は増えん」
波の形で増水のピークを知る。鵜飼屋で教わった川の知識だった。
(魚類生態写真家)












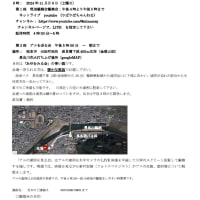













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます