


潮のポンプ
川の下流域には天然の「ポンプ」がある。一日に二回、大量の水を海に送り出している。このポンプの正体は、潮の満ち引きだ。潮が満ちるとき、海の水は川を遡る。潮が引くときに、留まっていた海水は、川の流れとともにいっきに海へと流れ下る。
潮によって水位が上下し、流速が変化する「潮のポンプ」のあるところは、潮を感じる場所ということから「感潮域」と呼ばれている。長良川の場合、感潮域は新幹線長良川橋の上流、河口から三十八㌔付近まで。感潮域の上流部は淡水だが、下流には海水が混ざった、汽水域ができる。
アユの仔魚は、腹に栄養分を持って生まれる。その栄養だけで十日ほどは生きていけるのだが、五日目くらいから餌を食べないと飢えてしまう。餌となるのは小さなエビカニの仲間だ。淡水と海水が混ざった汽水域にいる。
長良川でアユが産卵する場所は、感潮域より少し上流の瀬から、河口より六十二㌔付近までの約二十三㌔に及ぶ。【仔魚】は六㍉ほどと小さく、泳ぐ力は弱い。その小さなアユが、遠い下流の餌のある汽水域までたどりつけるのは潮のポンプのおかげだ。
アユが卵からかえるのは夜だ。昼間は川底で休み、浮いて下るのも暗くなってからだ。【仔魚】は他の魚にとっては良い餌だから、昼間に下れば食べられてしまう。秋から冬、昼間よりも夜の潮が大きく引く。仔魚は、夜、「潮のポンプ」の流れに乗り、下ることができた。
河口堰(ぜき)は潮止め堰とも呼ばれる。止めるのは潮の満ち引きであり、塩分だ。河口堰建設により潮のポンプはなくなり、汽水域も河口堰の下流へ十㌔あまり後退し、仔魚にとって、えさ場はさらに遠くなった。
汽水域に達する日数は、建設前に四日未満、それが建設後には十二日以上も掛かるようになった。ふ化後五日から餌をとるという仔魚は、生きていけたのか。(魚類生態写真家)
アユの仔魚は、腹に栄養分を持って生まれる。その栄養だけで十日ほどは生きていけるのだが、五日目くらいから餌を食べないと飢えてしまう。餌となるのは小さなエビカニの仲間だ。淡水と海水が混ざった汽水域にいる。
長良川でアユが産卵する場所は、感潮域より少し上流の瀬から、河口より六十二㌔付近までの約二十三㌔に及ぶ。【仔魚】は六㍉ほどと小さく、泳ぐ力は弱い。その小さなアユが、遠い下流の餌のある汽水域までたどりつけるのは潮のポンプのおかげだ。
アユが卵からかえるのは夜だ。昼間は川底で休み、浮いて下るのも暗くなってからだ。【仔魚】は他の魚にとっては良い餌だから、昼間に下れば食べられてしまう。秋から冬、昼間よりも夜の潮が大きく引く。仔魚は、夜、「潮のポンプ」の流れに乗り、下ることができた。
河口堰(ぜき)は潮止め堰とも呼ばれる。止めるのは潮の満ち引きであり、塩分だ。河口堰建設により潮のポンプはなくなり、汽水域も河口堰の下流へ十㌔あまり後退し、仔魚にとって、えさ場はさらに遠くなった。
汽水域に達する日数は、建設前に四日未満、それが建設後には十二日以上も掛かるようになった。ふ化後五日から餌をとるという仔魚は、生きていけたのか。(魚類生態写真家)











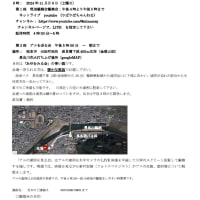













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます