養殖個体群に野生!のオスヤマメの精子をかけて回帰率の高いサツキマスの種苗をつくる。ボクのコメントも載っているけれど、長良川河口堰の影響について時間をかけて説明しているのだがその部分は書かれてはいない。新聞社にその筋からのご説明等が来るので書きにくいということがあるのだろうね。
テキスト版
回帰率高いサツキマス 天然と養殖掛け合わせ新種苗も
|
木曽川で捕獲された半天然のサツキマス(岐阜県河川環境研究所下呂支所提供) |
 |
◆岐阜県で放流事業
渓流魚アマゴが海に下り、再び川に戻ってくるとサツキマスと呼ばれる。美しい川の象徴とされるが、生息環境の悪化で激減している。屈指の漁場・長 良川が流れる岐阜県で、サツキマスの名付け親にもなった県河川環境研究所(各務原市)が、従来の養殖魚よりも川に帰ってくる率の高い魚を開発した。天然の 雄と養殖の雌を掛け合わせた“半天然”魚。来秋に県内の漁協が本格放流する予定で、期待を寄せる。
岐阜県は長良川のほか木曽川、揖斐川など有数の漁場がある。資源保護のため、研究所の前身の水産試験場が三十年以上前、海に下りやすいアマゴを開発し、漁協が毎秋、放流を続けている。
だが、一九九三年に三十二トンあった漁獲高は二〇一一年には二・六トンと一割以下に。長良川漁協(岐阜市)の山中茂副組合長(81)は「昔は一年で三百匹捕れたが、今は三十匹ほど。昔ほど海から上ってこなくなった」と嘆く。
研究所は一〇年から、過去に養殖魚を放流していない県内の川の上流部で採取した天然アマゴの雄と従来の養殖魚の雌を掛け合わせた魚を新たにつくっ た。養殖魚同士を掛け合わせた魚と別々の標識を付け、今秋までそれぞれ毎年千~二千五百匹を木曽川に放流。サツキマスに育って川に戻ってくる数を調べてい る。
その結果、今秋までに捕獲された半天然魚は二十六~三十八匹(1・3~1・5%)で、養殖魚の二~十二匹(0・1~0・5%)より二~十五倍多く捕獲された。
 |
担当の研究所下呂支所(下呂市)の大原健一主任研究員(40)は、養殖魚よりも半天然魚の方が自然の中で多く生き残り、川を上ると推測。「養殖魚は何十年と代を重ね、自然になじめなくなっているのでは。半天然の方が自然で生き残る力が強いのだろう」と話す。
研究所は今秋、半天然魚の受精卵五万七千粒を放流用種苗として生産し、養殖業者に販売。育ったアマゴを来秋、長良川や木曽川などで三漁協が放流する予定だ。
◆河川工事で産卵場減
放流用の新たな魚の開発に、長年サツキマスを研究している岐阜市の新村安雄さん(59)は「本来の野生の姿を取り戻す取り組みで、評価できる」としながらも「あくまで対症療法。人が介在しない、自然本来の機能を取り戻す取り組みも必要」と指摘する。
新村さんによると、サツキマスが減った理由の一つが、砂防事業や川の工事による産卵場所の減少だ。サツキマスは上流のふちで産卵。その際、卵を埋め戻す砂利が必要となる。
だが、砂防えん堤で魚が上れず、砂利がせき止められて産卵場所が失われているという。新村さんは「大きな岩や土木は止めるが、細かな砂利などは通すスリットダムを用いたり、魚道を改善したりするなどの工夫はできる」と話す。
地域の固有種の保存を訴える岐阜大の向井貴彦准教授(魚類生態学)は貴重な天然のアマゴを毎年、養殖のために捕獲する矛盾を指摘し、環境への影響を懸念。「各地に放流されると、遺伝的なかく乱につながる恐れもある」と話す。
<サツキマス>渓流魚のアマゴの一部が秋に体が銀色になって海に下り、体長30~50センチほどに成長する。翌春5月ごろ、生まれた川をさかのぼり、秋に産卵する。研究所前身の岐阜県水産試験場が命名した。ヤマメが海に下ったサクラマスとは別種。
(山本真嗣)











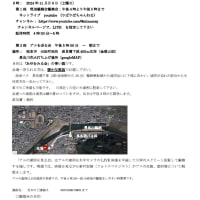













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます