環境研がメコン川で国際共同研究 オオナマズなど淡水魚を守れ(共同通信) - goo ニュース
たまたまだが、昨晩この研究チームのリーダーにメールを出した。福島さんとは以前から面識があって、ボク達が来月初めに行くメコン河調査で、サンプリング等で協力できないかと思ったからだ。
そのタイミングでこのニュース。
メコン河に雨季が来て、魚類の移動が始まるという共通するタイミングではあるのだけれど、こういった偶然をボクはこう考えて喜ぶことにしている。
川のかみさまのお導き!
☆テキスト版
メコン川の淡水魚を守れ 国際研究でダムの影響解明へ
メコンオオナマズなど多くの淡水魚がすみ、漁場としても重要なアジアの大河、メコン川の淡水魚の生態を総合的に調べ、ダム建設が生物多様性に与える影響の解明を目指す国際共同研究プロジェクトを、日本の国立環境研究所が中心になって始めることになった。関係者が24日、明らかにした。
メコン川は中国に源を発し、ミャンマー、タイ、ラオス、カンボジアを経てベトナムのデルタ地帯で海に注ぐ全長4千キロ超の大河。支流を含め大きなものだけでも30を超えるダム建設計画があり、川の生物多様性や漁業に依存する住民の暮らしに悪影響を与えることへの懸念が高まっている。
環境研のグループは、ダム建設が淡水魚の分布や生物多様性に与える影響の研究を北海道各地で進めており、この成果をメコン川に応用することを目指す。
同研究所の福島路生主任研究員は「ダム建設によって失われる漁獲量や漁業収入の額なども推定し、生物多様性や水産資源の保全に貢献するメコン川開発のシナリオを提案したい」としている。
共同研究では、川にすむ淡水魚の種類や分布、生息環境の特徴などを現地調査し、地図上にさまざまな情報を表示できる地理情報システム(GIS)を使ってデータベース化。カンボジアやタイ、ラオスなどで主な回遊魚約20種を採取し「耳石」と呼ばれる頭部の骨に蓄積された化学物質を手掛かりに、回遊ルートを解明する。
これらのデータを基に、ダム建設で回遊ルートが断たれたり、水量が減ったりすることが魚の生存に与える影響をコンピューターシミュレーションで推定。川の生態系に与える影響を最小限にするようなダムの建設地などを示す。
2009/06/24 09:16 【共同通信】
たまたまだが、昨晩この研究チームのリーダーにメールを出した。福島さんとは以前から面識があって、ボク達が来月初めに行くメコン河調査で、サンプリング等で協力できないかと思ったからだ。
そのタイミングでこのニュース。
メコン河に雨季が来て、魚類の移動が始まるという共通するタイミングではあるのだけれど、こういった偶然をボクはこう考えて喜ぶことにしている。
川のかみさまのお導き!
☆テキスト版
メコン川の淡水魚を守れ 国際研究でダムの影響解明へ
メコンオオナマズなど多くの淡水魚がすみ、漁場としても重要なアジアの大河、メコン川の淡水魚の生態を総合的に調べ、ダム建設が生物多様性に与える影響の解明を目指す国際共同研究プロジェクトを、日本の国立環境研究所が中心になって始めることになった。関係者が24日、明らかにした。
メコン川は中国に源を発し、ミャンマー、タイ、ラオス、カンボジアを経てベトナムのデルタ地帯で海に注ぐ全長4千キロ超の大河。支流を含め大きなものだけでも30を超えるダム建設計画があり、川の生物多様性や漁業に依存する住民の暮らしに悪影響を与えることへの懸念が高まっている。
環境研のグループは、ダム建設が淡水魚の分布や生物多様性に与える影響の研究を北海道各地で進めており、この成果をメコン川に応用することを目指す。
同研究所の福島路生主任研究員は「ダム建設によって失われる漁獲量や漁業収入の額なども推定し、生物多様性や水産資源の保全に貢献するメコン川開発のシナリオを提案したい」としている。
共同研究では、川にすむ淡水魚の種類や分布、生息環境の特徴などを現地調査し、地図上にさまざまな情報を表示できる地理情報システム(GIS)を使ってデータベース化。カンボジアやタイ、ラオスなどで主な回遊魚約20種を採取し「耳石」と呼ばれる頭部の骨に蓄積された化学物質を手掛かりに、回遊ルートを解明する。
これらのデータを基に、ダム建設で回遊ルートが断たれたり、水量が減ったりすることが魚の生存に与える影響をコンピューターシミュレーションで推定。川の生態系に与える影響を最小限にするようなダムの建設地などを示す。
2009/06/24 09:16 【共同通信】











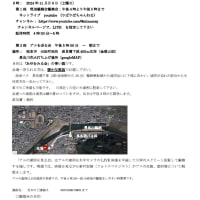













適切な調査手法や評価手法すらまだなのに
国環研は海外なのか....
耳石の分析に協力する事にしました。ナマズの耳石というのは見たことがない(見ようとしたことがない)けど、サツキマスよりも大きいのかな?
ダムを有効利用する為に必要な評価手法がない。と言う意味なのではいかね。
ともかく、メコン本流ダムでは多くの人々の生活が脅かされています。川からのタンパク質がなくなったら、悲惨な結果が起きるかもしれない。
幸いなことに(皮肉だからね)長良川河口堰建設で飢え死にした方はいなかったみたいだから…。
大きいとおもいます。一般に、
海産の魚の場合は、底性魚が
耳石が大きく、遊泳性魚は小さい
傾向があります。マグロ類は
あんな大きな体なのに、微小です。、
もし、この傾向からすると、大きい
ようにおもいます。また、コイ目
は耳石大きいようにおもいます。
一度、フナかなまずで摘出して
みれば。大きさにもよりますが、わたしはよく切れる包丁で、それを採取
してました。
そこで冷凍していたサツキマスの頭から耳石を取り出した。
いつか分析したいと思っていたのだけれど、予算がなくて手がつかなかったのよね。
河口堰ができる前のものという年代もののあったのだけど、何とか耳石を取り出すことができた。
サツキマスは耳石が薄い方だと思うから、コイ目は大丈夫だろうとおもうよ。ナマズは?どうだろうね。
もう時間もないので、現地に行ってから分析対象になっていない近縁の種を使って練習してみます。
ちなみに耳石の分析は「レーザーアブレーション誘導結合プラズマ質量分析計(LA-ICP-MS)」というものでするそうです。
耳石の採取だけに行くワケではないのですが、魚の頭をかち割る事になりそうです。
ついでに、咽頭歯集めてくるかなあ。中島さんへのおみやげに!
あの形はけっこう そそられます。
ニイムラさん,おきをつけて.できれば,これが,ナマズの耳石だという,アップを期待しております.耳石摘出,くれぐれも,切り傷に気を付けて,..あたしが不細工なだけかもしれないが.