
長良川の川漁師 大橋兄弟は秋にはモクズガニをカニカゴで獲っている。その場所は長良川の下流域で長良川河口堰で流れが無くなった場所だった。その場所でとうやってカニの下る道を探しているのか、ボクは最新の機材を使ってその謎を探ることにしたのだ。

その茫洋とも見える川のどこにカニの通り道があるのか。
長良川の川漁師、大橋さん兄弟は秋になるとカニカゴを仕掛けて海に下るモクズガニを捕らえる。漁場の羽島市地先は川の下流域にある。流れはもとより緩やかなのだが、三二キロ下流に河口堰ができてからずいぶんと様子が変わった。堰が完成する以前の長良川下流域は引き潮ともなると河口から15キロの木曾三川公園まで、砂地が現れて平瀬となって川は流れた。大橋さんの漁場付近は長良川のアユの一番下流の産卵場所だったが、いまでは満潮の高さに水位は上昇したまま、アユは卵を産まず、川の流れをみることはない。
私は一昨年秋、カニの通り道を探ることにした。
最新の魚群探知機には便利な機能がある。測った水深と場所のデータをパソコンにとり込めば水中の地形を地図の上に表すことができた。魚探を積んだゴムボートで漁場をくまなく走り回ること二日、漁場の地形図ができあがった。
そこには、水面からは見えない川の流れ、河道が示されていた。カニカゴは見えない河道にそって配置されているのだった。
魚探を使うこともなく、大橋修さんはどうやって河道を探しているのか。
「最近の器械はなんでもわかってまうなぁ。」
修さんは少し寂しそうな表情でそう言った。
「朝な夕なの水面のさざ波は流れで違うでね。竿で探れば深さと固さがわかる」
大橋さんは水面下に隠れている河道の場所を、目で見たわずかな水面の変化で読み、竿で河床を探り見つけていた。そうした工夫を重ねて、長良川河口堰で変わってしまった川での漁を続けきたのだった。
12月15日国連食料農業機関は「清流長良川の鮎」を世界農業遺産として認定した。大橋さんの漁場のある羽島市から下流の長良川はその範囲に含まれてはいない。(魚類生態写真家)











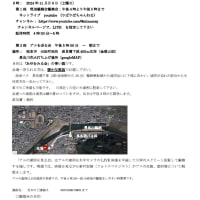















ありがとう。