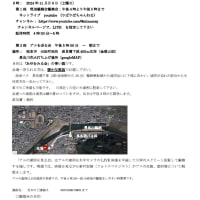自治体が堤防を守るために植えたヤナギ。そのヤナギが住民に知らされることも無く切られてしまった。今年は河川法が改正されて20年となる。河川法は長良川河口堰建設を契機として改正され、治水利水一辺倒だった河川管理の目的に環境が加えられた。そして、保全改革の立案には住民参加も制度として盛り込まれた、はずだった。形骸化する改正河川法を憂いて書きました。
ヤナギと河川法
みなで土地を出し合い、堤防の建設を要望した。未遂に終わったそうだが、昭和天皇の鵜飼ご観覧の際、堤防建設を直訴しようとする動きもあったという。岐阜市中川原は、長良川の右岸、鵜飼大橋の上流にある。
ようやく、堤防ができ、高水敷の水際にはヤナギが茂った。ところが、今年の3月、国土交通省はこのヤナギを切り倒してしまった。
「あのヤナギは、自治会が中心になって植えたものです。畑で苗木を作り、三百数十本を水際に植え、守ってきたのですが、我々の知らない間に伐採がはじまりました」
中川原に住む酒井寛(72)さんは、驚いて国土交通省の長良川第一出張所に出向いた。出張所長の説明は、流れの妨げとなるから樹木を除去した。漁協には連絡したが、地権者ではない自治会には連絡しなかった。という内容だった。
残念だったのは国土交通省の担当者間で、今までの経緯が伝えられてこなかったことだ、と酒井さん。
1999年、大水で長良川は流路を変え、中川原の堤防前の護岸がえぐられた。その時、建設省時代に植えられたヤナギも蛇籠とともに流失した。人々は、地区を守ろうと、国土交通省の復旧工事に合わせて、2002年にヤナギを植えた。
ヤナギは元の場所で大きく育った。2014年8月、長良川は増水し、下流では避難勧告がでるほどの水量だったが、激流はヤナギで阻まれ、中川原の堤防際の流れは静かだったという。
1997年、河川法が改正された。治水と利水という川の役割に、環境が加えられた。第一条に「河川環境の整備と保全」が明記され、整備計画を立てるには、住民の意見も反映するなどの手続きも定められた。
法改正は、長良川河口堰問題など、各地で起こった自然保護運動が一つのきっかけとなったとも言われる。改正から二十年を経て、川と人との係わりが、改めて問われているのだと思った。
(魚類生態写真家)
参考資料
この記事を書くにあたって、以下の広報を参考に取材いたしました。ご提供下さった。岐阜市中川原の酒井寛さんに感謝申し上げます。