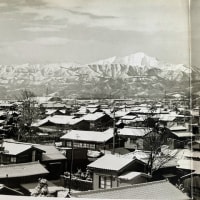●査定チーム入りで交付税担当(その2)
地方交付税制度は、その自治体の人口と面積を基本に、道路面積や河川延長、学校や児童、福祉施設や生活保護者などなど、行政の仕事が求められる項目ごとに単価を設定し、その自治体における各々の数量や規模を掛けて基準となる「財政需要額」を積み上げた上で、別途積み上げた税収など自前の財政収入との差引きを出し、収入で補いきれない需要額を、所得税や法人税など国税として徴収された中の税財源の一部の配分により補填することで、国内の地方公共団体があまねく必要な行政需要に応えていけるように設計されたものだ。自治体間で税収に格差の大きい中で自然体にしておけば必要な行政サービスに格差が生じ、貧しい地方は寂れてしまう。均霑的な行政の確保をつうじて国全体を維持するための重要な制度だ。
一口に基準となる行政需要といっても、公共土木、環境、福祉、産業、教育など多岐に亘るので、項目毎の単価やそれを掛け合わせる単位、そして補正する係数、それらによる計算式は、細かく細分化されて緻密であり、それらをまとめられた担当者必携の手引書は「電話帳」と揶揄されるほどの分厚いものであった。私は引き継ぎを受けてから解説書や関連資料などを十分に読み込む暇もなく、4月の初旬から膨大な作業に追われることとなった。
地方交付税は、国税の一部を減資とて国の調整を経て自治体が配分を受けるという構造から、国を親に見立てた「仕送り」のように語られることがあるが、一方で、便宜的にそのような体裁をとっているが、そもそもは地方固有の財源であると言う哲学を持っている。哲学というのは不適当かも知れない。これはかつて国会質疑に応えて首相答弁でも確認されている事柄なのだから。
なので、交付税の配分にあたっては一義的に国の指揮の下に入るものの、地方は国からの配分をただ待ち受ける姿勢ではなく、自らが必要とする交付税額を算定して国に求めるという能動的な姿勢が重要視される伝統がある。そこで、自治体の交付税担当者には、自身の自治体の財政需要を自らつぶさに積み上げ、そこから差し引く税収などの財源もきっちりと精査するという膨大な事務作業が必要となるのだ。
交付税担当は年度初めから仕事の立ち上がりが早い、例年7月には当年度の交付税額が決定する日程とされているので、4月早々に全国の担当者が霞ヶ関の会議に集められ、総務省の担当から今年の交付税算定のための調査票などが配布され変更点などが説明される。基本的な行政需要の調査において年次的に変更する必要があるのかとも思うが、行政改革を背景とする交付税措置対象の厳格化など見直しが進められていて、調査票の変更なども少なくないのだ。
2センチ近い厚さに及ぶ今年度算定用の調査票の束を国から受け取ったら、調査対象となる多数の関係課ごとに調査票を振り分けて作成の依頼を発出する作業を如何に素早くできるかが最初の勝負となる。調査票の国への提出期限はモノによりまちまちで、作業内容の多い割に早い提出期限のものもある。関係課の作業時間も確保しなければならない。私が交付税担当に着任した年は曜日の関係で例年に無く調査期間がタイトであった。国から調査票を受領して翌日一日掛けて照会発出作業をすれば良かった例年と異なり、4月7日の月曜日朝一からの霞ヶ関における会議の翌8日午前中に発出しないと間に合わなさそうだ。
運の悪いことに4月5日の土日に法事があって実家に帰省宿泊することもあり、私は実家にて御斎を終えたほろ酔いの土曜の深夜に関係課への調査依頼のための資料の整理などをして準備を進めた。そして、7日は朝一番で上京し、夕方の新幹線の車内で国から配布されたばかりの調査票をめくりながら、関係課へ照会を発出するにあたっての必要事項のメモ入れなどを1時間半の乗車中続けた。ちょうど空席が多い車内だったので、書類を広げて作業することができて良かった。後にも先にも新幹線の車内であれほど集中して仕事作業をしたことはない。"名にし負う"査定チーム一員となったからには担当作業の遅延などで上司や周りに迷惑をかけたくない一心だったのだ。
一口に基準となる行政需要といっても、公共土木、環境、福祉、産業、教育など多岐に亘るので、項目毎の単価やそれを掛け合わせる単位、そして補正する係数、それらによる計算式は、細かく細分化されて緻密であり、それらをまとめられた担当者必携の手引書は「電話帳」と揶揄されるほどの分厚いものであった。私は引き継ぎを受けてから解説書や関連資料などを十分に読み込む暇もなく、4月の初旬から膨大な作業に追われることとなった。
地方交付税は、国税の一部を減資とて国の調整を経て自治体が配分を受けるという構造から、国を親に見立てた「仕送り」のように語られることがあるが、一方で、便宜的にそのような体裁をとっているが、そもそもは地方固有の財源であると言う哲学を持っている。哲学というのは不適当かも知れない。これはかつて国会質疑に応えて首相答弁でも確認されている事柄なのだから。
なので、交付税の配分にあたっては一義的に国の指揮の下に入るものの、地方は国からの配分をただ待ち受ける姿勢ではなく、自らが必要とする交付税額を算定して国に求めるという能動的な姿勢が重要視される伝統がある。そこで、自治体の交付税担当者には、自身の自治体の財政需要を自らつぶさに積み上げ、そこから差し引く税収などの財源もきっちりと精査するという膨大な事務作業が必要となるのだ。
交付税担当は年度初めから仕事の立ち上がりが早い、例年7月には当年度の交付税額が決定する日程とされているので、4月早々に全国の担当者が霞ヶ関の会議に集められ、総務省の担当から今年の交付税算定のための調査票などが配布され変更点などが説明される。基本的な行政需要の調査において年次的に変更する必要があるのかとも思うが、行政改革を背景とする交付税措置対象の厳格化など見直しが進められていて、調査票の変更なども少なくないのだ。
2センチ近い厚さに及ぶ今年度算定用の調査票の束を国から受け取ったら、調査対象となる多数の関係課ごとに調査票を振り分けて作成の依頼を発出する作業を如何に素早くできるかが最初の勝負となる。調査票の国への提出期限はモノによりまちまちで、作業内容の多い割に早い提出期限のものもある。関係課の作業時間も確保しなければならない。私が交付税担当に着任した年は曜日の関係で例年に無く調査期間がタイトであった。国から調査票を受領して翌日一日掛けて照会発出作業をすれば良かった例年と異なり、4月7日の月曜日朝一からの霞ヶ関における会議の翌8日午前中に発出しないと間に合わなさそうだ。
運の悪いことに4月5日の土日に法事があって実家に帰省宿泊することもあり、私は実家にて御斎を終えたほろ酔いの土曜の深夜に関係課への調査依頼のための資料の整理などをして準備を進めた。そして、7日は朝一番で上京し、夕方の新幹線の車内で国から配布されたばかりの調査票をめくりながら、関係課へ照会を発出するにあたっての必要事項のメモ入れなどを1時間半の乗車中続けた。ちょうど空席が多い車内だったので、書類を広げて作業することができて良かった。後にも先にも新幹線の車内であれほど集中して仕事作業をしたことはない。"名にし負う"査定チーム一員となったからには担当作業の遅延などで上司や周りに迷惑をかけたくない一心だったのだ。
(「財政課14「査定チーム入りで交付税担当(その2)」編」終わり。「財政課15「査定チーム入りで交付税担当(その3)」」に続きます。)
☆ツイッターで平日ほぼ毎日の昼休みにつぶやき続けてます。
https://twitter.com/rinosahibea
☆ツイッターで平日ほぼ毎日の昼休みにつぶやき続けてます。
https://twitter.com/rinosahibea