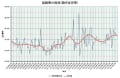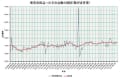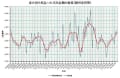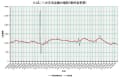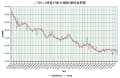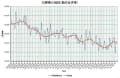このブログで報告しているような需給分析を行うため、その基礎となる数値のデーベースをマイクロソフトの「Excel」と「Access」で自作していますが、当初の作成開始から長時間が経過したため大幅なメンテナンスが必要でした。
その作業もほぼ終了しましたので、ブログを再開いたします。
なお、このブログで定期的に勤労者世帯の家計収支(バランス)について報告を行っているのは、2012年12月26日に発足した第2次安倍政権(平成29年10月22日の総選挙を経て、現在は11月1日より第4次安倍内閣)が打ち出した経済政策(いわゆる三本の矢など)による雇用拡大や所得の向上などが、どのように家計に浸透してくるかを追跡することを目的として、四半期に1度の割合で家計調査データを分析しその推移を見ることとしています。
直近では、家計調査の2017年12月分速報が、2018年1月30日に公表されました。
下表は、家計調査報告―平成29年(2017年)12月分速報-に掲載された、勤労者世帯の収支内訳です。
収支の推移を見て行くため、上記項目の2009年1月から2017年12月までの各月数値を米国センサス局の季節調整法X-13Arima-Seatsを用いて分析し、得られた「季節調整済」「傾向値」をグラフ化し、ビジュアル的に推移を掌握できるよう工夫してみました。
◇実収入の推移(勤労者世帯)について
分析期間(2009年1月から2017年12月)における実収入の推移は、2009年1月の528,000円から2011年4月の503,900円までの間は、リーマンショックの影響で減少傾向で推移した後、5月の505,400円から2017年12月540,900円までの間は、期間中若干の増減は有るものの、増加傾向での推移となっています。

(グラフをクリックすると拡大したグラフを見ることができます。以下のグラフについても同じです。)
家計調査報告では、実収入は「7か月連続の実質増加」と説明されていますが、分析結果では傾向値の前年同月比では2016年8月から2017年3月までの間連続8か月の増加した後4月、5月と減少し、6月から12月までの間は7か月連続で再び増加しています。
前月比では2016年10月から2017年1月までの間連続4か月増加し、2月、3月と減少した後4月から11月の間は8か月連続で増加し、12月は減少となっています。
○世帯主収入の推移(勤労者世帯)について
分析期間における世帯主収入の推移は、2009年1月の424,900円から2012年8月の407,500円までは期間中若干の増減が含まれるものの減少傾向で推移し、9月の407,600円から2017年12月の419,100円までは若干の増減が含まれるものの増加傾向での推移となっています。

家計調査報告では、世帯主収入は「4か月ぶりの実質減少」と説明されていますが、分析結果では傾向値の前年同月比では2016年6月から2017年3月までの間連続19か月の増加となっています。
前月比では2016年10月から2017年9月までの間連続12か月の増加し、10月から12月の間は3か月連続で減少となっています。
・(世帯主の)定期収入の推移(勤労者世帯)について
分析期間における世帯主の定期収入の推移は、2009年1月の356,400円から2011年2月の343,600円までの間は、リーマンショックの影響から減少傾向となっています。
2011年3月の343,900円から2017年12月の349,000円までの間は、平均的には347,700円±2,400円(0.7%)と若干の増減を繰り返しながら、横ばい状態での推移となっています。(下図のグラフでは、y-軸のスケールの関係で振幅幅が大きく表れています。)

家計調査報告では、世帯主の定期収入は「4か月ぶりの実質減少」と説明されていますが、分析結果では傾向値の前年同月比では2016年10月から2017年3月までの間連続15か月の増加となっています。
前月比では2016年10月から2017年9月までの間、2017年4月に減少となったもののはぼ連続12か月増加し、10月から12月の間は3か月連続で減少となっています。
・(世帯主の)臨時収入・賞与の推移(勤労者世帯)について
分析期間における世帯主の臨時収入・賞与の推移は、2009年1月の69,700円から2012年6月の57,800円の間は減少傾向で推移した後、7月の58,000円から2017年12月の78,100円までの間は増加傾向となっています。

分析結果では、傾向値の前年同月比では2016年11月から2017年3月までの間連続5か月減少し、その後は4月から12月までの間連続9か月の増加となっています。
前月比では2016年4月から11月までの間連続8か月減少し、2016年12月から2017年12月の間連続13か月増加となっています。
○(世帯主の)配偶者の収入の推移(勤労者世帯)について
分析期間における世帯主の配偶者の収入の推移は、2009年1月の57,800円から2011年4月の51,700円までの間は減少傾向で推移した後、5月の51,800円から2017年12月の70,500円までの間は、期間中若干の増減が含まれるものの増加傾向での推移となっています。

家計調査報告では、世帯主の配偶者の収入は「3か月連続の実質増加」と説明されていますが、分析結果では傾向値の前年同月比では2016年12月から2017年8月までの間連続9か月し減少、9月から12月の間は連続4か月増加となっています。
前月比では2016年5月から2017年4月までの間連続12か月減少し、5月から12月の間は連続8か月減少となっています。
○他の世帯員収入の推移(勤労者世帯)について
分析期間における他の世帯員収入の推移は、2009年1月の10,500円から2014年6月の7,200円の間は増減が含まれるものの減少傾向での推移、7月の7,300円から2017年12月の9,000円までの間は若干の増減が含まれるものの増加傾向での推移となっています。

家計調査報告では、他の世帯員収入は「6か月ぶりの実質減少」と説明されていますが、分析結果では傾向値の前年同月比では2016年4月から2017年11月までの間、2017年4月の減少が含まれるもののほぼ連続20か月増加し、12月は減少となっています。
前月比では2017年4月から8月までの間連続5か月増加し、9月から12月の間は連続4か月減少となっています。
◇非消費支出の推移(勤労者世帯)について
分析期間における非消費支出の推移は、2009年1月の92,400円から2011年3月の87,400円までの間はリーマンショックの影響で収入が減少したことに伴い減少傾向で推移し、4月の87,600円から2017年12月の100,700円までの間は増加傾向での推移となっています。
非消費支出が100,000円(年ベースで1,200,000円)を超えたのは2017年11月のことです。
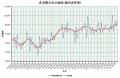
家計調査報告では、非消費支出は「4か月連続の実質増加」と説明されていますが、分析結果では傾向値の前年同月比では2015年11月から2016年8月までの間連続10か月減少し、9月から2017年12月までの間は連続16か月増加となっています。
前月比では2015年5月から2016年1月までの間連続9か月減少し、2月から2017年12月までの間は23か月連続で増加となっています。
◇可処分所得の推移(勤労者世帯)について
分析期間における可処分租特の推移は、2009年1月の432,200円から20147年12月の438,600円の間、2017年6月以降増加していますが平均的には426,700円±4,600円(1.1%)とほぼ横ばい状態での推移となっています。

家計調査報告では、可処分所得は「7か月連続の実質増加」と説明されていますが、分析結果では傾向値の前年同月比では2015年10月から2016年5月までの間連続8か月減少し、6月から2017年12月までの間は2017年5月に減少となったもののはぼ連続19か月増加となっています。
前月比では2015年12月から2016年9月までの間連続10か月増加し、10月から2017年12月までの間は2017年6月に増加したもののほぼ15か月連続で減少となっています。
◇消費支出の推移(勤労者世帯)について
分析期間における消費支出の推移は、2009年1月の322,100円から2017年12月の313,800円までの間、平均的には315,900円±3,600円(1.1%)と横ばいから緩やかな減少傾向となっています。

家計調査報告では、消費支出は「3か月ぶりの実質減少」と説明されていますが、分析結果では傾向値の前年同月比では2015年8月から2016年12月までの間連続17か月減少し、2017年1月から12月までの間は連続12か月増加となっています。
前月比では2016年8月から2017年9月までの間連続14か月増加し、10月から12月までの間は3か月連続で減少となっています。
◇平均消費性向(%)の推移(勤労者世帯)について
平均消費性向とは可処分所得に占める消費支出の割合のことです。
したがって、数値が上方へ動く場合は消費を増やし、下方へ動く場合は消費を減らす(節約)マインドのことです。
分析期間における平均消費性向(%)の推移は、2009年1月の78.9%から2017年12月の75.5%までの間は、2012年2月から2014年10月の間増加傾向となったものの、緩やかな減少傾向となっています。

家計調査報告では、平均消費性向(%)は「季節調整値でみると70.8%で、前月に比べて1.2ポイントの低下となっています」と説明されていますが、分析結果では傾向値の前年同月比では2014年11月から2017年12月までの間連続38か月の減少となっています。
前月比では2017年3月から10月までの間、連続8か月減少し、11月、12月は増加となっています。