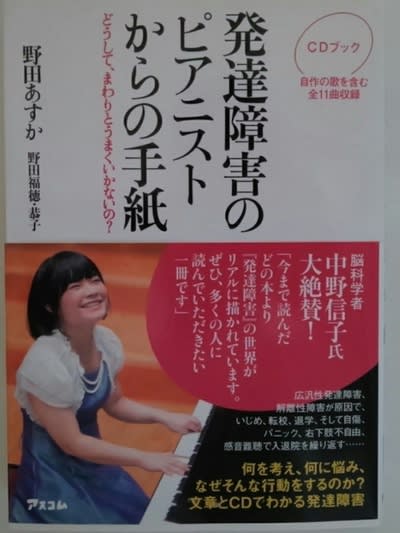『さくらと扇』(神家正成 徳間書店)
新聞の紹介記事で見つけて、後で読もうと思っていたのを、半年ほどしてから入手した。
歴史小説は巷に溢れていて、読み物的な、消費されて終わる品質のものが少なくない。だから余程のことがないと冒険はしない。たとえば地元に縁ある武将の話とか、個人的に思い入れある戦国大名のストーリーなら、多少は文章がまずくても感情移入できる。まあガッカリしても良いから読んでみようと思う。本作もそのような経緯で手に取った。
何故か分からないが凋落した由緒ある武将に惹かれる。かつて熱中した歴史シミュレーションゲーム『信長の野望』においても、足利将軍家や姉小路家が捨てがたかった。弱いからスリルがあるし、なんとか生き延びさせようと判官贔屓の情熱が沸いてくるのだ。
さらに弱小過ぎて、『信長の野望』においても一部のシリーズでしか大名として登場しないのが、古河公方や小弓公方の足利家だ。で、本作は、この足利家を舞台に描く話なのである。これまで題材に選ばれたことはないだろう。読んで損なしと思った。マニア心をくすぐる。歴史小説にも隙間産業があるのだろうか。
古河公方家が戦国期、北条家の傀儡となり、さらに足利義氏が世継ぎないまま死に、小弓公方系の男子が婿入りして江戸の世に名を残した。という経緯は知っていた。本作は、義氏の娘で婿を取って名を残した足利氏姫と、婿の姉で、家を守るため秀吉の側室に入った足利嶋子、ふたりの女性を主人公として描かれる。
子を成し或いは政略結婚で家名を守る、女の戦がテーマで、チャレンジングな内容だが、歴史ものとしては難しいだろうと思う。
どうしても普通の武将を中心に据える話に比して、合戦の場面はメインにならない。いろいろな駆け引きや、女ゆえの知恵を活用した権謀術数で、“戦”は進められる。
数年前の大河ドラマ『女城主直虎』もそうだったが、退屈さは否めない。本書は枕頭で読み進めたが、なかなか熱中はできなかった。
人間の人生模様を描くドラマとしては、面白かった。終盤に向け、次々と伏線が回収されていく構成も、なかなかのものだった。
ただ、ちょっと子供向けというか、『ジャンプ』にでも連載されている歴史マンガみたいに、くさい表現が散見され鼻についた。現代におけるエンタメ系歴史小説が纏う、デフォルトの匂いなのかもしれない。もしくは、最初から読者をジャンプのような週刊コミック誌愛読の輩と想定しての文体だったのか。

新聞の紹介記事で見つけて、後で読もうと思っていたのを、半年ほどしてから入手した。
歴史小説は巷に溢れていて、読み物的な、消費されて終わる品質のものが少なくない。だから余程のことがないと冒険はしない。たとえば地元に縁ある武将の話とか、個人的に思い入れある戦国大名のストーリーなら、多少は文章がまずくても感情移入できる。まあガッカリしても良いから読んでみようと思う。本作もそのような経緯で手に取った。
何故か分からないが凋落した由緒ある武将に惹かれる。かつて熱中した歴史シミュレーションゲーム『信長の野望』においても、足利将軍家や姉小路家が捨てがたかった。弱いからスリルがあるし、なんとか生き延びさせようと判官贔屓の情熱が沸いてくるのだ。
さらに弱小過ぎて、『信長の野望』においても一部のシリーズでしか大名として登場しないのが、古河公方や小弓公方の足利家だ。で、本作は、この足利家を舞台に描く話なのである。これまで題材に選ばれたことはないだろう。読んで損なしと思った。マニア心をくすぐる。歴史小説にも隙間産業があるのだろうか。
古河公方家が戦国期、北条家の傀儡となり、さらに足利義氏が世継ぎないまま死に、小弓公方系の男子が婿入りして江戸の世に名を残した。という経緯は知っていた。本作は、義氏の娘で婿を取って名を残した足利氏姫と、婿の姉で、家を守るため秀吉の側室に入った足利嶋子、ふたりの女性を主人公として描かれる。
子を成し或いは政略結婚で家名を守る、女の戦がテーマで、チャレンジングな内容だが、歴史ものとしては難しいだろうと思う。
どうしても普通の武将を中心に据える話に比して、合戦の場面はメインにならない。いろいろな駆け引きや、女ゆえの知恵を活用した権謀術数で、“戦”は進められる。
数年前の大河ドラマ『女城主直虎』もそうだったが、退屈さは否めない。本書は枕頭で読み進めたが、なかなか熱中はできなかった。
人間の人生模様を描くドラマとしては、面白かった。終盤に向け、次々と伏線が回収されていく構成も、なかなかのものだった。
ただ、ちょっと子供向けというか、『ジャンプ』にでも連載されている歴史マンガみたいに、くさい表現が散見され鼻についた。現代におけるエンタメ系歴史小説が纏う、デフォルトの匂いなのかもしれない。もしくは、最初から読者をジャンプのような週刊コミック誌愛読の輩と想定しての文体だったのか。