











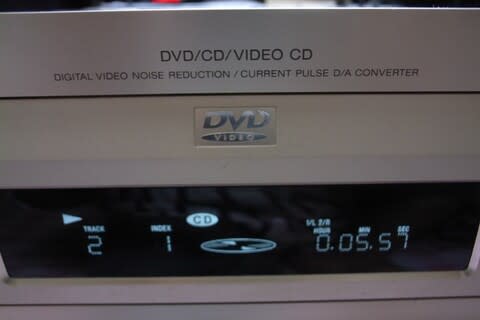












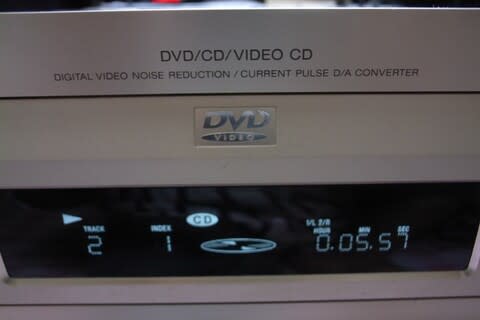















あー疲れた・・・・ 50℃60%rhの槽に手を突っ込んで動作確認、意外に
体力使うよ。腕が筋肉痛だ。仕事とは言え、性がない。
(金曜日は ー10℃は冷たいよー霜焼けになった、かじかんじゃった)
土曜日だが、1.5時間で終了させる。コレで来週は多少楽になる。
時間を見ると、am9:30なり・・・ ちょうどいい時間にサトー電気は開店する。
いいじゃない・・・ それではって、言うことで、車を転がす。
ブラックでも、ご安全に・・・・(おすすめしません)
昔の職場で一緒に働ていた、K君がいました。 彼は傍から見ると、
某団体に所属しているかのようです。 しかし、言葉遣いは非常に
丁寧です。(俗世間の道理を会得されている。
お祖父様から、よく、軍歌を聴いていて、彼は今でも歌えます。
いいことじゃないですか。育つ環境がよいです。ほんとにいい奴です。)
バイク・クルマ・時計いじりに造詣が深く、楽しんでおりました。(今でもそうだよね)
飛び抜けているものがある方はほんと面白い。(いいね)
(ちょっと、低車高、平べったいタイヤ、踏切や段差のあるところは斜めに
入らないと越せない自慢の車におじいさんが一言、お前の車は
乗りたくない、体が痛くなる・・・・ 痛く心に響いたらしく、車高を多少上げ
柔らかい乗り心地にしたそうな・・・・ いい話じゃないですか、
ホントに心温まる・・・・ 家族想いね)
彼からの依頼で、小型のスクータでちょっとハイスピードで楽しんでいる
仲間の噂でスクータのバッテリーに電解コンデンサの容量を徐々に
落とした物を並列に入れることで、エンジン音が静かになって、馬力が
出るとの噂がある。 そこで彼は電解コンデンサを4種類入手してきて、
作ってくださいよとの依頼があった。
4700μF、1000μF、220μF、10μFみたいな感じでそれらをパラって
適当なケースに入れ込んで、当時、仕事で使っていた封止材(エポキシ)
でケーシングした。その時の引き出しの線も3.5スケアあるくらいの
車用のドレスアップ線材をカシメて、引き出しケーブルとした。
私も、電解コンデンサのバイパスとして、セラコンなどの低容量を
付けることはあるが、ホントに改善効果あるのかな〜ト・・・?
彼に完成品を渡した。 すると・・・ まじでエンジン音が静かになって
動きが滑らかになった と言うじゃないですか・・・
私も感動した。 そうか効果があったか。
ある種の周波数成分の分散化、容量の大きいものは、低い周波数、
容量の小さいものは高い周波数成分の通り道ができて、ノイズ成分を
吸収(損失、コンデンサは消費しないはずだが、あくまでも理想)して
くれるのでは? (総合的にインピーダンスが下がるかも
某ノイズの指南書にもバイパスコンのところにも書いてあった。
いまでも、私のバイブルです。)
そこで・・・・
「嘘だと、思ったーラ、やって! みな・・・」
ピタゴラスイッチで民生先生も歌っている。
{ちょっと時間がかかるかもしれないぞー} コレは松ぼっくりの回
前回まで、部品交換を行ったが、もう少し伸びしろがあるのでは?
やってみた・・・
ゴールドとブラックとエルナのブラウンコンデンサの混合であるが、
純正はエルナのブラウン一色である。あまり音が好きでなかった。
小さな容量はそのままにして、電源系のコンデンサをゴールドと
ブラックへ変更した。一部と言うよりは、在庫がなくなり・・・・
本来であれば100μFのところを47μFへ変更したり、逆に220μF
のところに330μFを奢ったりした。まあ、電源関連なので多少上下しても
いいじゃないか。D/Aコンバータのバッファーは在庫が尽きたので
ソニーのFA3ESから剥ぎ取ったエルナーの目の覚めるような明るいレッドを
使用しなければならなかった。
左右独立しているので2倍必要なので意外に数量が多い。
確かに、そのときはノーマルよりは音の変化は前回に書いたが、
もう一つ、面白いことできないかなー? と 部品の在庫を見ていると
「嘘だと、思ったーラ、やって! みな・・・」
やってみよ・・・・
基板上の交換したコンデンサがゴールドなら、小さいコンデンサはブラック。
ソレができないときは、同種のゴールド、ひと桁台の容量を基板裏に
取り付ける。 D/Aコンバータのバッファーだけは追加しなかった。
個性が出るかなーと思って。エルナーの明るいレッドなので・・・
そうすると・・・・ 驚くぐらいの音質変化あり。
高域はシュッとした感じでガンガンなっているがうるさくない・・・
コレ不思議、分解能が非常に向上、全体がなめらかな音の出方。
面白い。コレはアタリです。
特に効いているのでは?ってところは、D/Aコンバータの電源関連
のところです。100μF→47μFへ変更して、1μFを裏に取り付けた。
意外に手を入れない場所かもしれませんが、回路図から見ても
かなり、ローカル電源を必要としています。(クロックもしかり)
まあ、プラシーボ感を揺さぶります。
メインのコンデンサと小容量コンデンサの銘柄違いの組み合わせ
も面白かもね。
簡単なグレードアップ(もれなく、プラシーボが付いてきます)。
The Essntial 5TH DIMENSION を聴いているが、
あの軽やかなベースラインがキレイに聞こえる。当然5人の声も
軽やかで気持ちが良い。(アクエリアス/レッツ サンシャイン イン)
こんなのも、今まで聞こえたなっかたの? って言われても
駄耳なもので、ご勘弁を・・・・(テレビを見るくらいの音量です)
この改良であれば、メインのコンデンサを交換しなくても、
1/10 〜1/100位の静電容量を極性さえ間違えなければ、問題なし。
しかし、間違えると、地獄を見ますよ。
あと、何気に、コンデンサ、改造でググると、漢の改造をされているページ
があリます。ショートやむやみにケーブルの延長することは、ご注意ください。
特にリード線のインダクタンス成分が影響しますので、程よい長さで、
はんだ付けができて、他のはんだ箇所に接触しないように気を配ります。
(やり過ぎは要注意です)、できたら、小さなセラコンで良いので、
パスコン0.1μFがあれば最適でしょう。(別に根拠ありませんが、計算すると
その容量が出るらしいですが、私は適当です。回路シミュレータがある
のでそちらで・・・どうぞ・・・)
近頃のセラコンは耐圧に要注意です。意外に25Vってこともありますので
電位の高い箇所は要注意ですね。よくご確認の上、ご使用ください。
ふた昔は、50V耐圧が多かったが、低電圧化の小型化で耐圧も低いものが
でまわっていますので、ご注意ください。特に80〜90年台の機種を
扱う場合はね・・・・ 小さく水色の衣を纏われると、耐圧の記号も解りづらく
なります。(マジで仕様書読まないと、危ないです。 サトー電気の
おっちゃんとその話に以前なった。
この土曜日も、開店直後のサトーさんのところにゆくと・・・半分シャッターが
空いていたが、ガラス扉は半分空いていた。
私はまだなのかなーと、薄暗い店内を外から見ていたが、おっちゃん(店主)
の姿が見られないので、川崎稲荷社へお参りに行った。
そうすると、何やら人影があった。その方は店舗を見ていたが、引き返して
いったみたいだが、私が半分開いたガラス越しに伺っていると、その方は
その扉をあけて、ご入店した・・・・。 そうすると、おっちゃんが急いで
いつもの出入り口側のシャッターを開けに来た。おいらは、笑っていた。
「ひゃーひゃーはっはー、今開いた!!」と声を出した。
(だって、ページには自粛営業で10時から営業って書いてあったから・・・・
平常時は10:30だけどね。 話ししていると・・・・、
やっぱり、開店直後は忙しいらしい・・・そりゃそうだ
「アムステルダムの朝は早い」、どこの朝も早く、忙しいのだが、珈琲呑んでる
場合じゃないよね、急いで出るよ、今は体温測ってるよ。これは今、重要ね)
やっぱり、川崎稲荷社にお参りして、霊験あらたかなことが起きたかな?
最初のお客様はかなり、お急ぎのご様子でした。
上原ひろみのスペクトラムを、聴いてますが、ピアノの響きも心地よく、
低い弦の響きも楽しいです。
個人的にはコンデンサの大容量化は好みません。容量や耐電圧が
足らない場合は足し合わせて(ええ、懐もよく考えて)実現しますが
よほどの場合以外は実施しません。
容量や熱で煽られて劣化(明らかに液漏れ)しているもの、もしくは
あからさまに、音がおかしいと判断したものは交換します。
5倍10倍の大容量は動作中や電源の入り切りの時の挙動が怖くて
ためらいます。(さあーて、何が怖いんでしょう?)
まあ、殆どは予防効果を狙ってですがね。
私のショボいシステムでも、十分音楽に浸れます。
オスカー・ピーターソンのウイゲットリクエストを聴いていますが、
面白いね、抑えられた、ナイーブな演奏も心地よく聴かせてくれる。
(だめシステムだから、そう聞こえるかもね)
傍と思ったが、Xtal直下の小さなセラコンで音質が変わる気がします。
これは今回のセラコン、ちょっと前のめり気味で、おとなしめかな?

前回のセラコン、立ち上がり付近のコブがある。
こっちの方が高調波が多いと思う。
立ち下がったところに僅かな盛り上がりが見られる。
上の波形とは、FFTの位置が1div違いますがちょと違うかな?

前回使用していた、セラコンと違うセラコン(同容量)を交換したら
FFTの波形に違いが出てきた。高調波成分が違うんだなと・・・・
交換後の音は高域のシンバル系のシャリシャリ音が大人しくなってます。
(だけど、うるさく聞こえない)

前回のほうが良かったかもしれない。シンプル波形です。
矩形波に段差になっているところは気がかりですが・・・・もしかしたら
反射波のいたずらかも・・・・

井筒香奈恵のリンデンバウムよりはシンプルな構成で聴かせてくれるが
アップライトピアノの響きと大きさ、ボーカルのバランスが絶妙です。
ウッドベースの弦を爪弾く感じがいい感じです。
久々にアイ・パターン何故か?オートセッティングでないと見られない。
何か、足りない設定項目あるのかな?

PD−2000は、このままで楽しもう。また、何か粗が出てきたら
また考えよう。
試しに・・・ やってみた。
CDP−502ES 実際には、前回の時にパスコンを噛ませている。
D/Aコンバータとクロック、デジタルフィルターと電源のコンデンサに
数μF付近を基板裏でパラってみた。
74HCU04の電源ラインをタンタルコンデンサから電解コンデンサへ
変更した。(まあ、まあ、大目に見てください)

コンバータとクロックへも数μFとセラコンを取り付ける。

デジタルフィルタにも同様なことを行った。

場所が狭いので、セラコンは止めた。

電源の3300μFのところにブラックの10μFを取り付ける。

音質変化は、まじで、同じような傾向の改善ができたと思います。
「嘘だと、思ったーラ、やって! みな・・・」
{時間と手間がかかるよ、極性に注意しなっ! 502ESでも
ウラ面のシルク印刷極性逆だったぞーぅ}
デジタルフィルタの低いものは、この小容量コンデンサパラレル法
面白いかもよ、プラシーボで構いません。
それでは、体調に気をつけ、ご安全に・・・・・
本日も限られたもので遊ぼう!! PD−2000をつい最近見られた方が
いらっしゃったので、以前から面白いかもと思うことをやってみよー!!(エイエイ)
さーテンションが上がってまいりました。(ほんまか?)
アマゾンでマスク50枚購入してしまいました。もうそろそろ、出回って、も・・・
(殆ど無い)思ってたが、うちの在庫失くなってきたしね。
神奈川は県知事より神奈川に来ないで、その他の県に往かないで って
エリアメール飛んでくるし、まじで勢い弱まらない。
都道府県の方が真剣に頑張ってる、どうなんでしょうね?
ジョンソン首相もウイルスから復帰したのだから、英雄ですね。
体験者だから、発言に重みがある。
確か、2〜3月に患者の激励に素手で握手していて、大丈夫かなーと
思ってた矢先に患っちゃって、大変だったが・・・・
(だけど、完全防護した姿で患者を激励するのも、なんだか説得力
無いけど、ジョンション首相は病院に行って激励したことは
英国では好印象だね。
(川崎市もGB応援してます。バスに書いてある。ちょうど、
この時期にGBフェアーみたいのやっている)
チャーチルさんも体を張って危険なこと率先してやっていた
気がする。 いますべき行動を自らの行動で示す。
ホントに器のデカい方だ。 そりゃ国民も納得するね。
珈琲呑んでる場合じゃない。 そう言えば姿見えない? かな〜
各都道府県の行政の方には感謝したい。)
緊急事態宣言1ヶ月延長ですので、みなさんもご安全に・・・・
前記事で秋月のLTC1799をクロック替わりに使用して結構、使えるなと・・・
温度安定性は±40ppm/℃ ほぼ大丈夫でないかい?
そもそも水晶発振器の置き換え用の石である。出力波形も結構キレイだしね。

繰り返し波形なのでアベレージングかけてます。
それでも、そこまで変形しない。
この段差波形は高調波がいたずらしている。
それでも、シュミットトリガなどで波形整形すると、
キレイになるかね。
この信号をSM5803のXtal入力に入れていた。
FFT波形はまだコレくらいで済んでいますが、複数波入れると
ソレはもう高調波の嵐です。
Xtalの駆動方法を変更すると音質が変わる。
(良いか悪いかの判断は、アナタ次第です。)
PD−2000は、SM5803内蔵の発振回路で使用されていた。
XR−V73のLTC1799を奪い取り、取り付けてみた。
(おいおい、秋月さん閉店中だしね、通販はオッケイ)
周波数もほぼ安定していますが、Xtal駆動の時の安定度までには追いつきません。
やってないが、74HC14シュミットトリガをかけるとキレイな方形波が得られるのでは?
高調波ノイズが放射されるのでそこは対処すれば良いかもしれません。
実はこの波形での音は少し問題あるみたいです。音場が小さくなり、
音が団子になりやすい。 XR−V73のときには気づかなかった・・・(音作りの一部かな)
今回は、オーバーサンプリングICの方がクロックを生成している。
そこを取っ払ってLTC1799の出力をXTIへ入力する。
SM5803の電源ラインを見るとIC付近で供給している。
そこへも、ちょーローノイズ電源のコンビでDC10V系から頂いて

独立供給とした。
それよりは共立のクロックキットの方が良いが、発注するのが面倒くさくなった。
身近にあるものを利用して遊んでみました。
ハイファイエンジンでパイオニアのPD−5000(PD−93)のクロック駆動を
見てみた。 Xtalを74HCU04で駆動している。外部で独立して駆動させている。
ナカミチ、マランツSACDなどのプレイヤーもアンバッファーで駆動している。
バッファー2ケを通した場合。(出力に370Ωを付けたので
出力が小さく見える。)
PD93の駆動回路を手本にして駆動した。

コレではチトマズイのでその後にもう1段バッファーを入れてみる。
ちょっとしきい値レベルが低いか・・・

FFTの波形も多少、おとなしくなったように見える。
これらの波形は、近頃、テクトロニクスのオシロが故障し始めてるので
置き換えようと、アジレントの物に移行しようと思います。
カラーで鮮やかです。ただし、一部機能が足りないもの、帯域は200MHz
まで欲しかった。(チューナのとき有難い) 入力インピーダンスが1MΩのみ・・・
帯域幅は我慢するしかないが、 数MHzのクロックを見ようとすると
やっぱり、Z0プローブのお世話にならないとだめです。
一般的な10:1プローブでは反射が多く波形がなまりすぎです。
そうすると、1MΩ入力オンリーであれば、50Ωのフィードスルーが必要ですが、
何分、高価です。そこで、なんちゃって50Ωフィードスルーの登場です。
適当にやってみた。(テクトロくんには50Ω入力があったのだが・・・・)

T型分岐に100Ωパラで50Ω 適当フィードスルー
入力インピーダンス1MΩでは、全く相手にされない波形(三角波となる)、
50Ωにすることで、波形らしきものが見える。
(ホントはわからないよ、電圧もほぼとしかいいようがない)
見えないと、見えるとでは大違い(だけど、ほんとかな)
16.9344MHzも観測しようとすると、大変です。
接続はダイレクトにはんだ付けします。

この下に、秋月のちょーローノイズ電源がある。

50Ωフィードスルー(適当です。手持ちのコネクタ
これしかないし)

LTC1799の出力(複数波)
チョット、派手に出ています。収まりが悪い。複数波で高調波が
暴れるとなると、周波数の変移が多いのかね?
それとも凹んだ所の成分が変動している?

74HCU04 3段バッファー(複数波)
高調波が交互に強弱が出ている。やっぱりXtalを駆動すると
単純になる。 レベルも押さえられている。

これらの波形と高調波の違いで、音場の広がりと、高音部の表現力が
異なります。やはりXtalの74HCU04の方が音質的には良好です。
LTC1799もノーマルよりは面白いと感じます。
前回までのPD−2000の嫌のところは、何か低域が力強い。

ノーマルの写真 銅箔巻のコンデンサが47μF50V
バイポーラ(ニチコンでした)
ちょっと、爽やかに聴きたい。コンデンサの組み合わせは標準そのもの
で交換は一切していない。D/Aコンバータと出力のバッファーオペアンプを
NJM5532DDとOPA2134に変更した。

D/Aコンバータ直後、バッファーが手前
奥側が出力バッファー
ブラックミューズ47μF50Vシリーズ接続
でバイポーラ仕様
ちょっと、飽きた感じがあった。もうちょっと、繊細さを表現して欲しい。
この組み合わせでは、何か?高音が早い時点でロールオフして、コモッた
感じである。全然爽やかでない。アンプの癖もあると思うが・・・
いまは、元気で動作している、ヤマハのプリメインCA-1000Ⅲである。
当時(2019年5月)は何だっけな? もしかすると・・・・、
東亜のP−75DとTA-E86か?
いろいろなアンプでPD−2000を鳴らしてきたが、基本的に低域の力強さ
があって、変更した経緯がある。
PD−2000の中身のゴージャスさを活かしたい。

この電源は同じ大きさのコンデンサが4ケ並んでいる。中央は銅箔が巻かれて
音質にこだわりましたって、主張している。手持ちのコンデンサは耐圧と容量が
なかなか合わない、それで回路図見ると両端はシリーズレギュレータで
+5Vとー12Vである。その出力だから、35Vは要らない。よって手持ちの25V
中央は手持ちの35Vの1000μFかなオマジナイで銅箔を巻いてあげた。
この基板類で困るのが、コンデンサの設置場所にまで他の部品リード線が
入り込んでいる。
少しでも大きな形状の物を入れようとすると、抵抗のリード線
にぶつかる・・・だから、小さめのコンデンサは浮かして取り付けられている。

交換後だが、その前もコレと同じ状況です。
レギュレータのヒートシンク取り付けると、
コンデンサと抵抗にぶつかる。
何かの理由があると思うが、少し頂けない。 特に5Vのレギュレータ付近は
ドロップ電圧が高く発熱が大きいそこの1000μFは750μFくらいまで低下している。
困ったものです。コンデンサの位置ずらしと小さな放熱器を取り付けた。
そのため、小型のコンデンサと抵抗2本もぶつかるのでウラ面に取り付ける。

そうしても、低域の表現はまだ力強い・・・ 多少高音の表現も多くなったが
もっと、爽やかさと奥行き感が欲しい。
出力バッファーのところにバイポーラの47μF50Vがあるこれを
緑ミューズ50V100μFがあったので交換した。

緑ミューズでも、いいが、容量が大きすぎたか?
が、もう少ししっとりとした響きが欲しかったので、最終的には
ブラックミューズ100V47μFシリーズ接続でバイポーラとした。
ピアノの響きが良好となる。
8倍オーバーサンプリングだが、ノーマルよりは響きとつややかさ
の表現が向上していると感じます。(当然、プラシーボバッチリです)
D/Aコンバータ後バッファーは、LME49720(コレは特に効きます)
出力バッファーは OPA2134で使用中です。
・そうそう、部品交換中に抵抗1本とジャンパー線、ネジ基板上に落とす・・・
見つからない・・・本体逆さにして振るがほんとに落ちているのか?
こういう時にこんな穴がその付近に空いている・・・

そうこのブラックホールは何でも飲み込む、悪いやつ。
おかげで、右腕筋肉痛です。 (ショート怖いから、筐体ひっくり返す)
ちょうど、追加基板の真下辺りにこの穴が・・・・
基板同士が電源配線で繋がっているので簡単に外せない。
アンプの場合は、修理に必要なので全部外したが、僅かなことなので
ワイヤーラッピングは外さなかった。
音質重視で2階建てになっています。
午後は掃除して、カラーレーザープリンタを設置しようかね。
(もう、インクジェットはええは、正月大変だった。目詰まりと
クリーニングだけでインク消費、挙句の果は、動作不能・・・
もういい。。。。)
広島の親父にマスクを送ってあげよう。大変そうだしね・・・・
ごきげんよう、お互いさまで、ご安全に・・・・
さあ!! 今回もマイナー路線ぶっちぎりましょうかね。 調子悪いのが当たり前!!だが、
風邪だと思う・・・(コロナじゃないよ、体温毎日、測ってるもんね)、熱い寒い
が極端なので、寝る時の長袖Tシャツを着るのを忘れていた・・・
その事もあり、どうも寝相が悪いと背中が出て寝冷えして、軽い頭痛・・・
いつものパブロンゴールドA顆粒を飲むと、朝にはスッキリです。
毎日の体温測定は忘れずに、指差し確認よし、ご安全に・・・
多摩方面のオフで、懐が寂しい時に何気に気になっていた、モノがあった。
大概、皆さんスルーされる。オーレックスのシステムコンポ用のCDプレイヤー
である。裏側を見ると、デジタルアウトはなく、アナログのみ・・・
コレはもしや・・・ 初期のCDプレイヤーである。
オーバーサンプリングも軽いであろう。非常に潔い方針でヘッドフォン
出力はありません。
しかし、何故か、デザインや佇まいに東芝の匂いがありません。
銘板みると・・・ ケンウッドさんがオーレックスさん向けに製造しているものでした。

そんなことは実は、つい1ヶ月前に気づいたのでありました。
当家にきて、放置プレイで約7ヶ月くらい寝かせていました。
レシーバー1やCDP−502ESを弄っている時にゴールド化を行いました。
非常にシンプルですが、基板のデザインはケンウッドのままです。
ですが・・・、非常にコストダウンの嵐が吹いています。

コンデンサ類は小さめ、デジタル部はセラミックコンデンサでパスコン程度の

この下にCX23035がある。
このセラミックコンのみ、富士通のXtal
(青大将直方体)
もので動作するでしょうなレベルです。
が、オーディオ系は結構、しっかり、構成されています。
電源類はディスクリート構成、デジタル、アナログ、別系統仕立てです。
そこで、目を引く青大将の青みの強いコーティングのハイブリッド基板があります。

もしかして、オーバーサンプリング 無いのかなー?
ということで、改めて石の構成を見る。
CX23035→CX20152 あっ、ダイレクトだ・・・・ すでにNOS仕様でした。

オマケに貰ったOSコンデンサ!!
耐圧10Vなので早速使ってみる。

D/AコンバータCX20152
最初はゴールドのコンデンサ

OSコンデンサがあったので、交換した。
少し足が酸化しているが十分はんだが付く。
利用価値が判断できる人ならば、お宝です。
それで、ハイブリッド基板(TDK製)のローパスフィルターで減衰させている。
サンプルホールドはuPC4084 (JFETのオペアンプTL084のクワッド版)と
FET 2SK163とコンデンサで構成している。
クロックも富士通製の緑色の樹脂パッケージの8.467MHz、表示は8467
ナンジャラホイ?周波数だったのね・・・ はじめはそういう製品番号かと
思ったわ・・・ (さすが老舗、重電!!シーメンスと仲が良かったのね)
しかし、この機種の発売時期から考えると、2倍、4倍オーバーサンプリング
であっても、おかしくないと考える・・・ しかも、大変なローパスを使うよりは
オーバーサンプリング導入したほうが性能・うり文句に最適なのに・・・
当時の価格も6万円くらいであろうか?
ちょっとシーラカンス的CDプレイヤーではないか?
一部、回路構成が異なるが、ケンウッドの類似機種では、DP-850が近い。
上記の石の構成がほぼ同じである。

何気にゴールド化とブラック化
スペースがないのでチョット浮いている。
ヒートシンクも奢ってあげた。微妙な向き方は
ショート対策、どこかと接触する。
ヘッドフォンアンプなしでテンキーつきでDP-850よりも、小型でキュートです。
ソニーのCDP-102と同じ大きさです。 逆にDP−850はデザインが・・・
イマイチですね。(ものすごく大味なデザイン・・・プレイボタンは当時のトリオ・
ケンウッドのトレードマーク、そこまでせんでもプレイボタン判るがな)
両者の発売時期を考えると?
CDP−102 1985年 2倍オーバーサンプリング 89、800円
XRーV73 1986年 ノンオーバーサンプリング 55、000円

本家のソニーさんは次から次へと最新デバイスを搭載してオーバーサンプリング
で可聴域内への折り返し雑音の影響を低減させて、忠実性を得るために
開発の一途を辿る。 しかし、どうも、東芝さんはあまりやる気がないのか?
トリオ・ケンウッドに頼っていた気がします。 チューナー、CDプレイヤー
しかり・・・ そのおかげで、非常に面白い現象が起きたのがこのV73である。
人気のないコンポサイズで結構、マニアックな構成は流石です。
(あくまでも、個人的感想です。ハイレゾの方から見れば、笑われて、終了です)
お値段も、持ってけ価格の1000円でした。CDのマークも赤色です。
大概、白色インクです。 黒のパネルにおしゃれです。
Aurexのロゴもいいですね。
出力バッファーのオペアンプは当初は何だっけ? 恐らく、DP-850の構成からは
NJM2068DDです。意外に気を使っています。

手前側は何でしょう?不明
奥側は出力バッファーとりあえずの
NJM2114DDです。ちょっと分解能悪い。
この音では、イマイチなので、NJM2114DDで遊んでいたのですが、分解時に
当家はオペアンプ在庫が底をつき始めたときだったので、どうかなー?
と、とりあえず、鳴らしていた。今回、ブログに載せようと再度、聴き直しているが
MUSE8820がちょうど1ケ余っていたので、取り替えると透明感が出てきて、
繊細な表現をします。コレはあたりでした。
ガッツン、ガツンよりは良いようです。 ヤマハのCA-1000Ⅲで鳴らしていますが
いい感じです。

放熱器の上空温度、44.805℃
内部はもっと熱いかも。 A級ドライブ中
オーバーサンプリング無しで、少しだけ? 手を入れてやると、面白い発見が
あって楽しいです。
それに、しても・・・、こんなマイナー機種で遊んでいる人は何人いるのでしょうか?
ぷっ・・・・(笑わない、今吹き出したでしょ)
そりゃ、欧州の高級機とかは手が届きませんので、貧乏サラリーマンは
マイナー機種のジャンク漁りが関の山でしょう。
それでも、もっと楽しいことは、 できるかなっ。? (ゴンタくん、フゴフゴです)
そうだ、謎のクリスタルを半導体式に変えてしまえー・・・
12行前くらいに出力バッファーを弄って、ちょっと、変わったが、もう少し分解能アップ
したい。 中低域の表現が少し団子になっている。

以前、秋月でLTC1799モジュール基板を購入した。1kHz〜30MHzまで
発振できる。しかも、外付けの抵抗値で可変できる。
安定性もそりゃ、ちゃんとしたクロックモジュール(ワンダーキット)よりは劣るかも
しれないが、CX23035のセラミック小容量2ケと内蔵のアンバッファーで駆動される
(と思う)発振よりは、もっと面白い表現できるかも・・・・
私の改造法(改悪かもね)は以前より、 Xtal inへクロックを注入している。
使用される電圧に合わせて、適当にダンピング抵抗を挟む事もある。
今回は10Ωを通してみた。(効果のほどは・・・ プラシーボっ)
動けばこっちのものよ。(大胆かつスピーディーに、その他悪影響は個人の範囲で)
Xtalもメーカーや駆動方法によって、音が変わる事は体験してきた。
やってみた。
プラシーボ満載だが、おお、音が分離してきた。良い傾向である。
しかし、電圧依存性が少し悪さしている。お手軽には秋月のモジュールだけでも
その効果は味わえます。(1kHzくらいの幅で変動する)

ゲート時間は1秒だがまあ安定している。
それにしても凄い石です。
回路基板の5Vを電源としている。
何が悪いって? CX23035の供給電圧が上下すること・・・特別に電源ラインを
強化されていない(もとはセラミックコンデンサ0.1μFのみだったが、オマケに貰った
OSコンデンサ10V100μFを充てがった)ので、いろんなものが動作し始めると
多少変動する。
それでもCX23035は当然動作する。 その変動が発振周波数に影響しデジタル
信号の僅かな変化に結びつくのかもね・・・
クロックの駆動方法を外部からの発振方法に変更することで、音の情報量が
増大する。(不思議だね)とくに、音場、分解能も改善するのと、以前から言って
いるが低域の表現が一気変化する。
LTC1799のみでも効果はあるが、そこに同社の ちょーローノイズ・プログラマブル
可変電源キットを入れるとどうなる? 欲が湧いてきた。

テスト中、CX23035とメモリとクロック
基板をちょーローノイズ電源で駆動
効果あるかも・・・・・

いい感じです。 多少のブレでも良いです。
音の違いに驚きです。
幸いにも買い置きがあるのでやってみた。安定性はみなさん、ご存知の通りです。
回路図と基板パターンとにらめっこしながら、電源の切り分け場所を考える。
パターン切断すると、手元がぶれて、隣のパターンに傷を入れてしまった。
線でその箇所を補修する羽目になった。
CX23035とそのメモリーの5V系のみ電源をちょーローノイズに変更した。
同系統の5V発生場所(2SB941のエミッタ側 12V)より供給してみた。

最終的に基板を適当に固定した。
それにしても、このシルクはケンウッドですね。
すると、なんてことでしょう・・・ 周波数カウンタの値が500Hz位の幅で
変動するが、無いよりはマシである。
すると、低域表現がほんとに変わる。電源の安定性に感謝である。
特にボーカルものは面白いくらい、いい感じです。
CX23035も電源別にしたのでこの効果もあったかもね。
分解能、繊細さ、静けさへも、非常に効果がある。

シンプルだが、弄り甲斐、音の変貌ぶりが
面白いです。ローパスフィルターでも感動
ワンダーキットのクロックモジュールは通販だが、この秋月の2種は
アキバに往けばすぐに入手可能なところがよい。
遊びの醍醐味ですね。
それでは、体調管理、コロナに負けないよう、ご祈念しまして、
(皆さん、一斉に・・) ” 明日も、ご無事で、ご安全に・・・ ”
ほんま、大変なことなってるでー、ナショジオで去年の暮あたりに
放送された、ザイールエボラのドキュメンタリと1980年台に発生した
アメリカでのエボラ対策のドラマは、今を予見しているかのうような
ものです。フォックスさん、ナイスタイミングです。
(USAMRIIDのあの夫妻凄いね)
そのときは、パンデミックて怖いね、エボラなんて日本に来ないわね
と思っていたが、今のウイルスが来るとは到底、考えてもいなかった。
ドラマはホントに内容が濃く、毎週楽しみにしていたが、
こんなことになるとは・・・・
2014〜2019年(特に2019年)のエボラ流行、その時のWH◯の初動、
認識の遅さが各国の対応をさらに遅らせた。(なんか、似てるぞ)
皮肉であるが、アフリカで医療従事者が防護服や医療器具が不足して
洗浄しながら対応していた。 発展途上国の影響もあるが、今や
経済発展している国でさえも、同じことが起きている。
私達の国も早く、医療従事者への負担を少なくなるような対応を
望みたい。(そっちの方に重きを置いて欲しい。人は消耗品ではありません。
命がけなのだから・・・・、配達員さんも大変だよ)
いまの状況はその時のエボラと同じ道を歩んでいる。
アフリカでの2019年の収束は、やはり現地の方々の予防対策が
ようやく功を奏してきた。(手洗いの習慣や葬儀の慣習の見直し)
しかし、これらウイルスは突然収束して、またいつか、現れる。
これらがドラマでの締めくくりである。
突然変異でまた、何ぞ起きる気がする・・・・ 年末か・・・・
(インドの少年はそう思っている。)