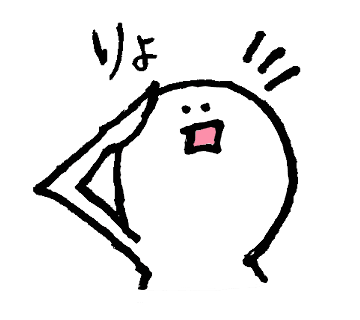神戸女学院大学名誉教授で思想家の内田樹(うちだ・たつる)氏のブログ(「内田樹の研究室」3月28日)に、氏が2年前に大阪府の国語科教員たちに向けて行った「母語の生成と機能」に関する講演録が掲載されていました。
内田氏はこの講演の中で、古語辞典が一冊あれば誰でも古典文学(などの先人の残した記録)に容易にアクセスできる言語環境にある国は、東アジアの中でも日本だけだと指摘しています。
氏は、多くの東アジアの国では、特殊な専門教育を受けたわけでもない一般人が古典を理解することは既に困難になっていると説明しています。
例えばベトナムでは、それまで使われていた(漢字とベトナム語の万葉仮名的な表記法である)「チュノム」のハイブリッド言語が、17世紀以降の西洋文化の流入とともにアルファベット表記の「クオック・グー(國語)」に表記法を変えてしまった。
その結果、欧米の言語と同じ表記となって便利にはなった一方で、市井の人々は漢字・チュノム混じりで書かれたテクストを読むことができなくなったということです。
古典どころか、祖父母が書いた日記も手紙も読めないし寺院の扁額も何を書いてあるのかがわからない。利便性の代償として、ベトナム人は世代として2代前以前の自国文化のアーカイブへのアクセス権をほぼ失ったと氏はしています。
果たして、それは間尺に合う取引だったのかどうか。ベトナムばかりでなく、フィリピンやマレーシア、シンガポール、インドネシアなど多くの東南アジアの国々で(国民のアイデンティティに関わる)同様の問題を抱えているということです。
隣国、韓国でも事情は似ていると内田氏はこの講演で述べています。
韓国では1970年代に漢字廃止政策が採択されたことは日本でも広く知られています。
その理由の一つには日本の植民地時代に日本語使用を強制されたことに対する反発があり、さらに漢字は習得が難しいので、漢字の読み書きができる階層とできない階層の間で文化的格差が生じるリスクがあるということで、ハングルに一元化されたということです。
確かに私の記憶でも、70年代までの韓国の新聞や街の看板などには「漢字」が多用されており、日本人にも(何が書いてあるのかが)何となくわかりました。しかし、現在のソウルの街は、アルファベットと(韓国人以外には記号にしか見えない)ハングルの〇や□に溢れていると言っても過言ではないでしょう。
ハングルへの一元化によって、韓国の教育の平準化は確かに進んだと内田氏は評価しています。しかし、ベトナムの場合と同様、そこに先行世代と使用言語が違うという事態が生じたのもまた事実だということです。
一世代前の人が書いたものが読めない。今の韓国の若者たちは、漢字は(本来は漢字に由来するはずの)自分の名前くらいしか書けないのが普通だと氏は言います。
例えば、氏が韓国の学生と(韓国江原道に)五台山月精寺という名刹を訪ねた時、扁額の「五台山月精寺」という文字を読めた学生は一行の中にひとりもいなかった。中高年ならまだしも、40代くらいになると、それくらいの漢字でも読むことが難しくなっているのが韓国の実情だということです。
日本では、「韓国の英語教育はすごい」とよく言われますが、確かにそこには「必然性」があると内田氏はしています。
韓国は、表意文字である漢字を捨てて表音文字であるハングルしかない。日本で言えば、ひらがなだけで暮らしているようなものだということです。
そうした状況で学術論文を全部ひらがなで書くという手間を考えたら、外来のテクニカルタームなどはそのまま原綴りで表記した方が圧倒的に効率的に決まっている。だから、漢字が使えない以上、英語への切り替えは必然的だったというのが韓国の言語環境に関する内田氏の認識です。
しかし、一方で氏は、母語では学問的な文章を書くことができないというのは、やはり大きなハンディになるのではないかと考えています。
自然科学なら英語で(そこそこは)行けるかも知れませんが、英語でやったのでは、韓国オリジナルな社会科学や人文科学は出てこない。というのも、文系の学問は母語のアーカイブの中で熟成するものだからだということです。
今の韓国の学術的環境では、1970年以前になされた知的営為へのアクセスが日々困難なものになっていると内田氏は指摘しています。
韓国では、先行世代がその言語的能力を振り絞って書いたテクストを読むことが難しくなっている。このことはいずれある時点で、韓国の次世代の知的生産性、知的創造性にとっての大きなハンディになるだろうと氏は予想しています。
内田氏によれば、今、韓国の大学で一番人気のない学科は、韓国文学科と韓国語学科と韓国史学科だということです。
多くの優秀な学生が、実学的な専門を修めてアメリカに留学して学位を取ろうとする。それは、そういう人たちが韓国のこれからのリーダーになることを意味していると氏は言います。
しかし、自国の言語にも文学にも歴史にも、特段の関心がないという人たちに韓国のこれからの国のかたちを決めさせるというので本当に大丈夫なのか。有史以来、東アジアに花開いた朝鮮民族の素晴らしい文化アイデンティティが、ここ数年で過去のものとなり、やがて失われてしまうのではないかという懸念がそこにはあります。
翻って、日本でも、文系の学問に対する風当たりが強くなっているのは事実でしょう。古典や漢文などは一体なんの意味があるんだ、そんなものになんの有用性もないというようなことを言う人たちが多くなっていると内田氏も指摘しています。
それでも、母語のうちにこそ文化的な生産力の源はあるというのが、この講演における氏の主張の要諦です。
二千年前からこの言葉を使ってきた全ての先人たちと、私たちは文化的に「地続き」の場所にいる。そして、日本の場合は、ありがたいことに、言語を政治的な理由で大きくいじらなかったので、700年前の人が書いた文章を辞書一冊あれば、誰でもすらすらと読むことができるということです。
内田氏は、それがどれほど例外的で、どれほど特権的な言語状況であるのか、日本人は知らな過ぎると指摘しています。
グローバリストたちは、もう古文や漢文なんかいいから、英語をやれと言う。でも、それは自国語で書かれた古典のアーカイブへのアクセスの機会を失うということを意味していることを、私たちは忘れてはいけないということです。
「言葉」なんてシンプルなストックフレーズを使い回せばいいと思っている人間が、日本の場合、政官財メディアの指導層のほとんどを占めていると内田氏は言います。なので、(日本のリーダーたちの間に)「生きた言葉」を使える人がほとんどいなくなってしまったという、痛ましい現実があるというのが、日本の現状に関する氏の認識です。
母語を受け継ぎ、子どもたちを生きた日本語の使い手にしていくことは、次の世代に自分たちの歴史や文化を預けるということだと内田氏は考えています。
東アジアが地政学的に大きく動いている現在、子供たちに、日本の文化や日本人のものの考え方、そして社会そのものを引き受けてもらえるように支援していことこそ、親世代の責任なのではないかと指摘する内田井の視点を、私も大変興味深く受け止めたところです。