
「北桑時報」の平成25年270号が年末に届いた。<能勢朝次先生のこと(その1)>という、関西外国語大学特任教授・山口満さんの記事が目にとまった。
能勢朝次先生と言えば我が母校山国小学校の校歌の作詞者だ。この事については、6年ほど前にこのブログでふれたことがある;
・「山国小学校」の校歌です
http://blog.goo.ne.jp/mfujino_1945/e/cbbe6be8412f1ddb02c3f7d83fbf5197
・「山国小学校」の校歌-読み
http://blog.goo.ne.jp/mfujino_1945/e/c4e89ad59edb5350dc4c24b91cfce8a6
・伝統・郷土意識について
http://blog.goo.ne.jp/mfujino_1945/e/c9ff080b1d5b09397e2ada5c91a067f4
・【京北のツアーガイド資料】・山国神社
http://blog.goo.ne.jp/mfujino_1945/e/ca91018bca2490443918cffa578bb864
京北中江町ご出身ということくらいの知識を持ち合わせていなかったが、我がブログで硯水亭氏から次の様なコメントを残してもらい、能楽研究に貢献された偉い先生だと教えて貰った;
>能勢朝次先生は私が能楽を習って間もない若い頃に難渋に難渋を重ねて読ませて戴いた本の著者で、いつしか私が抱える一つのテーマにもなってしまった端緒になった本=『能楽源流考』を書かれた先生でした。理路整然としていて、実に実証主義的な文章は大好きでした。現在では先生の時代より幾分研究は進んでおりますが、能楽研究の分野では未だにバイブル的存在になっているものです。
またWikipediaの記事を読むと;
>以後、能楽史研究においては、本著の学説をいかに乗り越えるかが目標とさえ言われている、、
>審査要旨については能勢朝次君著「能楽源流考」に對する受賞審査要旨(日本学士院公式サイト)を参照
といった説明がなされている。
山口満さんは、
>ちなみに、この時、中間子理論の湯川秀樹博士が能勢先生と共に恩賜賞を受賞されている。この一事をもってしても、能勢先生がふるさと・北桑の誇るべき先達であることは明かである。しかし、一般的には、京北でも美山でも、先生の名前や業績はあまり知られていない。『故郷逍遙』(町誌別冊、京北町、平成17年)に取り上げられていないことも、意外な印象を受ける。
と、生い立ちから始められている。次号が楽しみになってきた。
ちなみに、この故郷逍遙の「ふるさと縁の先達」に載せられているのは;
藤野斎・牧野省三・野尻岩次郎・河原林義雄・稲波益太郎・村山彌一郎・永井登・永井道雄・石浦寒次郎・井川市太郎・野尻重雄・岡本清一・草木慶治・川本邵・福田尚・高宮輝千代といった方々で、その功績が説明されてる。
今回次の2点に触れておきたい。
1. 山口さんによると、能勢先生は、
・京都府立園部中学校校歌(昭和2年4月)
・園部小学校校歌(昭和3年10月)
・山国小学校校歌(昭和7年4月)
と三つの校歌を作詞されたとのこと。園部小学校校歌はウエブで見ることができたが、園部中学校のそれはヒットせず。旧制中学校でしょうから、もしかして今の園部高校の校歌かなと思いを馳せたがこれでもなさそう。
2.もう一つは、この山国小学校校歌の碑が小学校の敷地内でなく山国自治会館前に建てられていること。山国小学校と黒田小学校が合併して京北第2小学校になったが、この校歌が歌われていた元山国小学校敷地内に建てられていない。今更どうこう言う筋合いはないが、私個人としてはどうも釈然としない。黒田小学校の人達への配慮もあったのではとも想像するが、校歌の碑はそれが歌われていた地に建てられるべきではなかろうかという気持ちは棄てきれない。










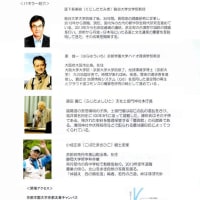
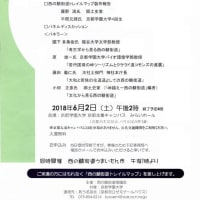
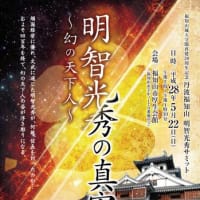


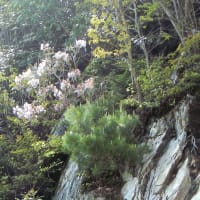


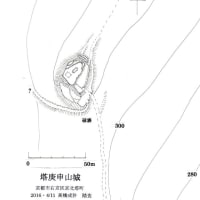

作詞 能勢朝次 作曲 佐々木すぐる
一
さやけく負ひし勤皇の
ほまれに映ゆる園部城
其の昔遠く偲びつゝ
進取の意気と智を磨く
これぞ我等が学園の
中を貫く生命なる
ニ
春こそ匂へ小桜の
陵をうづむる花の雪
秋玲瓏の気に澄みて
淇水に宿る月の影
これぞ我等がいさぎよく
濁世を抜ける姿なる
初代校長の萱島徳氏の「校歌の由来」(園部高校120年誌/私も編集委員でした)によれば、校歌の依頼は大家ではなくて園部中学に所縁(ゆかり)のある人を物色し、能勢氏に委嘱したとあります。
作曲者も校長と親しかった佐々木氏に依頼したそうです。ただ2人とも校長より年齢が若かったので、校歌発表の際は氏名を伏せたとのことです。後になって思えば礼を失した、と反省の弁を記しています。
なお、作曲の佐々木氏は、「月の砂漠」「お山の杉の子」「赤ちゃんのお耳」などの童謡の作曲者として後に名を知られるようになった、との由です。
余談ながら、校章の図案は福田平八郎画伯です。なお、歌詞の中の「小桜」は学校(城)の建つ地名です。
総合同窓会では、この園中校歌を卒業の当事者達が歌いますが、私は高校の校歌しか知りません。なお、高校の校歌の作詞は中西信太郎・作曲は岩上行忍となっています。
私は京都の友人はいないんですが、京都人には昔から興味はありました。とにかくしゃべりがうまいですね。上岡竜太郎、島田紳助、やしきたかじん、とくにたかじんは西成出身、京都育ちで最強です。たぶん彼らは自分と他人の距離のとりかた、空気の読み方が抜群に上手なのでしょう。ややこしい話題はスルーするのも上手いですね。そしてそれは京都の風土と関係しているのかなと思ったりします。道草師匠をはじめ、mfujinoさん、gunkan atagoさん、俳かい堂さん、みなさん一家言の持ち主で、感心します。あたかも、京北サロンの雰囲気があります。楽しませてもらいます。
山国小学校の校歌が、学校の敷地にないのは確かに不自然ですね。子どもたちが、毎日歌詞をながめてこそ郷土の誇りを身につけるというものでしょう。二つの小学校が合併したから、もうひとつの学校に気がねしたことは十分考えられますね。とすればみみっちい話、ほんとうの田舎根性ではないですか。おっと、余所者がなにをくちばしをはさむか、という話ですが、私もわりとおこりっぽいという自己紹介のつもりです。
本来は、ハノイ在住の私もブログを立ててベトナムの生活などを紹介すればいいのでしょうが、PCの知識に乏しく、今度日本の友人が来た時にでも、ブログを作ってもらおうかなとも考えていますが、生来のなまけもの、続ける自信もあまりありません。コメントの長いめを書くということで許していただきたいとおもいます。
校歌の宿命かも知れませんが、大阪などでも小学校などは随分と統廃合が進み、多くの歌が忘れられていこうとしています。場所はともあれ、こういう形で歌が残されていくのはいいことですね。
能勢先生のことについては何も知らないのですが、稲波姓や河原林姓、勿論藤野姓も、今から思うと京北出身だったんだなあという人たちを多く知っています。
能勢先生の臭いを感じられる歌詞ですね。ただ正直な感想としては、一番最後に作詞された山国小学校のが味が深く感じます。と、まあこれは我田引水そのものとのご批判は覚悟の上での発言ですが(^_・)
私が感銘を受けるのは昔の日本語の素晴らしさです。漢文の素養がその底にあるからでしょうか。NHKの朝ドラ、「はねこんま」で父親が主人公の娘に宛てた手紙が読まれるシーンがありました。その時昔の人の文章は型にはまりつつ、何とその心の伝達力があるのだろうといたく感じたことを思い出しています。これはまた、昨年他界した我がビジネスフランス語の師匠が書くテレックス文の凝縮された文章をタイプしていてこれにも感動していたことも思い出しています。
型にはまり、圧縮された世界で見事に言うべきことを言い表している世界のほんの一部でも触れられたことは噛みしめるべき経験と思っています。
この欄をお借りしますが、園部中学校のリンクが間違っていましたので本文を少し訂正しました。
私は会津人の様な背骨を持ち合わせておりませんので、山国隊のことは冷静に判断することが出来ると自己分析しています。例えばあるサイトで、<何億円もの借金を抱えてしまう戦に出掛けたばかげた我が先祖、、>というサイトがありましたが、その女性の意見にも、成る程、と頷く気持ちもあるからです。でも、そう言っちゃあお終いよ~、と彼女には反論しますけどね。
我が祖先たる山国隊結成とその後の活躍は私に力を与えてくれましたし、誇りに思っています。大袈裟に言えば、何が高杉晋作よ、何が新撰組よ、とまで時々発言してしまいます。長州藩の農民よ、新撰組よ、金貰うて仕事しただけやんか、こっちは手弁当やで~、その志の高き農民の爪の垢でも煎じて飲め、という心意気でありますし、この心意気は大切な事でありましょう(^_・)
この、<又はかしこき御いくさの、御さきとなりてつかえつる、、>とある校歌碑について、昨日ある山国在住の人と、<あれは何だよ、、黒田の人に遠慮したんかしら、それとも黒田からコンプレインがあって引っ込んだんやろか?>と宴席で持ちかけたのですが、<山国の人はそれだけ奥ゆかしいんよ>と返され、お互いに笑いあったことでした。
浮舟さんはハノイご在住とのこと、ぼちぼちいろんな体験などを交えて話してください。まあそのうち、え~い面倒やなあ~、ブログで書くか~、という事になるかも知れませんね。それはそれで待ち遠しいことではありますが(^_・)
眺めの、おっと、長めのコメントでお許しをなんて言わずにどんどんどうぞ。嫌なコメントでしたら無視も出来るのがオンラインの良いところ。これが顔を付き合わす世界では難しい。返事の方が長くなってしまったかなあ、、お許しを。
補足です。徘徊堂さん=gunkanatagoさんです。本拠ではgunkanatagoさん、外では徘徊堂さんですが、私は徘徊堂さんの方が好きですね。
稲波姓は上弓削騒動や絹糸で出てくるでしょう。河原林姓ですが、亀岡に河原林町がありますね。あと鳥居、水口、高室、辻姓、、おっとこの辺にしておきます。
校歌碑はやはりそれが歌われた場所にないと何故か心に引っかかるものがあり書かせて貰いました。しかしそれをちゃんと残して頂いたことは場所以前に感謝する気持ちには変わりありません。まあ、普通校歌を石碑で残すってことは稀なのではないでしょうか。京北の小学校でも戦後には新しいものになりましたが、この校歌は戦後も生き残り、従って終戦の年に生まれた私もこの校歌を斉唱しましたが、今にして思うに有り難いことだと感謝しています。
「なあ、冬眠してたん?」と言われてもしかたがないほどご無沙汰していました。原因はあかぎれです(笑 *寒さに冒されて手足の皮膚が荒れ、裂けて痛むもの*(広辞苑より)
今や死語に近いでしょうが・・・そう右手親指の先が割れて痛くてパソコンも携帯電話も打てないのです。まるでおしんさんの手でした。
新年から言い訳が過ぎました、ご免なさい。
北桑時報、私も届きました。いつも楽しみで読ませて頂きます。今回の能勢朝治氏のお名前、初めてうかがいました。
mfujinoさんの郷土には立派なお方がいられるのですね。郷土の誇りでしょう。
父の岩本、妻の佐々木でもない、能勢姓は母方でしょうか?
京都市は学校統合の際の名称は、旧校のどこにも属さない全く新しい校名をつけるそうですね。怒りっこなし
ですね。以前新聞で知りました。
碑の場合は胴でしょうか?でも校歌があるのは羨ましい限りです。K小学校は無かったと思いますが、それとも忘れたのかな?いや無かった筈です。:緑も深き杉木立・・・これは周中の校歌でした。雪の周山中学校の卒業式が昨日の様に思い出されます。
ノンちゃんですが、本年もよろしくお願いいたします。
合併してどういう名前にするかってやっかいな問題ですね。どちらの名前も廃するというのは一つの智慧ですね。以前このブログで、飛鳥と明日香、何で「明日香村」やねん、と話題にしたことを思い出しました。阪合村、高市村、飛鳥村が合併するとき飛鳥を残すと他の2村は吸収された格好になるので、明日香村に、だそうですね。どちらも採らないというのは、仰る様に恨みっこ無しでいいのですが、古い名前が消えてしまうのは寂しいもんだという気持ちは棄てがたい。寂しいというか味気なくなり、何か大切な物を棄てる要素もあり、複雑な気持ちになります。滋賀県の安土はどうなったんでしょうか。さて三方良しの近江商人のふるさとはどう解決されたのか気になります。
校歌の碑をどこに置くか、いろんな意見があったことでしょうし、私と同じ思いを持った人も当然おられたことでしょうが、何れにしても碑を建てて残して頂けたのは素晴らしいことだと思っています。それだけ能勢先生の歌が心に染み渡ったという事でしょう。元弓削小学校にも博習館の歌の碑が建てられていたと思います。
ノンちゃん? 私の娘はノンちゃんです、のりっぺとも呼びます(^_^)