 9月5日(土)
9月5日(土)今日は映画「たまゆら~卒業写真~ 第2部・響-ひびき-」を観に桜木町に行って来たよ。

まぁ映画については明日の週報?で話すとして…前作(第1部)も公開2週目初日の初回(土曜)に同じく桜木町に観に行ったんだけど、そのときまだ有休持ってなかったんで午後から出勤するためにスグ帰ったんだわ。

今日は元々休みだったんでね…じゃあ、映画観た後(まだ10時半にもならないんで)真っスグ帰るのももったいない…ってことで周辺の史跡ハントをすることにしたんだよ。

映画は10:10すぎに終わり、映画館を出てスグ「桜木町」から京浜東北線に乗って「新子安」で降りました。

それから歩いて横浜駅方面に戻る形で史跡ハントをしていきます。



これは大口通にある「足洗川の碑」です…ココに流れていた川で「浦島太郎」が足を洗った言い伝えがあるんだって。


これは「相應寺」です…通りがかりだったんで寄ってみました。

これは本堂です。


これは…サル地蔵?


これは「蓮法寺」です。

ココには…


「浦島太郎」に関する史跡があります…写真右は戦前まで浦島丘の頂上にあった「白幡の碑」です。


今、auのCMでも注目を集めている
 「浦島太郎」ですが…ココ横浜市神奈川区には浦ちゃんにまつわる伝説が残ってるんだよ。
「浦島太郎」ですが…ココ横浜市神奈川区には浦ちゃんにまつわる伝説が残ってるんだよ。
お伽話で子供のころから知ってる「浦島太郎」ですが…助けたカメに連れられて竜宮城に行き、乙姫様のもてなしを受けるんだよね。

そして、いつしか3年の歳月が流れ…父母恋しさに暇を告げると、乙姫様は別れを惜しんで「玉手箱」と「聖観世音菩薩」を太郎に与えました。

神奈川区に伝わる話では、故郷の土を踏んだ太郎には見るもの聞くものすべて見知らぬものばかりでした…ついにこの玉手箱を開くと、中から白い煙が出てきて白髪の老人になってしまいました。

3年と思ったのが実は300年で既に父母はこの世の人ではなく、武蔵国白幡の峰に葬られていると聞いて尋ねてみると…二つの墓石が淋しそうに並んでいました。

太郎は墓の傍らに庵を結んで菩薩像を安置して父母の菩提を弔いましたが、この庵がのちの「観福寿寺」で、通称「うらしま寺」と呼ばれました。
残念なことに明治5年、神奈川の宿は大火により焼失し、本尊の聖観世音菩薩は「慶運寺」に移され、遺物は丘のふもとにあるココ「蓮法寺」にも移されました。



これは「浦島太夫・太郎父子の供養塔」と「亀塚の碑」(どちらも写真左)です。

これは本堂です…「亀化大竜女の石像」があるんだって。


寺紋もカメだね。



それから浦島町に行ってみました…周囲には亀住町や浦島丘といった「浦島太郎」に関連する地名が多いんだよ。

この辺りも国道15号線の先はスグ海で…運河?を隔てた新浦島町なんかは埋立地なんでしょ?


この辺は路地が狭くて…よく見ると路地の奥に「白山神社」を発見

でも、この付近にある「浦島の足洗井戸」は探せなかったわ。


これは「浦島町浜公園」に描かれている壁画だよ。



日本全国に浦島太郎伝承地は150ヶ所以上あるとも言われてるんだって…



これは「神奈川通東公園」です…ココは昭和40年(1965年)に移転するまで「長延寺」という寺が建っていたそうで、この寺は開港当時「オランダ領事館」に充てられていました。

ここまでの主なルートだよ。


これは「良泉寺」です。

開港当時、諸外国の領事館に充てられることを快しとしなかった寺の住職は、本堂の屋根を剥がして修理中であるとの理由を口実にして幕府の命令を断ったと云われています。

京急のガードの先にも神社がありそうなんで寄ってみました。

これは「笠のぎ稲荷神社」(「のぎ」は禾偏に皇)です。


元寇に当たっては「北条時宗」より神宝を奉納されたという古社であります。



左側のキツネ様は巻物みたいの咥えてるね。



これは阿弥陀を主尊とする「板碑」だそうです。

これは“浦島寺”こと「慶運寺」です。



ココは開港当時「フランス領事館」として使われていました。

龍の口から流れる水をカメが受けている手水鉢です。


これは本堂です。


これは「浦島父子塔」です。


コレ、もしかして乙姫様?ただの菩薩様?


この中に太郎が乙姫様より賜った「聖観世音菩薩像」が安置されているんだって…乙ちゃ~ん




これは「成仏寺」です…ココは幕末期には外国人宣教師たちの宿舎となりました。

ヘボン式ローマ字を創始したことで有名なアメリカ人宣教師・医師の「ジェームス・カーティス・ヘボン」もこの寺に滞在しました。
「JIN-仁-」の2巻と15巻では、幕末期の横浜が舞台の回があるよ。



この「滝の川公園」には「明治天皇行在所之蹟」碑がありました…かつては神奈川宿として天皇も訪れるほど栄えていたってこと?



これは「浄滝寺」です…幕末期の横浜開港時には「イギリス領事館」に充てられていました。

妙湖尼が営んでいた庵に「日蓮聖人」が立ち寄り、妙湖尼が日蓮聖人に感服して寺院としたといいます。

それから京急線(写真)とJR線を横断して国道1号線へ…


これは「本覺寺」です…幕末の横浜開港時には「ハリス」が自ら見分け、横浜港が一望できることから「アメリカ領事館」となりました。

「横浜開港之首唱者 岩瀬肥後守忠震」の碑です。
「岩瀬忠震」は幕末に海防掛目付に任ぜられた後、外国奉行にまで出世し、開国論の中心的存在として活躍した人物です。

日米修好通商条約においてはアメリカ総領事「ハリス」に対し、下田奉行「井上清直」と共に交渉にあたり、ハリスの要求した江戸・品川・大坂などの開港希望地をしりぞけ、幕府百年の計のためにと横浜の開港を首唱したのです。

当時、山門はペンキで白く塗装され、この山門は後も震災・戦災を免れて現存しています。


「生麦事件」では負傷者(ウッドソープ・クラークとウィリアム・マーシャル)が逃げ込み、治療を受けました。



地蔵堂のお地蔵さま。


これは…子宝の観音様かな?

「慶運寺」以降のルートでーす。


それから「反町」から東急東横線に乗り「白楽」で降りました。



六角橋商店街・ふれあい通りを抜け…

これは「宝秀寺」です。


「日本武尊(やまとたけるのみこと)」が東征の時、ココの「大伴久応(おおとものきゅうおう)」という者の庵に泊り、翌朝「日本武尊」が五位木という木の六角の御箸を用い、これを久応に賜りました。

久応はこの箸に天照大神・日本武尊と書いて日夜礼拝したことから、村名を「六角箸村」と称し、後に「六角橋村」と改称したといいます。



「大伴久応」の庵が、現在の「宝秀寺」です。


これは「杉山大神社」です。

ココも「日本武尊」が御祭神になってるよ。

これは拝殿と本殿です。

これは舞殿です。


これは稲荷社です。



石仏です。


これは「祐天地蔵尊」です。


また「六角橋ふれあい通り」に戻り…


昼飯は「焼小籠包」(3個¥300)を食べたよ…中にスープがタップリ入ってて美味かった~

他に担担麺とかもあったんで食べてみたかったけどさ…どうも1人だと飲食に金かける習慣が無くて。

15時ごろ地元に戻り、献血してから家に帰ったけど…脚がヘロヘロになってたわ。

やっぱ長距離を歩くのは危険なのか


















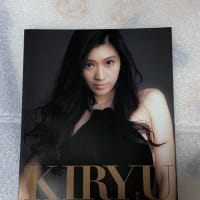




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます