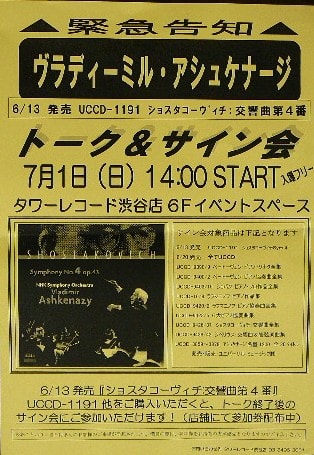最近なんだか忙しくて、ちょっとブログ更新意欲(体力?)が減退しています。
6月にあれやこれやコンサート入れたけど、
(6月に固まって来るし(涙))
行くのがおっくうになりつつあります。
ということで、実はあんまり予習をしなかったです。
それはともかく、
一曲目は、チャイコフスキー、イタリア奇想曲。
追加があったのは知ってたんですが、全然予習しなかったです(汗)。
何回かは聴いたことあるけど、全然覚えてなくて。
曲はイタリアというよりは、くるみ割り人形な感じ、つまり、
ロシアの冬の暖炉の前みたいな感じでした。
暖かくて楽しいんですが、全く太陽の匂いがしなかったです。
チャイコフスキーは全く太陽と無縁な感じの人だし、
プレトニョフも
You belong to the nightな感じの人だし、ロシアのオケだし、
イタリア~な感じを求めるのは無理だったのかもしれません。
でも、綺麗な曲でした。曲名とのギャップを気にせずに、
チャイコフスキーの可愛らしい曲というイメージで聴けばOKなんでしょう。
続いて、ラフマニノフ ピアノ協奏曲3番、ソリストは上原彩子。
今回ほとんど予習しなかったので、
実は、この曲をピンポイントで聴きに行ったのに近い状態だったんですが、
ひでぇ。
ハンガリー国立フィルの時ほどじゃないですが、
オケとピアノが全く合ってなかったです。
カデンツァとかは良かったんですけどね~。
テンポがしょっちゅうずれてたし、
オケとピアノの音のバランスが悪かったし。
上原彩子って音量無いんですかね?
他の曲より編成を小さくしたオケの音に負けてました。
ピアノが主旋律を奏でてるときに、特に大きくも無いオケの音にかき消されて
聞こえなくて。
パンフを見ると、RNO、来日してからこっち毎日コンサートやってます。
6/1もどこぞの音大でやったらしいです。
で、上原彩子との競演はこの日が初めて。
ということは、全然リハーサルやってないんじゃ?
ぶっつけか、当日の朝に1回やったか、そんなもんじゃないかと。
そういうことは往々にしてあるとは噂には聞いてますが、
高いチケット料金取るんだから、そういうことをするときは、
それでもちゃんといける演奏家でやって欲しいです。
昨日のラフマはあの値段で売り物にしてはいけないレベルでした。
まあ、チケットが高い理由の半分は円安のせいだと思うけど。
それでもねぇ~。
正直あれだけ聴きに行ったのに、あんな状態だったので爆死しました(涙)。
プレトニョフもやる気なさそうに、バーにもたれて指揮してましたしねぇ。
カーテンコールなんか一度も出てこなかったですよ。
まあ、本人も納得してないのかもしれませんね。
でも、ブラボーが飛ぶんですよねぇ。
ハンガリー国立フィルの時も飛んでたけど、
あれって何? 聴いてないの? 何でもいいの? 指が回ってればいいの?
お友達? 雇われブラボーおじさん?
それともチチが揺れてたからOK?
どうでもいいけど、上原彩子の衣装、チチが揺れてました(爆)。
上半身ホルターネックな感じのドレスで、
多分、ブラジャーもコルセットも無しで、ドレスの内側につけた
パッドだけだったんじゃないかと。
パーティーで着るならともかく、コンサート用の衣装にするなら、
特注でコルセット作った方が良かったんじゃないでしょうか。
なんかすご~く変な感じでした。
で、次はショスタコの交響曲第5番。
正直、ショスタコ大っ嫌いで。
意欲減退云々関係なく予習なんかしたくなかったです。
まあ、前にゲルギエフを聴きに行くために予習したし、
去年、ショスタコイヤーとかで耳にタコが出来るほど聞かされたし、
改めて予習しなくてもいいかな、とか思ってました。
これが、意外に良かったんですよ。
この日一番の出来かなぁ。
あんまりショスタコっぽくなくて、ちょっとプロコフィエフっぽくて
すごく聴きやすかったです。
まるたがショスタコ嫌いな理由の7割くらいが無くなってた感じがします。
そもそもそんなに聴きこんでないから、どこがどうって具体的に言えないんですが。
まるたがショスタコ嫌いな理由は、
あの気味の悪い繋がり方のメロディーと不協和音を
ヒステリックな金管と腹に響く低音で強調してるところなんですが、
昨日のは、曲が自然に響くテンポやイメージを設定し、
不協和音の中でも響きの綺麗な部分やつながりやすい部分を抜き出して強調してたように思います。
全体をそんな感じで作ってるから、強い音であの特有のメロディを出すところとの
コントラストがハッキリしてて、
強い部分は、自然に受け止めるのではなく何か特異な部分として聴けばいい、
という感じで聴けたんですね。
ふ~ん、意外と聴きやすくなるんだ、と思いました。
だからといって、これでショスタコのイメージが改善されたってことは
無いですけど。プレトニョフだからだと思うし。
こういうの聴くとやっぱこの人って曲の構成力高いなぁと改めて思います。
しかし、まるたはショスタコ嫌いなので昨日のは全くOKですが、
ショスタコのショスタコらしいところが好きな人に受けたかどうかは?です。
RNOはアジアツアーの殆ど毎日コンサートという無理な日程の割には、
疲れが出てなくて、音の揃いも良かったし、外したり、ひっくり返ったり、
遅れたりっていうのが殆ど無かったです。
ロシアのオケだけあって、やっぱり管楽器が良かったですね~。
金管がへたれてないのはもちろんだけど、
木管が良かったなー。オーボエの人がすごーく良かったです。
それから、
前にフェドセーエフのモスクワ放送響を聴きに行ったときも感じましたが、
やっぱり指揮者とオケの意思の疎通の仕方が客演でやるのとじゃ全然違いますよね。
東フィルとやるとどうしてもプレトニョフ特有のとっぴな部分が浮き上がってしまって、
変わってりゃそれでいいみたいな一部のクラヲタには受けるのかもしれないけど、
ちょっと全体的な統一感とかまとまりに欠けてしまう印象がありました。
RNOはさすがに長年付きあってるだけあって、
隅々までプレトニョフの解釈がいきわたっていて、
そこだけ取り出せばとっぴとも思える部分が、
全体の中で上手く流れに乗っているというか、
きちんと構成された一部分として存在しているように聞こえました。
最後にアンコールは
J.シュトラウスII ハンガリー万歳
グリンカかと思った(笑)。
ハチャトゥリアン レギンスカ
ボロディンかと思った(笑)。
どちらもノリのいい軽快な曲でした。
この辺りではプレトニョフもご機嫌でしたね。
やっぱラフマニノフは納得してなかったんでしょうねぇ。
いや、それってちゃんとリハーサルしなかったのが悪いわけだし。
つーことで、火曜日(だったかな?)にリターンマッチしてきます。
今度は曲目的にももうちょっと楽しめると思うんですが、
どうかなぁ。