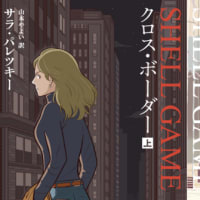ヘニング・マンケルといえば、
ヘニング・マンケルといえば、
クルト・ヴァランダーのシリーズがなんと言っても人気だ。
クルト・ヴァランダーはスウェーデンの南端の田舎町、
イースタの警察署に勤務する刑事で、事件を解決する手腕はすごいのだけど、悩める中年だ。
一方、『北京から来た男』はノンシリーズの単発物。
2014年に単行本として出版されたものの文庫化。
スウェーデンの寒村で、ほぼすべての村人が惨殺される事件が起きた。
女性裁判官のブリギッタは、亡くなった母親がその村の出身であることを知り、現場に向かう。
犯人は、なぜこのような凄惨な殺人を行わなければならなかったのだろう?
事件は思わぬ展開を見せ、アメリカの開拓時代、
19世紀の中国の寒村、現代中国の北京、
そしてアフリカのモザンビーク、ロンドンと、時代と世界をまたにかけて展開していく。
超大国になりつつある中国に対する分析が、説得力があり、面白い。
読後感は人それぞれだと思うけど、少し荒唐無稽という印象が残る。
ミステリの帰結としては万全ではないのかも…、と思ってしまう。
読み応えのある作品だった。
だけど、クルト・ヴァランダーのシリーズのほうが好きだなー。
クルト・ヴァランダーの何やかやと内省するところが好きなのだ。
 ヘニング・マンケルが初めてお目見えしたのは、2001年のこと。
ヘニング・マンケルが初めてお目見えしたのは、2001年のこと。
雑誌か新聞に書評が出ていてどうやら面白いらしい、ということで買って読んだ本だ。
たしかに読ませる。
そのころは、マイクル・コナリーのハリー・ボッシュのシリーズや、
ディック・フランシスの競馬スリラーが席捲していた。
イギリスの作家、R・D・ウィングフィールドの『クリスマスのフロスト』が訳出されて数年後のことだ。
そこにヒョロヒョロと迷い込んだように北欧の作家のミステリが文庫として出版された。
面白いじゃない! と思った。
あれから15年が過ぎ、その間に訳出されたヴァランダーものはすべて読んでいる。
そして、ヘニング・マンケルは間違いなく面白い優れもののミステリを届けてくれる、
親愛なる作家として確固たる地位を築いていった。
そりゃそうだろ。
何しろ、クルト・ヴァランダーのシリーズは35ケ国の言語に翻訳され、
2000万部以上を売り上げているという。
世界的な作家なのだ。
 でも、残念なことに、2015年に、ヘニング・マンケルは67歳で肺がんで亡くなっている。
でも、残念なことに、2015年に、ヘニング・マンケルは67歳で肺がんで亡くなっている。
「巨星、墜つ」とこの作家を翻訳出版していた創元社は追悼していた。
自分が入れ込んでいる作家が亡くなるのは淋しいものだ。
ミステリは、作家の息遣いを現在進行形で感じながら読むのがいい。
そういう活きの良さが、作品の魅力をかき立てると思うのだけど、どうだろう。