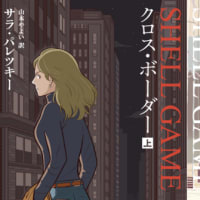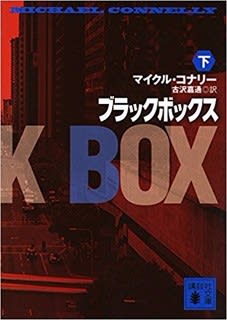

 ロス市警のハリー・ボッシュのシリーズのように、
ロス市警のハリー・ボッシュのシリーズのように、
主人公の人生そのものがミステリーの中心にすえられている小説の場合、
たまに取り上げられている事件が読者である自分の意にそわなくたって、
がっかりしたりはしないものだ。
もちろんこの本は、いつものように面白く読めたし、読みごたえもあった。
だけど、ロスの暴動に始まり、第一次湾岸戦争で時を遡り、
なおかつ大団円はヘリコプターとの応酬。
殺されたのは白雪姫と呼びたくなるような 色白で金髪の北欧美人のジャーナリスト。
こんなふうに大仕掛けなネタのわりに、そもそもの発端の事件が…。
じゃないか??
憎むべきは卑劣な男どもなのだが、若干消化不良の読後感が…。
でも、小説の出来が悪いと言っているわけじゃない。
 この本で印象的で素敵なのは、
この本で印象的で素敵なのは、
娘のマデリンが誕生日のプレゼントに贈ってくれた
アート・ペッパーのライブ録音コレクション。
それについて言及されている部分だ。
そのCDとは、最近リリースされた『未発表アート』で第一巻から六巻まである。
アートの未亡人がリリースさせたもので、
未亡人は「ウィドーズ・テイスト(未亡人の趣味)」というレーベルを持っているのだそうだ。
ボッシュが心に留めた演奏は 30年前にイングランドのクロウドンのクラブで録音された
“息を呑むくらい美しい「パトリシア」”
「一九八一年のこの夜、ペッパーは融通無碍だった。
この一曲で、だれも彼よりもうまく演奏できないことを証明している、
とボッシュは思った。
『この世のものならぬ』という意味の言葉を正確に把握しているとは思わなかったが、
心に浮かんできたのはその言葉だった。
その曲は完璧だった。サクソフォンは完璧だった。
ペッパーと三人のバンドのからみあいと意思疎通は完璧であり、
ペッパーの四本の指の動きとみごとに合っていた。」
そんなふうに作家であるコナリーは書いている。 そしてまたこんなふうにも。
「これは娘のことなんだ」ボッシュは言った。
マデリンは本越しに父親を見た。
「どういう意味?」
「この曲さ。『パトリシア』。アートは、娘のためにこの曲を書いたんだ。
娘の人生の長い期間、アートは彼女から離れていたんだが、
娘を愛しており、娘と会えないのを悲しんでいた。
それがこの曲から聞こえるとは思わないか?」
マデリンは少し考えてから、うなづいた。
「そうだね。サクソフォンが泣いているみたいに聞こえる」
 この部分を読んだとき、
この部分を読んだとき、
すぐにYoutubeでアート・ペッパーの「パトリシア」を検索して聴いた。
ボッシュの、ひいては作家であるコナリーの思いにダブらせながらアートの演奏に聞き入り、
そしてまた本を読んだ。
この音楽を共有する同時性というか、共時性がとても素敵だった。
そういう小説なのだと思う。