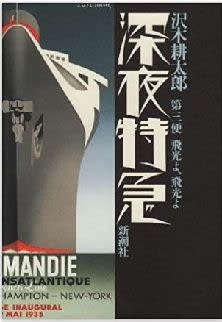この単行本「逆ソクラテス」は、集英社が2020年4月30日に発行したものです。

この単行本「逆ソクラテス」には、5編の短編が収められています。後半の「非オプティマス」「アンスポーツマンライク」「逆ワシントン」の3篇は、この単行本のために書き下したオリジナルです。
この後半の3篇は、同工異曲のような話です。主人公は小学生の高学年の仲間です。この主人公の小学生たちはいろいろと考え、体験します。“大人の人間関係”の入り口を体験します。
短編の「非オプティマス」の中では、担任のやや気弱な教師と見られていた久保先生が「みんなに覚えていてほしいことは、人は、ほかの人との関係で生きている、ってことだ」といい、いくらか話をした後で「人が試されることは、だいたい、ルールブックに載っていない場面なんだ」と話します。
他人に迷惑をかけることの意味合いを、小学生にかみ砕いて伝えます。
短編「アンスポーツマンライク」では、バスケットボール競技での、スポーツマンらしくないファールの“アンスポーツマンライクファール”をしてしまった小学6年生のバスケット仲間との話です。
バスケットボール競技のチームメイト5人は地元の中学から、それぞれ別々の高校に進学し、久しぶりに再会し、小学校6年時の試合を振り返ります。
その帰りに、無意味に弱い者を傷つけている犯罪者に出会い、この5人でこの暴漢を倒します。久しぶりのチームプレイでした。
さらに、数年後にこのチームメイトは再会します。バスケットボール競技のコーチングでは「型に嵌(は)めようとする指導者が多い」などと、子供の教育法を語ります。
このように書くと、この短編集は人間の生き方の教育法をストレートに書いているようにお感じでしょうか、短編のストーリーは複雑で話の展開が簡単には読めません。
この後半の「非オプティマス」「アンスポーツマンライク」「逆ワシントン」の3篇を読んで、作家の伊坂幸太郎さんは小学生時代からあれこれと考え、1971年生まれなので約50歳になっても悩み続けている様子が分かります。
こうした話の流れは、伊坂幸太郎さんの小説のテイストでは珍しいものです。軽い味わいで、話の流れが変化に富むというこれまでとは、違うものです。
この短編集は、人気ミステリー作家の伊坂幸太郎さんの変曲点なのかもしれません。
2010年代を小学生で過ごした子供たちは、昔と違って、スマートフォンを持ち、SNSを駆使し、Webサイトを閲覧しと、それ以前の昔の小学生と違って情報にあふれている世界を生きてきました。昔のような小学生とは違う、人生観を持って成長したことと思います。
前回、この伊坂幸太郎さんの最新刊の単行本「逆ソクラテス」をご紹介したには、2020年7月8日編です。ご覧ください。