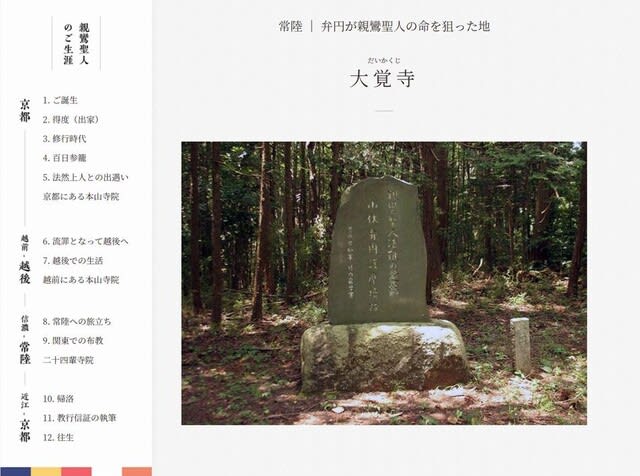え~と。。。今回は、コチラの「正月の記事」
「元旦は」「やっぱり京都の」「本山お参り」!! - 浄土真宗・他力信心の境地 (goo.ne.jp)
にてご紹介しました
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
「親鸞聖人生誕850年特別展」
に行ってきましたので、
さりげなく少しだけご紹介しておきますね。。。(^▽^;)ノ
・・・というのは。。。
まぁ・・・至極当然なのですが
「博物館内」は「撮影禁止」なので!!
ココで「ババン!!!!」・・・と出せる「お宝写真」もなく、
「南都北嶺のゆゆしき先生方」のように「ウンチク」を披露できるような「知識」
もありませんので、
「行くまでの道中」のみ
・・・を淡々と載せていこうと思います。。。(´・ω・`)ショボーン
まぁ、「雰囲気」くらいは感じ取れるかなぁ。。。
・・・ってコトで、よろしくお願いいたします。。。(o*。_。)oペコッ


・
・
・
・
・
・
・
🔶まずは「京都国立博物館」の場所から~♡ (≧∇≦)ノ

まぁ、こんな感じで、「最寄りの駅」がない、めっちゃビミョーな「場所」で。。。
しかも「京都駅」~「京都国立博物館」までは「約1.7キロ」
・・・とこれまた「ビミョーなキョリ」でさ。。。
普段鍛えている「れおん」にとっては、ワザワザ「交通機関」を使うまでもない位置関係のため、
とりあえず歩いていくコトにいたしました。。。( ̄▽ ̄;)ノ
🔶そして本山お参り~♡ (≧∇≦)ノ
目的は「親鸞聖人の名宝展」だけれども。。。
せっかく「京都」まで来て「阿弥陀様を素通りする」・・・ってのは、
ちょ~っと気が引ける・・・というか「有り得ない選択肢」だと思うので。。。(^▽^;)ノ
北へまっすぐ「本願寺」に直行です!! (`・ω・´)ゞ
( ^ω^)・・・。
・・・とは言っても、「お西」は「目的地の反対側」なので。。。
「東本願寺」のみの参詣でした。。。申し訳ないっす。。。(^▽^;)ノ
・・・ってコトで、境内に入ってみると。。。
というか「入る前」から「観光バス」も横付けされていて、
やけに賑やかだなぁ・・・と思ったら、、、
どうやら「イベント中」だったみたいです。。。ヽ(=´▽`=)ノ

((あ、行ったのは4月末ですので、コチラのイベントはもう終了しています。。。(´・ω・`)ショボーン))
まぁ・・・なんにせよ、
「お寺にヒトが集まる」ってのはイイことだね。。。(*・∀-)bグッジョブ

「お正月」は・・・ヒトがゼンゼン居なくて、閑散としていたから。。。( ;∀;)ノ
とりあえず「ちびっ子」たちがいて、ホッといたしました。。。(´;ω;`)ブワッ


この「お買い物広場」のプレハブなんだけれど。。。
コイツがココにいる(ある)せいで「建物の写真」がめちゃくちゃ撮りづらかったので、
そこがちょっと残念だったかなぁ・・・と。。。(^▽^;)ノ
でも、ぱっと見、
(後ろもお手洗いだし)ココに設置するしかないから仕方がないっすね。。。(´・ω・`)ショボーン
・・・ってコトで、
ココの場所のギリギリのところで撮った写真がコチラっす。。。(`・ω・´)ゞ
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓


まぁまぁ、、、なんとか撮れていると思いました。。。(*^。^*)ノ
🔶京都タワー~♡ (≧∇≦)ノ
「東本願寺」の「阿弥陀堂門」を出たところから「パシャリ」。。。(❀╹▿╹)ノ☆

「雲一つない」イイお天気でした。。。✌('ω'✌ )三✌('ω')✌三( ✌'ω')✌
🔶鴨川の風景~♡ (≧∇≦)ノ



もう「数百メートル」歩くと「目的地」の「京都国立博物館」です。。。(*´∀`*)ゞ
🔶京都国立博物館~♡ (≧∇≦)ノ
「親鸞聖人の看板」がデカデカと掲げてあるのですぐわかります。。。

写真は撮っていませんが、右手は「三十三間堂」です。。。
「帰りに寄ろう~♡」・・・と、思っていたのですが、、、
「親鸞聖人特別展」の「出品数」がボリューミー過ぎて、
時間が無くなってしまい行くことができませんでした。。。Σ( ̄ロ ̄lll)ガーン
・・・ってか、
「親鸞聖人展」をフツーに留まらずに見て回っても「2時間~2時間半」掛かるので、
ワリと早い時間から観光しないと時間的にかなりキビしいです。。。(lll-ω-)ズーン
お気をつけあれ!!!! (`・ω・´)ゞ
・・・ってコトで、「券売機となり」の「看板」。。。

そして「館内」までの「庭園」。。。





・・・ってコトで、
「写真」はココでお~しまい!! ( ;∀;)ノ
あとは。。。
みなさんが「親鸞聖人-生涯と名宝展」に足を運んで。。。
宗祖「親鸞聖人」の「御生誕」と
「親鸞聖人」がお伝えくださった「弥陀の本願成就のみ教え」を喜びましょう。。。(≧∇≦)ノ
2023年5月21日(日)まで開催していますので、
是非是非、ご覧くださいませ。。。(*- -)(*_ _)ペコリ

・
・
・
・
・
・
・
🔶最後に、たいして役に立たない個人的な忘備録。。。
「れおん」は、人間がもともと「しょ~もないヤツ」なので、
「歴史的背景」「学術的説明」や「伝記的エピソード」等は、
まったく語ることができません。。。( ;∀;)ノ
・・・が、すこ~し「所感」を書いておこうと思います。。。(^▽^;)ノ
🔹拝観料は、大人1,800円、大学生1,200円、高校生700円。。。
🔹博物館内すべてが「親鸞聖人関連」の「展示物」で、
まず、3階に案内されて、そこからぐるぐると1階まで展示されています。。。
🔹所要時間は、フツーに回って「約2時間強」かなぁ。。。(^▽^;)ノ
🔹出品数は全部で181点ですが、展示期間が異なりますのでご注意ください。。。
🔹全体的に「おぉ!!!!」って思う「名宝」は「高田派」のモノが多かったです。。。
🔹去年、群馬県に行ったときに
【2022年夏の旅(その2)】【群馬県邑楽郡板倉町「宝福寺」】 - 浄土真宗・他力信心の境地 (goo.ne.jp)
「宝福寺」というお寺を見学しましたが、
そのときに「カギ」が掛かっていて拝観できなかった「性信上人坐像」が展示されていました。。。
((9か月ぶりの再会だー!!・・・って、あのときは見てないんだケドね。。。(´・ω・`)ショボーン))
🔹以前、どこかの書き込みで「高田派のお坊さん」が・・・
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
「念仏を称えてください」と伝えているのは「念仏が往生の正因である」からです。
専修寺と本願寺の中で「往生の正因は信心なのか念仏なのか」という議論は、
覚如上人の時代から延々と議論され続けている所であります。
しかし「信心正因 称名報恩」は覚如上人がいいだしたことでありますから
「覚如上人の教え」ではありますが「親鸞聖人の教え」ではありません。
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
ってのを読んでいたので、
「覚如上人」の頃から「宗派間でイザコザ」があったのかなぁ。。。( ;∀;)ノ
・・・と思いきや、
「高田派」が「名宝」として大切にしている「親鸞聖人伝絵」の詞書が「覚如上人」だった
ので、ちょっとズッコケました。。。(笑)
「人間が言うコト」は「個人の都合」や「思い込み」が入っているから、、、
「れおんが思うコト」には「個人の都合」や「思い込み」が入っているから、、、
「見聞きしたすべて情報」を「参考程度」に留めておかないとなぁ・・・ってコトと、
やっぱり物事は「伝言ゲーム」よりも「百聞は一見に如かず」だよなぁ。。。
・・・とつくづく思いましたとさ。。。(*^。^*)ノ