いよいよ年末に突入ですね。
今日は下の息子と主人は、小田原から大阪の実家へ車で帰省。
すいていたようで、すいすいと行けたとのこと。
私は、昨日の深夜埼玉へ来て、今日は午後一から仕事。
3人の可愛い女の子たちに英語をたたきこみ、ランチ後はずっと上の息子としゃべりっぱなし。
というか、息子がずっと高校生活をしゃべる、しゃべる。
止まらない。
3時間はしゃべっていたかも・・・
いやあ、面白かったこと。
ゲラゲラ笑ってしまうほど面白かった。
ユニークで個性あふれる私立高校の先生たちの個々の説明から、テスト内容、文化祭までのクラスの様子。
息子の話から、レベルの高い先生たちがテストのうわべの点数だけではなく、内容までしっかり見て評価してくださっていることもわかった。
結果、息子がいかに今の学校に満足し、充実した日々を過ごしているかがわかった。
息子を含めた生徒会の1年生3人も生徒会活動もクラス活動や部活と両立させながら、必死に頑張っているようだ。
息子はせっかく大学付属校に入ったのだから、学業をこなしながら、「本当に自分のやりたいことに重きを置いてやる」というスタンスのようだ。
自分なりに考えてテスト勉強の配分もしているようだ。
この学業と部活や生徒会活動などの活動とのバランスをとるのはかなり難しそうな気がするが、息子は淡々とこなしている。
親としてはハラハラしながらついつい勉強のことを心配してしまうのだが、「まぁ、本人に任せるしかないな」と思う。
26日行われた早稲田大学での早稲田高等学院主催の討論会でもさまざまな高校生や大学生と知り合い、新しいネットワークを広げた息子。
百人弱の高校生が集まり、さまざまな議題で討論し、午後は個性的な大学生と交流し、刺激的な体験だったようだ。
厳しい経済情勢のため、内向きになっているといわれている大学生だが、息子の話を聞いていると、いくつもの会社を起業したり、海外に飛び出して日本語教師をしたりと積極的な大学生たちも多くいるようだ。
詳しく知りたい方は、息子のブログでの報告をぜひ読んでみてください!
なかなか面白いことを書いています。
http://blog.goo.ne.jp/yuyabaseball/e/55a02c224f66507a3113c40ec8964a5a
最近朝日新聞に連載されていた「いま子どもたちは――つながる」という興味深い特集を紹介しよう。
以下、朝日新聞12月26日付朝刊 p31より
最近の高校生の傾向として、「同世代として、高校生はいろんな人と合う機会が限られていると思う。他校の人との出会いなんて「塾が一緒」くらいしかなく、校内ですべて解決してしまう。遊びも部活も勉強も。「他校の人とつながらなくても十分楽しめる」というのが今の高校生じゃないかな。高校生団体は関東に20くらいある。出会う場がないというより意識の問題だと思う。」(水落有起)「高校生って基本的に現状に満足しているよね。」(矢田久美子}「満足の沸点が低い」(熊澤拓)
結局、二極化しているというわけか・・・
また、12月23日付けの同じ特集の記事では、博報堂・若者生活研究室原田曜平氏がネット社会の中での子どもたちの賢い生き方を指摘している。
「ネットで上で見ず知らずの人と交流しているというのは大人の勝手な想像。若者の方が怖さや面倒くささを知っている。(中略)子どもたちと実際に接していると初対面の人と関係を結ぶのが高いと感じます。(中略)でも、雇用も経済も不安定になり、人口が減って高年齢層が増えている社会で、若い子たちが安定志向になるのは、世の中を冷静に分析できているからだと思います。根性論的に、やみくもに経済成長を唱える大人や政治家より、よほど地に足がついているのではないでしょうか。」
うーん、大人たちが考えているよりも子どもたちは先の先を読んで行動しているのかもしれない。
恐るべし、君たち!
今日は下の息子と主人は、小田原から大阪の実家へ車で帰省。
すいていたようで、すいすいと行けたとのこと。
私は、昨日の深夜埼玉へ来て、今日は午後一から仕事。
3人の可愛い女の子たちに英語をたたきこみ、ランチ後はずっと上の息子としゃべりっぱなし。
というか、息子がずっと高校生活をしゃべる、しゃべる。
止まらない。
3時間はしゃべっていたかも・・・
いやあ、面白かったこと。
ゲラゲラ笑ってしまうほど面白かった。
ユニークで個性あふれる私立高校の先生たちの個々の説明から、テスト内容、文化祭までのクラスの様子。
息子の話から、レベルの高い先生たちがテストのうわべの点数だけではなく、内容までしっかり見て評価してくださっていることもわかった。
結果、息子がいかに今の学校に満足し、充実した日々を過ごしているかがわかった。
息子を含めた生徒会の1年生3人も生徒会活動もクラス活動や部活と両立させながら、必死に頑張っているようだ。
息子はせっかく大学付属校に入ったのだから、学業をこなしながら、「本当に自分のやりたいことに重きを置いてやる」というスタンスのようだ。
自分なりに考えてテスト勉強の配分もしているようだ。
この学業と部活や生徒会活動などの活動とのバランスをとるのはかなり難しそうな気がするが、息子は淡々とこなしている。
親としてはハラハラしながらついつい勉強のことを心配してしまうのだが、「まぁ、本人に任せるしかないな」と思う。
26日行われた早稲田大学での早稲田高等学院主催の討論会でもさまざまな高校生や大学生と知り合い、新しいネットワークを広げた息子。
百人弱の高校生が集まり、さまざまな議題で討論し、午後は個性的な大学生と交流し、刺激的な体験だったようだ。
厳しい経済情勢のため、内向きになっているといわれている大学生だが、息子の話を聞いていると、いくつもの会社を起業したり、海外に飛び出して日本語教師をしたりと積極的な大学生たちも多くいるようだ。
詳しく知りたい方は、息子のブログでの報告をぜひ読んでみてください!
なかなか面白いことを書いています。
http://blog.goo.ne.jp/yuyabaseball/e/55a02c224f66507a3113c40ec8964a5a
最近朝日新聞に連載されていた「いま子どもたちは――つながる」という興味深い特集を紹介しよう。
以下、朝日新聞12月26日付朝刊 p31より
最近の高校生の傾向として、「同世代として、高校生はいろんな人と合う機会が限られていると思う。他校の人との出会いなんて「塾が一緒」くらいしかなく、校内ですべて解決してしまう。遊びも部活も勉強も。「他校の人とつながらなくても十分楽しめる」というのが今の高校生じゃないかな。高校生団体は関東に20くらいある。出会う場がないというより意識の問題だと思う。」(水落有起)「高校生って基本的に現状に満足しているよね。」(矢田久美子}「満足の沸点が低い」(熊澤拓)
結局、二極化しているというわけか・・・
また、12月23日付けの同じ特集の記事では、博報堂・若者生活研究室原田曜平氏がネット社会の中での子どもたちの賢い生き方を指摘している。
「ネットで上で見ず知らずの人と交流しているというのは大人の勝手な想像。若者の方が怖さや面倒くささを知っている。(中略)子どもたちと実際に接していると初対面の人と関係を結ぶのが高いと感じます。(中略)でも、雇用も経済も不安定になり、人口が減って高年齢層が増えている社会で、若い子たちが安定志向になるのは、世の中を冷静に分析できているからだと思います。根性論的に、やみくもに経済成長を唱える大人や政治家より、よほど地に足がついているのではないでしょうか。」
うーん、大人たちが考えているよりも子どもたちは先の先を読んで行動しているのかもしれない。
恐るべし、君たち!


















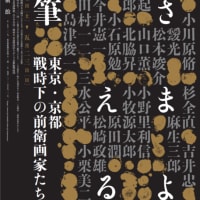
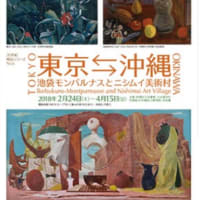
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます