*例によって、私の理解した、書けた範囲でのメモ。かなり部分的なメモです。
*私は講演部分のみ参加。質疑の部は不参加でした。
◼️情報組織化研究グループ月例例会
◾️背景
○「これからの学術情報システムの在り方について」(2015.5)
・電子情報資源のデータ管理・共有
・NACSIS-CAT/ILL の軽量化・合理化
◾️「共有」を目指して
○(1) 各機関→他の機関へ
・IRDB。「タイトル」レベルのメタデータは搭載されない。
・リンクリゾルバの重要性
↓
○国内にナレッジベースを「ERDB-JP」
https://erdb-jp.nii.ac.jp
・メタデータの登録やメンテナンスは、パートナー77機関によって自律的に対応(品質確保の課題)
- JAIRO Cloud 自動連携
・データフォーマット。米国情報標準化機構NISOが定める KBART (Knowledge Bases And Related Tools) を日本語用に拡張した「KBART拡張方式」で出力可能
(けれど、ヨミの項目がなかったりとか)
・CiNii Articles でもリンクが活用される。しかし、品質が…と。
○(2) 外から各機関へ
・印刷体に対する行き届いた管理が、電子リソースの場合は?
・リンクリゾルバやディスカバリーサービスがあろうとも、ナレッジベースを適切に管理しない限り、行き届いたサービスにはならない!
「ライセンス侵害」を引き起こす事態をさける。アーカイブ権の管理は、適切な資産管理に。
◾️商用システムにおける電子リソース「共有」機能の検証
○LSP
・商用LSP例
Alma (Ex Libris / ProQuest)
WorldShare Management Services (WMS) (OCLC)
Sierra LSP (Innovative Interfaces)
・OPAC、ディスカバリーなどで、ライセンス(利用条件)の表示が可能(APIで参照可能)。
◾️「共有」の展開:システムワークフロー検討作業部会の活動(予定)2019〜
(1) 統合的発見環境を可能にする新たな図書館システム
(2) 持続可能な運用体制の構築
(3) システムの共同調達・運用への挑戦
(4) メタデータの高度化
(5) 学術情報資源の確保
○業務量を増やさないよう、印刷体と電子リソースの区別なく運用可能な業務フロー
○新たな図書館システム、共同調達
・「中央システム」(NII)
・ローカルシステムも共同調達
◆ついにオフィシャルな場で出た⁉︎
○システムモデル検討作業部会
(1) 運用モデル・体制
コミュニティ形成、コスト負担
(2) 共同調達・運用
○システムワークフロー作業部会
(1-1) 中央システム整備:電子リソース対応
(1-2) 中央システム整備:メタデータ高度化
(2) 図書館システム整備
(3) ERDB-JP 運用
(4) CAT2020運用移行支援
○2019年度は、「中央システム」想定のLSPを利用して検証予定
◾️所感
・議論が想像より進んでいるという印象。
・システムの共同調達、共同利用と言えば、高専図書館がされていると随分前から聞いていますが、実際の話は聞いたことがありません。どこかで事例報告でもあればと。
・海外に目を移すと、北米では共同利用というのが散見されてきました。最近私が訪問した香港のいくつかの大学図書館、カナダ・ノバスコシア州の大学図書館のディスカバリーサービスの共用(?)も、よく似た事例でしょうか。
*私は講演部分のみ参加。質疑の部は不参加でした。
◼️情報組織化研究グループ月例例会
◾️背景
○「これからの学術情報システムの在り方について」(2015.5)
・電子情報資源のデータ管理・共有
・NACSIS-CAT/ILL の軽量化・合理化
◾️「共有」を目指して
○(1) 各機関→他の機関へ
・IRDB。「タイトル」レベルのメタデータは搭載されない。
・リンクリゾルバの重要性
↓
○国内にナレッジベースを「ERDB-JP」
https://erdb-jp.nii.ac.jp
・メタデータの登録やメンテナンスは、パートナー77機関によって自律的に対応(品質確保の課題)
- JAIRO Cloud 自動連携
・データフォーマット。米国情報標準化機構NISOが定める KBART (Knowledge Bases And Related Tools) を日本語用に拡張した「KBART拡張方式」で出力可能
(けれど、ヨミの項目がなかったりとか)
・CiNii Articles でもリンクが活用される。しかし、品質が…と。
○(2) 外から各機関へ
・印刷体に対する行き届いた管理が、電子リソースの場合は?
・リンクリゾルバやディスカバリーサービスがあろうとも、ナレッジベースを適切に管理しない限り、行き届いたサービスにはならない!
「ライセンス侵害」を引き起こす事態をさける。アーカイブ権の管理は、適切な資産管理に。
◾️商用システムにおける電子リソース「共有」機能の検証
○LSP
・商用LSP例
Alma (Ex Libris / ProQuest)
WorldShare Management Services (WMS) (OCLC)
Sierra LSP (Innovative Interfaces)
・OPAC、ディスカバリーなどで、ライセンス(利用条件)の表示が可能(APIで参照可能)。
◾️「共有」の展開:システムワークフロー検討作業部会の活動(予定)2019〜
(1) 統合的発見環境を可能にする新たな図書館システム
(2) 持続可能な運用体制の構築
(3) システムの共同調達・運用への挑戦
(4) メタデータの高度化
(5) 学術情報資源の確保
○業務量を増やさないよう、印刷体と電子リソースの区別なく運用可能な業務フロー
○新たな図書館システム、共同調達
・「中央システム」(NII)
・ローカルシステムも共同調達
◆ついにオフィシャルな場で出た⁉︎
○システムモデル検討作業部会
(1) 運用モデル・体制
コミュニティ形成、コスト負担
(2) 共同調達・運用
○システムワークフロー作業部会
(1-1) 中央システム整備:電子リソース対応
(1-2) 中央システム整備:メタデータ高度化
(2) 図書館システム整備
(3) ERDB-JP 運用
(4) CAT2020運用移行支援
○2019年度は、「中央システム」想定のLSPを利用して検証予定
◾️所感
・議論が想像より進んでいるという印象。
・システムの共同調達、共同利用と言えば、高専図書館がされていると随分前から聞いていますが、実際の話は聞いたことがありません。どこかで事例報告でもあればと。
・海外に目を移すと、北米では共同利用というのが散見されてきました。最近私が訪問した香港のいくつかの大学図書館、カナダ・ノバスコシア州の大学図書館のディスカバリーサービスの共用(?)も、よく似た事例でしょうか。















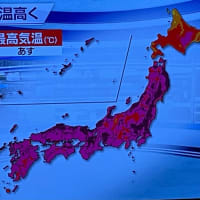
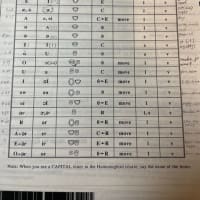









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます