・大阪大学 総合図書館
・講師: 上田晶子(名古屋大学・国際開発研究科)
上田先生が阪大で「アカデミック・スキルズ」の授業をされていた時、私もライティング講座等を担当していました。その授業を直接お手伝いしたのは別の同僚でしたが、当時いろいろと情報交換させていただいたこともあり、今回参加しました。
■自己紹介
○学部4年、イギリスのランカスター大学
・構成のしっかりした授業。Reading List 3-4ページ/1回
・"Essay" 何を書くの??
・"Argument"??
~ 日本の大学の「アカデミック」とイギリスの違い。
・Post Graduate Diploma (国際関係論、ランカスター大学)
・ロンドン大学
■イギリスの大学で強調されていたもの
1.Argument
2. Structure
3. Criticak Thinking
■Critical Thinking
・アメリカ人の友人とのエピソード
"子どもの頃からやっているので、あえて説明するのが難しい"
○ S. Cottrel "Critical Thinking Skills"
- Scepticism and trust 懐疑的でありながら
根拠に基づいた思考 "based on X, Y, Z".
- Method rather than personality trait 人の性格ではなく手法
○Critical = 批判的?
・「慎重に吟味する」
分かっていること、分かっていないこと
条件、前提、文脈
・さまざまな場面で
-情報源; 他のアーギュメントの評価;
○Critical に読む
- Structure
- Facts
- Assumption (憶説)
- Causal relations (因果関係)
- Correlation (相関)
- In-groups/ out-groups (含まれるものと、含まれないもの)
- Bias
- Reasoning (論拠)
○(悪い)サンプル
○Critical Thinking が追求するのは…
・正確さ; 論理性、合理性; 偏らない見方; 全体像と部分
・「主体的な、根拠に基づいた判断」こそがキモ
⇔ 鵜呑み
■ Argument アーギュメント
○「オピニオン」との比較
"Your ideas or beliefs about a particular subject" (Longman D)
"...not necessarily based on fact or knowledge" (Oxford D)
○「アーギュメント」
"a reason or set of reasons given in support of an idea, action or theory" (Oxford D)
"a point of view that has been articulated with the express purpose of convincing you or its valiadity or truth" (U of Essex の資料)
○アーギュメントの要素
・問題、課題:問題の背景
・証拠(主張を支える証拠。反証。あいまいな証拠)
*自分の主張を支える証拠は、積極的に使う傾向
*反証してみても、主張は成立するか。
反証は自分の味方: 自分の主張をより正確に記述できる
・根拠付け
・結論
○「事実」「オピニオン」「アーギュメント」の例
・「アーギュメント」
主張 + 証拠 + 根拠 + 結論
○根拠と論理
・「事実それ自体は意味をなさない。事実は文脈の中におかれ、分析と、説明をへて、はじめて意味をなすのである」
*) Adam Bonnett, How to argue, 2011
薄い本だが、内容充実
○なぜ「アーギュメント」が重要か
・「アーギュメント」は、ある主題についての知識を構築するのに貢献。
・「アーギュメント」を使うことは、知的・学術的な分析と知識の追求に積極的に関わること。
・「アーギュメント」の目的は、ある問題についての、自分の結論が正しいこと、あるいは、他の結論よりも、より真実=より深い理解に近い ことを示す。
■イギリスの研究室から
○
通りの名前「LOGIC LANE」
○博士課程時代の指導教官
「でも、その細かなデータが何を意味しているのか。発表全体として何が言いたいのかは、不明だった」(他の日本人発表者に対して?)
○
・アーギュメントとは、今の学界での議論に参加するもの
・だから、どこで行われているどの議論に参加しているのかを表明する必要
(先行研究レビューの重要性)
■いくつかの誤解(受講者からの反応)
○「一つの主張につながっていることは、その論文が偏ったものにならないか」
→ 主張をためらっている?
→ 知りうる全てを斟酌したうえで、知ることのできていない部分が分かっているなら、その結論は、限定されたものになるはず。"~の範囲でこういうことが言える"
・証拠として使う情報を慎重に吟味
・分析を慎重に吟味
・それによって出てきた結論というのは、学術的に一定の水準に到達しているはず。
○「この論文の学問上の貢献って、そんな大発見とか、壮大な理論ではないですけど」
→それでいいのです。
ヘンリー・バーンステインは、学問とは小さな煉瓦をひとつひとつ積み重ねていくようなものと言ったとか。
→ただ、よりよい貢献はある。
例、「この地域における、この研究はない」と言ってしまうより、
このような研究がないことで、学問上どのような不都合が生じているかを言った方がよいだろう。◆
例:この事象のこの側面が見えていないので、この事象の理解に偏りができてしまっている…
■博論執筆の大変さ…(上田先生の経験から)
・大変だったが、学問に対する楽しみ、知的なクリエイティビティ があった。
・博士進学を悩んでいる人がいたら、ぜひ勧めたいという心境。
・「アカデミック」なスキルを身につけたから、そう思えるのではないか。
■その経験を伝えるため「アカデミック・スキルズ」開講
・2012~2014年度 @阪大
○受講生の声
・大学は「学びの場」(vs.「試される場」、選抜される場)
真実を知る。『学術論文は知の貢献』
・働く中で人に何かを説明したり…
■最後に
■質疑
○
→(ライティング・セミナーで)論文に「スタック」しても、小休止せずに、あと5分考える。すると、次につながることが分かった。◆
・講師: 上田晶子(名古屋大学・国際開発研究科)
上田先生が阪大で「アカデミック・スキルズ」の授業をされていた時、私もライティング講座等を担当していました。その授業を直接お手伝いしたのは別の同僚でしたが、当時いろいろと情報交換させていただいたこともあり、今回参加しました。
■自己紹介
○学部4年、イギリスのランカスター大学
・構成のしっかりした授業。Reading List 3-4ページ/1回
・"Essay" 何を書くの??
・"Argument"??
~ 日本の大学の「アカデミック」とイギリスの違い。
・Post Graduate Diploma (国際関係論、ランカスター大学)
・ロンドン大学
■イギリスの大学で強調されていたもの
1.Argument
2. Structure
3. Criticak Thinking
■Critical Thinking
・アメリカ人の友人とのエピソード
"子どもの頃からやっているので、あえて説明するのが難しい"
○ S. Cottrel "Critical Thinking Skills"
- Scepticism and trust 懐疑的でありながら
根拠に基づいた思考 "based on X, Y, Z".
- Method rather than personality trait 人の性格ではなく手法
○Critical = 批判的?
・「慎重に吟味する」
分かっていること、分かっていないこと
条件、前提、文脈
・さまざまな場面で
-情報源; 他のアーギュメントの評価;
○Critical に読む
- Structure
- Facts
- Assumption (憶説)
- Causal relations (因果関係)
- Correlation (相関)
- In-groups/ out-groups (含まれるものと、含まれないもの)
- Bias
- Reasoning (論拠)
○(悪い)サンプル
○Critical Thinking が追求するのは…
・正確さ; 論理性、合理性; 偏らない見方; 全体像と部分
・「主体的な、根拠に基づいた判断」こそがキモ
⇔ 鵜呑み
■ Argument アーギュメント
○「オピニオン」との比較
"Your ideas or beliefs about a particular subject" (Longman D)
"...not necessarily based on fact or knowledge" (Oxford D)
○「アーギュメント」
"a reason or set of reasons given in support of an idea, action or theory" (Oxford D)
"a point of view that has been articulated with the express purpose of convincing you or its valiadity or truth" (U of Essex の資料)
○アーギュメントの要素
・問題、課題:問題の背景
・証拠(主張を支える証拠。反証。あいまいな証拠)
*自分の主張を支える証拠は、積極的に使う傾向
*反証してみても、主張は成立するか。
反証は自分の味方: 自分の主張をより正確に記述できる
・根拠付け
・結論
○「事実」「オピニオン」「アーギュメント」の例
・「アーギュメント」
主張 + 証拠 + 根拠 + 結論
○根拠と論理
・「事実それ自体は意味をなさない。事実は文脈の中におかれ、分析と、説明をへて、はじめて意味をなすのである」
*) Adam Bonnett, How to argue, 2011
薄い本だが、内容充実
○なぜ「アーギュメント」が重要か
・「アーギュメント」は、ある主題についての知識を構築するのに貢献。
・「アーギュメント」を使うことは、知的・学術的な分析と知識の追求に積極的に関わること。
・「アーギュメント」の目的は、ある問題についての、自分の結論が正しいこと、あるいは、他の結論よりも、より真実=より深い理解に近い ことを示す。
■イギリスの研究室から
○
通りの名前「LOGIC LANE」
○博士課程時代の指導教官
「でも、その細かなデータが何を意味しているのか。発表全体として何が言いたいのかは、不明だった」(他の日本人発表者に対して?)
○
・アーギュメントとは、今の学界での議論に参加するもの
・だから、どこで行われているどの議論に参加しているのかを表明する必要
(先行研究レビューの重要性)
■いくつかの誤解(受講者からの反応)
○「一つの主張につながっていることは、その論文が偏ったものにならないか」
→ 主張をためらっている?
→ 知りうる全てを斟酌したうえで、知ることのできていない部分が分かっているなら、その結論は、限定されたものになるはず。"~の範囲でこういうことが言える"
・証拠として使う情報を慎重に吟味
・分析を慎重に吟味
・それによって出てきた結論というのは、学術的に一定の水準に到達しているはず。
○「この論文の学問上の貢献って、そんな大発見とか、壮大な理論ではないですけど」
→それでいいのです。
ヘンリー・バーンステインは、学問とは小さな煉瓦をひとつひとつ積み重ねていくようなものと言ったとか。
→ただ、よりよい貢献はある。
例、「この地域における、この研究はない」と言ってしまうより、
このような研究がないことで、学問上どのような不都合が生じているかを言った方がよいだろう。◆
例:この事象のこの側面が見えていないので、この事象の理解に偏りができてしまっている…
■博論執筆の大変さ…(上田先生の経験から)
・大変だったが、学問に対する楽しみ、知的なクリエイティビティ があった。
・博士進学を悩んでいる人がいたら、ぜひ勧めたいという心境。
・「アカデミック」なスキルを身につけたから、そう思えるのではないか。
■その経験を伝えるため「アカデミック・スキルズ」開講
・2012~2014年度 @阪大
○受講生の声
・大学は「学びの場」(vs.「試される場」、選抜される場)
真実を知る。『学術論文は知の貢献』
・働く中で人に何かを説明したり…
■最後に
■質疑
○
→(ライティング・セミナーで)論文に「スタック」しても、小休止せずに、あと5分考える。すると、次につながることが分かった。◆















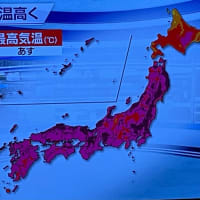
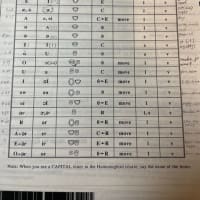









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます