(つづき)
*例によって、私の理解した、書けた範囲でのメモ。
■■アカデミックデータマネジメント環境での図書館員の役割(梶田、京都大情報環境機構)
*大学ICT推進協議会の年次大会はデータマネジメントの話題も出る?
2019年は12月12日(木)~12月14日(土)に福岡で開催
https://axies.jp/ja/conf
■自己紹介、研究者のコンテキスト
・どのような研究者も、論文発表へのプロセスでデータ管理を必ずしている。
■1.研究者ファーストとしたあるべき姿(私見)
○コンテキストの変化
・研究公正(京大ではデータは10年保存)
・オープンアクセス など
■2.研究データのための図書館
○「研究データのための図書館」からの23のアドバイス
■3.京都大学における研究データマネジメントに係る活動
○The Purdue University Research Repository (PURR)の紹介
https://purr.purdue.edu/
○京都大学
・2017年11月 アカデミックデータ・イノベーションユニット
・2018年度 「どういう研究データが京大にあるのか」基礎調査
・まずはボトムアップ的にスタート
<所感>
・研究者のコンテキスト、データ管理をどうしているかということを、図書館員はあまり知らないと思われます。もちろん全ての分野は無理として、実例をいくつか知っていると、議論の前提を知ることにもなるかと。
私も大学院生として、その一端を経験しつつありますが、
=======================
■■大学図書館によるオープンサイエンス支援:国内事例を作る(山中、京都大学附属図書館)
<2019.2.25 追記>
京都大学図書館機構がWebサイト「研究データの公開支援(試行)」を公開したようです。
https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/bulletin/1381108
■自己紹介
・WoSに Data Citation Index があることを知ったのをきっかけにデータ公表について、実感。
・ジャーナルの投稿規程に、データジャーナルへの投稿が触れられている。データジャーナルへの投稿料も必要。
■1.京都大学図書館機構が取り組むオープン化
○オープンアクセス推進事業
・プロジェクトチーム
■2.京大図書館における研究オープンデータへの取り組み
○研究公正、「データ保存サービス」
○検討開始の契機
・教員からの問い合わせ など
○図書館が関わる学内の検討体制
・アカデミック・イノベーション・ユニット; 図書館機構・オープンアクセス特別委員会; 工学研究科・オープンデータ検討WG
○検討結果:まず取り組むこと
・桂図書館での支援業務
・論文のエビデンスデータ公開を、まず行う
・利用者への情報提供(Webサイト作成中)
○今後
・データリポジトリの検討
・研究データ取り扱いガイドライン
・関連部署 など
○職員の研修成果活用
○データリポジトリの検討
機関リポジトリを改修か、クラウド移行か、研究データはクラウドか
○教員から寄せられた意見
いろいろもっともな声
説明対象者の明確化、過不足ない資料
○オープン化だけでも、やるべきことが多い
・研究公正だけでなく、倫理審査規程も見ておく方がよい。
○データマネジメント全般は?
○検討の方向性
・いまできること、今いる図書館員ができること
・これか図書館ができること、新たな職種(人材配置)が必要なこと
~これらを分けて考えると、建設的な議論ができるのでは。
=======================
■■パネルディスカッション
○竹内: 梶田講演で「絵が描けている」ことに感銘。関わろうとしている人が関わりやすい。
○参加者:国立大学図書館の採用試験のあり方は。
○竹内:伝統的なライブラリースクールは絶滅危惧種。iSchool が大きな流れだろう。
どう雇用するかは大きな課題。ゼネラリスト的に取るのはどうにかしたいが、100人単位で図書館職員がいる大学はいいが、千葉大で10人規模のチーム? 職員の半分になってしまう。
○参加者: 京大のユニットの活動で基礎調査アンケート。具体的に。
○梶田:10問あまり。最後まで回答した人は200人あまり。5件程度をヒヤリング予定。
○参加者: 論文のエビデンスデータを当面の対象と。例えばどのような分野など傾向や、戦略など。
○山中: まずは理系(だったかな)
○司会者: 何をすべきという面もあるが、ハゲタカジャーナルには出さないようになど、避けるべきことを周知することも。
養成の面では、会計士の学び直しプログラム。10年ほど前に国際会計基準に。
*例によって、私の理解した、書けた範囲でのメモ。
■■アカデミックデータマネジメント環境での図書館員の役割(梶田、京都大情報環境機構)
*大学ICT推進協議会の年次大会はデータマネジメントの話題も出る?
2019年は12月12日(木)~12月14日(土)に福岡で開催
https://axies.jp/ja/conf
■自己紹介、研究者のコンテキスト
・どのような研究者も、論文発表へのプロセスでデータ管理を必ずしている。
■1.研究者ファーストとしたあるべき姿(私見)
○コンテキストの変化
・研究公正(京大ではデータは10年保存)
・オープンアクセス など
■2.研究データのための図書館
○「研究データのための図書館」からの23のアドバイス
■3.京都大学における研究データマネジメントに係る活動
○The Purdue University Research Repository (PURR)の紹介
https://purr.purdue.edu/
○京都大学
・2017年11月 アカデミックデータ・イノベーションユニット
・2018年度 「どういう研究データが京大にあるのか」基礎調査
・まずはボトムアップ的にスタート
<所感>
・研究者のコンテキスト、データ管理をどうしているかということを、図書館員はあまり知らないと思われます。もちろん全ての分野は無理として、実例をいくつか知っていると、議論の前提を知ることにもなるかと。
私も大学院生として、その一端を経験しつつありますが、
=======================
■■大学図書館によるオープンサイエンス支援:国内事例を作る(山中、京都大学附属図書館)
<2019.2.25 追記>
京都大学図書館機構がWebサイト「研究データの公開支援(試行)」を公開したようです。
https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/bulletin/1381108
■自己紹介
・WoSに Data Citation Index があることを知ったのをきっかけにデータ公表について、実感。
・ジャーナルの投稿規程に、データジャーナルへの投稿が触れられている。データジャーナルへの投稿料も必要。
■1.京都大学図書館機構が取り組むオープン化
○オープンアクセス推進事業
・プロジェクトチーム
■2.京大図書館における研究オープンデータへの取り組み
○研究公正、「データ保存サービス」
○検討開始の契機
・教員からの問い合わせ など
○図書館が関わる学内の検討体制
・アカデミック・イノベーション・ユニット; 図書館機構・オープンアクセス特別委員会; 工学研究科・オープンデータ検討WG
○検討結果:まず取り組むこと
・桂図書館での支援業務
・論文のエビデンスデータ公開を、まず行う
・利用者への情報提供(Webサイト作成中)
○今後
・データリポジトリの検討
・研究データ取り扱いガイドライン
・関連部署 など
○職員の研修成果活用
○データリポジトリの検討
機関リポジトリを改修か、クラウド移行か、研究データはクラウドか
○教員から寄せられた意見
いろいろもっともな声
説明対象者の明確化、過不足ない資料
○オープン化だけでも、やるべきことが多い
・研究公正だけでなく、倫理審査規程も見ておく方がよい。
○データマネジメント全般は?
○検討の方向性
・いまできること、今いる図書館員ができること
・これか図書館ができること、新たな職種(人材配置)が必要なこと
~これらを分けて考えると、建設的な議論ができるのでは。
=======================
■■パネルディスカッション
○竹内: 梶田講演で「絵が描けている」ことに感銘。関わろうとしている人が関わりやすい。
○参加者:国立大学図書館の採用試験のあり方は。
○竹内:伝統的なライブラリースクールは絶滅危惧種。iSchool が大きな流れだろう。
どう雇用するかは大きな課題。ゼネラリスト的に取るのはどうにかしたいが、100人単位で図書館職員がいる大学はいいが、千葉大で10人規模のチーム? 職員の半分になってしまう。
○参加者: 京大のユニットの活動で基礎調査アンケート。具体的に。
○梶田:10問あまり。最後まで回答した人は200人あまり。5件程度をヒヤリング予定。
○参加者: 論文のエビデンスデータを当面の対象と。例えばどのような分野など傾向や、戦略など。
○山中: まずは理系(だったかな)
○司会者: 何をすべきという面もあるが、ハゲタカジャーナルには出さないようになど、避けるべきことを周知することも。
養成の面では、会計士の学び直しプログラム。10年ほど前に国際会計基準に。















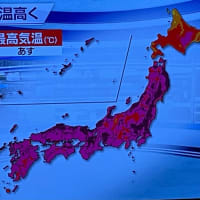
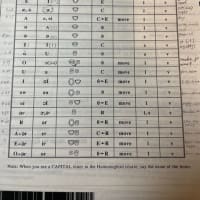









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます