年金コラム③
「共済制度について」の研修会において
先日(1月14日)神奈川社労士会年金研究会相模ブロックで、共済年金の制度等について研修会が座間市民会館内で行われました。
講師は、元大蔵省主計官でおられた、関根先生。講義の教材は、先生のお書きになられた共済制度(医療・年金)ガイドブック。とても判りやすく、社労士合格者なら充分理解可能な本です。
さて、今日のコラムは共済年金の紹介がメインではありません。ご講義の中で最近期の公的年金の一元化議論が取り上げられました。かかる一元化議論が4年以上もかかっても今だに結論をえていないとのこと。これは、周知のことでしょう。
そこで、話の中で一元化に反対しているのは、むろん、官公庁側ですが反対議論の大きなポイントは3階部分である「年金の職域加算部分」がカットされることにある様です。
具体的な反論の1つに、「民間部門には、DCやDBという3階部分の年金制度があるじゃないか!」「共済年金制度にはかかる部分はなく、また、加入もできない」ことを指摘していました。上記の反論をきくと、普通の人々は素直に信じてしまいがちです。ここで断っておきますが私は、DB(Defined Benifit Plan)確定給付企業年金&DC(Defined Contribution Plan)確定拠出年金自体は、教科書に載っている通り年金の3階建てと称するのは誤りと言っているのではありません。⇒私自身は、DBやDCは中二階部分と考えていますが・・。
↓
というのは、企業はDCやDBを導入するにあたり、退職給付(退職金)を全額もしくは50%
等減額したその見合いで実行しているのです。従来の満額の退職金を支給した上でのDCでないことは言うまでもありません。
↓
一方公務員は、通常平均約2,900万円の退職金を受領しているという。その上で報酬比例部分(基礎年金はむろん支給)の退職共済年金が支給され、加えて、職域加算が(報酬比例部分の約2割相当←勤続20年以上)受給できるのです。
↓
従って、上記の一元化議論の中で、民間の私的年金とを比較する際に、DBやDCを職域加算と同様の3階建てとして扱うことが誤りといっているのです。
ましてや、DC自体、加入者は4百万人強であり、全体の雇用者約54百万人から公務員の数を引いた約5千万のうちですから、民間労働者全体の8%(正規労働者の十数%)しか 該当者がいません。
↓
ところで、DCには、企業型年金(掛金は事業主が拠出)と個人型(自営業者等が加入)年金がありますが、この個人型に至っては、そもそも2階建てに相当する厚生年金が原則ないので、3階になる筈がありません。だからこそ、私は「中二階年金」といっているのです。
↓
今後とも、新聞誌上で、年金制度につき議論がされることでしょう。が、決して、誤解のなき様、せめて、社労士だけは各種カラクリをあばくべきと考えます。最後に、年金制度も、このままの給付水準で行く限り、数年で破綻する懸念もある様です。新聞誌上で、繰上げ支給を推奨する記事も散見されています。ひょっとして、繰上げ受給申請は、的を得た選択かも知れませんヨ!!
結論は、将来において・・・?。
Toshi-rinkan












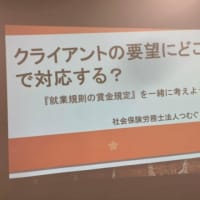







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます