 特徴がないエダシャク幼虫の典型ナカウスエダシャク幼虫
特徴がないエダシャク幼虫の典型ナカウスエダシャク幼虫2016年の連休明けに琵琶湖博物館に出勤すると、5月1日大津市園城町のキリシマツツジで武田さんが見つけた黒っぽいエダシャク幼虫が届いていた。一緒にヤガなど他の幼虫も数種あったが、寄生蠅におかされており羽化しなかった。大分医大に転勤して、大分市の低山地で採った幼虫からやはり寄生蠅が多く出て、未だに何の幼虫かわからない写真がたくさん残っている。
不思議なことに12年暮らした九重町地蔵原は、大分市など低地と比べると寄生蠅が少なく、その代わり寄生蜂特にコマユバチがよく出た。私はファーブルの影響もあってハチも好きな昆虫であり、特にコマユバチは生態が面白いので、また私が一目置いて張り合っているファーブルはコマユバチの真の面白さをどうやら知らなかったようなので、余力があれば前に飼育し生活史がわかっている蛾の幼虫も何度も繰り返して飼育し寄生蜂が羽化するのを楽しんだ。
第6巻のシャクガ上科の紹介で書いたように、①シャクガ科の先祖は尺取り虫型歩行する細長い幼虫の体形と、②それに伴う枯れ枝などに擬態する方向に一斉に進化した。だからこの科の幼虫は互いに似ている。特にエダシャク亜科の幼虫は区別が難しい。ツツジのエダシャク幼虫も以前飼ったようにも思うし、また初めて出会ったようでもある、つまりありふれた小枝に擬態している平凡な幼虫だ。かれらは目立たぬようにひっそりと暮らしており、危険を察知すると突然、落下する。しかしふつう糸を吐いてぶら下がり、敵が立ち去ると糸を手繰って元の場所に戻ってくる。小学校低学年のころ先生が質問するためみんなを見回すとき、私は目立っても叱られ、目立たなければハキハキしろとまた叱られた劣等生だから、擬態する虫の心がよくわかる。
図版1~2は5月7日撮影した体長30mmの幼虫である。黒っぽい幼虫であるが写真を少し修整して斑紋を識別できるようにした。写真1は側面、2は背面である。5月9日脱皮は確認できなかったが体長33mmを超えたので写真3を撮った。地色が少し変わり赤みを帯びている。5月16日とうとう蛹化した。少し糸を吐いた形跡があったが、蛹は飼育容器の底に転がっていた。体長12mmである。5月28日雌のシャクガが羽化した。調べてみるとナカウスエダシャクAlcis anguliferaだった。図版の写真6はその個体ではなく、羽化した個体は展翅中なので地蔵原高原産雌の写真を掲載した。
この蛾は普通種の代表で低地から平地まで採れており、個体数も多い。幼虫もよくわかっており、バラ科、ブナ科、ツツジ科、マツ科など様々の植物を食べる。もっとも私自身が本種を飼育・羽化させたのはこれが初めてである。しかしこんな普通種の幼虫を飼い写真を撮ったことがまったくなかったとは思えない。調べれば私の膨大な写真ファイルに1枚ぐらい残っているかもしれない。これと言って特徴のない幼虫が多いエダシャク幼虫の中でももっとも代表的な幼虫の一つである。
鱗翅目の幼虫の色彩はいつも書くように変異が多い。明らかに気温や湿度が関係しており、高温・多湿の時期は黒っぽく、逆に涼しい時期は色が淡くなる。幼虫の研究者は本州に多い。たまたま私は九州に住んで同じ種の幼虫の食性や色彩変異を観察することができた。私が昆虫記を書き始めたのは本州の人が常識だと思うことが九州では通じないことがママあることに気付いたからだ。










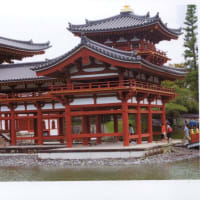
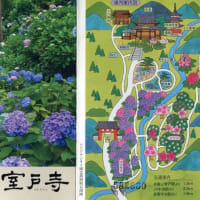








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます