 ザトウムシ(座頭虫)の話
ザトウムシ(座頭虫)の話九重町地蔵原で見かけたクモを写真に撮っていたので、パワーポイントでアルバムを作りまず自分で同定した後、クモの研究者関根幹夫さんに同定していただいた。アルバムの最後の図版は九重山系で見かけた2種のザトウムシであった。関根さんはその2種はカイキザトウムシ亜目の1種と書いており、種名はわからない。漢字をあてると怪奇座頭虫かなと思った。インターネットで調べるともう一つヘイキザトウムシ亜目がある。こちらは兵器座頭虫かな?
私はザトウムシという名と外観を知っているだけなので、この機会にフリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』などを参考にザトウムシとは何かわかったことを紹介しよう。
ザトウムシ類は節足動物門クモ綱ザトウムシ目に属する。最古の化石記録は4億1千万年前(デボン期に相当)のものがあり、3億年以上もの間それほど形が変わっていないらしい。なお日本からは81種のザトウムシが記録されているそうだ。
私の見た2種のうち一つは米粒大の体に恐ろしく細く長い針金状の脚が4対あり、前方に向かって脚で探りながら歩くから体が前後にゆっくりとゆらゆら揺れる。アメリカなどでは「足長おじさん」と呼ばれているらしい。座頭虫は盲人が杖で前を探りながら歩く姿と似ているのでついた名前だそうだ。これは葉の上にいることもあるが、九重自然史研究所の常設夜間採集設備の付近や幕の上でも時々見かけた。小さな虫を食べているらしい。
もう一つの種は写真2に示すように胴体が大きく、体は頭胸部と腹部からなり、頭胸部と腹部との間や腹部の体節は明瞭で、クモ類のような腹柄はない。写真は九重山系黒岳御池で撮影した。この種の脚はそれほど長くなく、静止している時は写真のように腹面は葉に接している。背面の中央近くに、一対の単眼があるそうだ。頭胸部の背面はキチン質の丈夫な背板に覆われる。カイキザトウムシ類は、頭胸部と腹部の背板は分かれている。
付属肢は頭胸部に6対あり、1対の鋏角と触肢、4対の歩脚をもつ。身体の前端に短い鋏状の鋏角があり、口はその間の腹面側に開く。 鋏角は3節からなり、先の2節が鋏を構成する。これは餌をつかみ、引き裂くのに用いられ、他の付属肢を清掃するのにも使うとある。ザトウムシ類は、クモ綱のなかでは例外的に雄がペニスを有し、真の交尾を行う。雌雄は向き合って、腹面を触れ合う形で交尾をする。クモの場合は交接といい雄が雌の生殖口に触肢にためた精子を注入する。
なお最新のコンピューター技術により、フランスの鉱床から見つかった2種の化石を基に3Dモデルを制作した結果、3億500万年前から現在と同じ不気味な姿をしていたことがわかったそうだ。そのチームの一員でロンドン自然史博物館の古生物学者ラッセル・ガーウッド(Russell Garwood)氏は、これらの化石は「炭酸鉄の塊である菱鉄鉱の中に保存されていた」もので、この鉱物は「岩石の生成初期に沈殿するもので、ときとして生物の死骸の周囲に沈殿し、(死骸が)押しつぶされるのを防ぐ。その後、死骸は朽ち果て、生物の形をした空洞が残る」という。ところで下線を引いた部分から判断するとやはり外国人も怪奇な生き物だと考えているようだからもしかすると漢字は怪奇座頭虫かもしれない。
追記
ザトウムシの記事をインターネットで調べたがカイキ亜目とヘイキ亜目がなぜか片仮名表記されており、どんな漢字を当てるのかわからなかった。分類学用語だからラテン語かもと思いラテン語辞書を引いたがわからなかった。外国人も怪奇な虫と書いているし、中には槍のような突起を持っているものもいる。それで怪奇座頭虫と兵器座頭虫かと思ったが、念のため関根さんに尋ねると実は開気と閉気であった。わかったときはもう怪奇と兵器と書いたブログを公開してしまっていたと信じていたが実はまだ公開していなかった。そこで公開するにあたりわざとオリジナルなブログと追記をつけることにした。なぜならこの間違いは私が間違った例の中でも一番の傑作だからだ。










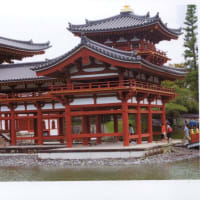
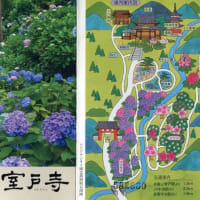








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます