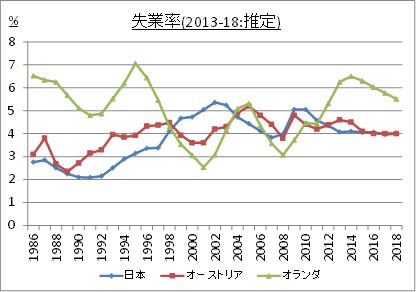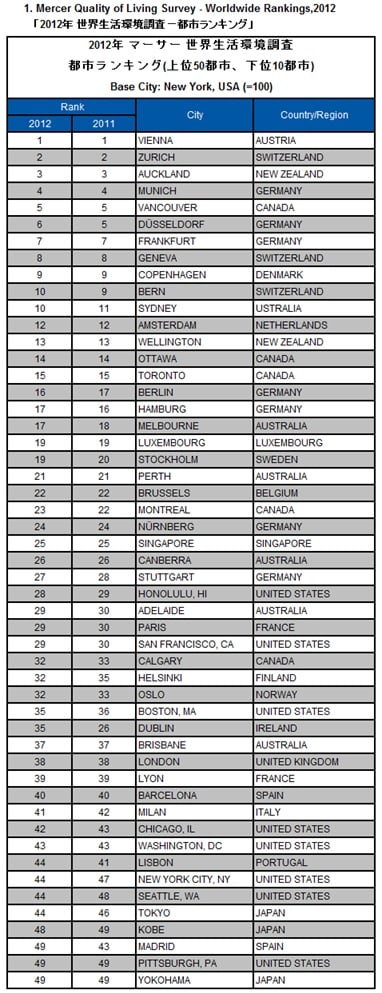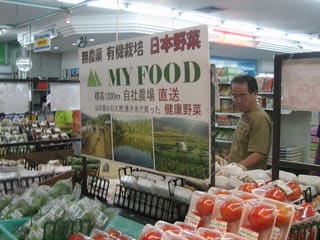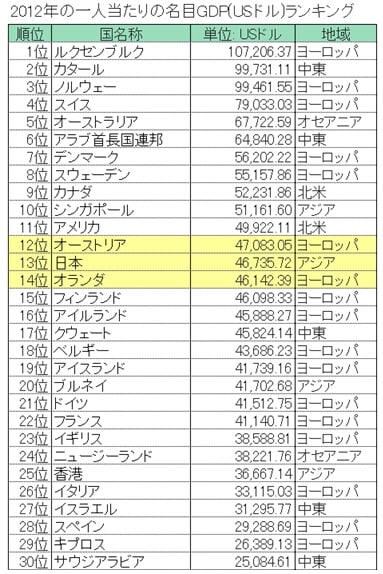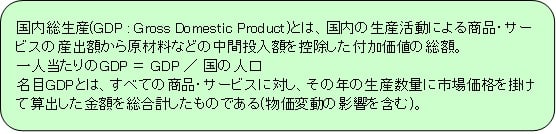前回からの続き。
5)社内外との人事交流
ほぼ1年にわたって展開したクリーン・コンピューター作戦の仕上げは、次期工場システムを開発するジョイント・プロジェクト・チームの編成だった。
次期システムの詳しい内容は省略するが、その範囲と機能はこのブログに示した「工場のビジネスモデル(2011-12-11)」と「工場機能の階層図(2011-12-25)」のとおりだった。その工場を管理する手法は、アメリカ生まれのMRP【注】だった。MRPは、コンピューターの性能が向上するにつれて欧米で普及した生産管理手法、この手法を日本流にアレンジするのがジョイント・プロジェクト・チームの目標だった。
【注:MRP(Material Requirements Planning:資材所要量計画)は60年代にアメリカで開発された生産管理手法、今日では世界に広く普及している。このジョイント・プロジェクトが開発したシステムは、日本初のMRPだった。】
このプロジェクト・チームは、システム系と工場系の要員で編成した。システム系の要員は電算室、子会社のシステム部門、コンピューター・メーカーから、工場系の要員は本社と子会社の生産管理、生産技術、品質管理、技術管理、製品開発、購買などの主任クラスから、それぞれ選出した。最終的にはシステム系は約30名、工場系はコンサルタントを含む約30名の規模になった。
特に、アメリカ人のコンサルタントのうち、1名はデータベース技術、1名はコンピューター・システム・パフォーマンスの分野で世界トップ・クラスのエキスパートだった。
異なった社内経験をもつ若い人材を一つのプロジェクトに統合して、互いに未知の知識・経験を身に付けさせる。これは、先進的な工場システムとそれを担うコンピューターに明るい人材を育成しようとする経営陣の願いだった。このような経営陣は、当時の日本では珍しかった。
工場本館に開設したプロジェクト室を基地として、メンバーはシステムのロジックと工場の運用ルールを設計した。先端技術の導入とはいうものの、日本のビジネス習慣との調和も大切、生産現場との意見交換を重ねて皆が納得するシステム設計を心掛けた。
もともとシステム開発担当者たちは、見よう見まねで覚えた仕事のやり方だった。しかし、社外のトップ・クラスの専門家と机を並べて新しいシステムを開発する機会は、学校では得られない貴重な体験だった。数年にわたるこの機会に、システム系や工場系の区別もなく、メンバーたちは一から出直す気持ちで新しい考え方のシステムに取り組んだ。
また、工場運営については、当時の国連加盟国より多い160ヶ国に製品を提供する会社として、世界に通用する生産管理を目指した。
日本の生産管理用語には、企業ごとの方言が多い。この機会に用語の標準化を進めた。APICS(American Production and Inventory Control Society:米国生産在庫管理協会)の用語集と日本の大学による和訳にもとづいて用語解説書も作成した。APICSを通じて、国際的な生産管理のスタンダードに接した・・・何事も基本を知らない自己流は伸び悩むが、基本を踏まえた上での自己流は大きく伸びる。
結果として、たとえば、「大量の仕掛品在庫&受注製品の欠品」(Before)⇒コンピューター・システム
⇒「仕掛品在庫の減少&受注製品への即応」(After)=無駄のない工場が実現した。
プロジェクトが進むにつれて、チーム・メンバーはシステム導入の準備と工場現場の改善に時間を振り向けた。たとえば、社内外の部品搬送コンテナー(通い函)の標準化、生産指示書や注文書のバーコード化、生産基礎データの作り込みなど、素材加工、機械加工、表面処理、最終組立にまたがる作業は膨大だった。
このシステムは、経営陣からのトップ・ダウンで開発した戦略システム、10年近くの歳月で全面的に稼働した。それは、下からのボトム・アップで開発する合理化システムとは異質のシステムだった。
素材加工工場からパイロット導入を始め、導入が進むにつれてプロジェクト室からメンバーが一人一人と新しい職場に移っていった。元SEの生産管理課長、元生産技術のSEなどと人材の社内交流が実現した。
新しい担い手を得た新しいシステムが定着するにつれて、期待効果は定量・定性の両面で予想を上回った。また、雨後の竹の子のような旧システムを一掃した・・・新しいぶどう酒は新しい革袋に・・・新約、マタイ、9章、17;ルカ、5章、38。
以上で「変化に直面して、いったん立ち止まり、体制を整えて、ことに当る」という一つの事例を紹介した。この事例では、先端技術の導入、チーム・メンバーと工場の順応性、経営陣のリーダーシップの3つが相乗してプロジェクトは成功した。先端技術、順応性、リーダーシップがキー・ワードである。
この事例とはスケールの違う大きな変化に直面している今日、ここでコーヒー・ブレイクを取る。次回はさくらの咲く頃、3月25日の「日本の将来---5.展望(1)」に続く。