
原発事故の収束は、冷却機能安定という大きな目標までの道筋さえ見えない状態が続いている。
やはり、東電とか政府(保安院)などよりも、原発設備メーカーのノウハウに頼るほかないことがはっきりしてきた。
東芝、日立も、それぞれに廃炉計画案を出してきたが、
これらのメーカーは、米仏をはじめとする海外原発メーカーとの付き合いも深いので、期待できると思う。
「最短10年で撤去し、更地に戻す」と頼もしい限り。ぜひ、そうあって欲しい。
避難所のnewsでは、まだまだ過酷な環境の中で、先の見えない生活が続く。
その中で、最近は助け合い、感謝といった面が多く報道されるようになってきた。
マスコミも、やっと冷静に事態を観る余裕ができてきたのだろう。
過酷な復旧作業、高齢者が多い避難所では、自衛隊、ボランティア、自治体の救援など、人間としての”言葉・思い・行い”に心からの感動を覚える。
よく、神様は”耐えられない試練は与えない”という。
聖書:ローマ人への手紙5:1-5で
「苦難は忍耐を、忍耐は練達(品性)を、練達は希望を生む」
しかし、一瞬にして犠牲になった方々にとっては、実に空しい言葉だ。
これは、残された被災者の方々に向けた言葉になるが、希望を手にするまでの道のりは苦しい闘いの連続になる。
今、いろんなところで生まれている善意は、とても信じられないほどの、ある意味で奇跡でもあると思う。
海外20ケ国、地域からも、救助隊、医療隊、原子力専門家が現地に入り、40ケ国からの支援物資が届いているという。
スコップで必死に瓦礫を撤去する海外ボラランティア、涙を流しながら哀悼歌を合唱するケニアの少女たち、貧しい生活の中から寄付金も。
米軍2万人の「ともだち作戦」でも、さすがに隣人愛に富むお国柄、その救助、捜索する姿には尊敬の念を覚えた。
身近にも、アメリカからの義援金で、日常品を持って現地に向かった牧師さんたちや同級生でボランティア登録している人たちがいる。
苦しみの中では、国を問わず、人間としての絆、地球市民という言葉が、実感できる。
それにしても、こういった危機でしか、政治、経済、社会のいろんな面での本質があぶりだされないというのは、何とも歯がゆい。
危機に際して、頼りになるのは、日頃から現場・現実に目を向けて、地道に使命感を持って働いてきた人たちだと、改めて思う。
結論ありきの原発ルネサンス、親方日の丸の東電、足の引っ張り合いの政治家たちの無能さ、こういった大きなシステムに巣食う人たちの質が問われなければならない。
追記:2011.4.16
昨夜、マイケル・サンデル教授「究極の選択:大震災後の世界をどうするか」
ボストン、上海、東京の学生たちとの白熱した議論。
東北の被災地での助け合い、略奪や便乗値上げが無いことに対する
外国の称賛と驚き。
個人主義の欧米 ⇔ 日本の共同体意識 という対比、勇敢に難題に立ち向かう原発作業員、
日当40万円というインセンティブは妥当か?
使命感と世間の抑制など、賛否両論。
家族という共同体が、単一民族の中で価値観を共有して国に拡大したという意見も。
教授からの問いかけ「原子力の将来をどう考えるか?」
シナリオ① リスクを最小限にして原発に依存
② 依存を減らして、生活の水準を落とす
特徴的なのは、ボストンの学生は全員①、日本は②が多いこと。
原爆被災国、大震災直後でもあり、当然だろう。
リスクを取る欧米、完璧主義の日本、という国民性の違いも感じた。
教授は、ルソーは「グローバルな人道主義は世界に広めると薄まる」と言ったが、
グローバルな共感を期待できるか?と投げかける。
ある学生:ルソーの時代になかったinternetというコミュニケーションの力で、
地球の裏側で起きたことに共感できる。
教授は「共同体意識が地球規模に拡大する変化の始まり」を指摘した。
私たちの常識は、世界の非常識という一面と、困難に出会った時の共感は人間として普遍的なものだとも感じる。
今、この大震災で起きている事実を注意深く見守っていきたい。
やはり、東電とか政府(保安院)などよりも、原発設備メーカーのノウハウに頼るほかないことがはっきりしてきた。
東芝、日立も、それぞれに廃炉計画案を出してきたが、
これらのメーカーは、米仏をはじめとする海外原発メーカーとの付き合いも深いので、期待できると思う。
「最短10年で撤去し、更地に戻す」と頼もしい限り。ぜひ、そうあって欲しい。
避難所のnewsでは、まだまだ過酷な環境の中で、先の見えない生活が続く。
その中で、最近は助け合い、感謝といった面が多く報道されるようになってきた。
マスコミも、やっと冷静に事態を観る余裕ができてきたのだろう。
過酷な復旧作業、高齢者が多い避難所では、自衛隊、ボランティア、自治体の救援など、人間としての”言葉・思い・行い”に心からの感動を覚える。
よく、神様は”耐えられない試練は与えない”という。
聖書:ローマ人への手紙5:1-5で
「苦難は忍耐を、忍耐は練達(品性)を、練達は希望を生む」
しかし、一瞬にして犠牲になった方々にとっては、実に空しい言葉だ。
これは、残された被災者の方々に向けた言葉になるが、希望を手にするまでの道のりは苦しい闘いの連続になる。
今、いろんなところで生まれている善意は、とても信じられないほどの、ある意味で奇跡でもあると思う。
海外20ケ国、地域からも、救助隊、医療隊、原子力専門家が現地に入り、40ケ国からの支援物資が届いているという。
スコップで必死に瓦礫を撤去する海外ボラランティア、涙を流しながら哀悼歌を合唱するケニアの少女たち、貧しい生活の中から寄付金も。
米軍2万人の「ともだち作戦」でも、さすがに隣人愛に富むお国柄、その救助、捜索する姿には尊敬の念を覚えた。
身近にも、アメリカからの義援金で、日常品を持って現地に向かった牧師さんたちや同級生でボランティア登録している人たちがいる。
苦しみの中では、国を問わず、人間としての絆、地球市民という言葉が、実感できる。
それにしても、こういった危機でしか、政治、経済、社会のいろんな面での本質があぶりだされないというのは、何とも歯がゆい。
危機に際して、頼りになるのは、日頃から現場・現実に目を向けて、地道に使命感を持って働いてきた人たちだと、改めて思う。
結論ありきの原発ルネサンス、親方日の丸の東電、足の引っ張り合いの政治家たちの無能さ、こういった大きなシステムに巣食う人たちの質が問われなければならない。
追記:2011.4.16
昨夜、マイケル・サンデル教授「究極の選択:大震災後の世界をどうするか」
ボストン、上海、東京の学生たちとの白熱した議論。
東北の被災地での助け合い、略奪や便乗値上げが無いことに対する
外国の称賛と驚き。
個人主義の欧米 ⇔ 日本の共同体意識 という対比、勇敢に難題に立ち向かう原発作業員、
日当40万円というインセンティブは妥当か?
使命感と世間の抑制など、賛否両論。
家族という共同体が、単一民族の中で価値観を共有して国に拡大したという意見も。
教授からの問いかけ「原子力の将来をどう考えるか?」
シナリオ① リスクを最小限にして原発に依存
② 依存を減らして、生活の水準を落とす
特徴的なのは、ボストンの学生は全員①、日本は②が多いこと。
原爆被災国、大震災直後でもあり、当然だろう。
リスクを取る欧米、完璧主義の日本、という国民性の違いも感じた。
教授は、ルソーは「グローバルな人道主義は世界に広めると薄まる」と言ったが、
グローバルな共感を期待できるか?と投げかける。
ある学生:ルソーの時代になかったinternetというコミュニケーションの力で、
地球の裏側で起きたことに共感できる。
教授は「共同体意識が地球規模に拡大する変化の始まり」を指摘した。
私たちの常識は、世界の非常識という一面と、困難に出会った時の共感は人間として普遍的なものだとも感じる。
今、この大震災で起きている事実を注意深く見守っていきたい。










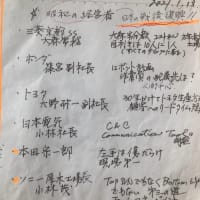
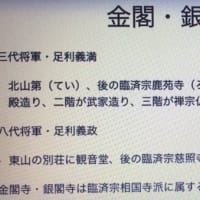
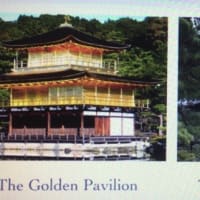
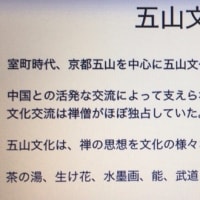
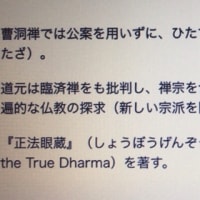
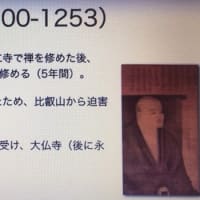
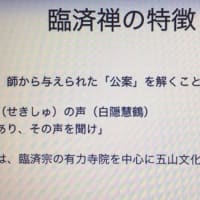
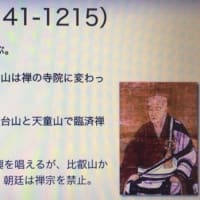
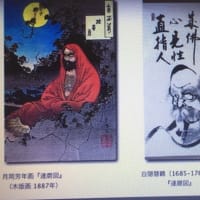
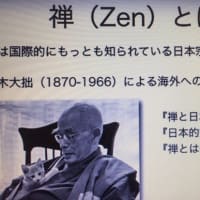
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます