
石見の伝説と歴史の物語−167(応仁の乱その後−1)
55.応仁の乱その後 応仁の乱は、足利義政と足利義視が東西に別れて戦った。 この兄弟にはもう一人兄弟が関東にいた。 前述した、初代の堀越公方である足利政知である。 義政、義...

石見の伝説と歴史の物語−166(応仁の乱−3)
54.応仁の乱(続き) 54.6.応仁の乱(3) 54.6.1.朝倉孝景の寝返り 文明3年(1471年)5月21日、斯波義廉(前管領)の宿老で西軍の主力であった朝倉孝景が、義...

石見の伝説と歴史の物語−165(応仁の乱−2)
54.応仁の乱(続き) 54.5.応仁の乱(2) 54.5.1.大内政弘 大内政弘は、室町時代の文安3年(1446年)、大内氏第13代当主・大内教弘の嫡子として生れた。 前...

石見の伝説と歴史の物語−164(応仁の乱−1)
54.応仁の乱 椀飯(おうばん) 椀飯とは、他人を饗応する際の献立の一種で、平安時代から始まっている。後には饗応を趣旨とする儀式・行事自体をも指した。 室町幕府においては、有...
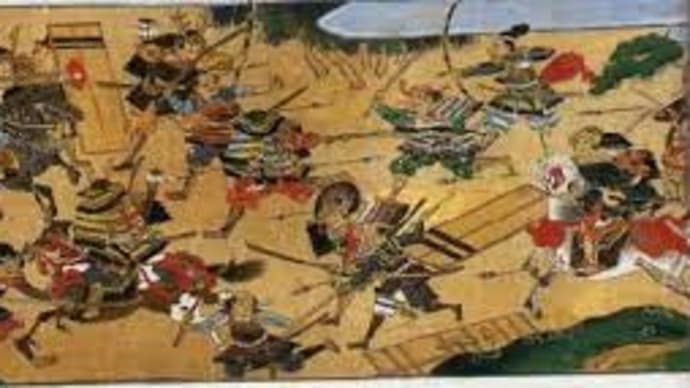
石見の伝説と歴史の物語−163(大乱の序章 斯波氏の内紛・将軍家の内紛)
53.大乱の序章(続き) 53.2.斯波氏の内紛 53.2.1.斯波氏 斯波氏は足利氏第4代当主足利泰氏の嫡男であった足利家氏が祖である。 家氏が誕生したとき、その母は正室...

石見の伝説と歴史の物語−162(大乱の序章 畠山氏の内紛)
53.大乱の序章 応仁の乱は、室町時代中期の応仁元年(1467年)に発生し、文明9年(1477年)までの約11年に及んで継続した内乱である。 その内乱は室町幕府...

石見の伝説と歴史の物語−161(南北朝合一)
52.南北朝合一 時代は第3代室町将軍足利義満のときまで遡る。 <第3代室町将軍足利義満> ...

石見の伝説と歴史の物語−160(戦乱の時代へ 永享の乱・享徳の乱)
51.戦乱の時代へ(続き) 51.2.永享の乱 話は、足利義教暗殺前に戻る。 室町将軍と鎌倉公方の対立 鎌倉公方は、室町幕府初代将軍の足利尊氏の子足利基氏の家系が代々世襲し...

石見の伝説と歴史の物語−159(戦乱の時代へ 第6代将軍足利義教)
51.戦乱の時代へ 51.1.第6代将軍足利義教 第6代将軍足利義教は嘉吉元年(1441年)6月、猿楽を鑑賞していた時に、乱入してきた赤松家の武士に首をはねられ殺害された。 ...

石見の伝説と歴史の物語−158(鎌倉時代と室町時代)
49.鎌倉時代と室町時代 49.1.武家の移動 鎌倉時代の初めまでは、人々は遠くに移り住むことは少なかった。 有力な武家でも、分家した一族は惣領の近隣の地に住み、その地を開墾...










